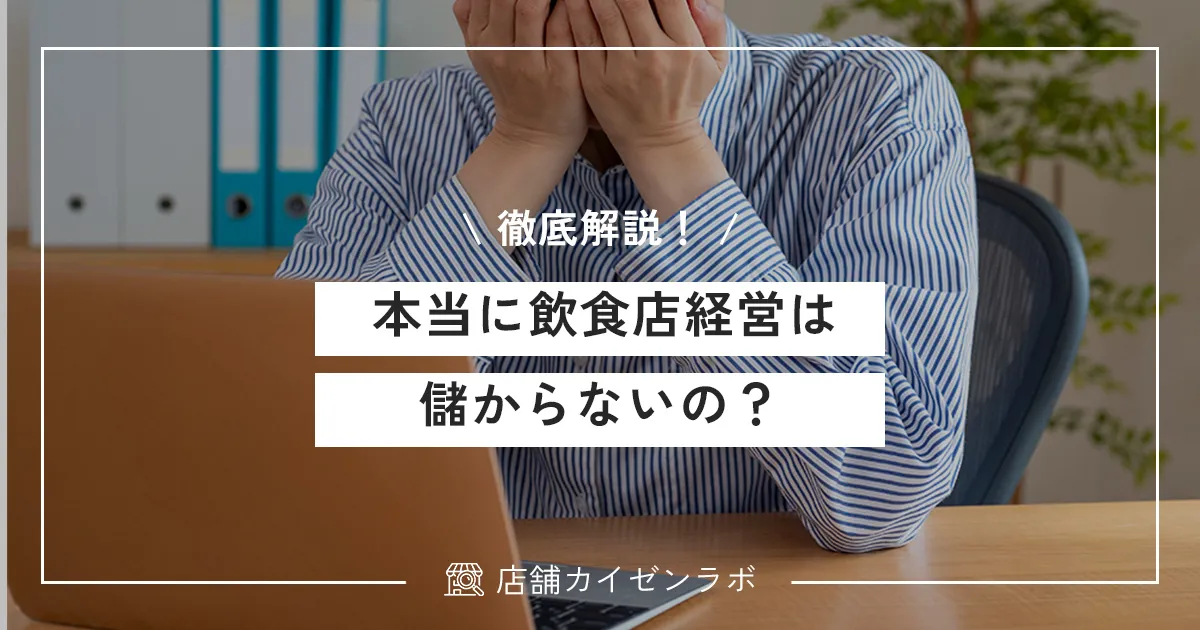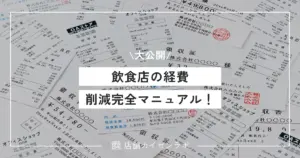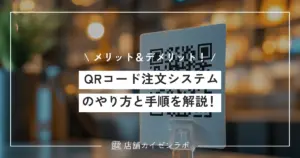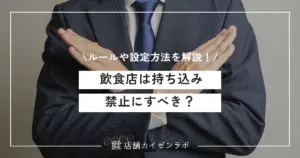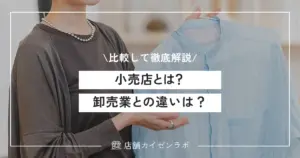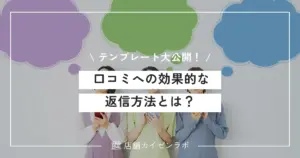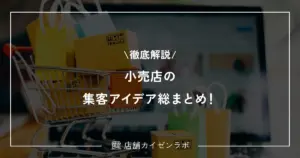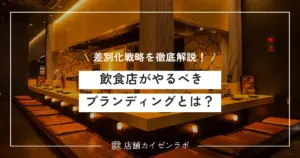第1章. 飲食業界が「儲からない」と言われる理由とは?

1-1. 廃業率から見える厳しい実態
飲食店は開業から1年以内に廃業する確率が高いとよく言われます。実際、飲食業界の廃業率は他業種と比較しても高めで、特に個人経営の店舗は資金繰りや経営ノウハウ不足が原因で早期に撤退を余儀なくされることが少なくありません。こうした現状を見ると、「飲食店を出しても儲からないのでは?」と感じてしまうのも無理はないでしょう。
また、食材や人件費をはじめとする経営コストの上昇、複雑な手続きや厳しい衛生管理など、飲食店ならではの難しさが多く存在します。しかも、競合店の多さによって価格競争が激化しやすく、一定の売上を確保するのが難しい構造になっているのが大きな要因です。
1-2. 利益率が低いと言われる理由

飲食店は「利益率が低い」ビジネスだとよく耳にします。その背景には、まず原価率の高さが挙げられます。食材費をきっちり抑えないと利益は出にくいのですが、安易に原価を下げれば料理のクオリティが低下し、リピート率の低下を招きます。
さらに、飲食業は「人」が商品価値を左右する場面が多いのも特徴的です。ホールスタッフやキッチンスタッフの接客・調理レベルが低いと顧客満足度が下がり、客足が遠のいてしまいます。しかし、人材を確保しようとすれば人件費が上がり、経営コストが増大してしまうのです。そのため、原価と人件費の両輪が経営者を常に悩ませる構造が「利益率が低い」というイメージを強めています。
また、飲食店の売上は天候や立地条件、イベント時期などの外的要因にも左右されやすく、「儲からない月」が出ることも珍しくありません。家賃などの固定費は毎月一定額がかかるのに対し、売上は波が激しいため、繁忙期と閑散期のバランスをうまく取る必要があります。このように変動要素が多いと、利益を安定させるのは容易ではありません。
利益率改善の仕組みについては、小売業の視点『小売店が目指すべき利益率の目安とは?原価や費用を下げて収益性を高める仕組みを大公開!』も参考になります
1-3. 「儲からない」は本当に避けられないのか?
これまでの事例だけを見ると「飲食店は儲からない」と悲観的になりそうですが、実際には成功している店舗も確かに存在しますが、すべての店がそうとは限らず、「儲からないまま撤退する店」も少なくありません。ポイントは、コンセプトの明確化と徹底したコスト管理、そして効果的な集客戦略の実践です。
たとえば、同じジャンルの料理店でも「地域密着型」や「高級路線」「バーチャルレストランと併用」など、店舗ごとに強みを明確化できれば一定の顧客を獲得し続けられます。また、仕入れ先との交渉で原価率を下げたり、独自のサービスで付加価値を高めたりといった工夫をするお店は、利益を上げている例も多いのです。つまり、「飲食店は儲からない」と一括りにはできない部分も大きいといえます。重要なのは、自分の店舗ならではの経営スタイルを確立し、どのように時代や顧客ニーズに合わせて変化できるかでしょう。飲食店経営者自身が数字を日々チェックし、改善を続ける店舗は厳しい状況下でも生き残り、さらには売上を伸ばしているケースがあります。
第2章. 飲食店経営が儲からない12個の原因

開業における初期費用のリスクから、競合やコスト管理、人材教育まで、飲食店経営を左右する多角的な問題を一章に凝縮しました。
2-1. 物件取得と内装工事に潜むリスク
飲食店を始めるにあたって、最初に立ちはだかるハードルの一つが店舗物件の取得と内装工事です。
- 家賃が高額になりやすい好立地
- 居抜き物件でも想定外の追加費用
- 衛生基準や設備要件への対応
ポイント
- 立地優先の物件探しは家賃と保証金の負担を増大させるリスク大。
- 内装費用はイメージ通りを追求すると予想以上に膨らむケースが多い。
- 衛生面・消防法など、飲食店ならではの規制をクリアするための設備投資が必須。
筆者の実践談
2-2. オープン前に頭を悩ませる資金繰りのリアル
内装費や設備投資に資金を大量投入すると、すぐに資金調達の壁にぶつかります。担保や信用情報が不十分だと、融資条件が厳しくなる可能性も。
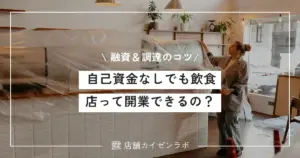
- 銀行融資:日本政策金融公庫や民間金融機関への申請では、綿密な事業計画とシミュレーションが求められる。
- 補助金制度:自治体や商工会の助成金を活用できる場合はあるが、時期や条件が限られる。
- クラウドファンディング:プロモーション力が重要で、達成しても手数料や返礼品コストを考慮すべき。
ワンポイント
2-3. POSレジやキャッシュレス決済導入のコストメリット
キャッシュレス決済が普及する時代、クレジットカードやQRコード決済への対応は必須。しかし手数料が発生するため、導入コストと利益への影響を見極めなければなりません。
一方、POSレジを使えば売上集計や在庫管理の効率化に加え、注文ミスによるロスを削減できます。顧客データを蓄積することで、リピーター向けのクーポンやメルマガ配信などの戦略も打ち出せるのが利点です。
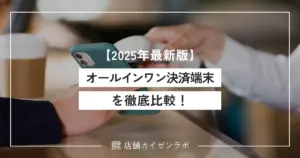
- ポイント
- キャッシュレス決済の手数料は2~5%ほど
- POSレジ導入でスタッフの動線管理が改善
- 長期的には人件費削減やミス防止にも寄与
- キャッシュレス決済の手数料は2~5%ほど
2-4. 過剰出店の背景と地域特性の見落とし
飲食業界は需要に対して店舗数が多く、過剰出店の状態です。特に人気エリアでは小規模な飲食店が乱立し、結果的に価格競争が起こりやすい構造になっています。
また、地域特性を見誤るとターゲット層とメニューのズレが生じ、いくら味やコスパが良くても「儲からない原因」となってしまいます。
- 分析ポイント
- エリアがオフィス街か住宅街か観光地か
- 周辺住民の所得水準やライフスタイル
- 他店の価格帯やメニューとの比較
- エリアがオフィス街か住宅街か観光地か
2-5. メニューやサービスの差別化不足
「どこにでもある定番メニュー」しかないと、顧客は価格でしか判断できなくなり、結果的に「儲からない」構造に陥ります。さらに、いまはSNSで写真映えや体験価値が注目される時代。差別化が不十分だと埋もれてしまいがちです。
- 具体例
- 新メニュー開発:産地直送の食材や季節限定メニュー
- サービスの独自化:記念日特典、SNS投稿で割引など
- 雰囲気づくり:照明やインテリアを統一し、特別な世界観を演出
- 新メニュー開発:産地直送の食材や季節限定メニュー
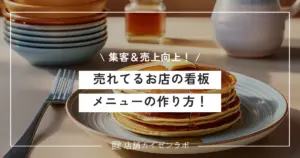
2-6. ランチ営業やバーチャルレストランの活用と落とし穴
単価が低いランチは「儲からない」と思われがちですが、実は夜の高単価メニューへの導線になる可能性を秘めています。平日ランチで店を知ってもらい、週末や夜の再来店へつなげる戦略は効果的です。
一方、バーチャルレストランやゴーストキッチンは家賃や内装費を抑えながら複数ブランドを展開できる利点がありますが、オンラインでの集客力がないと売上に直結しにくく、結果「儲からないビジネスモデル」にもなり得る点には注意が必要です。
2-7. 人件費と原価率が同時に高騰するジレンマ

飲食店が「儲からない」と感じる最たる要因が、人件費と食材原価の上昇です。
- 人件費:優秀なスタッフを確保するために時給アップや福利厚生を整える必要がある。
- 食材原価:世界的な食品価格の高騰や輸送コストの上昇で、原価率が30~40%を超えるケースも。
ダブルパンチの結果
2-8. 食材ロスと廃棄コストの重圧
飲食業の利益率を下げる大きな要因に食材ロスがあります。仕込みすぎた食材や売れ残りは、ただ廃棄コストを生むだけでなく、社会的なフードロス問題にも影響。包装材や容器のコスト、ゴミ処理費用など、見えにくい雑費も積み重なると無視できない金額になります。
- ロス削減ヒント
- 棚卸し頻度を上げて在庫を常に可視化
- メニュー構成を複数メニューで使い回せる形に
- 小ロット発注が可能な仕入れ先を開拓
- 棚卸し頻度を上げて在庫を常に可視化
2-9. 家賃・光熱費・雑費が積み重なる罠
人気エリアの家賃は高額なうえ、長時間営業による光熱費もバカになりません。さらに、洗剤やトイレットペーパー、調理器具の買い替えといった細かい消耗費が意外と経営を圧迫します。
特に新規開業時は後から追加で必要になる設備や備品が出てきやすいので、初期見積もりを厳しめにしておくと痛い目を見ずに済むでしょう。
2-10. スタッフ教育不足によるクオリティ低下
飲食店はサービス業+接客業であるため、スタッフの質がそのまま顧客満足度に直結します。オーダーミスや不親切な対応が目立つと、SNSの口コミなどで悪評が広まりやすく、客足が遠のく原因になります。
- 改善ヒント
- マニュアル整備:メニュー説明や接客対応を体系的にまとめる
- 定期研修:ロールプレイや試食会でスタッフの知識と接客スキルを底上げ
- フィードバック面談:店長やオーナーがスタッフと対話し、モチベーションを維持
- マニュアル整備:メニュー説明や接客対応を体系的にまとめる

2-11. SNS・口コミを活かせないお店の共通点
若い世代の多くは、SNSや口コミサイトの評価を見てから店選びをしています。定期的な情報発信や魅力的な写真の掲載を怠ると、非常に大きな集客機会を逃してしまうのです。
また、口コミサイト上の低評価に対するフォローや誤解の解消をしないと、悪い印象が固定化されてしまうリスクが高まります。
- 具体的なSNS施策
- 写真の質にこだわる(プロカメラマン起用やスマホ撮影の工夫)
- 適切なハッシュタグ設定(#地域名 + #料理ジャンルなど)
- キャンペーンやクーポン発行でフォロワー数を増やす
- 写真の質にこだわる(プロカメラマン起用やスマホ撮影の工夫)
口コミ対応のポイントは『口コミへの効果的な返信方法とは?印象の良い例文やテンプレートを大公開!』にまとめられています。
2-12. リピーター対策を怠ると新規客ばかり追いかける悪循環に
飲食店の売上を安定させるには、リピーターの存在が欠かせません。いくら新規集客を頑張っても、再来店率が低ければ広告費の割に売上が伸び悩む悪循環に陥ります。
- クーポンやポイントサービスで再訪を促す
- 季節限定商品やイベントで常連客を飽きさせない
- 顧客の声を反映して新メニュー開発
筆者の体験談
月々かかる経費の内訳と対策は、『飲食店で毎月かかるランニングコストの内訳と目安!効果的なコスト削減方法まで大公開!』の記事も参考になります
第3章. 儲かる飲食店への第一歩!まずはコンセプトとメニューを再構築しよう!

3-1. “集客商品”と“高収益商品”の役割分担
飲食店のメニューは「すべて同じように利益を出す」ことを目指すより、集客商品と高収益商品を明確に分けた方が賢明です。たとえば、SNS映えするスイーツや話題のドリンクを「客寄せ」として提供し、原価率が低く利益率の高いメインメニューでしっかり利益を確保する方法があります。こうした戦略をとる店は意外に多く、チェーン店でも「安いランチセット」は実は利益度外視で客を呼び込む役割を担っている例が少なくありません。
- 具体例
- 集客商品:インパクト重視や旬の食材を使った季節限定メニュー
- 高収益商品:ドリンク類、追加トッピング、サイドメニューなど原価を抑えられる商品
- 集客商品:インパクト重視や旬の食材を使った季節限定メニュー
高収益商品を訴求するには、効果的なポップ作成『飲食店の売上につながるポップの作り方!デザインの作成方法からおすすめツールまで!』も有効です
3-2. 独自の世界観を打ち出すブランディング
経営を成功させるためには、店舗のコンセプトを明確に打ち出すブランディングが欠かせません。どこにでもあるメニュー、どこにでもある内装、どこにでもある接客では、たとえ味が良くても「また行きたい」と思わせる力が弱いでしょう。近年は消費者が「体験」を重視するようになっており、世界観やストーリー性を持ったお店に人が集まりやすい傾向があります。
- ブランディングのステップ
- ターゲット設定:どの年齢層・性別・ライフスタイルをメイン顧客にするか
- コンセプト明確化:店舗のテーマやストーリーを言語化
- ビジュアル統一:ロゴ、内装、ユニフォームなどで世界観を演出
- ターゲット設定:どの年齢層・性別・ライフスタイルをメイン顧客にするか
飲食店のブランディングの詳細については『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』でまとめています。
3-3. バーチャルレストランやゴーストキッチンの導入事例
実店舗を構えるだけが飲食店の形態ではなくなりつつあります。デリバリー需要が拡大する中、キッチン設備だけ借りて複数のメニューをオンラインで展開する「バーチャルレストラン」や「ゴーストキッチン」は、家賃や内装投資を大幅に抑えられるメリットがあります。
一方で、認知度や信用度を高めるのに時間がかかり、SNSやプラットフォームへの掲載だけでは多くの注文を獲得できないケースもあります。特にブランドイメージが確立していない状態で参入すると、価格競争や広告費の過剰投下に陥りやすく、結果として「儲からない展開」になりかねないので注意が必要です。しかし、既存の実店舗を持っている経営者がサブブランドとしてバーチャル展開を行う場合は、相互に集客効果を高める戦略も期待できます。
- 導入時のチェックポイント
- 立地:デリバリー対応エリアの人口や需要を把握
- 調理効率:デリバリー用のメニューは調理工程や包材選びが勝負
- オペレーション管理:配達時間や品質の管理が成功の鍵
- 立地:デリバリー対応エリアの人口や需要を把握
ゴーストキッチンの収益構造と注意点は『ゴーストレストランは本当に儲かるの?失敗しないためのコツを大公開!』の記事で学べます
第4章. 儲からない原因を潰すためにコスト管理とオペレーションを改善!
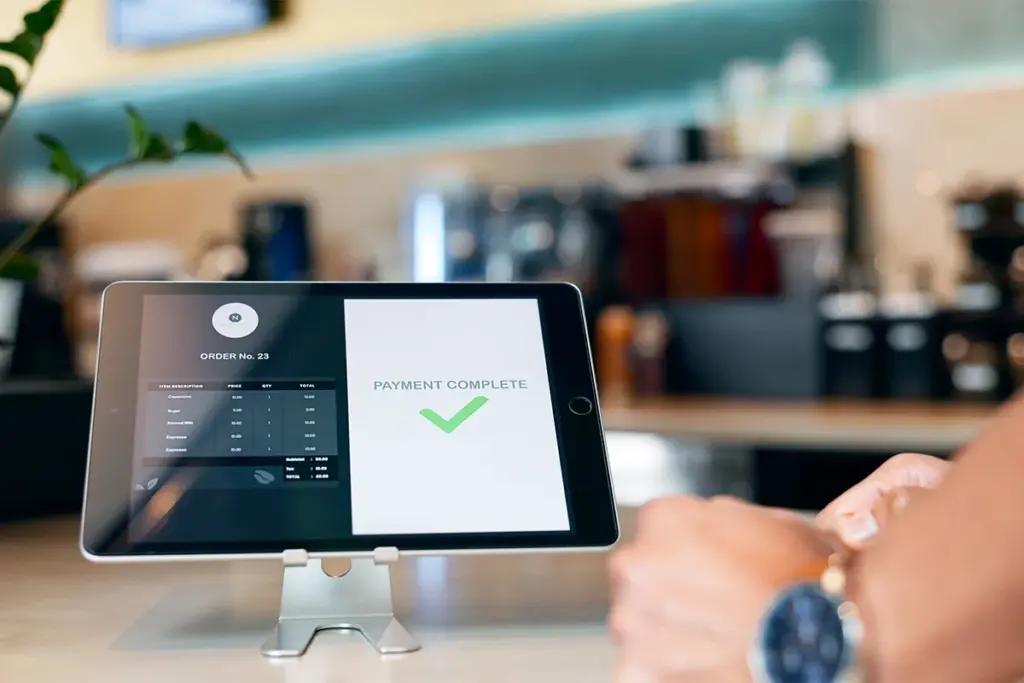
4-1. 原価率を30%前後に抑える実践法
飲食店の経営において、原価率(食材コストの比率)は必ず意識したい指標です。多くの店舗が目安とするのは30%前後で、これより高いと儲からない状態に陥りやすくなります。
逆に、原価率を過度に抑えすぎると料理のクオリティが落ち、顧客離れにつながるリスクもあります。つまり、バランスを見極めた食材の選定とメニュー構成が必要です。
- メイン食材の一括仕入れ
仕入れ先との交渉を重ね、大量発注によるスケールメリットを得られれば、食材原価を抑えられます。特に肉や魚など消費量が多い食材は、信頼できる卸業者との関係を築くことが重要です。 - 食材の使い回し設計
仕込み段階で複数メニューに対応できるようにしておくと、食材の無駄を減らせます。スープやソースなどはまとめて作り、提供の際に味付けを少し変えるなどの工夫もポイントです。 - 歩留まり(ぶどまり)を意識する
歩留まりとは、仕込み時に出る食材の可食部比率を示す考え方です。高い歩留まりをキープできれば、ロスを削減し、実質的な原価率を下げることができます。
コスト削減の具体策については『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』の記事が参考になります
4-2. 日別損益と棚卸しで“無駄”を見逃さない
飲食業は日々の売上が天候やイベントなどの外的要因に左右されやすく、儲からない日が続くことも珍しくありません。
そのため、「毎日売上とコストを振り返る習慣」が大きな差を生むのです。日々のPOSレジデータを確認し、売れ筋商品と不人気商品の動きを正確に把握することが重要です。
- 日別損益のチェックポイント
- 食材仕入れコスト:在庫と売上の釣り合いをこまめに確認
- 人件費:繁忙日・閑散日ごとにスタッフの配置を最適化
- 棚卸し:在庫ロスや盗難リスクを早期に察知
- 食材仕入れコスト:在庫と売上の釣り合いをこまめに確認
筆者の体験談
4-3. 調理と接客の動線設計で人件費を最適化
店内オペレーションを見直すことで、人件費を抑えながらサービスの質を維持できる場合があります。例えば、厨房内の動線を最適化すれば、少人数でも効率よく料理を提供できますし、ホールの配置や配膳ルートを工夫すれば、スタッフの疲労を軽減しつつ回転率を上げられることもあります。
オーダーシステムの導入で、スタッフ負担を減らす方法は『QRコード注文システムのやり方と手順を解説!簡単にできる導入方法からメリット・デメリットまで!』です。
- 動線設計のヒント
- セルフサービス導入:ドリンクバーなどを導入して、スタッフの動きを減らす
- オーダーシステム:スマホ注文やタブレット注文を活用して、注文ミスや接客負担を低減
- オープンキッチン化:狭いスペースでも調理状況が見えるようにすれば、料理の出し入れがスムーズに
- セルフサービス導入:ドリンクバーなどを導入して、スタッフの動きを減らす
人員配置と動線が最適化されると、スタッフ同士の連携ミスも減り、顧客が待たされる時間を短縮できます。結果的に顧客満足度が高まり、リピーター増加につながることで儲からない構造からの脱却が期待できるのです。
オペレーション改善で人件費を最適化する方法は『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』に詳しくまとまっています。
第5章. マーケティング施策とリピーター育成で売上増加を狙おう!

5-1. SNS広告やインフルエンサー活用での相乗効果
現代のマーケティングにおいて、SNSは欠かせない集客ツールです。特にInstagramやTikTokなど、ビジュアルや短い動画で料理の魅力を伝えやすいプラットフォームを活用すれば、拡散力は非常に高まります。効果的な画像や動画を投稿し続けることで、顧客との信頼関係を築きやすくなるでしょう。

- インフルエンサー活用の注意点
- 店舗のコンセプトに合ったインフルエンサーを選ぶ
- 投稿や撮影のルールを事前に共有し、店のイメージを守る
- 報酬形態は商品提供だけでなく、成果報酬ベースも検討
- 店舗のコンセプトに合ったインフルエンサーを選ぶ
ただし、高額なインフルエンサーに依頼したからといって必ず集客に成功するわけではありません。地域密着型の小規模アカウントや、ジャンル特化の有力ブロガーと提携するほうが、費用対効果が悪く儲からない広告投資を避ける意味でも有効です。
SNSと合わせてMEO対策も行うことで、より集客力が高まりますので『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』も参考にどうぞ。
5-2. 顧客リスト・メルマガ・LINE公式アカウントの運用
一度来店した顧客を再び呼び込むには、顧客リストの整備と活用が不可欠であり、儲からない状態を脱却する鍵にもなります。SNSフォロワーやメルマガ登録者、LINE公式アカウントの友達追加など、いろいろな手段でコンタクトポイントを作ると、再訪を促しやすくなります。
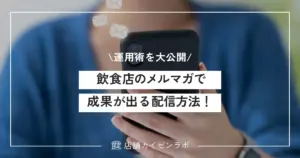
- 運用のポイント
- 定期的なクーポン配布:新メニューや季節限定商品に合わせて発行
- 個別メッセージの配信:誕生日や記念日に特別サービスを案内
- 友達紹介制度:登録者が友人を紹介すると特典が受けられる仕組み
- 定期的なクーポン配布:新メニューや季節限定商品に合わせて発行
こうした仕組みを導入すると、広告費をかけずとも確実に「来店見込みの高い顧客」にアプローチできるのがメリットです。また、来店ごとに貯まるスタンプカードやポイントカードは、アナログでも効果的なリピート戦略と言えます。
アンケートで顧客の本音を集め、再訪を促す方法は『飲食店がアンケートを活用して顧客満足度を上げる方法!必要な項目と質問例を大公開!』です
5-3. テイクアウト・デリバリー戦略で客単価アップ
コロナ禍をきっかけに、テイクアウトやデリバリーを始める店舗が急増しました。今では「家で美味しい料理を楽しみたい」というニーズが根強く残っています。そこで、店内飲食だけでなくテイクアウト専用メニューやデリバリー限定セットを用意すると、売上の幅が広がります。
- 包装・容器へのこだわり
自宅で食べるときも、見た目の良さや温かさをキープできる包装を選ぶとリピートが増えます。 - ファミリー向けセット
家族や友人とシェアできる大皿やパーティーセットは、客単価が高くなりやすい傾向があります。 - デリバリーアプリ選定
Uber Eatsや出前館、menuなど複数のプラットフォームを比較検討して、手数料や集客力を見極めるのが大切です。
第6章. 儲からない飲食店でよくある疑問

6-1. Q1:利益率が低いなら値上げすれば解決するのでは?
A: 単に値上げしても一時的に売上が増えるだけで、顧客離れのリスクも高まります。むしろ食材原価や人件費の見直し、接客向上など複数の要素を同時に改善し、価格以上の価値を感じてもらうことが大切です。
6-2. Q2:SNSを頑張っても本当に集客につながるの?
A: SNSは新規顧客獲得やブランド認知度向上に効果的です。ただ更新が不定期で情報が古いと逆効果になる場合も。定期的な発信、魅力的な写真・動画、ハッシュタグ活用など基本を徹底し、顧客とのコミュニケーションを継続することがポイントです。
6-3. Q3:人手不足だからこそ人件費を削るべきでは?
A: 人材確保が難しいからこそ、スタッフへの投資は必要です。安易に時給を下げたり人数を減らしたりするとサービス品質が落ち、クレームや離職率が上昇して逆にコスト増につながります。研修や評価制度を整え、定着を図るほうが長期的に安定します。
6-4. Q4:高級路線に変えればすぐに客単価は上がる?
A: 高級路線は客単価は上がりやすい反面、求められる料理やサービス水準も高くなります。価格に見合った空間演出や接客、ブランディングが整っていなければ、むしろ評判を落とすリスクも。立地や客層との相性を見極めて判断しましょう。
6-5. Q5:とにかくメニュー数を増やせば顧客が飽きないのでは?
A: メニューが増えるほど食材ロスやオペレーションの複雑化を招きがちです。むしろ“売れ筋”と“利益率”のバランスを見極め、厳選したメニューで回転効率を高めるほうが結果的に満足度も収益も向上します。定期的な棚卸しで改善を図ると効果的です。
6-6. Q6:安いキャンペーンで新規客を集めれば儲かる?
A: 値引きや格安キャンペーンは短期的に集客できる反面、低価格のイメージが定着すると通常価格に戻した際に離脱を招きます。むしろ再来店を促す特典やポイント制度を用意し、顧客単価とリピート率を上げる工夫が儲からない状態の打開策となります。価格より付加価値を伝えましょう。
第7章. しっかりと対策すれば儲からない状態から飲食店も抜け出せる!

飲食店が「儲からない」とされる背景には、初期費用の高さや薄利多売の構造、競合過多など複合的な要因が存在します。しかし、日次レベルで原価や人件費を管理し、スタッフ教育やSNS戦略を怠らず、顧客との信頼関係を地道に育てることで、売上と利益率を確実に伸ばすことは可能です。
価格を見直すだけではなく、サービスや店舗体験に付加価値を生み出す施策を組み合わせ、既存客のリピーター化を強化すれば、飲食ビジネスに「儲かる仕組み」を導入できます。多角化やバーチャルレストランなどの新しい試みにも柔軟に対応し、儲からない要因を取り除いていく努力が、時代や市場の変化に適応するうえで経営継続のカギとなるでしょう。