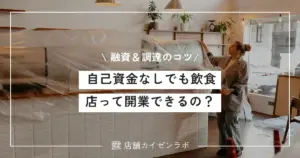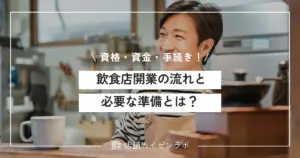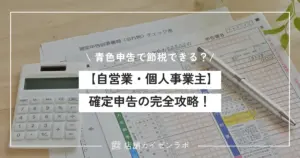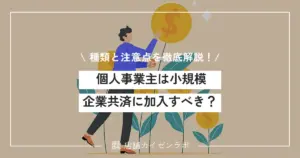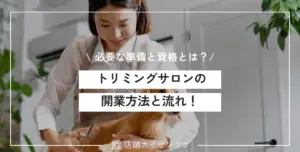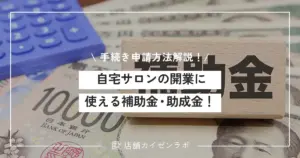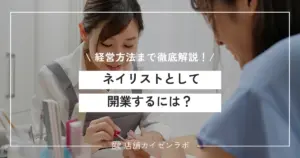「いつか自分の飲食店を持ちたいけれど、何百万円もの開業資金なんて用意できない…」 「会社を辞めて独立するのはリスクが高い。まずは副業から小さく試してみたい」
そんな想いを抱えるあなたに、今、大きな注目を集めているのが「間借り飲食店」という選択肢です。この記事では、飲食業界で10年以上、店舗開発からコンサルティングまで手掛けてきた筆者が、低リスクで夢への第一歩を踏み出すための「間借り開業」の全てを、具体的な成功・失敗事例を交えながら徹底的に解説します。
第1章 低リスクで夢を叶える「間借り飲食店」とは?基本を徹底解説

まずは「間借り飲食店」がどのようなものなのか、その基本的な仕組みと、なぜ今これほどまでに注目されているのかを理解しましょう。言葉は聞いたことがあっても、具体的なイメージが湧いていない方も多いのではないでしょうか。
1-1. そもそも「間借り飲食店」とは?シェアレストランとの違い
間借り飲食店とは、一言でいえば「既存の飲食店の使われていない時間帯(アイドルタイム)や定休日に、厨房設備や店舗スペースを借りて営業する」ビジネスモデルです。
例えば、夜しか営業していないバーの昼間の時間帯を借りてランチ専門のカレー屋を開いたり、定休日のカフェを借りて週末限定のスイーツ店を開いたりするケースがこれにあたります。
貸す側の店舗オーナーは、本来なら収益ゼロの時間帯を貸し出すことで家賃収入を得られ、借りる側は、通常なら数百万円以上かかる物件取得費や設備投資をほぼゼロにして、低コストで自分の店を開業できる、まさに「Win-Win」の仕組みなのです。
ここで、似たような言葉である「シェアレストラン」や「ゴーストレストラン」との違いを明確にしておきましょう。あなたが目指すスタイルはどれに近いか、確認してみてください。
| 営業形態 | 特徴 | 初期費用 | 自由度 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|
| 間借り飲食店 | 既存店舗のアイドルタイムを1対1で借りる | 低 | 中 | 自分のコンセプトを試したい、将来の独立を目指す人 |
| シェアレストラン | 1つの厨房や店舗を複数の事業者で共有する | 極低 | 低 | とにかくコストを抑えたい、週1日など限定的に始めたい人 |
| ゴーストレストラン | 客席を持たず、デリバリー専門で営業する | 中〜低 | 高 | 調理に集中したい、デリバリー市場に特化したい人 |
デリバリー専門のゴーストレストランも選択肢の一つですが、具体的にどのようなビジネスモデルで、どうすれば成功できるのでしょうか。『ゴーストレストランは本当に儲かるの?失敗しないためのコツを大公開!』で、失敗しないためのコツを詳しく解説しています。
1-2. なぜ今、間借り飲食店が注目されるのか?高まるニーズの背景
近年、テレビや雑誌で「間借り」という言葉を目にする機会が増えたと感じませんか?その背景には、借り手と貸し手、双方のニーズが時代に合致したという明確な理由があります。
借り手側のニーズは、やはり「低リスクでの独立・副業志向の高まり」です。中小企業庁の調査によれば、飲食店の開業には平均して1,000万円近い資金が必要とされています。この高額なハードルが、多くの人の「夢への挑戦」を阻んできました。しかし、間借りなら数十万円から開業が可能。会社員を続けながら週末だけ、といった副業スタイルも実現しやすく、本格的な独立前の「お試し期間」として活用する人が急増しているのです。
飲食店コンサルタントA氏の見解
一方、貸し手側のニーズも深刻です。原材料費や光熱費の高騰に苦しむ飲食店にとって、店舗の空き時間は「収益を生まないコスト」でしかありません。そのアイドルタイムを貸し出すことで、毎月の家賃や光熱費の足しになるだけでなく、間借り店の集客が自店の認知度向上につながるという相乗効果も期待できるのです。
このように、挑戦したい「借り手」と、遊休資産を有効活用したい「貸し手」のニーズが合致したことで、間借りという文化が急速に広まっています。
【この章のチェックポイント】
間借りは、既存店の空き時間を借りる低コストな開業方法です。まずは自分のやりたいことが「間借り」「シェア」「ゴースト」のどれに当てはまるか考えてみましょう。
第2章 開業前に知るべき間借り飲食店の5つのメリット
間借りの基本的な仕組みがわかったところで、次にその具体的なメリットを5つのポイントに絞って深掘りしていきます。これらのメリットを理解すれば、なぜ多くの人が最初のステップとして間借りを選ぶのか、納得できるはずです。
間借り開業のメリットを理解する前に、まずは通常の飲食店開業にどれくらいの準備と資金が必要かを知っておくと、その魅力がより一層際立ちます。『飲食店開業の流れと必要な準備とは?資格・資金・手続きを完全解説!』では、物件探しから始める一般的な飲食店開業の全ステップを解説しています。
2-1. 【メリット①】圧倒的な低コストで開業できる
最大のメリットは、何と言っても開業資金を劇的に抑えられることです。通常の店舗開業で必須となる以下の費用が、間借りではほとんどかかりません。
- 物件取得費(保証金、礼金、仲介手数料など):数百万円
- 内装・外装工事費:数百万円
- 厨房設備費(コンロ、冷蔵庫、シンクなど):数十万〜数百万円
2-2. 【メリット②】最短数週間でのスピード開業が可能

通常の飲食店開業は、物件探しから始まり、契約、内装設計、工事、許認可申請…と、オープンまでに半年から1年かかることも珍しくありません。一方、間借りは既に営業許可が下りている店舗を利用するため、このプロセスを大幅にショートカットできます。
物件とのマッチングがスムーズに進めば、契約からわずか数週間で開業することも可能です。このスピード感は、「やりたい」という熱意が冷めないうちに行動を起こせるという、計り知れない価値を持ちます。
成功事例:Webデザイナー Aさん(30代)
2-3. 【メリット③】本格開業前のテストマーケティングに最適
「自分の料理は本当にお金を出してもらえる価値があるのか?」これは、独立を考える誰もが抱く不安です。間借りは、この問いに低リスクで答えを出すための最高の実験場となります。
- どのメニューが人気か?
- 価格設定は適切か?
- 想定したターゲット層は来店してくれるか?
- 一人で効率的にオペレーションを回せるか?
これらの要素を実際の営業を通して検証し、データを集めることができます。このテストマーケティング期間で得た経験と顧客からのフィードバックは、将来自分の店を持つ際の、何物にも代えがたい財産となります。
テストマーケティングで最も重要なのが、お客様を惹きつける「看板メニュー」の存在です。多くのファンを生み出す看板メニューの作り方や、集客に繋げるための考え方を『売れてるお店の看板メニューの作り方!集客や売上向上に繋げるには?』で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
2-4. 【メリット④】撤退コストや手間が少なくリスクが低い
挑戦に失敗はつきものです。万が一、事業がうまくいかなかった場合でも、間借りは最小限のダメージで撤退できるという大きな安心感があります。
通常の店舗では、途中解約による高額な違約金や、スケルトン状態に戻すための原状回復費用で数百万円の負債を抱えるケースも少なくありません。しかし、間借りの契約は数ヶ月単位の短期間であることが多く、原状回復も基本的な清掃で済む場合がほとんど。金銭的にも精神的にもプレッシャーが少なく、再挑戦しやすいのが特徴です。
事業再生コンサルタントB氏のコメント
2-5. 【メリット⑤】既存店の集客力や認知度を活用できる
開業初期の最大の壁は「集客」です。ゼロから店の存在を知ってもらうのは、大変な労力がかかります。しかし、既に地域で認知されている人気店や、駅前の一等地にある店舗を間借りできれば、その集客力やブランド力を借りることができます。
オーナーのお店の常連客が「昼は違う店をやっているんだ、行ってみよう」と興味を持ってくれたり、オーナーがSNSで告知に協力してくれたりすることも。これは、ゼロから始める個人店にはない、非常に大きなアドバンテージです。
【この章のチェックポイント】
間借りのメリットは「低コスト」「スピード」「低リスク」に集約されます。これらの利点を最大限に活用できる事業計画を立てられるかどうかが、成功の鍵です。
第3章 間借り飲食店の5つのデメリット
夢のようなメリットがある一方、間借りには光があれば影もあります。契約してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、現実的なデメリットもしっかりと直視しておきましょう。これらを事前に理解し、対策を練ることが失敗を避ける最善の方法です。
3-1. 【デメリット①】内装や設備の自由度が低い

これは最も多くの人が直面する壁です。間借りはあくまで「他人の店舗を借りる」ため、内装を自分好みに変更したり、大型の厨房設備を自由に追加したりすることは基本的にできません。
「壁紙をこの色にしたい」「カウンターのデザインを変えたい」といった要望はまず通らないと考えましょう。借りた店舗の設備と雰囲気の中で、いかに自分のコンセプトを実現するか、という「制約の中での創造性」が求められます。
カフェ開業を目指したCさん(20代)の失敗
3-2. 【デメリット②】営業日や時間が制限される
間借りは、オーナーの店舗が営業していない「アイドルタイム」を利用するのが基本です。そのため、営業できる曜日や時間は必然的に制限されます。
「ランチ営業が好調だから、ディナーも営業して売上を伸ばしたい!」と思っても、夜はオーナーが営業するため、それは叶いません。売上を最大化する機会が物理的に制限されてしまう点は、大きなデメリットと言えるでしょう。
3-3. 【デメリット③】オーナーの都合で営業停止になるリスク
間借り営業は、良くも悪くもオーナーの存在に大きく依存します。つまり、自分の努力や人気とは無関係な外部要因によって、突然営業場所を失うリスクを常に抱えています。
- オーナーが店を閉めることにした
- 物件が売却されることになった
- オーナーとの人間関係が悪化した
このような理由で、「来月で貸すのをやめます」と一方的に通告される可能性もゼロではありません。事業の継続性が不安定な立場であることは、覚悟しておく必要があります。
3-4. 【デメリット④】売上拡大に限界がある
前述の「営業時間の制限」に加え、「客席数」も既存の店舗に依存するため、間借り営業の売上には物理的な上限が存在します。月商100万円を超えるような大きな成功を収めるのは、極めて難しいのが現実です。
例えば、具体的な数字で考えてみましょう。
席数15席×客単価1,200円×満席率70%×回転数1.5回転=1日の売上18,900円
この条件で月20日営業した場合、月商は約38万円。ここから賃料、原材料費、光熱費などを差し引くと、手元に残る利益はいくらになるでしょうか。間借りは「大きく稼ぐ」ためのモデルではなく、「経験を積む」「副収入を得る」ためのステップと捉えるのが賢明です。
間借り営業では売上に上限があるため、利益を確保するにはコスト管理が非常に重要になります。家賃や原材料費だけでなく、見落としがちな経費を削減する具体的な方法を『飲食店で毎月かかるランニングコストの内訳と目安!効果的なコスト削減方法まで大公開!』で解説しているので、ぜひご一読ください。
3-5. 【デメリット⑤】社会的信用を得にくい場合がある
事業を拡大していく上で、金融機関からの融資は重要な選択肢となります。しかし、間借り営業は固有の店舗住所を持たないため、融資審査において不利になる場合があります。
金融機関は「事業の継続性」を重視しますが、間借りはオーナーの都合で終了するリスクがあるため、どうしても評価が慎重になりがちです。将来的に融資を受けて自分の店を持ちたいと考えている場合、この点はハードルになる可能性があります。
元金融機関担当者の本音(匿名)
【この章のチェックポイント】
デメリットを理解し、「そのリスクは許容できるか?」「対策は打てるか?」を自問自答することが重要です。これらの制約を乗り越える覚悟が、成功への道を切り拓きます。
第4章 間借り営業におすすめの業態6選

間借りのメリット・デメリットを理解した上で、次に考えるべきは「何を売るか?」です。間借りには、その特性を活かせる「向き・不向き」の業態が存在します。ここでは、少ない設備と限られた時間でも成功しやすい、おすすめの業態を6つ、具体的な成功事例と共に紹介します。
4-1. カフェ・喫茶店
カフェは、間借り営業の王道ともいえる業態です。大規模な厨房設備が不要で、コーヒーメーカーや最低限の調理器具があれば始められます。特にドリンク中心であれば、オペレーションもシンプルで一人でも運営しやすいのが魅力です。
成功の鍵は「専門性」。ただコーヒーを出すのではなく、「自家焙煎のスペシャルティコーヒー」「特定の国の豆に特化」「季節のフルーツを使ったオリジナルドリンク」など、他にはない付加価値を打ち出すことで、熱心なファンを獲得できます。
週末限定のスペシャルティコーヒー店 Dさん
4-2. カレー専門店
カレーもまた、間借りの定番かつ成功しやすい業態です。最大のメリットは、営業前にカレーを大量に仕込んでおけること。営業中はご飯を盛り付け、カレーを温めてかけるだけなので、限られたランチタイムでもスピーディーに提供でき、高い回転率を実現できます。
スパイスの組み合わせ次第で、スリランカ風、南インド風、欧風など、無限のバリエーションを生み出せるのも強み。「激辛」「薬膳」「ヴィーガン」など、コンセプトを尖らせることで、ニッチなファン層をがっちり掴むことが可能です。
4-3. バー
カフェやレストランの営業が終了した深夜帯や、定休日を利用して営業しやすいのがバーです。本格的な調理設備はほとんど不要で、お酒とグラス、製氷機があれば始められます。
ここでも重要なのは「コンセプトの専門特化」です。例えば、「国産クラフトジン専門」「希少なスコッチウイスキーの飲み比べセット」「ノンアルコールカクテル専門」など、オーナーの個性や知識を活かしたテーマ設定が、他店との差別化につながります。お客様との会話も重要な商品となるため、コミュニケーション能力も成功を左右します。
4-4. ラーメン屋
意外に思われるかもしれませんが、ラーメン屋もオペレーションを工夫すれば間借りで十分に可能です。ポイントは「仕込みの徹底」。スープやチャーシューなどの主要な具材は、別の場所(自宅や仕込み専用のキッチンなど)で事前に調理しておきます。
店舗では麺を茹で、スープを温め、盛り付ける作業に集中することで、ランチタイムの短い時間でも効率的に営業できます。居酒屋の昼時間を間借りすれば、夜の営業で使っている寸胴やコンロを活用できるケースも多く、相性の良い組み合わせと言えるでしょう。
居酒屋オーナー(40代)
4-5. 軽食・専門特化店(タコス、バインミーなど)
調理工程がシンプルで、テイクアウトにも対応しやすい軽食も間借りに最適です。特に、タコス、バインミー、おにぎり、サンドイッチといった業態は、作り置きできる具材が多く、注文を受けてから短時間で提供できます。
特定のメニューに特化することで、食材ロスを減らし、オペレーションを極限まで効率化できるのが強みです。ヘルシー志向、ヴィーガン対応、グルテンフリーなど、現代の多様な食ニーズに応えるコンセプトを打ち出すことで、新たな市場を開拓できる可能性も秘めています。
4-6. 季節限定店(かき氷、おでんなど)
「夏の間だけ」「冬の間だけ」といった季節限定の営業スタイルは、短期間の契約が基本となる間借りのメリットを最大限に活かせます。
夏は、フルーツをふんだんに使った高級かき氷や、クラフトシロップのかき氷。冬は、こだわりの出汁で煮込んだおでんや、アツアツのぜんざいなど。季節感を前面に押し出すことで、お客様の「今しか食べられない」という心理を刺激し、高い集客効果が期待できます。
【この章のチェックポイント】
自分のやりたいことと、間借りの「省スペース・短時間」という特性がマッチする業態を選びましょう。成功の鍵は、どの業態であっても「専門特化」と「効率的なオペレーション」です。
第5章 間借り飲食店の開業資金と月々の料金相場
「実際に間借りを始めるには、一体いくらかかるのか?」これは誰もが気になるポイントでしょう。この章では、開業に必要な初期費用から月々のランニングコストまで、具体的な数字を交えながらリアルな費用感をシミュレーションします。
5-1. 料金形態は3種類!固定制・売上歩合制・ハイブリッド制
間借りの賃料(利用料)の支払い方には、主に3つのパターンがあります。それぞれの特徴を理解し、自分のビジネスモデルに合った契約形態を選ぶことが重要です。
| 料金形態 | 概要 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|
| 固定制 | 毎月決まった額を支払う | 売上が伸びても支払額は一定で、利益を最大化しやすい | 売上がゼロでも支払い義務が発生する | 売上に自信がある、利益計画を立てやすい人 |
| 売上歩合制 | 売上の〇〇%を支払う | 売上が低い時の負担が少ない、リスクが低い | 売上が伸びると支払額も増え、利益が圧迫される | 初めてで売上予測が立たない、リスクを抑えたい人 |
| ハイブリッド制 | 最低保証賃料+売上歩合 | 固定制と歩合制の良いとこ取り | 料金計算がやや複雑になる | オーナー側がリスクヘッジしたい場合に多い |
月商50万円の場合の手残り比較
仮にあなたの店の月商が50万円、原材料費が15万円(30%)だったとします。
- 固定制(月10万円)の場合:50万 – 15万 – 10万 = 手残り25万円
- 売上歩合制(25%)の場合:50万 – 15万 – (50万×0.25) = 手残り22.5万円
このケースでは固定制の方が有利ですが、売上が20万円だった場合はどうでしょう。固定制の手残りは5万円ですが、歩合制なら10万円残ります。自分の売上予測とリスク許容度を天秤にかけて、慎重に選びましょう。
5-2. エリア・業態別に見る間借りの賃料相場
賃料は、当然ながらエリアや借りる時間帯によって大きく変動します。ここでは、一般的な相場感を掴むための目安を提示します。
| エリア | 時間帯 | 賃料相場(月額) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 都心部(渋谷・新宿など) | ランチ(週5日) | 15万円~30万円 | 家賃は高いが、集客力も高い。ハイリスク・ハイリターン。 |
| 準都心・地方都市 | ランチ(週5日) | 8万円~15万円 | 比較的コストを抑えられ、地域密着でファンを作りやすい。 |
| 都心部(渋谷・新宿など) | ディナー・バー(週5日) | 10万円~25万円 | 業態によるが、ランチよりはやや安価な傾向。 |
| 週末のみ(土日) | 終日 | 5万円~10万円 | 副業で始める人に人気。固定客を掴むことが重要。 |
5-3. 賃料以外にかかる初期費用と運転資金の内訳
「間借りは安い」と言っても、賃料以外にも準備すべき費用があります。見落としがちなコストをリストアップしましたので、自己資金を準備する際の参考にしてください。
| 費目 | 金額目安 | 概要 |
|---|---|---|
| 保証金・契約金 | 5万円~20万円 | 賃料の1~2ヶ月分が相場。契約終了時に返還される場合も。 |
| 許認可取得費用 | 3万円~5万円 | 食品衛生責任者の講習費や、営業許可申請の手数料など。 |
| 厨房備品・食器類 | 5万円~15万円 | 借りる店舗にない調理器具や、コンセプトに合った食器など。 |
| 食材仕入れ費 | 5万円~10万円 | 開業当初の数日分を見越して準備。 |
| 販促費 | 3万円~10万円 | ショップカード、チラシ、SNS広告費など。 |
| 当面の運転資金 | 10万円~20万円 | 売上が安定するまでの生活費や、不測の事態に備える資金。 |
| 合計 | 31万円~80万円 |
開業資金を考える上で、レジ周りの設備も重要です。最近ではお客様の利便性を高めるキャッシュレス決済の導入が不可欠になっています。個人事業主でも手軽に導入できるおすすめの決済端末や、手数料を抑える選び方を『個人事業主のキャッシュレス決済導入なら!絶対おすすめな端末5選と選び方を徹底解説!』で比較・解説しています。
【この章のチェックポイント】
費用計画は、楽観的ではなく悲観的に立てることが鉄則です。想定外の出費に備え、自己資金は多めに準備しておきましょう。
第6章 失敗しない!間借り飲食店開業までの7ステップ完全ガイド
ここからは、いよいよ実際に行動に移すための具体的な手順を7つのステップで解説します。この通りに進めていけば、誰でも着実に開業準備を進めることができます。各ステップでやるべきことを明確にし、一つずつクリアしていきましょう。
6-1. 【STEP1】コンセプト設計:誰に、何を、どう売るか
全ての土台となる、最も重要なステップです。ここで手を抜くと、後々の全てがブレてしまいます。「誰に」「何を」「どのように」提供して喜んでもらうのか、解像度高く具体化しましょう。
- ターゲットは?:
20代の女性?健康志向のビジネスマン?地域のファミリー層? - 提供する価値は?:
本格的な味?ボリューム?健康?非日常的な空間? - 他店との違いは?:
なぜお客様は、他の店ではなくあなたの店を選ぶのか?
- ターゲット:近隣で働く30代女性、一人ランチ
- 提供価値:野菜たっぷりで罪悪感のない、見た目もおしゃれな薬膳カレー
- 差別化:10種類以上のスパイスを使用。週替わりでデトックス効果のある副菜を提供。
6-2. 【STEP2】事業計画と資金調達:無理のない計画を立てる
STEP1で固めたコンセプトを、具体的な「数字」に落とし込む作業です。難しく考える必要はありません。エクセルなどで簡単な収支計画表を作成しましょう。
- 売上予測:客単価 × 席数 × 回転数 × 営業日数
- 費用計算:原材料費(売上の30%程度)、賃料、光熱費、販促費など
- 利益計画:売上 – 費用 = 利益
この計画を元に、自己資金で足りない分をどう調達するか検討します。親族から借りる、クラウドファンディングを利用する、日本政策金融公庫などの公的機関から融資を受ける、といった選択肢があります。
事業計画を立ててみたものの、自己資金だけでは少し心もとない、と感じる方もいるかもしれません。実は、自己資金が少なくても飲食店を開業する方法はあります。融資や補助金を活用するコツをまとめた『自己資金なしでも飲食店って開業できるの?融資・調達のコツや費用を抑える方法まで!』も、ぜひ参考にしてみてください。
6-3. 【STEP3】物件探し:理想のスペースを見つける方法
コンセプトに合う物件(スペース)を探します。探し方にはいくつかのチャネルがあります。
- 間借り専門マッチングサイト:最も効率的。「シェアレストラン」「軒先レストラン」などが有名。エリアや時間帯で検索でき、情報量も豊富。
- SNS:X(旧Twitter)やInstagramで「#間借り募集」「#間借りしたい」などのハッシュタグで探す、または自分で募集する。
- 直接交渉:理想的な雰囲気の店を見つけたら、勇気を出して直接オーナーに交渉してみる。熱意が伝われば、意外な道が開けることも。
6-4. 【STEP4】内見と条件交渉:確認必須のチェックリスト

- 【間借り物件 内見チェックリスト】
| カテゴリ | チェック項目 | 確認内容・メモ | チェック |
|---|---|---|---|
| 厨房設備 | コンロの口数と火力 | 十分な数か?火力の調整はスムーズか? | □ |
| 冷蔵・冷凍庫の容量 | 使える範囲はどこまでか?容量は十分か? | □ | |
| シンクの数とサイズ | 食材用・洗浄用など、用途を分けられるか? | □ | |
| 作業スペースの広さ | 調理や盛り付けに十分なスペースがあるか? | □ | |
| 換気扇・グリストラップ | 正常に作動するか?清掃状況はどうか? | □ | |
| インフラ | コンセントの数と位置 | 必要な場所に十分な数があるか? | □ |
| 電気容量(W/A) | 複数の機器を同時に使用できるか?(最重要) | □ | |
| ガスの種類と元栓の位置 | 都市ガスかプロパンか?緊急時に止められるか? | □ | |
| 水道(水圧・お湯) | 水圧は十分か?お湯はすぐに出るか? | □ | |
| 客席・共用部 | 客席数とレイアウト | 想定する客数を収容できるか? | □ |
| テーブル・椅子の状態 | ガタつきや破損はないか? | □ | |
| トイレの清掃状況 | お客様が快適に使える状態か?男女別か? | □ | |
| 空調設備 | 正常に作動するか?効き具合はどうか? | □ | |
| その他 | 利用可能な備品・食器 | どこまで借りられるか?(鍋、フライパン、皿など) | □ |
| ゴミの処理方法 | 事業ゴミの分別ルール、回収日、費用負担は? | □ | |
| 搬入・搬出経路 | 食材や機材を運び込むルートは確保できるか? | □ | |
| 周辺環境・近隣店舗 | 昼夜の人通り、近隣に競合はいるか? | □ | |
| 臭い・騒音のルール | 営業時に配慮すべきことはあるか? | □ |
6-5. 【STEP5】契約締結:契約書で確認すべき重要項目
条件交渉がまとまったら、いよいよ契約です。後々のトラブルを避けるため、必ず書面で契約を交わしましょう。特に以下の項目は、一言一句、納得できるまで確認してください。
- 契約期間と更新条件
- 賃料と支払い方法、光熱費の負担割合
- 利用可能な曜日と時間
- 利用可能な設備・備品の範囲
- 禁止事項(喫煙、大音量の音楽など)
- トラブル発生時の責任の所在(食中毒、火災、器物破損など)
- 原状回復の範囲と費用負担
- 解約条件(何ヶ月前に通知するか、違約金の有無など)
6-6. 【STEP6】許認可の取得と各種届出
物件が決まったら、並行して行政手続きを進めます。飲食店の営業には、保健所の「飲食店営業許可」が必須です。誰の名義で許可を取得するかは、オーナーと必ず協議してください。既存店の許可を承継できる場合もあれば、新たに自分の名義で取得し直す必要がある場合もあります。この詳細は、次の第7章で詳しく解説します。
保健所への事前相談の重要性
6-7. 【STEP7】開業準備:オペレーションと集客の設計
いよいよ最終準備です。限られた時間と設備で、いかに効率よく、お客様を満足させられるか。調理から提供、会計、片付けまでの一連の流れをシミュレーションし、無理のないオペレーションを構築します。
同時に、集客活動も本格化させましょう。オープン前からInstagramやXで店のコンセプトやメニュー、開業準備の様子を発信し続けることで、オープン日には「待ってました!」と駆けつけてくれるファンを作ることができます。
特に、低コストで始められるInstagramでの発信は、間借り飲食店の集客に欠かせません。オープン前からファンを作るための効果的な投稿内容や運用のコツについて、『【完全版】飲食店のインスタグラムの活用術を大公開!集客に効果的な運用方法を解説!』で詳しく解説しています。
【この章のチェックポイント】
開業準備は、一つ一つのステップを着実に踏むことが成功への近道です。特にコンセプト設計と事業計画は、全ての行動の土台となるため、時間をかけてじっくりと取り組みましょう。
第7章 間借り開業に必要な資格と手続き
無事に店舗が決まっても、すぐに営業を始められるわけではありません。飲食店を開業するには、法律で定められたいくつかの資格取得や手続きが必要です。特に保健所や税務署への届出は、知らなかったでは済まされない重要なもの。ここでしっかりと確認し、漏れなく準備を進めましょう。
7-1. 食品営業許可
これは、飲食店を営業するために絶対に必要な許可です。管轄の保健所に申請し、施設の衛生基準が満たされているかどうかの検査を受け、合格することで交付されます。
間借りの場合、最も重要な論点が「誰の名義で許可を取得するか」です。これには主に2つのパターンがあります。
- オーナー(貸主)の許可を承継するケース:既存店の営業許可を、間借り営業者も利用する形。この場合、新たな申請は不要ですが、食中毒などが発生した際の責任の所在が曖昧になりがちです。
- 間借り営業者(借主)が新規で取得するケース:自分の名前で新たに営業許可を取得する形。手続きの手間はかかりますが、責任の所在が明確になります。
自治体による違いと注意点
この営業許可の扱いについては、全国で統一された見解がなく、自治体(保健所)によって判断が大きく異なります。「オーナーの許可でOK」とする保健所もあれば、「営業者が異なるため、新規取得が必須」とする保健所もあります。
7-2. 食品衛生責任者
各店舗に必ず1名以上「食品衛生責任者」を置くことが、食品衛生法で義務付けられています。これは、店舗の衛生管理を担う責任者のことです。
調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている方は、申請するだけで資格者証が交付されます。これらの資格がない場合でも、各都道府県が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば、誰でも取得できます。
7-3. 菓子製造業許可
もしあなたが、店舗で製造したクッキーやケーキ、パンなどをテイクアウト用に包装して販売したい場合、「飲食店営業許可」とは別に「菓子製造業許可」が必要になることがあります。
この許可は、飲食店営業許可よりも施設の基準(例:作業場が壁などで区画されていることなど)が厳しく設定されているため、間借り先の施設がその基準を満たしているか、事前に保健所へ確認が必須です。
7-4. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜0時から日の出までの時間帯に、お酒をメインに提供する営業(バーなど)を行う場合は、店舗の所在地を管轄する警察署へこの届出書を提出する必要があります。
注意点として、店舗の場所が「住居専用地域」など、深夜営業が禁止されている用途地域に指定されている場合は、この届出は受理されません。バーの間借りを検討している場合は、契約前に必ず警察署の担当窓口で確認しましょう。
7-5. 開業届・青色申告承認申請書
個人で事業を始める場合、事業開始から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出する義務があります。
そして、開業届と必ずセットで提出したいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。これを提出することで、確定申告の際に「青色申告」が可能になり、最大65万円の所得控除をはじめとする、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。節税の第一歩として、絶対に忘れないようにしましょう。
間借り開業 許認可・届出チェックリスト
自分の計画に必要な手続きはどれか、チェックを入れて確認しましょう。
| 資格・手続き名 | このような場合に必要 | チェック |
|---|---|---|
| 食品営業許可 | 飲食店を営業する場合(必須) | □ |
| 食品衛生責任者 | 飲食店を営業する場合(必須) | □ |
| 菓子製造業許可 | 製造した菓子をテイクアウト販売する場合 | □ |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜0時以降に酒類を提供する場合 | □ |
| 開業届 | 事業を開始した場合(必須) | □ |
| 青色申告承認申請書 | 税金の優遇を受けたい場合 | □ |
| 防火管理者選任届 | 店舗の収容人数が30人以上の場合 | □ |
開業届とセットで提出したいのが「青色申告承認申請書」です。なぜなら、最大65万円の所得控除など、大きな節税メリットがあるからです。『【自営業・個人事業主】確定申告の完全攻略ガイド!青色申告で節税する7ステップを解説!』で、初めての方でも分かりやすいよう、青色申告の具体的な手順を7つのステップで解説しています。
【この章のチェックポイント】
許認可や届出は、後回しにせず、物件契約と並行して早めに動き出すことが重要です。特に保健所や警察署への「事前相談」は、無駄な手戻りを防ぐために必ず行いましょう。
第8章 トラブルを未然に防ぐ4つの重要注意点

間借り営業は、オーナーとの信頼関係の上に成り立つビジネスです。ささいな認識のズレが、大きなトラブルに発展することも少なくありません。ここでは、よくあるトラブル事例を元に、気持ちよく事業を続けるために守るべき4つの注意点を解説します。
8-1. 契約内容は書面で明確にする
最も重要で、全ての基本となるのが「契約書の締結」です。親しい間柄であっても、「言った」「言わない」のトラブルを避けるため、口約束は絶対にやめましょう。賃料、利用時間、光熱費の負担割合、利用可能な設備、禁止事項、解約条件など、些細なことでも必ず書面に落とし込み、双方が署名・捺印して保管してください。
弁護士が監修した契約書のテンプレートをインターネットで探し、それをベースに自分たちの条件に合わせてカスタマイズするのがおすすめです。双方が納得できるまで、内容を丁寧にすり合わせましょう。
トラブル事例:光熱費の負担
8-2. 衛生管理の徹底と保険への加入
万が一、自分の店から食中毒が発生したり、火事を起こしてしまったりした場合、店の信用失墜はもちろん、オーナーの店舗にも計り知れない損害を与えてしまいます。衛生管理の徹底は、間借り営業者の最低限の義務です。 加えて、リスクに備えるための保険加入は必須と考えましょう。特に、食中毒や異物混入などでお客様に損害を与えた場合に備える「PL保険(生産物賠償責任保険)」には必ず加入してください。
オーナーが加入している店舗の火災保険や施設賠償責任保険の内容を確認させてもらいましょう。その上で、補償が不足する部分を自分の保険でカバーする形を取ると、無駄なくリスクに備えられます。
衛生管理を徹底していても、お客様からのクレームがゼロとは限りません。万が一の事態に備え、お客様の信頼を損なわないための正しいクレーム対応の基本を学んでおくことも重要です。『飲食店の理想のクレーム対応を解説!対応方法の基本から謝罪の注意点まで!』で、具体的な対応方法と謝罪のポイントを解説しています。
8-3. オーナーとの良好なコミュニケーション
間借り営業の成功は、オーナーとの良好な関係なくしてあり得ません。オーナーは単なる大家ではなく、あなたの事業を応援してくれる一番のパートナーになり得る存在です。日々の挨拶はもちろん、営業に関する報告・連絡・相談(ホウ・レン・ソウ)を徹底しましょう。
成功オーナーがやっている習慣
8-4. 原状回復のルールを事前に確認する
契約終了時に最もトラブルになりやすいのが「原状回復」の問題です。「どこまで清掃して返すか」「傷や汚れの修繕費用は誰が負担するか」といった点で、認識の齟齬が生まれやすいのです。
契約時に、店舗の隅々まで写真を撮っておきましょう。そして、「退去時は、この写真の状態に戻す」という合意をオーナーと結び、その旨を契約書にも明記しておくのが最も確実です。特に厨房の油汚れや排水溝の清掃範囲は、具体的に確認しておくべきポイントです。
【この章のチェックポイント】
トラブルの多くは、事前の確認不足とコミュニケーション不足から生まれます。「これくらい大丈夫だろう」という安易な思い込みを捨て、常にオーナーへの敬意と感謝の気持ちを忘れないことが、長く事業を続ける秘訣です。
第9章 夢への第一歩、まずは小さな挑戦から始めよう
ここまで、間借り飲食店を開業するためのノウハウを網羅的に解説してきました。多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点もあり、決して簡単な道のりではないと感じたかもしれません。
しかし、思い出してください。間借り営業の最大の魅力は、圧倒的な低リスクで「夢への一歩」を踏み出せることです。何百万円もの借金を背負うリスクを冒すことなく、自分の料理やサービスが世の中に通用するのかを試せる、またとない機会なのです。
この記事を読んで、「自分にもできるかもしれない」と少しでも心が動いたなら、ぜひ行動に移してみてください。まずは週末だけの営業から、あるいはランチタイムだけの挑戦からで構いません。完璧な計画を立てることに時間を費やすよりも、まずはお客様の前に立ち、一皿を提供してみる。その小さな成功体験と、お客様からの「美味しかったよ」の一言が、あなたを次のステージへと導く、何よりの原動力となるはずです。
この記事が、あなたの夢の扉を開く、ささやかな鍵となることを心から願っています。