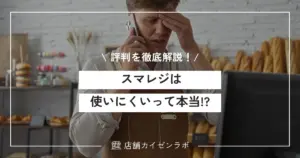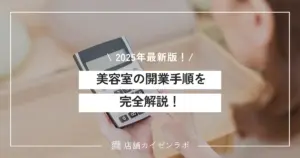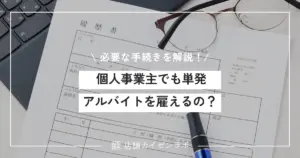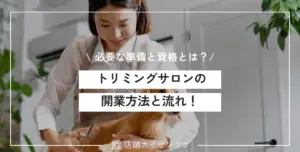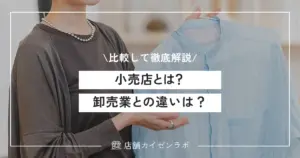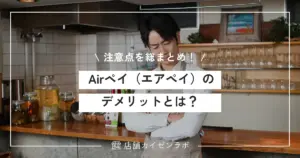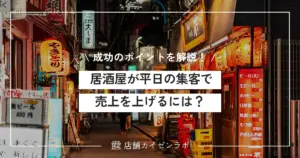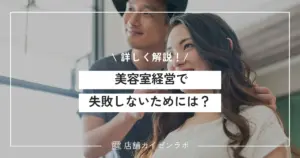お客さんが来ないお店の問題はどこにある?
「料理の味には自信があるのに、なぜかお客様が増えない…」 「SNSも頑張っているはずなのに、客足が遠のいていく…」
店舗を経営していると、そんな出口の見えない悩みに突き当たることがあります。頑張っているのに結果が出ない時ほど、辛いものはありません。
しかし、ご安心ください。お客様が来ないのには、必ず明確な理由があります。そして、その原因は、突き詰めるとたった2種類にしか分けられません。
客が来ない原因はたった”2種類”に分けられる
あなたの店が抱える問題は、お店の「外」にあるのでしょうか? それとも「中」にあるのでしょうか?
- 原因①:店外要因(そもそも、店にたどり着けていない)
- これは、お店の存在や魅力が、まだ見ぬお客様に正しく伝わっていない状態です。「知名度が低い」「ネット上の情報が少ない」「立地が悪いと思い込んでいる」といった問題がこれにあたります。
- 原因②:店内要因(一度来ても、満足せず帰ってしまう)
- これは、せっかく来店してくれたお客様を満足させられず、次回の来店に繋げられていない状態です。「清潔感がない」「接客が悪い」「商品の価値が伝わっていない」「リピートしたくなる仕組みがない」といった問題がこれにあたります。
【改善の鉄則】まず改善すべきは「店内要因」から
ここで非常に重要なのが、改善には「優先順位」があるということです。 もし、あなたの店に「店内要因」の問題がある場合、焦って広告を打ったり、新規集客に力を入れたりしてはいけません。
なぜなら、それは穴の空いたバケツに、必死に水を注ぎ続けるようなものだからです。 せっかく新規のお客様が来ても、店内で不満を感じてしまえば、二度とリピートしてくれないばかりか、悪い口コミが広がる原因にすらなりかねません。
まずは、あなたの店が「一度来てくれたお客様を、確実に満足させられる状態」になっているかを確認する。 これが、V字回復への、最も確実で、最も早い近道なのです。
この記事では、まず第1章で、あなたの店の問題が「店外要因」と「店内要因」のどちらに根ざしているのかを診断します。そして、その原因に応じた正しい解決策を、具体的な手順と共に徹底的に解説していきます。
もう一人で悩む必要はありません。さあ、一緒に問題の根本原因を見つけ出し、お客様で賑わうお店を取り戻しましょう。
第1章 客が来ない店に共通する8つの特徴と原因を診断

導入でお伝えした通り、お客様が来ない原因は「店外」と「店内」の2つに大別できます。この章では、より具体的に、客足が遠のいているお店に共通する8つの特徴をリストアップしました。
ご自身の店舗がどの項目に当てはまるか、ぜひ自己診断しながら読み進めてみてください。問題の根本原因がどこにあるのか、きっと見えてくるはずです。
【店外要因】そもそもお客様が店にたどり着けていない特徴
まず、お店の魅力以前に、その存在や価値がお客様に「伝わっていない」ケースです。どんなに良い商品やサービスがあっても、知られなければないのと同じです。
1-1.「店の知名度」が低い
多くの客が来ない店がまずぶつかる壁は「そもそも店の存在を知られていない」という問題です。特に飲食店やバーのように“通りがかったら入る”といった偶発的な来店が期待しにくいジャンルでは、認知度が足りないと顧客が集まりにくくなります。
「味は良いのに近所の住民ですら知らない」というケースは意外と多く、SNSやポータルサイトでの情報発信を怠ると、人々の比較リストにすら入れてもらえません。お店がオープンしても、チラシや地域メディアなどで集客の露出を高めていない場合、新規客が常連客に育つまでに時間がかかり、立地が良くても“空気のような存在”となってしまいがちです。
1-2.「店の情報」が不十分
お客様は来店前にネット検索やSNSの口コミを活用して、店を比較検討するのが当たり前の時代です。メニューや価格、場所、営業時間など基本的な情報が見つからないと、他店のほうが安心という理由でそちらに流れてしまいます。特に飲食店では「どんな料理があるか」「客単価はどれくらいか」が分からないと足が向きにくいですよね。
SNSの効果的な使い分けについては、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事が参考になります
地域特化の情報サイトやGoogleビジネスプロフィールへの登録・写真の充実など、細部まで自店の情報を提供しておくことが決め手となります。また、イベントや期間限定メニューなどタイムリーな情報が発信できていないと、せっかくの話題作りも埋もれてしまいがちなので要注意です。
1-3.「立地条件が悪い」を言い訳にWeb集客していない
立地が悪い店舗は、どうしても一見客が来にくいという悩みを抱えがちです。「駅から遠い」「駐車場がない」「人通りが少ない」などは、事実としてハンデにはなるでしょう。しかし、立地条件を嘆くだけでは解決しません。

そもそも客が来ない原因は立地のせいだけではないケースも多いです。MEO(Googleビジネスプロフィール)を活用して周辺住民にアピールしたり、わざわざ行きたくなるような独自サービスを打ち出したりするなど、対策は豊富にあります。店舗情報が少ない、SNSに投稿していない、といった認知不足を改善すれば「隠れ家感」がむしろ強みに変わることもあります。立地条件を理由にする前に、まずは改善できる施策を洗い出すことが大切です。
【店内要因】一度来ても次がない店の特徴
次に、せっかくお客様が来店してくれたにも関わらず、満足させられずに「もう二度と来ない」と思わせてしまっているケースです。これが最も深刻な問題です。
1-4.「店舗やスタッフの清潔感」が欠けている
お客様は価格や味だけでなく”居心地”にも敏感です。特に料理を扱う飲食店の場合、トイレやテーブル、スタッフの服装が不潔な印象を与えると一瞬でイメージダウンにつながります。小料理バーなどではカウンター席の隅々までチェックが入りやすく、「清潔じゃない」と思われたら口コミですぐに悪評が広まってしまうでしょう。
ネット上の評価サイトやSNSでは「店内が汚れていた」という口コミがネガティブ拡散されやすく、次の来店意欲を大きく削いでしまいます。当たり前のようで当たり前にできていない“清潔感”の徹底こそが、顧客を失わない基本中の基本といえるでしょう。
悪い口コミへの対応については『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』をご覧ください
1-5.「接客態度」が悪い
無愛想な態度や横柄なスタッフの対応は、一度でも経験すると「二度と行きたくない」という感情を呼び起こします。店舗の来店数が伸び悩む場合、立地や価格だけでなく“接客”を見直す必要があります。お客様との直接的なコミュニケーションが多いぶん、ちょっとした言動がSNSで拡散されるリスクも高いです。

たとえば、バーで「常連客には愛想が良いのに、一見さんを雑にあしらう」といったケースは特に危険です。口コミサイトで低評価が付けば、新規来店が大きく減少してしまいます。良いサービスも悪いサービスもデジタル上で拡散される時代ですから、接客の質をおろそかにすると売上に直結するのは言うまでもありません。
好印象な接客に改善したい方は、『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』の記事を参考にどうぞ。
1-6.「技術・サービス」の質が低い
美容室なら技術力、カフェやレストランなら料理の安定感など、サービスの品質そのものが低いとリピーター獲得は難しくなります。開店直後には新規客が興味本位で訪れるかもしれませんが、技術や味が不十分だと「もういいや」という印象を持たれてしまい、再来店が見込めなくなるのです。
また、実際には特定スタッフの離職や仕入れ先変更などでサービス品質が落ちることもあります。そこに気づかず従来のまま運営していると、「最近質が下がった」という口コミが広まり、特に常連客の離脱が加速してしまいます。サービスの質を定期的に確認し、何か問題があれば早急に手を打つのが重要です。
1-7.「リピーター育成」の仕組みがない

店舗運営では「新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍」と言われるほど、リピーターの存在が重要です。しかし、リピートを意識した特典や会員制プログラム、スタッフからの声かけといった仕組みが欠けていると、せっかく来店したお客様も“一見さん”で終わってしまいがちです。
たとえば、ポイントカードやLINE公式アカウントによるクーポン配信は、定番でありながら効果的な施策。何度も足を運んでくれる常連客を優遇すると、自然と周囲にも良い評判が伝わります。リピーター獲得の取り組みを疎かにせず、地道に繰り返すことが店舗の長寿命化につながるのです。

1-8. 他店の悪口など「ネガティブな空気」が蔓延している
集客競争が激しいと、つい「ライバル店は料理の質が低い」「あそこは接客が悪い」などと言いたくなる場面もあるかもしれません。しかしお客様の多くは、他店を下げる発言を聞くと「ここもどうせ同レベルかも」とか「スタッフの雰囲気が悪そう」と感じてしまいます。結果として、SNSの口コミやレビューサイトで“感じの悪い店”のイメージが定着してしまうのです。
飲食店や美容サロンなど、人対人のコミュニケーションが重視される業態では尚更、ネガティブ発言は控えたほうが無難です。他店と比較するなら、自店の強みをポジティブに伝えるほうが、長期的にはイメージアップや常連客づくりにつながります。
第2章 客が来ない店の「本当の原因」を特定し、改善する方法

第1章の診断で、あなたの店の課題が「店外要因」と「店内要因」のどちらにありそうか、大まかに見当がついたかもしれません。しかし、「おそらくこれが原因だろう」という思い込みだけで改善策を打つのは危険です。この章では、より客観的に、そして顧客の視点に立って「本当の原因」を特定するための具体的な方法を解説します。
2-1. 店舗分析にはカスタマージャーニーが効く
「価格が高いからだ」「立地が悪いからだ」など、感覚的に原因を捉えてしまうと、的外れな施策に時間とお金を浪費しかねません。そこでおすすめなのが、顧客の行動プロセスを可視化する「カスタマージャーニー」というフレームワークです。
これは、お客様があなたのお店を知ってから、実際に来店し、リピーターになるまでの一連の「旅(ジャーニー)」を地図のように描き出すものです。
飲食店のカスタマージャーニーの例
- 認知: SNSや知人の口コミで、お店の存在を初めて知る。
- 興味・関心: 「どんなお店だろう?」と興味を持つ。
- 情報収集・比較: Googleマップやグルメサイトで、メニューや価格、他店の口コミなどを調べる。
- 来店・体験: 実際に来店し、料理や接客を体験する。
- 再来店・リピート: 満足すれば、また来ようと思う。不満があれば、二度と来ない。
このように顧客の行動を細かく分解し、「自店は、この旅のどの段階でお客様を取りこぼしているのか?」を検証します。
例えば、SNSで知られても(認知)、Googleマップ上の情報が少なくて比較検討で負けているのか(情報収集・比較)。あるいは、一度は来店してくれても(来店・体験)、接客が悪くてリピートに繋がっていないのか(再来店・リピート)。原因を具体的に洗い出すことで、打つべき対策の精度が格段に上がります。
筆者実践談
2-2. お客様が本当に知りたい情報を理解する
カスタマージャーニーの中でも、特に重要なのが「情報収集・比較」の段階です。お客様は来店前に、一体どんな情報を重視しているのでしょうか。
株式会社TableCheckが2023年に行った調査によると、飲食店をインターネットで探す際に最も参考にされているのは「Googleマップ」で、その割合は79.3%にものぼります。これは、グルメサイト(65.3%)や個人のブログ・SNS(38.1%)を大きく上回る数字です。
このデータは、Googleビジネスプロフィール(Googleマップ上に表示される店舗情報)を充実させることが、いかに重要かを示しています。
「何を食べられるか」「いつ営業しているか」「価格は妥当か」といった基本情報はもちろん、「クレジットカードは使えるか」「禁煙か喫煙か」「お店の雰囲気はどうか」といった、より詳細な情報が求められています。
お客様が知りたい情報を、最も見られている場所(Googleマップ)で、写真や動画を交えながら分かりやすく提供すること。それが、比較検討の段階で競合に負けないための、そしてお店の魅力を正確に伝えるための、最も効果的な第一歩なのです。
第3章. 「店外要因」を解決する!新規顧客の集客方法7選

第1章の診断で、あなたの店の課題が「店外要因」、つまり「そもそもお店の存在や魅力がお客様に伝わっていない」ことにあると分かった場合、まず取り組むべきは新規顧客に向けた集客施策です。
どんなに素晴らしい商品やサービスも、知られなければ始まりません。この章では、お店の認知度を高め、お客様が来店する「きっかけ」を作るための、すぐに実践できる7つの方法を解説します。
【Point】オンラインとオフラインの二刀流で、認知度を最大化する
集客と聞くと、SNSなどのオンライン施策ばかりに目が行きがちですが、店舗ビジネスにおいては、地域住民に直接アプローチできるオフライン施策も同様に重要です。両方を組み合わせる「二刀流」で、取りこぼしなくお客様にアプローチしましょう。
3-1. チラシを活用して地域住民へ直接アプローチ
デジタル全盛の時代でも、地元の方に直接リーチできるチラシは、依然として強力な集客ツールです。特に店舗周辺の住宅街に向けてポスティングすることで、「近所にこんなお店があったのか」と認知度を効率的に上げることができます。割引クーポンを付けたり、地域イベントの告知を兼ねたりすれば、来店動機をさらに強化できるでしょう。
デザインはシンプルかつ目を引くように。料理の写真や分かりやすい地図、お店のSNSアカウントに繋がるQRコードなどを載せておけば、オンラインへの誘導も可能です。
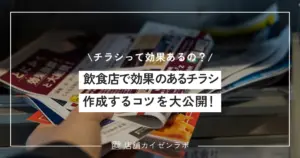
ポスティングの具体的な方法と成功事例は『飲食店のポスティング成功完全ガイド!最も集客効果が高い方法を大公開!』で解説しています
3-2. ホームページ&ブログで信頼感を高める
公式ホームページやブログは、24時間365日働き続ける、あなたのお店の「インターネット上の本店」です。SNSだけでは伝えきれない、お店のこだわりやコンセプト、スタッフの人柄などを丁寧に発信することで、「ここは信頼できるお店だ」という安心感をお客様に与えることができます。
また、ブログで地域の情報を絡めた記事などを定期的に更新すれば、検索エンジンからの評価も高まり、「地域名+業種」といったキーワードで検索した潜在顧客に見つけてもらいやすくなります。
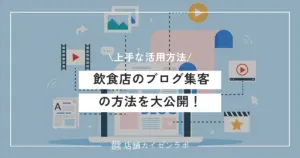
3-3. SNSを使ってストーリーや季節感を演出する

InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSは、写真や動画で、お店の魅力をリアルタイムに伝えるのに最適なツールです。特に若年層は、SNSで「映えそう」「雰囲気が良さそう」と感じれば、それが来店の決め手になることも少なくありません。
単に料理の写真を載せるだけでなく、限定メニューの仕込み風景や、常連客との心温まるやり取りなど、“ストーリー”を感じさせる内容を投稿するのが効果的です。お店の世界観そのものを発信していく、という意識で活用しましょう。
特にInstagramは飲食店との投稿相性が良いとされています。詳しい運用方法については『【完全版】飲食店のインスタグラムの活用術を大公開!集客に効果的な運用方法を解説!』を確認ください。
3-4. MEO(Googleビジネスプロフィール)で地図検索対策
第2章でも触れた通り、今やMEO対策は地域密着型ビジネスの生命線です。「地域名+業種」(例:渋谷 カフェ)で検索をした際に、Googleマップ上で自店を上位表示させるための施策は必須と言えます。
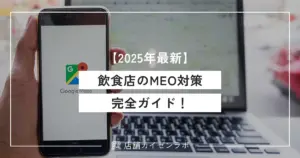
実施すべきことは、主に以下の3つです。
口コミの管理と返信
寄せられた口コミには、感謝の気持ちと共に丁寧に返信します。これにより、お客様とのコミュニケーションを大切にする姿勢が伝わり、お店の信頼性が高まります。Googleからもアクティブな店舗と判断されやすくなります。
店舗情報の正確な入力
店名、住所、電話番号、営業時間を正確に登録します。
写真の充実
外観、内観、メニュー、スタッフなど、お客様が知りたいと思う写真を豊富にアップロードします。
3-5. SEOを通じたホームページへの集客強化
SEO(検索エンジン最適化)は、「〇〇市 バー おすすめ」といった、より具体的なニーズを持ったお客様をホームページに呼び込むための施策です。MEOが「地図上での発見」を目的とするなら、SEOは「より深い情報提供による納得感の醸成」を目的とします。
競合が多いエリアでも、例えば「〇〇市 一人飲みに最適なバー」のように、お店の強みをキーワードに盛り込むことで、ニッチなニーズを持つ顧客層に響かせることができます。効果が出るまで時間はかかりますが、一度上位表示されれば、安定的に質の高いお客様を呼び込める強力な資産となります。
SEOを活用したホームページ集客については『【完全版】飲食店のSEO対策攻略ガイド!店舗への集客効果や具体的な施策まで徹底解説!』にまとめています。
3-6. 看板・のぼりで「通りすがり客」を逃さない
Web上の施策と同時に、お店の前を通る人々へのアピールも忘れてはいけません。魅力的な看板や、動きのあるのぼりは、「このお店、何だろう?」と興味を引くための重要なフックです。
「本日のランチ」「ハッピーアワー実施中!」といった、今この瞬間の“お得”や“限定”が分かる情報を提示することで、通りすがり客の「ちょっと寄ってみようかな」という気持ちを後押しできます。

3-7. 広告を適切に使ってリーチを拡大する
地域のフリーペーパーや、Google広告、SNS広告などの有料媒体を利用すれば、ターゲットとする顧客層に、短期間で集中的に情報を届けることができます。
ただし、広告はあくまで「認知拡大のブースター」です。やみくもに出稿するのではなく、「新規オープンキャンペーンの告知」「季節限定イベントの集客」など、目的を明確にすることが重要です。投資対効果を常に意識し、少額から試しながら、最も反応の良い媒体や訴求内容を見極めていきましょう。
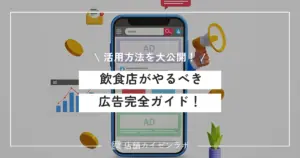
ただし、広告費には上限があるため、投資対効果(ROI)をしっかり管理する必要があります。数値データを検証しながら、反応が低い場合は訴求内容を変えたり、ターゲティングを細かく絞ったりして最適化を図りましょう。広告と先述のチラシやSNS運用を組み合わせれば、認知度アップと固定客獲得を同時に目指せます。
飲食店のWEBマーケティングを網羅的に知りたい方は『飲食店のWEB集客方法完全ガイド!効果的なマーケティング施策で店舗売上を増加させよう!』がおすすめです。
第4章 「店内要因」を解決する!リピーターを生み出す方法

第1章の診断で、あなたの店の課題が「店内要因」、つまり「せっかく来店してくれたお客様を満足させられず、リピートに繋げられていない」ことにあると分かった場合、どんなに新規集客を頑張っても、それは穴の空いたバケツに水を注ぐのと同じです。
この章では、その「穴」を塞ぎ、お客様が「また来たい!」と思ってくれるお店になるための、リピーター育成の具体的な方法を解説します。
【Point】なぜリピーターが重要?新規獲得コストは5倍かかる
マーケティングの世界には「1:5の法則」という有名な法則があります。これは、「新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかる」というものです。リピーターは、安定した売上をもたらしてくれるだけでなく、良い口コミを広めてくれる最高の宣伝パーソンでもあります。だからこそ、まず「店内」の改善に注力することが、経営安定への一番の近道なのです。
4-1. 「常連客が離れた」サインを見逃さないチェックポイント
「最近、あのお客様を見かけないな…」と感じたら、それは危険信号です。常連客が離れる際には、必ず何らかの原因があります。そのサインを見逃さず、迅速に対処することが重要です。
- 最後の来店からどれくらい経過しているか?
- POSデータや予約台帳の履歴をもとに「3ヶ月ご来店がなければ危険サイン」のように、自店なりの基準を設けましょう。離れてからの期間が短いほど、呼び戻せる可能性は高まります。
- 常連客の“お決まり商品”が無くなっていないか?
- いつも頼んでいたメニューや、愛用していたサービスが突然廃止されたのをきっかけに来なくなることもあります。レストランなら「お気に入りのデザートがメニュー落ちしていた」という理由でリピーターが離れるケースは意外と多いです。
- スタッフが変わってサービスの質が変わった?
- 人事異動やスタッフの離職により、接客の雰囲気が変わることも常連客が離れる大きな原因です。特に美容室やバーなど“担当者”によって体験価値が左右される業種は要注意。スタッフ間で顧客情報の引き継ぎを徹底することが求められます。
4-2. DMやLINE公式アカウントで「もう一度来店」を後押し
お客様が来なくなった理由が推測できても、ただ待っているだけでは戻ってきてはくれません。お店側から「あなたのことを覚えていますよ」というメッセージを送ることが、再来店の強力なきっかけになります。
- DM(ダイレクトメール)は、特別感を演出できる
- 手間はかかりますが、手書きのメッセージを添えたハガキなどは、お客様の心に響きます。「〇〇様、お変わりありませんか?新しいメニューの試食会をご用意しました」といったパーソナルな呼びかけは、デジタルにはない温かみと特別感を演出できます。
- LINE公式アカウントなら、手軽にアプローチできる
- スマートフォンで簡単にクーポンやメッセージを届けられるのがLINEの強みです。「お久しぶりです!〇〇様限定でドリンク1杯無料クーポンをお届けします」といった形で、再来店のハードルを下げてあげましょう。タイミング良く情報が届けば、「そういえば、また行ってみようかな」と思い出してもらえる可能性が高まります。
スタンプカードの運用でリピーター率を上げる方法は『飲食店はスタンプカードを導入すべき?具体的な効果とリピート顧客を作るための活用方法を徹底解説!』です。
4-3. イベントや限定特典で“もう一度行きたい”気持ちを刺激
お客様がお店から足が遠のく理由の一つに、「飽き」や「マンネリ」があります。常に新しい刺激や楽しみを提供し、「また行きたい」と思わせる「再訪理由」を意図的に作り出すことが大切です。
- 限定メニューやコラボ企画
- 「今しか食べられない」「ここでしか体験できない」という限定性は、強力な魅力です。地元の人気店とのコラボスイーツや、季節ごとの特別ディナーコースなど、新鮮な話題を提供し続けましょう。
- 記念日や誕生日を狙ったサプライズ
- お客様の誕生日や来店記念日に合わせて、特別なメッセージや特典をお届けするのも非常に効果的です。「自分のことを覚えていてくれた」という喜びは、お店への強い愛着(ロイヤルティ)に繋がります。「大切な日は、あのお店で過ごしたい」と思ってもらえる関係性を目指しましょう。
顧客の声を集めて再来店につなげる方法は『飲食店がアンケートを活用して顧客満足度を上げる方法!必要な項目と質問例を大公開!』で解説しています
第5章. 客が来ない店から人気店になった3つの大逆転成功事例

5-1. 紹介カードで新規顧客を拡大した成功例
客が来ない店から脱却したある美容室オーナーが実践したのが「既存顧客×友人紹介カード」の仕組みでした。内容は「カードを渡した新規さんが割引を受けられるだけでなく、紹介した常連客にも次回の割引特典がつく」というWin-Winな制度です。
- 仕組みのポイント
- カードにはお店のSNSやLINE公式アカウントのQRコードも掲載し、オンラインでの拡散を促す。
- 「紹介で来店した人」と「紹介した常連客」の両者にメリットがあるため、積極的に友人を誘ってもらいやすい。
- カードにはお店のSNSやLINE公式アカウントのQRコードも掲載し、オンラインでの拡散を促す。
成果:リピーター&新規顧客が同時に増えた
5-2. リピート率向上で売上が約10倍に伸びたサロンの事例
客が来ない店の状態だったあるエステサロンでは「新規客に限れば広告で順調に集まるが、定着率が低い」という課題を抱えていました。そこで取り入れたのが「来店1回目から3回目までのステップアップ特典」と「カルテの徹底管理」です。
段階的特典の内容
1回目:通常価格を10%オフ+次回予約でフェイシャルオプション無料
2回目:コース料金15%オフ+友人紹介カード進呈
3回目:VIPカード発行で以降ずっと5%オフ
さらに、来店後には肌の状態や施術の感想などをカルテに詳細に記録し、次回訪問時に「前回より肌の乾燥が軽減しているので、今回は保湿メインでアプローチしましょう」といった提案を徹底。
実際の成果
5-3. チラシとネット集客を組み合わせた効果倍増の例
客が来ない店だったある焼き鳥店が実施した施策は、近隣住民向けのポスティングチラシとGoogle広告(エリアターゲティング)を同時に使った手法です。チラシでは「週末限定クーポン」を大きく打ち出すのが特徴で、同じデザインをオンライン広告にも展開。半径3km以内のユーザーがスマホで検索した際に「週末限定クーポン」のネット広告が表示されるよう調整しました。
結果:認知度×口コミの相乗効果
リピーターを増やす施策については『飲食店におすすめな最強集客ツール25選!新規やリピーターを来店に繋げる効果的な活用方法!』の記事でまとめています。
第6章. 不人気で客が来ない店でよくある疑問6選

6-1. Q1:宣伝しても来ないのは商品のせい?
A:商品自体に魅力が足りない可能性もありますが、宣伝経路や店舗イメージ、接客など他要因で来店ハードルが上がることも。まず原因を多角的に分析し、商品の強みやサービス全体を見直すのが重要です。口コミをチェックし、顧客ニーズを検証すると改善が見えます。
6-2. Q2:うちの店は立地が悪い。集客は諦めるしかない?
A:立地条件が悪くても、コンセプトやSNSの活用次第で十分に集客を狙えます。駅から遠いなら“隠れ家”をアピールし、送迎や看板で迷わない工夫を施す方法も。顧客が「わざわざ行きたい」と思う独自性を磨けば、立地のハンデはカバーできるでしょう。口コミ、メディア露出を継続すれば十分に勝負できます!
6-3. Q3:お客からの口コミを増やすコツは?
A:口コミは自然に広がる仕掛けを作るのが重要。SNS映えする料理や店内装飾、写真OKのフォトスポットなど“シェアしたい”要素を用意し、お客さまが楽しく投稿できる環境を整えましょう。投稿画面提示で特典を付与すると、口コミ数増加に繋がりやすい特徴があります。顧客投稿リポストで盛り上がり促すのも有効です。
6-4. Q4:飲食店の店舗スタッフをどう教育すればいい?
A:スタッフ教育はマニュアルだけでなく、顧客視点の“気づき”を促す仕組みづくりが鍵です。朝礼やロールプレイングで接客対応を共有し、実際のクレーム事例を元に改善策を議論すれば、臨機応変な応対力が身につきます。定期チェック大切です。
スタッフの教育方法については『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』にまとまっています。
6-5. Q5:飲食店のSEO対策って本当に効果があるの?
A:SEO対策は中長期で自然検索からの集客を増やす施策です。キーワード選定やコンテンツの質を高めることで“地域名+業種”検索などに上位表示され、認知拡大が期待できます。即効性は低めですが、一度成果が出れば安定的に新規客を呼び込む力をもっているのが特徴です。定期的な見直しも不可欠ですよね!!
6-6. Q6:スタッフのモチベーションが売上に影響するの?
A:スタッフのモチベーションは接客態度やサービス品質に直結し、来店客の満足度やリピート率を左右します。スタッフがやりがいを感じ働くと雰囲気が良くなり、口コミ評価も高まりやすいです。定期的な面談や表彰制度などの仕組みを整えれば、売上アップに繋がる可能性が高まります。
第7章. 客が来ない店の特徴を理解して人気店を目指そう!
客が来ない店の特徴には、情報不足や接客態度、立地条件など様々な課題が潜んでいます。本記事では新規客の獲得から常連客の再来店施策、SNSや口コミの活用、スタッフ教育に至るまで幅広い視点で問題を解決する方法を紹介しました。短期的な広告頼みではなく、リピーター育成や定期的な改善を組み合わせることで、安定的な売上アップを狙えます。さらに、スタッフと目標を共有し、チーム全体で店づくりを続ける姿勢こそが“行列ができる店”への近道です。取り組みを継続すれば、必ず次のステップが見えてくるでしょう。
接客や立地など個別要素だけでなく、情報発信やスタッフ満足度も含めた総合的な視点が、成功への近道と言えます。客が来ない店の中には一時的に話題になっても定着しない店がある一方で、地道に改善を重ねリピーターを増やす店は安定した売上を確保できます。本質的には、顧客が店で何を求め、どう感じているかを深く理解し、スタッフと情報を共有し続ける姿勢が非常に大切です。