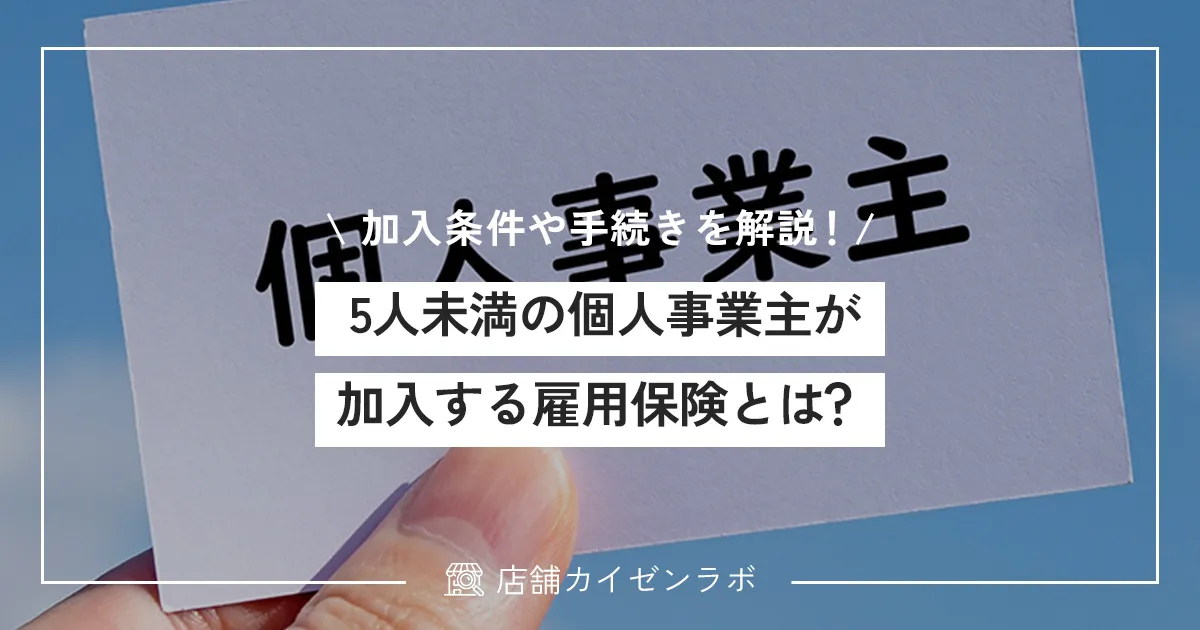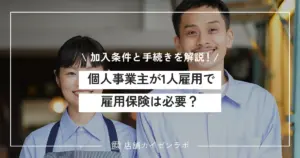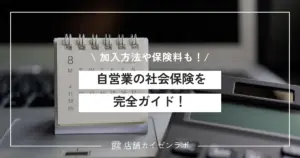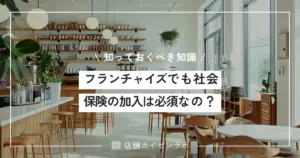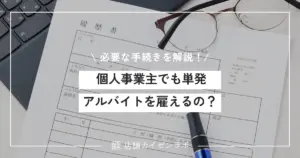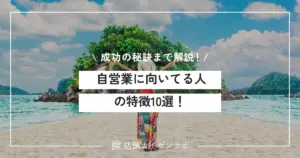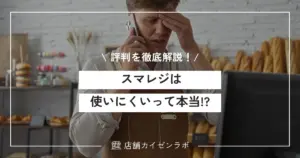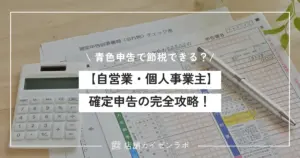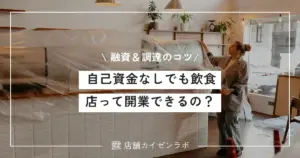第1章 従業員5人未満の個人事業主が加入すべき保険は2種類

「初めて従業員を雇ったけど、保険の手続きって何から手をつければいいの?」
「うちは5人未満の小さなお店だから、社会保険は関係ないよね?」
個人事業主として人を雇用するとき、こんな疑問や不安が頭をよぎりますよね。ご安心ください。従業員5人未満のあなたの事業所で「今すぐやるべきこと」と「じっくり検討すべきこと」は、実はとてもシンプルです。
この章では、あなたが最初に抱える疑問に、結論からズバリお答えします。
1-1. 義務:労働保険(雇用保険・労災保険)への加入
あなたが従業員を一人でも雇用したなら、事業の規模や業種、従業員の雇用形態(正社員・パート・アルバイト)に関わらず、「労働保険」への加入が法律で義務付けられています。 これは「5人未満だから」という例外はありません。
労働保険は、以下の2つの保険をまとめた総称です。
- 労災保険(労働者災害補償保険): 従業員が仕事中や通勤中にケガ・病気・死亡した場合に、治療費や休業中の生活費などを保障する保険です。
- 雇用保険: 従業員が失業した場合に、再就職までの生活を支えるための手当(失業手当)などを給付する保険です。
つまり、従業員が安心して働ける環境を提供するための、最低限のセーフティーネットと言えます。
専門家のコメント
この記事を読み終えたら、まずはこの労働保険の手続きから着手しましょう。具体的な手順は第3章で詳しく解説します。
1-2. 任意:社会保険(健康保険・厚生年金)への加入

次に、よく混同されがちな「社会保険」についてです。結論から言うと、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所の場合、社会保険への加入は義務ではありません。
社会保険は、以下の2つを指します。
- 健康保険: 従業員やその家族が病気やケガをした際の医療費負担を軽減する保険です。
- 厚生年金保険: 従業員の老後の生活を支える「国民年金」に上乗せされる年金です。
では、加入しなくても良いのかというと、そうとも限りません。あなたは「任意適用」という制度を使い、自らの意思で社会保険に加入するかどうかを選択できます。
加入には保険料負担というデメリットがありますが、人材採用や従業員の定着といった大きなメリットもあります。これは、あなたの事業の状況や将来のビジョンに合わせてじっくり検討すべき経営判断と言えるでしょう。
実践チェックポイント
まずは義務である「労働保険」の手続きから。社会保険の加入は後でじっくり検討しよう。
第2章 従業員数で保険のルールが変わる理由とは?

「なぜうちは社会保険が任意で、隣の5人いる会社は義務なんだろう?」 このシンプルな疑問を解消しておくと、今後の手続きや事業拡大の際の判断がスムーズになります。ここでは、保険のルールが従業員数によって変わる理由を、1分で理解できるように解説します。
2-1. あなたの事業所は「任意適用事業所」です
あなたが経営する「従業員5人未満の個人事業所」は、法律上「任意適用事業所」に分類されます。これは、「事業主の意思で、従業員の半数以上の同意があれば社会保険に加入できますよ」という位置づけの事業所です。
一方で、株式会社などの法人は規模に関わらず、また個人事業主でも従業員が5人以上になると、原則として「強制適用事業所」となります。この場合、事業主の意思とは関係なく、法律によって社会保険への加入が義務付けられます。
この違いを表にまとめると、以下のようになります。
| 強制適用事業所 | 任意適用事業所(あなたの事業所) | |
|---|---|---|
| 該当する事業所 | ・すべての法人事業所・従業員5人以上の個人事業所(※) | ・従業員5人未満の個人事業所・従業員5人以上でも一部業種の個人事業所(※) |
| 社会保険の加入 | 義務 | 任意(従業員の半数以上の同意で加入可) |
| 労働保険の加入 | 義務 | 義務 |
(※)理容・美容、飲食、農林水産業などの一部サービス業は、個人事業主の場合、従業員が5人以上でも任意適用となります。
つまり、あなたは社会保険に関して、法律から「選択の自由」を与えられている状態なのです。
2-2. 従業員が5人以上になると社会保険は「義務」になる
今は「任意」でも、事業が成長し、常時使用する従業員(正社員のほか、週の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であるパート・アルバイト等を含む)が5人になった瞬間から、あなたの事業所は「強制適用事業所」に変わります。
その際は、年金事務所へ「新規適用届」を提出し、社会保険に加入する義務が発生します。
失敗談:飲食店オーナーAさんのケース
従業員数が増えてきたら、単なる人数の問題だけでなく、保険の義務も変わるということを頭の片隅に置いておくことが、将来のリスク管理につながります。
ここで学べること
あなたの事業所は「任意適用事業所」。だから社会保険は選択できる、とシンプルに覚えよう。
第3章 従業員数5人未満の個人事業主が加入する労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き方法

お待たせしました。ここからは、あなたが「まずやるべきこと」、つまり労働保険の加入手続きについて、具体的な手順を解説します。手続きの全体像は「①労働基準監督署 → ②ハローワーク」という流れです。この順番さえ間違えなければ、決して難しいことはありません。
3-1. ステップ1:管轄の労働基準監督署で「保険関係成立届」を提出する
従業員を雇用したら、まずは事業所を管轄する労働基準監督署(労基署)へ向かいます。
- 提出する書類: 労働保険関係成立届
- 提出期限: 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
- 必要なもの:
- 事業所の印鑑(個人の実印)
- 事業所の所在地や事業内容がわかるもの(例:開業届の控え、事業所の賃貸契約書など)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
「労働保険関係成立届」は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできますが、労基署の窓口でもらうこともできます。
初めての届出で30分悩んだポイント
この届を提出し、控えをもらったら、最初の関門はクリアです。
3-2. ステップ2:管轄のハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」を提出する
労基署の次は、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。ここで重要なのは、必ず労基署で受け取った「労働保険関係成立届の控え」を持参することです。これがないと手続きができません。
- 提出する書類:
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届(従業員の人数分)
- 提出期限:
- 設置届:事業所を設置した日(雇用日)の翌日から10日以内
- 資格取得届:従業員を雇用した月の翌月10日まで
- 必要なもの:
- 労働保険関係成立届の控え(労基署で受け取ったもの)
- 事業所の印鑑
- 従業員の労働者名簿、出勤簿、賃金台帳
- 従業員のマイナンバーがわかるもの
- その他、事業の実態がわかる書類(開業届の控えなど)
この手続きで、あなたの事業所が「雇用保険に加入する事業所」として登録され、同時に従業員が「雇用保険の被保険者」となります。
もし本業が忙しく、手続きに不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に依頼するのも賢い選択です。
実践チェックポイント
①労基署で「成立届」→ ②ハローワークで「設置届」「資格取得届」。この順番と、ハローワークへ「成立届の控え」を持っていくことを絶対に忘れないこと。
第4章 従業員5人未満で社会保険に加入するメリット・デメリット

労働保険という「義務」の手続きの目処がついたら、次はいよいよ「任意」である社会保険について、あなたの事業にとって本当に必要かを考えるフェーズです。
月々の保険料負担は決して軽くありません。しかし、それを上回るメリットがあることも事実です。ここでは、判断材料となるメリットとデメリットを、経営者の視点から徹底的に比較検討します。
4-1. メリット①:求人応募が増える!人材採用で有利になる
「いい人がいれば、採用したいんだけどね…」 これは、多くの個人事業主が抱える共通の悩みではないでしょうか。社会保険への加入は、この採用問題を解決する強力な一手になり得ます。
「社会保険完備」という一言は、求職者、特に経験やスキルを持つ人材にとって「安心して長く働ける、しっかりした事業所」という信頼の証になります。実際に、大手転職サイトの調査でも、転職先を選ぶ際に重視する項目のトップクラスに「福利厚生の充実」が常にランクインしています。
成功事例:従業員2名のデザイン事務所 B社のケース
特にハローワークの求人票では、「社会保険完備」の有無はチェックボックスで明確に区別されるため、求職者の目に留まる確率が格段に上がります。
4-2. メリット②:従業員の安心と定着につながる
採用した優秀な人材に、長く活躍してもらうこと。これも経営の重要なテーマです。社会保険は、従業員の生活に直接的な安心感をもたらし、定着率(リテンション)の向上に大きく貢献します。
従業員にとって、社会保険(協会けんぽ)は、市区町村の国民健康保険にはない手厚い保障が魅力です。
- 傷病手当金:病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ場合、給与のおおよそ3分の2が最長1年6ヶ月間支給される。
- 出産手当金:出産のために仕事を休んだ場合、給与のおおよそ3分の2が支給される。
- 扶養制度:従業員の配偶者や子供の保険料負担がなくなる場合がある。
さらに、年金についても、国民年金(1階部分)に厚生年金(2階部分)が上乗せされる「2階建て」構造になるため、将来の年金受給額が大きく増えます。
国民年金と厚生年金の構造比較テーブル
| 保険の種類 | 社会保険未加入の場合(国民年金のみ) | 社会保険加入の場合(厚生年金) |
|---|---|---|
| 年金の構造 | 1階建て | 2階建て |
| 2階部分 | なし | 厚生年金(報酬比例部分) |
| 1階部分 | 国民年金(基礎年金) | 国民年金(基礎年金) |
4-3. デメリット:事業主と従業員の保険料負担が増える
ここまでメリットを強調してきましたが、もちろんデメリットもあります。それは、月々の固定費として保険料負担が発生することです。
保険料で増える固定費は、他のコスト最適化で相殺できます。実践手順は『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』。
社会保険料は、従業員の給与(標準報酬月額)を基に算出され、その金額を事業主と従業員で半分ずつ負担(労使折半)します。
仮に、月給25万円の従業員を1人雇用した場合、あなたの事業所が負担する社会保険料はいくらになるのでしょうか。以下のシミュレーション表をご覧ください。
月給別・社会保険料負担額シミュレーション(事業主負担分)テーブル
| 従業員の月給(標準報酬月額) | 健康保険料(事業主負担分) | 厚生年金保険料(事業主負担分) | 事業主負担額 合計/月 | 事業主負担額 合計/年 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 9,990円 | 18,300円 | 28,290円 | 339,480円 |
| 250,000円 | 12,987円 | 22,875円 | 35,862円 | 430,344円 |
| 300,000円 | 14,985円 | 27,450円 | 42,435円 | 509,220円 |
※上記は2025年9月時点の東京都の協会けんぽ保険料率(40歳未満・介護保険料なし)で計算した概算値です。実際の金額は、管轄の都道府県や年度によって異なります。
甘かった資金繰り計画
実践チェックポイント
保険料シミュレーションで資金繰りへの影響を計算し、採用強化や人材定着のメリットがコスト増を上回るか、慎重に検討しよう。
第5章 個人事業主が社会保険の任意適用する場合の手続き方法

メリットとデメリットを比較検討し、「よし、うちも社会保険に加入しよう!」と決断された方へ。この章では、具体的な手続きのステップを解説していきます。手続きの大きな流れは「①従業員の同意を得る → ②年金事務所で申請する」です。
5-1. 条件:従業員の半数以上の同意を得る
任意適用の申請には、大前提として社会保険の加入対象となる従業員の2分の1以上の同意が必要です。なぜなら、従業員側にも保険料負担が発生し、手取り額が減ることになるからです。
一方的に加入を決めるのではなく、従業員にしっかりと説明し、納得してもらうプロセスが不可欠です。
同意が得られたら、従業員に署名・捺印してもらった同意書を準備します。様式は特に決まっていませんが、日本年金機構のサイトに参考様式があります。
5-2. 手続き:年金事務所で「任意適用申請書」を提出する
従業員の同意が得られたら、いよいよ管轄の年金事務所で申請手続きです。
- 提出する書類:
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
- 任意適用同意書(従業員の半数以上が署名・捺印したもの)
- 事業主世帯全員の住民票(マイナンバー記載のないもの)
- 公租公課の領収証(事業税、所得税など)
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(加入する従業員分)
- (従業員の家族を扶養に入れる場合)健康保険 被扶養者(異動)届
- 提出先: 事業所の所在地を管轄する年金事務所
- 提出方法: 窓口持参、郵送、電子申請
必要書類は多岐にわたるため、事前に日本年金機構のウェブサイトで最新情報を確認し、チェックリストを作成することをおすすめします。
専門家のコメント
実践チェックポイント
まずは従業員への丁寧な説明と同意取得から。必要書類は事前に年金機構のサイトで確認し、漏れなく準備しよう。
第6章 個人事業主自身が加入できる保険と税金の知識
従業員の保険手続きを進める中で、「ところで、自分自身の保険はどうなるんだっけ?」という疑問が必ず浮かびます。従業員の保険と、事業主自身の保険はルールが全く異なります。ここで混同しやすいポイントを整理し、経営者として知っておくべき知識を解説します。
6-1. 原則は「国民健康保険・国民年金」!従業員との違い
非常に重要なことなので、結論を先に言います。 あなたの事業所が社会保険の任意適用を受けても、個人事業主であるあなた自身は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できません。
あなたは引き続き、お住まいの市区町村が運営する「国民健康保険」と「国民年金」に加入し続けることになります。
| 対象者 | 加入する医療保険 | 加入する年金制度 |
|---|---|---|
| 従業員 | 健康保険(協会けんぽ等) | 厚生年金保険 |
| あなた(個人事業主) | 国民健康保険 | 国民年金 |
私が法人成りを選択した時の理由
6-2. 【任意】労災保険の「特別加入制度」でリスクに備える
原則として事業主は労働保険に加入できませんが、一つ例外があります。それが労災保険の「特別加入制度」です。
これは、働き方が従業員と近い個人事業主が、業務中や通勤中のケガなどに備えるために、任意で労災保険に加入できる制度です。特に、ご自身も現場で作業される方は、万が一の休業リスクに備えて加入を検討する価値が非常に高いです。
加入できる主な業種・職種
- 建設業(一人親方)
- 個人タクシー、個人貨物運送業
- 漁船による漁業
- ITフリーランス(Webデザイナー、プログラマー等)
- アニメーション制作、柔道整復師 など
専門家 木村 裕一氏のコメント
6-3. 負担した保険料は「経費」か「所得控除」か?
従業員の保険料を負担することになると、確定申告の際の処理も気になりますよね。ここでも、「従業員の分」と「自分の分」では扱いが全く異なります。この違いを以下の表で確認しましょう。
保険料の会計処理と節税効果の違い
| 支払った保険料 | 区分 | 勘定科目 | 確定申告での扱い | 節税効果 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員の社会保険料(事業主負担分) | 経費 | 法定福利費 | 売上から差し引き、事業所得を圧縮する | 所得税・住民税・事業税・国民健康保険料が下がる |
| 事業主自身の国民健康保険料・国民年金 | 所得控除 | — | 所得から差し引き、課税所得を圧縮する | 所得税・住民税が下がる |
私が税理士からの指摘で学んだこと
ここで学べること
従業員の保険料は「経費」、自分の保険料は「所得控除」。労災の特別加入も視野に入れ、自身の保障も考えよう。
第7章 従業員がいる個人事業主によくある保険の質問
Q1. 従業員が10人未満でも、就業規則は作ったほうがいい?
A. 法律上の作成義務は常時10人以上の事業所からですが、10人未満でも作成を強く推奨します。労働時間や休日、賃金ルールを明文化しておくことで、従業員との無用なトラブルを未然に防ぎ、安心して働ける職場環境の基礎になります。
就業規則を作るなら、教育フローも同時に整えるのが効果的です。新人教育の型は『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』にまとめています。
Q2. 社会保険の加入義務があるのに未加入だと、どうなる?
A. 年金事務所の調査で指摘された場合、最大2年遡って保険料を追徴される可能性があります。さらに延滞金が課されることもあります。悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることもあるため、加入義務が生じたら速やかに手続きしましょう。
Q3. 青色事業専従者(家族従業員)の国民年金は免除できる?
A. いいえ、専従者であっても国民年金の加入は義務であり、保険料の免除はできません。ただし、所得が低いなどの理由で保険料の納付が困難な場合は、本人(専従者)が「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を申請することは可能です。
Q4. 従業員の給与や事業主が負担した保険料は、経費になりますか?
A. はい、従業員に支払う給与や、事業主が負担した労働保険料・社会保険料は、全額「経費」として計上できます。勘定科目はそれぞれ「給料賃金」「法定福利費」となり、事業の利益を圧縮するため、大きな節税効果があります。
Q5. 従業員が増えたら、法人化(会社設立)したほうがいい?
A. 一概には言えませんが、検討する価値は高いです。法人化すると、事業主自身も社会保険に加入できたり、給与所得控除を使えたりと税制上のメリットがあります。一般的に、事業所得が800万円を超えたあたりから法人化を検討する事業主が多いです。
法人化だけでなくFCという道もあります。比較と判断ポイントは『フランチャイズでも社会保険の加入は必須なの?経営者が知っておくべき保険の知識と手続き!』でまとめています。
Q6. パートやアルバイトでも、保険の加入は必要ですか?
A. はい、労働時間などの条件を満たせば加入義務があります。雇用保険は「週20時間以上」、社会保険は「正社員の労働時間・日数の概ね4分の3以上」が主な加入目安です。雇用形態ではなく、働き方の実態で判断されるので注意が必要です。
Q7. 従業員の保険料は、どうやって給与から天引きすればいい?
A. 毎月の給与計算の際に、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の「従業員負担分」を給与(総支給額)から差し引きます。この差し引いた保険料(預り金)と事業主負担分を合わせて、国に納付する流れとなります。
Q8. 手続きは専門家に依頼すべき?費用はどれくらい?
A. 時間と正確性を重視するなら専門家(社会保険労務士)への依頼がおすすめです。費用の相場は、労働保険の新規設立手続きで3万~5万円程度、顧問契約なら月額2万円~(従業員数による)が目安です。本業に集中できるメリットは大きいでしょう。
Q9. 従業員が5人以上になったら、何か手続きが必要?
A. はい、社会保険の「強制適用事業所」となるため、年金事務所へ「新規適用届」を提出する義務が発生します。従業員数が5人以上になった日から5日以内が提出期限です。任意適用中だった場合も、強制適用への切り替え手続きが必要です。