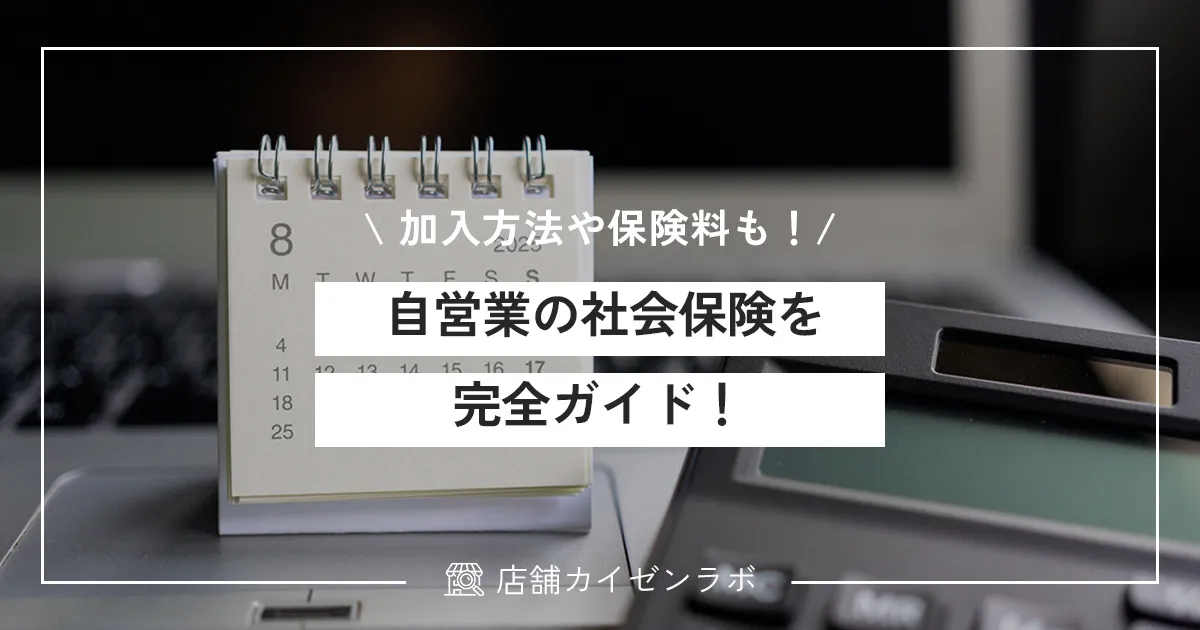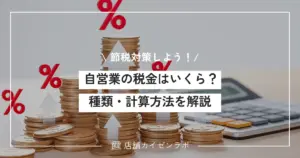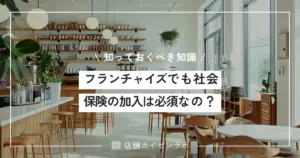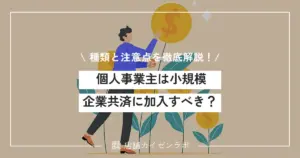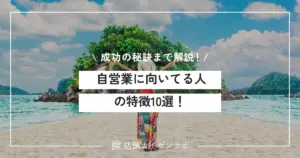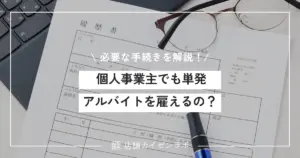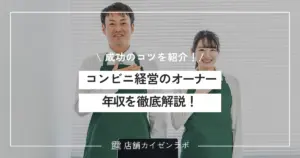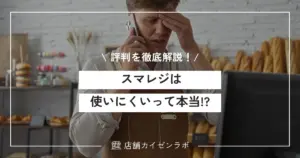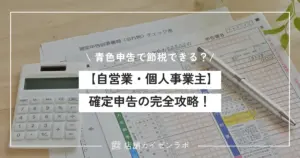第1章 自営業の社会保険を診断!状況に合わせた必要なこととは?

1-1. 30秒診断:独立・法人化?状況別に見るべき社会保険手続き
会社員から自営業・個人事業主へ。希望に満ちたスタートを切る一方で、多くの方が最初に戸惑うのが「社会保険の手続き」です。会社がすべてやってくれていた頃とは違い、これからはすべて自分で判断し、手続きをしなければなりません。
情報が多すぎて、何から手をつければいいか分からない…と感じていませんか?
私自身、会社を辞めて独立した当初、役所の窓口で「国民健康保険と国民年金の手続きをしてください」と言われたものの、任意継続という選択肢があることすら知りませんでした。結果的に最適な選択ができず、後から「もっと調べておけばよかった…」と後悔した経験があります。
そんな後悔をしないために、まずはこの30秒診断であなたの現在地を確認し、この記事で重点的に読むべき章を把握しましょう。
【あなたの状況はどれ?今すぐ読むべき章をチェック!】
- ① これから独立する・独立したばかり
- ② 事業が軌道に乗り、節税も考えたい
- ③ 初めて従業員を雇う・雇う予定
- 👉 第4章が必須!事業主としての法的義務と手続きを完全ガイド。
- ④ 保険料の支払いが厳しい…
- 👉 第7章へ!滞納リスクと、利用できる公的な救済制度を解説。
- ⑤ 法人化を検討している
- 👉 第6章で個人事業主との違いと損益分岐点を確認。
この記事では、あなたの状況に合わせて必要な知識と手続きがすべてわかるように、ステップバイステップで解説していきます。
1-2. 会社員との違いは3つ!自営業者の保険料負担と手続き

自営業者の社会保険を理解する上で、まず会社員時代との「決定的な違い」を3つ、心に刻んでおく必要があります。
保険料は「全額自己負担」になる衝撃
会社員時代、健康保険料や厚生年金保険料は給与から天引きされていましたが、その額は会社が半分を負担してくれていました。自営業者になると、この会社負担分がなくなり、すべて自分で納付します。
保障内容(特に年金)が手薄になる現実
会社員が加入する「厚生年金」は、全国民共通の「国民年金」に上乗せされる”2階建て構造”です。自営業者が加入する年金は、原則として1階部分の「国民年金」のみ。将来受け取れる年金額に大きな差が生まれるため、自分で上乗せ(iDeCoや国民年金基金など)を検討する必要があります。
すべての手続きを「自分」で行う責任
入社・退社時の手続きから、従業員を雇った際の手続き、毎年の確定申告での保険料控除まで、関連するすべての手続きを自分自身の責任で行わなければなりません。期限を過ぎたり、手続きを忘れたりすると、給付を受けられない、ペナルティが発生するなどの不利益に直結します。
この3つの違いを理解することが、自営業者として社会保険制度と賢く付き合っていくための第一歩です。
飲食店経営している方は保険料が重くなりがち。まずは固定費を見直しましょう。実践の手順は『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』で詳しく解説しています。
第2章 自営業者の医療保険|国民健康保険・任意継続など4つの加入方法を比較

会社を退職したら、まず最初に行うべきが公的医療保険への加入手続きです。日本ではすべての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が義務付けられています。選択肢は主に4つ。それぞれの特徴を理解し、あなたにとって最も有利な制度を選びましょう。
2-1. 国民健康保険(国保):加入手続きと保険料の計算方法
国民健康保険(国保)は、他の医療保険に加入していないすべての人が対象となる、自営業者にとって最も基本的な選択肢です。
■加入手続き
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で手続きが必要です。
手続きの流れ:
- 必要書類の準備: 健康保険資格喪失証明書(退職した会社から発行)、本人確認書類、マイナンバーがわかるものなど。
- 窓口で手続き: 市区町村役場の国保担当窓口で加入申込書を記入・提出。
- 保険証の受け取り: 通常、後日郵送で届きます。
■保険料の決まり方
国保の保険料は、前年の所得に応じて計算される「所得割」と、加入者全員が均等に負担する「均等割」の合算で決まります。この保険料率は自治体によって大きく異なるため注意が必要です。
主要都市の国民健康保険料シミュレーション(年収500万円・40歳未満・単身)
| 自治体 | 年間保険料(概算) |
| 東京都千代田区 | 約49万円 |
| 神奈川県横浜市 | 約52万円 |
| 大阪府大阪市 | 約50万円 |
| 福岡県福岡市 | 約46万円 |
| 北海道札幌市 | 約47万円 |
※上記はあくまで概算です。正確な保険料はお住まいの市区町村にご確認ください。
2-2. 健康保険の任意継続:メリット・デメリットと保険料の分岐点

退職前に加入していた会社の健康保険を、最長2年間、継続できる制度です。
■手続きと条件
退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合または協会けんぽに申請が必要です。1日でも過ぎると申請できないため、期限は厳守してください。
■メリット・デメリット
- メリット:
- 扶養家族をそのまま維持できる: 配偶者やお子さんを扶養に入れていた場合、そのまま継続できます。国保には扶養の概念がないため、これは大きなメリットです。
- 給付内容が手厚い場合がある: 健康保険組合によっては、人間ドックの補助や独自の付加給付が充実していることがあります。
- デメリット:
- 保険料が全額自己負担になる: 在職中は会社が半分負担してくれていましたが、任意継続では全額自己負担となり、保険料は原則2倍になります(上限あり)。
- 加入期間は最長2年間: 2年後には必ず国民健康保険などに切り替える必要があります。
2-3. 家族の扶養に入る:保険料負担ゼロの条件と注意点
配偶者や親族が会社員などで社会保険に加入している場合、その被扶養者になるという選択肢です。これが可能であれば、自分自身の保険料負担はゼロになり、最も経済的メリットが大きい方法です。
■扶養に入るための条件
主な条件は年収です。一般的に、今後の年間収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが求められます。
■注意点
この「年収」には、給与だけでなく事業所得や不動産所得なども含まれます。また、交通費や失業手当も収入とみなされる場合があるため、詳細は加入先の健康保険組合に確認が必要です。
扶養内で起業したWebデザイナー(30代・女性)
2-4. 国民健康保険組合(国保組合):特定業種の保険料メリット
医師、弁護士、税理士、建設業、IT、文芸・美術、食品販売業など、特定の業種の個人事業主が加入できる健康保険組合です。
■最大のメリット
所得に関わらず保険料が一定 国保組合の最大のメリットは、所得の増減に関わらず保険料が一定である点です。そのため、所得が高い人ほど国民健康保険に比べて保険料が割安になります。
■探し方と加入条件
「(自分の業種) 国民健康保険組合」で検索すると、関連する組合が見つかります。加入には、その組合が定める業種に従事していることや、組合の地域内に住所または事業所があることなどの条件があります。
【第2章のチェックポイント】
✅ 会社を辞めたら、まず「任意継続」と「国民健康保険」の保険料を必ず比較する。
✅ 扶養家族がいる場合は、任意継続が有利になる可能性が高い。
✅ 自分の業種で加入できる「国保組合」がないか一度調べてみる。
第3章 自営業の年金制度|国民年金と保険料を上乗せする3つの方法

医療保険と並んで重要なのが、老後の生活を支える「年金制度」です。自営業者は会社員と比べて将来の年金額が少なくなる傾向にあるため、現役時代から計画的に備えることが不可欠です。
3-1. 国民年金:加入義務と保険料の免除・猶予制度
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられているのが国民年金(基礎年金)です。
- 保険料: 年度ごとに定められます(令和6年度は月額16,980円)。
- 将来の受給額: 40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付した場合、65歳から満額の老齢基礎年金が受け取れます(令和6年度の満額は年額816,000円、月額68,000円)。
■保険料が払えない時の救済制度
失業や事業不振などで保険料の納付が困難な場合、未納のまま放置してはいけません。未納期間があると、将来の年金額が減るだけでなく、障害年金や遺族年金を受け取れなくなる可能性があります。必ず「保険料免除制度・納付猶予制度」を申請しましょう。
3-2. 年金の上乗せ制度比較:付加年金・国民年金基金・iDeCo
国民年金だけでは老後の生活が不安、という方がほとんどでしょう。自営業者には、将来の年金を増やすための心強い「上乗せ制度」が3つ用意されています。
自営業者のための年金上乗せ制度 3選比較表
| 制度名 | 掛金(月額) | 節税効果(所得控除) | 受給方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 付加年金 | 一律400円 | あり | 終身年金 | 少額で始められる。2年受給すれば元が取れる。 |
| 国民年金基金 | 最大68,000円 | あり | 終身年金が基本 | 公的な制度。プランが豊富で終身保障が手厚い。 |
| iDeCo | 最大68,000円 | あり | 一時金 or 年金 | 節税効果が最も高い。自分で運用商品を選ぶ。 |
※国民年金基金とiDeCoの掛金は合算で月額68,000円が上限です。
3-3. iDeCo(個人型確定拠出年金):最強の節税効果と始め方
3つの上乗せ制度の中でも、特に注目したいのがiDeCo(イデコ)です。掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受け取り時にも控除があるという「3つの税制優遇」があり、自営業者にとって最強の節税ツールと言えます。
■自営業者がiDeCoに加入する最大のメリット
会社員(企業年金なし)の掛金上限が月額23,000円なのに対し、自営業者(第1号被保険者)は月額68,000円まで拠出可能。年間最大81.6万円を所得から控除できるため、節税効果が非常に大きいのが特徴です。
■iDeCoの始め方 4ステップ
- 金融機関を選ぶ: 口座管理手数料が安く、商品ラインナップが豊富なネット証券がおすすめです。
- 申し込み: 選んだ金融機関のウェブサイトから申し込みます。
- 掛金を設定する: 無理のない範囲で月々の掛金額を決めます(年1回変更可能)。
- 運用商品を選ぶ: 投資信託などの中から、自分のリスク許容度に合った商品を選び、ポートフォリオを組みます。
私はiDeCoを始めて5年になります。月額68,000円をコツコツ積み立てた結果、以下のようになりました。
- 拠出額合計: 約408万円
- 現在の評価額: 約550万円(運用益+142万円)
- 5年間の節税額合計: 所得税・住民税合わせて約120万円 私のポートフォリオは「全世界株式インデックスファンド80%」「米国株式(S&P500)インデックスファンド20%」というシンプルなものです。節税しながら、将来のための資産形成が自動でできるiDeCoは、自営業者なら使わない手はない制度だと断言できます。
【第3章のチェックポイント】
✅ 国民年金の未納は絶対に避ける。支払いが厳しい場合は必ず免除・猶予申請をする。
✅ 3つの上乗せ制度(付加年金、国民年金基金、iDeCo)の特徴を理解し、自分に合ったものを選ぶ。
✅ 節税と資産形成を両立したいなら、iDeCoの活用を最優先で検討する。
第4章 従業員を雇用した場合の社会保険は?労働保険・厚生年金の加入手続き
事業が成長し、初めて従業員を雇う。これは事業主にとって大きな喜びですが、同時に社会保険に関する新たな「法的義務」が発生する瞬間でもあります。手続きの漏れは、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、法的な罰則につながる可能性もあるため、正確な知識が不可欠です。
4-1. 労働保険(労災保険・雇用保険):従業員1人からの加入義務
従業員を1人でも雇用した場合(アルバイト・パート含む)、事業主は「労働保険」に加入する義務があります。労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。
- 労災保険: 従業員が業務中や通勤中にケガや病気をした場合に給付を行う保険。保険料は全額事業主負担。
- 雇用保険: 従業員が失業した場合などに給付を行う保険。保険料は事業主と従業員の双方で負担。
■手続きの流れ
原則として、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、以下の手続きを行う必要があります。
- 管轄の労働基準監督署へ: 「労働保険関係成立届」を提出。
- 管轄のハローワークへ: 「雇用保険適用事業所設置届」と、従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。
飲食店オーナー(40代)の失敗談
初めての雇用は“教育設計”がカギです。手順と教材化は『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』が役立ちます。
4-2. 社会保険(健康保険・厚生年金):従業員5人以上で強制適用
個人事業所の場合、常時雇用する従業員が5人以上になると、業種によっては「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入が法律で義務付けられます(強制適用事業所)。
■強制適用となる主な業種
製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、メディア事業、など法律で定められた事業(法定16業種)が対象です。
■任意適用となる主な業種
一方で、弁護士・税理士などの士業、理容・美容業、飲食業、旅館・娯楽業などのサービス業、農業・漁業などは、従業員が5人以上でも任意加入とされています(ただし、従業員の半数以上が同意すれば加入が必要)。
■パート・アルバイトの加入要件
正社員だけでなく、以下の要件を満たすパート・アルバイトも社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
- 学生ではないこと
社保適用が広がるほど“稼ぐ仕組み”が重要に。ムダ取りの型は『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』で体系化できます。
4-3. 労災保険の特別加入:事業主自身のケガに備える制度
本来、労災保険は「労働者」を保護するための制度であり、事業主や役員は対象外です。しかし、労働者と同じように現場で作業を行うことが多い中小事業主や一人親方のために、任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」が用意されています。
■特別加入が強く推奨される人
- 建設業の一人親方、大工、とび職など
- 個人タクシー運転手や個人貨物運送業者(フードデリバリー配達員含む)
- ITフリーランス(システムエンジニア、プログラマーなど)
- アニメーター、デザイナー、柔道整復師など
■加入するメリット
万が一、仕事中にケガをして働けなくなっても、治療費の自己負担がなく、休業中は休業補償給付を受け取ることができます。これは、収入が途絶えると即座に生活が困窮する自営業者にとって、非常に重要なセーフティネットです。
現場でケガをした一人親方(大工・50代)
【第4章のチェックポイント】
✅ 従業員を1人でも雇ったら、すぐに労働保険の手続きを行う。
✅ 従業員が5人に近づいたら、社会保険の強制適用について専門家に相談する。
✅ 現場作業が多い事業主は、自分自身を守るために労災保険の「特別加入」を検討する。
第5章 社会保険料控除の活用方法!確定申告でできる自営業者の節税術!
自営業者が支払う社会保険料は、家計にとって大きな負担です。しかし、この負担は確定申告で「社会保険料控除」として申告することで、税金を大きく減らす効果があります。これは国が認めた正当な節税策であり、活用しない手はありません。
5-1. 社会保険料控除とは?経費との違いと節税効果
社会保険料控除とは、1月1日から12月31日までに支払った社会保険料の全額を、その年の所得から差し引くことができる制度です。
■「経費」と「所得控除」の違い
- 経費: 売上から直接差し引くもの。利益を圧縮する効果がある。
- 所得控除: 利益(所得)が確定した後、税金計算の前に差し引くもの。課税対象となる所得を圧縮する効果がある。
支払った社会保険料は経費にはなりませんが、所得控除として所得を減らすことで、結果的に所得税と住民税が安くなります。
節税効果シミュレーション
仮に課税所得500万円の個人事業主が、年間80万円(国保+国民年金)の社会保険料を支払ったとします。
- 控除がない場合:
- 所得税(20%):100万円 – 控除額42.75万円 = 57.25万円 住民税(10%):50万円
- 社会保険料控除(80万円)を適用した場合:
- 課税所得:500万円 – 80万円 = 420万円
- 所得税(20%):84万円 – 控除額42.75万円 = 41.25万円
- 住民税(10%):42万円
このケースでは、社会保険料控除を適用するだけで所得税が16万円、住民税が8万円、合計で年間24万円も税金が安くなります。これは非常に大きな効果です。
5-2. 控除の対象範囲:自分の保険料と家族の保険料
社会保険料控除の素晴らしい点は、自分自身のために支払った保険料だけでなく、「生計を一つにする」配偶者や親族のために支払った保険料も合算して控除できることです。
■控除対象となる社会保険料の具体例
- 自分自身の国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料
- 配偶者の国民年金保険料
- 大学生の子供の国民年金保険料
- 仕送りをして生計を支えている、離れて暮らす親の介護保険料や後期高齢者医療保険料
【第5章のチェックポイント】
✅ 支払った社会保険料は、全額「社会保険料控除」として確定申告で申告する。
✅ 生計を共にする家族の社会保険料を支払った場合、それも合算して控除できる。
✅ 国民年金保険料の控除証明書など、申告に必要な書類は必ず保管しておく。
第6章 法人化と社会保険について!個人事業主との違いと保険料の損益分岐点は?
事業が順調に成長し、売上や利益が一定の規模を超えてくると、多くの個人事業主が「法人化(法人成り)」を検討し始めます。法人化は、税金だけでなく社会保険の面でも大きな変化をもたらします。
6-1. 法人化による社会保険の変更点:厚生年金への強制加入
個人事業主から法人(株式会社や合同会社)になると、たとえ社長一人だけの会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。
■個人事業主と法人の社会保険比較
| 項目 | 個人事業主 | 法人(社長) |
|---|---|---|
| 医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等) |
| 年金制度 | 国民年金(1階建て) | 国民年金+厚生年金(2階建て) |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 会社と個人で折半 |
| 扶養の概念 | なし | あり |
| 保障内容 | 基本的な保障 | 障害厚生年金・遺族厚生年金など手厚い |
最大のメリットは、将来受け取れる年金額が「厚生年金」の分だけ上乗せされることです。また、病気やケガで障害が残った場合の障害厚生年金や、万が一の場合の遺族厚生年金など、保障内容が格段に手厚くなります。
法人化したWebデザイナー(30代・男性)
6-2. 法人化の損得シミュレーション:役員報酬と手取り額の変化
法人化すると、保険料は会社と個人で折半になりますが、役員報酬の額によっては、個人事業主時代よりも手取り額が減るケースもあります。
■法人化を検討すべきタイミング
一概には言えませんが、税理士などの専門家の間では、課税所得が800万円〜1,000万円を超えてくると、法人化した方が税金や社会保険料をトータルでコントロールしやすくなり、有利になるケースが多いと言われています。これは、個人事業の所得税率が所得の増加に伴い累進的に高くなるのに対し、法人税率が一定であるためです。
シミュレーション:利益800万円の場合の年間手取り額比較(概算)
- 個人事業主の場合:
- 所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた手取り額:約550万円
- 法人化(役員報酬800万円)の場合:
- 個人の手取り額:約600万円
- 会社が負担する社会保険料:約115万円
- 法人税等:約40万円
- 会社と個人を合わせたキャッシュフロー:約445万円
このケースでは、個人の手取りは増えますが、会社負担分を考慮するとトータルでは個人事業主の方が有利です。しかし、役員報酬の設定や経費の使い方次第でこの結果は大きく変わります。
法人化は数値で判断するのが安全です。KPIの設計と運用は『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』を参考にしてください。
【第6章のチェックポイント】
✅ 法人化すると、厚生年金に加入でき、将来の年金額や保障が手厚くなる。
✅ 法人化の検討は、課税所得が800万円を超えたあたりが一つの目安。
✅ 必ず税理士などの専門家に相談し、税金・社会保険をトータルで考えたシミュレーションを行う。
第7章 保険料の滞納リスクと救済制度とは?支払い困難な時の対処法

独立直後や事業不振など、予期せぬ事態で社会保険料の支払いが困難になることは誰にでも起こり得ます。そんな時、見て見ぬふりをして滞納を続けるのは最悪の選択です。国には正当な理由がある場合に利用できる救済制度が用意されています。
7-1. 保険料が払えない時の公的制度:減免・納付猶予の申請方法
競合サイトがあまり深掘りしない「救済制度」こそ、本当に困った時にあなたを助けてくれる情報です。諦める前に、まずはお住まいの市区町村役場や年金事務所に相談しましょう。
■国民健康保険料の「減免・徴収猶予」制度
災害、失業、事業の著しい損失などにより、保険料の支払いが困難になった場合、申請により保険料が減額・免除されたり、納付が猶予されたりする制度です。
- 申請窓口: お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課
- 主な対象者:
- 災害により重大な損害を受けた方
- 事業の休廃止や失業により収入が著しく減少した方(自己都合退職でない場合など条件あり)
- 手続き: 申請書と、収入の減少を証明する書類(廃業届、離職票など)を提出します。
■国民年金保険料の「免除・納付猶予」制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業などの理由により納付が困難な場合に、保険料の全額または一部が免除される制度です。また、50歳未満の方には「納付猶予制度」もあります。
- 申請窓口: お住まいの市区町村役場の年金担当課 または 年金事務所
- 手続き: 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出します。失業を理由とする場合は、離職票などの添付が必要です。
実際に減免申請をしたフリーランス(30代)
7-2. 保険料滞納のリスク:督促から財産差し押さえまでの流れ
もし、相談もせずに保険料を滞納し続けるとどうなるのでしょうか。そのプロセスは段階的に、しかし着実に進んでいきます。
納付期限を過ぎると、まず「督促状」が届きます。この時点では延滞金が加算されている場合がありますが、速やかに納付すれば問題は大きくなりません。
督促状を無視すると、より強い文面の「催告書」が送られてきます。電話や訪問による納付指導が行われることもあります。
「最終催告書」にも応じないと、役所は法律に基づき、あなたの財産を調査する権限を行使します。銀行口座の残高、売掛金、生命保険、不動産、自動車など、あらゆる財産が調査対象となります。
財産調査で差し押さえるべき財産が見つかると、予告なく「差押処分」が執行されます。ある日突然、銀行口座から預金が引き落とされたり、取引先に連絡がいき売掛金が差し押さえられたりします。こうなると、経済的なダメージだけでなく、社会的な信用も失墜してしまいます。
【第7章のチェックポイント】
✅ 保険料の支払いが困難になったら、滞納する前に役所や年金事務所に相談する。
✅ 減免や猶予の制度は、申請しなければ適用されない。
✅ 督促状が届いたら絶対に無視せず、すぐに連絡・相談のアクションを起こす。
第8章 自営業で必要な社会保険の手続きを正しく理解しておこう!
ここまで、自営業者を取り巻く社会保険制度について、網羅的に解説してきました。情報量が多かったと思いますが、最後に全体像を整理し、あなたが今日から何をすべきかを明確に示します。
8-1. 総まとめ:自営業者の社会保険制度 比較一覧表
この記事で解説した制度を一つの表にまとめました。ブックマークして、いつでも見返せるようにご活用ください。
自営業者向け 社会保険・関連制度 総まとめ一覧
| 制度分類 | 制度名 | 主な対象者 | メリット | デメリット・注意点 | 手続き窓口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療保険 | 国民健康保険 | 全ての自営業者 | ― | 所得に応じて保険料が増加。扶養の概念なし。 | 市区町村役場 |
| ― | 任意継続 | 退職後20日以内の者 | 扶養を維持できる。所得が高くても保険料に上限あり。 | 全額自己負担。最長2年。 | 健康保険組合/協会けんぽ |
| ― | 家族の扶養 | 年収130万円未満など | 保険料負担がゼロ。 | 収入に制限がかかる。 | 家族の勤務先 |
| ― | 国保組合 | 特定業種の事業者 | 所得に関わらず保険料が一定。 | 加入できる業種が限定される。 | 各国保組合 |
| 年金制度 | 国民年金 | 20歳以上60歳未満 | ― | これだけでは老後の保障が不十分。 | 市区町村役場/年金事務所 |
| ― | 付加年金 | 国民年金加入者 | 月400円で年金額UP。コスパが良い。 | 少額の上乗せ。 | 市区町村役場/年金事務所 |
| ― | 国民年金基金 | 自営業者(第1号) | 終身年金で手厚い。全額所得控除。 | 一度始めると自己都合でやめられない。 | 国民年金基金 |
| ― | iDeCo | ほぼ全ての現役世代 | 節税効果が最大。自分で運用できる。 | 60歳まで引き出せない。元本保証ではない。 | 各金融機関 |
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員を1人でも雇用 | (従業員の)業務災害を補償。保険料は全額事業主負担。 | 事業主は対象外(特別加入が必要)。 | 労働基準監督署 |
| ― | 雇用保険 | 従業員を雇用 | (従業員の)失業等を補償。 | 加入要件あり。 | ハローワーク |
| ― | 労災特別加入 | 一人親方など | 事業主自身の業務災害を補償。 | 任意加入。保険料負担あり。 | 労働保険事務組合 |
社会保険は開業手続きの一要素です。全体の流れは『小売店開業の流れと必要な準備を完全解説!店舗運営と資金管理の方法を大公開!』で俯瞰して漏れを防ぎましょう。
8-2. 今日から始めよう!
最後に、第1章の診断結果に応じて、あなたが次にとるべき具体的なアクションを提示します。この記事を読んだだけで終わらせず、今日から行動を始めましょう。
これから独立する・独立したばかりのあなたへ
- 退職後、すぐに会社の健康保険組合に「任意継続の保険料」を確認してください。
- お住まいの市区町村役場のウェブサイトで「国民健康保険料の概算額」を試算してください。
- 上記2つを比較し、有利な方の医療保険に期限内(任意継続は20日、国保は14日以内)に加入手続きをしてください。
- お住まいの役所で「国民年金」の加入手続きをしてください。その際、「付加年金」の申し込みも同時に行いましょう。
事業が軌道に乗ってきたあなたへ
- まだ始めていないなら、手数料の安いネット証券で「iDeCo」の口座開設を申し込んでください。
- 今年の所得を見積もり、iDeCoや国民年金基金の掛金をいくらに設定するか検討してください。
- 「社会保険料控除」の対象になる、家族のために支払った保険料がないか、領収書などを確認してください。
従業員を雇う予定のあなたへ
- 管轄の「労働基準監督署」と「ハローワーク」の場所と必要書類を確認してください。
- 従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、「労働保険」の成立手続きを必ず行ってください。
- 現場作業が多いなら、あなた自身を守るために「労災保険の特別加入」を検討してください。
社会保険は、複雑で面倒な手続きと感じるかもしれません。しかし、それはあなた自身とあなたの家族、そして従業員を守るための大切なセーフティネットです。この記事が、あなたの事業の健全な発展の一助となれば幸いです。