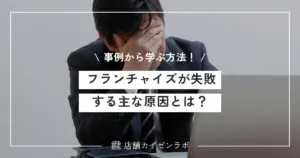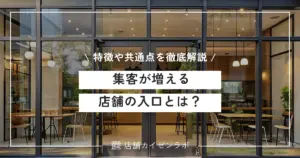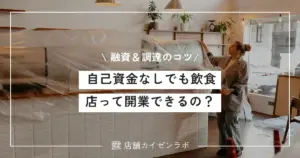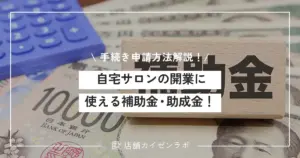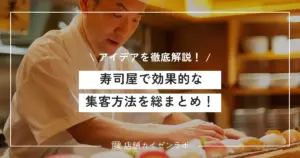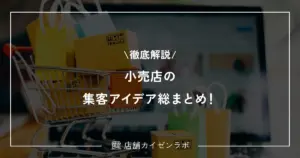第1章:なぜ今、あなたの店に「面白いイベント」が必要なのか?

「うちの料理は、味には自信がある。でも、なぜかお客様が増えない…」 競争の激しい飲食業界で、多くの経営者が同じ悩みを抱えています。美味しいのは当たり前。そんな時代に、お客様は何を基準にお店を選んでいるのでしょうか。
答えは、「そこでしか得られない体験価値」です。 この章では、単なる賑やかしではない、現代の飲食店経営における「戦略」としてのイベントの重要性を3つの視点から解説します。
1-1. 美味しいだけでは埋もれる時代。「体験価値」で選ばれる店になる
現代の消費者は、お腹を満たすためだけに外食をするわけではありません。友人との会話、新しい発見、非日常的な空間——そうした「食事+α」の体験、いわゆる「コト消費」にお金を払います。さらにトキ消費へと時代は移り。Z世代はイミ・エモ消費が増加傾向にあります。
「面白いイベント」は、このような体験価値を手軽に、かつ強力に提供できる最高の手段です。
- 「シェフと一緒にピザを作る」という学びの体験
- 「常連客だけが集まる日本酒会」という特別な体験
- 「サイコロを振ってドリンクが無料になる」というゲームの体験
こうした「思い出」は、料理の味と同じくらい、あるいはそれ以上にお客様の心に深く刻まれます。「あの店に行けば、何か面白いことがある」。そう思わせることができれば、お客様は数ある選択肢の中から、あなたの店を積極的に選んでくれるようになるのです。
1-2. イベントは最強の広告塔。SNSが勝手にお店を宣伝してくれる

一件のポジティブなクチコミが、何十万円もの広告費を上回る効果を生むのが今の時代です。そして、「面白いイベント」は、そのクチコミ(UGC:ユーザー生成コンテンツ)を自然発生させる、最高のエンジンとなります。
考えてみてください。お客様がSNSに投稿するのはどんな時でしょうか? それは、心が動いた瞬間です。「こんなの初めて!」「すごく楽しかった!」「誰かに教えたい!」——イベントは、そうした感情の起伏を生み出しやすいのです。
お客様が投稿してくれた一枚の写真、一本の動画が、その友人やフォロワーへと拡散していく。その連鎖は、あなたのお店が広告費を一切かけずに、最も信頼性の高い宣伝を、24時間365日続けてくれるのと同じ効果を持ちます。
都市部のあるカフェでは、週末限定の「パンケーキアート教室」を実施。参加者が作ったカラフルなパンケーキをInstagramにアップし合い、その写真がSNSでバズりました。結果、週末の予約が3週間先まで埋まるほどの盛況に。広告を打たずともSNS上のクチコミだけで集客できた一例です。
1-3. 価格競争から脱却し、熱狂的なファン(リピーター)を育てる
近隣の店が値下げを始めたから、うちも追随する…。そんな消耗戦から抜け出す鍵も、イベントにあります。イベントを通じてお客様とスタッフの間にコミュニケーションが生まれたり、お客様同士が繋がったりすることで、お店は単なる「食事をする場所」から、「好きな仲間と集うコミュニティ」へと変化していきます。
そうなれば、お客様は少しくらい値段が高くても、少し遠くても、あなたの店に来てくれるようになります。なぜなら、そこには価格では測れない「居心地の良さ」や「繋がり」という価値があるからです。
イベントは、お客様を「一見さん」から「常連客」へ、そして「常連客」を、お店を愛し、応援してくれる「熱狂的なファン」へと育てるための、最も効果的な投資なのです。
第2章 失敗しないイベントの「目的」と「ターゲット」設定法

面白いイベント企画を思いついた時、多くの人が「何をやるか(What)」から考えがちです。しかし、その前に必ずやるべき、そして最も重要なステップがあります。それが、「何のために(Why)」と「誰に(Who)」を徹底的に掘り下げることです。
この土台が曖昧なままでは、どんなにユニークな企画も「ただの自己満足」で終わってしまいます。この章の質問に答えていくだけで、あなたのイベントの成功確率は劇的に高まるはずです。
2-1. 【目的設定】イベントで何を解決したいのか?
まずは、あなたの店が今抱えている「一番の経営課題」を正直に見つめ直してみましょう。イベントは、その課題を解決するための「手段」です。目的が明確であれば、企画の方向性も自然と定まります。
あなたの店の課題は、主に次の4つのどれに当てはまりますか?
ケース①:新規顧客が足りない
「店の前は通るけど、入ってきてはくれない」
「オープン景気は終わったが、新しいお客様が来ない」
「SNSのフォロワーは増えない」
→ この場合の目的は「認知度向上」と「来店ハードルを下げる」こと。
ケース②:リピーターが定着しない
「一度は来てくれるが、2回目の来店に繋がらない」
「お客様の顔と名前が一致しない」
「常連客と呼べる人が少ない」
→ この場合の目的は「顧客との関係構築」と「再来店の動機付け」。
ケース③:客単価が低い
「席は埋まっているのに、なぜか利益が残らない」
「一番安いメニューばかり注文される」
「追加のドリンクやデザートが出ない」
→ この場合の目的は「高単価メニューの訴求」と「セット注文の促進」。
ケース④:店のブランドイメージが弱い
「『何がウリなの?』と聞かれると困る」
「SNSで発信する内容に困る」
「他店との違いを打ち出せていない」
→ この場合の目的は「専門性のアピール」と「コンセプトの浸透」。
さあ、あなたの店の「目的」は決まりましたか? その目的こそが、この先のアイデア選びの羅針盤となります。
2-2. 【ターゲット設定】 イベントは「誰」を最高に喜ばせるのか?
目的が決まったら、次は「誰に」そのイベントを届けるかを考えます。「すべてのお客様へ」というのは、結果的に誰の心にも響きません。ターゲットを絞り込むことで、企画は鋭く、魅力的になります。
まずは、大きく2つの軸で考えてみましょう。
既存の常連客 vs まだ見ぬ新規客
感謝を伝え、さらに深いファンになってもらうためのイベントか? それとも、お店の存在を知ってもらい、最初の一歩を踏み出してもらうためのイベントか? 両方を同時に狙うのは至難の業です。
個人客(おひとり様・カップル) vs 団体客(グループ・ファミリー)
静かに楽しむワークショップか? それとも、みんなでワイワイ盛り上がるゲーム大会か? ターゲットの利用シーンを想像することで、企画の雰囲気は自ずと決まります。
ターゲットの解像度を上げる3つの質問
さらにターゲットを具体的にするために、次の質問に答えてみてください。
- その人は、普段どんな雑誌を読み、どんなSNSを見ていますか?
(→ 告知すべきメディアが見えてくる) - その人は、イベントにいくらまでなら気持ちよく払ってくれますか?
(→ イベントの価格設定のヒントになる) - その人がイベントに参加して、友人に自慢するとしたら、何と言って話すでしょうか?
(→ イベントの「ウリ」や「キャッチコピー」が見えてくる)
ここまで考え抜けば、あなたはもう「誰に何を届けるべきか」を明確に理解しているはずです。この「目的」と「ターゲット」を胸に、いよいよ次の章で、具体的なアイデアを探しに行きましょう。
面白いイベントの集客にも活用できる販促手法を『【完全版】飲食店の販促方法をすべて大公開!売上や来店効果の高い手法を徹底解説!』でも紹介しています
第3章 【目的別アイデア集】集客を最大化する「面白い企画」15選

第2章で、あなたの店の「目的」と「ターゲット」が明確になりましたね。いよいよ、その課題を解決するための具体的なイベントアイデアを探していきましょう。
ここでは、「新規集客」「リピーター育成」「売上・客単価UP」という3つの大きな目的別に、明日から使える15のアイデアを厳選してご紹介します。あなたの店の目的に合ったセクションから、じっくりとご覧ください。
3-1. 《新規集客》まだ見ぬお客様を呼び込むイベントアイデア5選
「お店の存在を知ってほしい」「入店のきっかけを作りたい」という場合のアイデアです。話題性や参加しやすさが鍵となります。
① メディアも注目!動画映えする「チャレンジ企画」
- 【概要】大食い、激辛、巨大メニューなど、お客様が限界に挑戦する企画。動画映えしやすく、TikTokやYouTubeで拡散されやすいのが特徴。
- 【なぜ有効か】「完食で無料!」といった分かりやすいリターンがあり、ゲーム感覚で参加できるため、新規客、特に若者グループの来店動機に繋がりやすい。メディアに取り上げられる可能性も秘めています。
- 【特におすすめの業態】ラーメン店、カレー店、大衆食堂、居酒屋
- 【現代的なアレンジ例】単なる大食いではなく、「総重量5kgのデカ盛りパフェ」など、見た目のインパクトと写真映えを重視する。
② 地域を巻き込む「コラボ・タイアップイベント」
- 【概要】近隣の異業種店(例:書店、花屋、アパレル店)や、地域の農家、酒蔵などと協力して開催するイベント。
- 【なぜ有効か】コラボ相手の顧客層にアプローチできるため、自店だけではリーチできなかった新しいお客様に来てもらえる。地域貢献にも繋がり、お店のイメージアップも期待できます。
- 【特におすすめの業態】カフェ、ベーカリー、イタリアン・フレンチ、地域密着型のレストラン
- 【現代的なアレンジ例】地元の農家から仕入れた規格外野菜を使い、「フードロス削減コース」として提供。社会貢献に関心の高い層に訴求する。
③ 初めてでも安心。「初心者向け体験ワークショップ」
- 【概要】プロの技術を気軽に体験できる教室。「親子ピザ作り教室」「バリスタが教えるコーヒー淹れ方講座」「利き酒入門」など。
- 【なぜ有効か】「料理を食べる」だけでなく「作る・学ぶ」という体験(コト消費)は、強い来店動機になる。参加費を設定しやすく、確実に利益を確保しながら新規客を呼び込めます。
- 【特におすすめの業態】ピッツェリア、カフェ、和食店、ベーカリー
- 【現代的なアレンジ例】講師として地域のインフルエンサーを招き、集客力を高める。
④ 入るきっかけを作る「ワンコイン・お試しイベント」
- 【概要】「最初の1杯100円」「おつまみ3種盛り500円」など、赤字覚悟でハードルを極限まで下げた企画。
- 【なぜ有効か】「気になるけど、入る勇気がない」と感じている潜在顧客の背中を押す、最も直接的な方法。一度入店してもらい、お店の雰囲気や味を知ってもらうことが目的です。
- 【特におすすめの業態】バー、立ち飲み屋、専門性の高い(入りづらい雰囲気の)店
- 【現代的なアレンジ例】「街バル」のような地域一体型の飲み歩きイベントに参加し、チケット1枚で看板メニューを提供。
⑤ SNSで拡散!「ハッシュタグキャンペーン」
- 【概要】指定のハッシュタグ(例:#店名イベント)を付けてSNSに投稿してくれたお客様に、割引や一品サービスなどの特典を提供する。
- 【なぜ有効か】お客様自身が広告塔となり、そのフォロワーへと認知を広げてくれる。低コストで始められ、情報の拡散力を最大化できるのが魅力。
- 【特におすすめの業態】カフェ、スイーツ店、韓国料理店など、若者や女性客が多い全ての業態
- 【現代的なアレンジ例】「#店名で推し活」といったハッシュタグで、好きなキャラクターやアイドルのグッズと一緒に料理を撮って投稿してもらう。
3-2. 《リピーター育成》常連客との絆を深めるイベントアイデア5選
「一度来てくれたお客様に、また来てもらいたい」「もっとお店を好きになってほしい」という場合のアイデアです。特別感とコミュニケーションが鍵となります。
① 特別感で心を掴む「会員限定クローズドイベント」
- 【概要】LINE公式アカウントの登録者や、ポイントカード会員だけが参加できるシークレットイベント。
- 【なぜ有効か】「自分は特別扱いされている」という満足感は、顧客ロイヤルティを劇的に高める。「選ばれた人しか参加できない」という情報が、かえって新規客の興味を惹き、「自分も会員になりたい」と思わせる効果も。
- 【特におすすめの業態】ワインバー、日本酒バー、高級レストラン、寿司店
- 【現代的なアレンジ例】未発売の新メニューを誰よりも早く試食できる「先行テイスティング会」。
② お店を自分たちの場所に。「お客様参加型メニュー開発」
- 【概要】常連客を集め、次のシーズンの新メニューのアイデアを一緒に出し合ったり、試作品を食べ比べて投票してもらったりする企画。
- 【なぜ有効か】お客様は「消費者」から「お店作りのパートナー」へと意識が変わる。自分が開発に関わったメニューが登場すれば、愛着が湧き、友人を連れて再来店してくれる可能性も高まります。
- 【特におすすめの業態】居酒屋、カフェ、ラーメン店など、常連客との距離が近い店
- 【現代的なアレンジ例】完成したメニューに、考案したお客様のニックネームを付ける(例:「佐藤さんの気まぐれパスタ」)。
③ スタッフが主役!「推し活・応援イベント」
- 【概要】「スタッフ人気総選挙」を開催して投票してもらったり、スタッフの誕生日をみんなで祝ったりするイベント。
- 【なぜ有効か】お客様の目的が「料理を食べること」から「特定のスタッフに会うこと」に変わる。スタッフを「推す」という新しい来店動機が生まれ、強固なファンコミュニティが形成される。
- 【特におすすめの業態】コンセプトカフェ(メイド、執事など)、バー、居酒屋
- 【現代的なアレンジ例】各スタッフが考案したオリジナルカクテルを期間限定で販売し、注文数で人気を競う。
④ 共通の趣味で繋がる「コミュニティイベント」
- 【概要】特定のテーマを設け、同じ趣味を持つお客様だけを集める会。「ボードゲームナイト」「サッカー日本代表応援観戦会」「読書会」など。
- 【なぜ有効か】お客様同士が繋がり、お店が「コミュニティの拠点」となる。常連客が新しい友人を店に連れてくる、という好循環が生まれる。
- 【特におすすめの業態】スポーツバー、カフェバー、広いスペースのあるダイニング
- 【現代的なアレンジ例】特定のアニメや漫画ファンが集まる「オフ会」プランを用意し、場所を提供する。
⑤ 感謝を伝える「記念日・誕生日サプライズ」
- 【概要】顧客情報を基に、誕生日や記念日が近いお客様に特別なDMを送り、来店時にサプライズのデザートプレートや写真撮影を提供する。
- 【なぜ有効か】一斉配信のクーポンとは違う、パーソナルな「お祝い」は深く心に響く。「人生の大切な節目は、あのお店で」と思ってもらえる、リピーター育成の王道施策。
- 【特におすすめの業態】イタリアン・フレンチレストラン、ホテルダイニング、個室のある居酒屋
- 【現代的なアレンジ例】ペット同伴可の店なら、ペットの誕生日にワンちゃん用ケーキをサービス。
3-3. 《売上・客単価UP》利益に直結するイベントアイデア5選
「もっと注文してほしい」「高いメニューにも挑戦してほしい」という場合のアイデアです。付加価値の提案と、注文の楽しさが鍵となります。
① 付加価値で単価を上げる「高級食材・限定コース会」
- 【概要】「〇〇産A5ランク牛」「北海道から直送のウニ」など、普段は扱わない高級食材を使った、その日限りの特別コースを提供する。
- 【なぜ有効か】「今日しか食べられない」という限定性が、高価格への納得感を生む。イベントという非日常空間が、お客様の財布の紐を緩めさせる効果も。
- 【特におすすめの業態】高級レストラン、鉄板焼き、寿司店、割烹
- 【現代的なアレンジ例】クラウドファンディングで事前に参加者を募り、目標金額に達したら高級マグロの解体ショーを開催。
② 知的な体験を提供する「プロを招いたペアリング会」
- 【概要】ワインソムリエや日本酒の蔵元、チーズ職人などをゲスト講師として招き、料理とのマリアージュ(ペアリング)を学ぶ会。
- 【なぜ有効か】高価なドリンクも、専門家による解説という「知識・教養」の付加価値が加わることで、お客様は喜んで注文してくれる。ドリンクの売上を飛躍的に向上させるチャンス。
- 【特におすすめの業態】ワインバー、日本酒バー、ビストロ、イタリアン・フレンチ
- 【現代的なアレンジ例】「クラフトビールと餃子」「日本茶と和菓子」など、意外な組み合わせのペアリングを探求する。
③ セット注文を促す「テーマ別セット割引」
- 【概要】「とりあえずビールセット(ビール+枝豆+唐揚げ)」のように、単品で頼むよりお得なセットメニューを期間限定で提供する。
- 【なぜ有効か】お客様は「あれこれ選ぶのが面倒」と感じることがある。魅力的なセットを提示することで、注文の意思決定を助け、結果的に客単価を向上させる。
- 【特におすすめの業態】居酒屋、中華料理店、ビアガーデン、バル
- 【現代的なアレンジ例】「今夜はイタリアンな気分セット(グラスワイン+前菜盛り合わせ+パスタ)」など、利用シーンを想起させるネーミングにする。
④ “ついで買い”を誘う「物販・テイクアウト連動企画」
- 【概要】イベントで使用した特別なドレッシングや、お店オリジナルのレトルトカレーなどを、レジ横で販売する。
- 【なぜ有効か】店内での飲食体験に満足したお客様は、「この感動を家でも味わいたい」と感じる。客単価の上限である「胃袋のキャパシティ」を超えて、売上を上乗せできる。
- 【特におすすめの業態】ラーメン店(冷凍ラーメン)、カレー店(レトルト)、ベーカリー、カフェ(コーヒー豆)
- 【現代的なアレンジ例】イベント参加者限定で、オンラインショップの割引クーポンを配布する。
⑤ ゲーム性で注文を増やす「サイコロ・ガチャ割引」
- 【概要】ドリンクをおかわりする際、サイコロを振って出た目によって割引率が変わったり、ガチャを回して当たりが出たら一杯無料になったりする企画。
- 【なぜ有効か】「もう一杯だけ…」を後押しする、強力なエンターテイメント。損得を超えた「楽しさ」が、結果として注文数を増やし、客単価アップに貢献する。
- 【特におすすめの業態】居酒屋、バー、ビアホール、立ち飲み屋
- 【現代的なアレンジ例】スマホでQRコードを読み込んで引ける「オンラインガチャ」を導入し、人手がかからないようにする。
第4章 ただのアイデアを「行列のできるイベント」に変える3つの要素

第3章で、あなたの店の目的に合ったイベントアイデアの「種」を見つけることができましたね。しかし、多くの店がここで満足してしまい、「どこかで見たような、ありきたりなイベント」で終わってしまいます。
ここからが、競合と差をつける最も重要な工程です。選んだアイデアの種に、「独自性」「体験価値」「拡散性」という3つの魔法をかけることで、ただのアイデアを「行列のできるイベント」へと磨き上げていきましょう。
4-1.【独自性】なぜ「あなたの店」でなければならないのか?
面白そうなアイデアは、残念ながらライバル店も簡単に真似ができます。お客様に「このイベントは、他でもなく“この店”だから行きたい」と思わせるには、あなたのお店ならではの「独自性」を掛け合わせる必要があります。
難しく考える必要はありません。あなたの店の「強み」を再発見し、アイデアに掛け算するだけです。
あなたの店の強み発見シート
- 看板メニューや食材は? (例:創業以来のデミグラスソース、毎朝仕入れる新鮮な魚介)
- 名物スタッフはいる? (例:ソムリエ資格を持つ店長、元パティシエのアルバイト)
- お店の空間や立地に特徴は? (例:夜景が見えるテラス席、古民家を改装したレトロな内装)
例えば、第3章の「プロを招いたペアリング会」というアイデア。これだけだと普通ですが、あなたの店の強みを掛け合わせるとどうなるでしょう。
(アイデア) ペアリング会 × (強み) ソムリエ資格を持つ店長 → 【独自性のある企画】
「うちの店長が教える!コンビニお菓子と高級ワインの意外すぎるマリアージュ体験会」
このように、お店の強みを掛け合わせるだけで、他店には絶対に真似できない、魅力的なオリジナル企画が生まれるのです。
4-2.【体験価値】お客様に「最高の思い出」をどう提供するか?
お客様は、イベントに参加することで「モノ」ではなく「最高の思い出(コト)」を手に入れたいと思っています。企画を考える際は、お客様の五感や感情にどう訴えかけるかを意識することで、満足度は劇的に向上します。
体験価値を高める4つのスパイス
- 【物語性】 その食材がどうやって店に届いたか、そのメニューがどうやって生まれたか、といった背景ストーリーを語る。
- 【参加・没入感】 お客様を「観客」にせず、調理の一部を手伝ってもらったり、クイズを出したりして「参加者」にする。
- 【五感への刺激】 料理の見た目や香り、調理の音、店内の音楽、手触りの良い食器など、味覚以外の感覚にも訴えかける。
- 【非日常感】 照明を落とす、特別な制服を着る、特別なBGMを流すなど、普段の営業とは違う「ハレの日」の空間を演出する。
例えば、第3章の「高級食材・限定コース会」というアイデア。ここに体験価値を加えるとどうなるでしょう。
(アイデア) 限定コース会 + (体験価値) 物語性・五感への刺激 → 【体験価値のある企画】
「シェフがお客様の目の前で、生産者の想いを語りながら巨大な鮮魚を捌き、一番美味しい部分を振る舞うライブキッチンコース会」
ただ食べるだけよりも、記憶に残る満足度の高い体験になることは、火を見るより明らかです。
4-3.【拡散性】お客様が「思わず誰かに話したくなる」仕掛けとは?
現代のイベント成功に、SNSでの拡散は不可欠です。そして、「バズ」は偶然生まれるものではなく、意図的に設計することができます。「お客様が、誰かに話さずにはいられない」そんな仕掛けを企画に盛り込みましょう。
拡散性を生む4つのトリガー
- 【写真映え】 見た目のインパクトが強く、思わず写真に撮りたくなる要素。(例:巨大なパフェ、カラフルなドリンク)
- 【動画映え】 動きやサプライズがあり、動画で撮ると面白さが伝わる要素。(例:炎の演出、派手なパフォーマンス)
- 【意外性・驚き】 「まさか!」と思わせるような、常識を覆す組み合わせや結末。
- 【共感・応援】 頑張っている姿や、ストーリーに共感し、思わず「いいね!」を押したくなる要素。
例えば、第3章の「チャレンジ企画」というアイデア。ここに拡散性の仕掛けを加えるとどうなるでしょう。
(アイデア) チャレンジ企画 + (拡散性) 写真映え・動画映え → 【拡散性のある企画】
「激辛ラーメン完食チャレンジ!成功者には金色の巨大レンゲ(写真映え)で記念撮影!失敗者には面白い罰ゲーム動画(動画映え)をTikTokにアップ!」
このように、お客様がシェアしたくなる「ネタ」をあらかじめ用意しておくことで、イベントは自然と世に広まっていくのです。
第5章 イベント企画を成功に導く「告知」と「運営」の技術
素晴らしい企画も、お客様に知られなければ、そして当日の運営がスムーズでなければ、成功には至りません。この章では、練り上げた企画を成功に導くための、具体的な「実行マニュアル」を解説します。告知から当日運営、そして次へと繋げるフォローアップまで、この通りに進めれば安心です。
5-1. イベント告知の技術:アナログとデジタルの二刀流
告知の目的は、ただイベントの存在を知らせるだけではありません。「面白そう!」「絶対に行きたい!」と、お客様の期待感を最大限に高めることが重要です。
SNS媒体に関係なく告知するタイミングと頻度

SNSは媒体の種類「Instagram」「X」「TikTok」によって、それぞれ拡散の特性が違います。ですが、下記内容の告知方法であればどの媒体でも拡散される可能性が高いです。
どの媒体でも言えることは、SNSでの告知は一度で終わらせず、波状攻撃で期待感を醸成するのがセオリーです。
- 【1ヶ月前】第一報:
- 「〇月〇日、すごいイベントやります!」と、日程とテーマだけを匂わせるティーザー告知。詳細を明かさず、フォロワーの興味を惹きつけます。
- 【2〜3週間前】詳細公開・予約開始:
- イベントの全貌を公開し、予約受付をスタート。魅力的な写真や動画と共に、参加するメリットを伝えます。
- 【1週間前〜前日】リマインドと追加情報:
- 「残席わずか!」「限定メニューの仕込み風景をチラ見せ」など、カウントダウン的に投稿し、迷っている人の背中を押します。
またSNSを使った集客で必要な運用方法については『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事で詳しく解説しています。
チラシ・ポスターで地域に浸透させるコツ
デジタルだけでなく、アナログな告知も地域密着型の飲食店には非常に有効です。
- 「QRコード」を必ず入れる:
- チラシやポスターには、必ずSNSアカウントや予約フォームに飛ぶQRコードを印刷しましょう。アナログからデジタルへの橋渡しとなり、効果が倍増します。
- 「ちょい置き」を依頼する:
- 近隣の美容院や雑貨店など、ターゲット層が似ているお店に協力をお願いし、レジ横などにチラシを置かせてもらう「ちょい置き」は、低コストで効果的な手法です。
チラシの活用についてもっと詳しく知りたい方は、『飲食店がチラシで集客するには?効果の出るデザインの作成方法と配布のコツを大公開!』の記事がおすすめです。
5-2. イベント当日の運営術

当日は、予期せぬトラブルがつきものです。しかし、事前の準備と役割分担ができていれば、慌てることなくお客様の満足度を最大化できます。
スタッフの役割分担とリーダーの設置
当日の混乱を防ぐため、事前にスタッフの役割を明確にしておきましょう。
- リーダー: 全体を俯瞰し、指示を出す司令塔。トラブル発生時の最終判断者。
- 受付・案内係: お客様を笑顔で迎え、席へ案内するお店の顔。
- 進行・盛り上げ役: イベントの司会進行や、お客様とのコミュニケーションを担当。
- 厨房・ドリンク担当: イベント特別メニューの調理に集中。
スタッフが少ない店舗でも、「誰が何に責任を持つか」を決めておくだけで、動きの質が格段に上がります。
スタッフの接客の質を上げる方法について知りたい方は、『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』の記事をご覧ください。
当日のトラブルシューティング
よくあるトラブルへの備えがあれば、心に余裕が生まれます。
- 食材切れ: 想定より多めに仕込むのは基本。万が一品切れになった場合に備え、「幻の裏メニュー」などの代替案を用意しておくと、お客様をがっかりさせません。
- 急なキャンセル: 予約制の場合、事前にキャンセルポリシーを明記しておくこと。また、当日の飛び入り参加を若干名受け入れられるようにしておくと、空席を埋められます。
- クレーム発生: どんなに準備しても、クレームは起こり得ます。発生時は、まずリーダーが真摯にお客様の話を聞き、誠意をもって対応する、という基本動作を徹底しましょう。
5-3. イベント後のフォローアップ

イベントは、終わった瞬間から「次のイベント」が始まっています。熱が冷めないうちにフォローアップを行い、次回の成功へと繋げましょう。
参加者へのお礼とフィードバック依頼
イベント翌日、LINE公式アカウントやSNSのDMなどで、参加者一人ひとりにお礼のメッセージを送りましょう。その際に、「イベントの感想をお聞かせください!」とアンケートフォームのURLを添えれば、貴重な改善点が見つかります。
イベントレポートの作成と発信
当日の楽しそうな写真や動画をまとめ、「イベントレポート」としてSNSやブログで発信します。
- 参加者にとっては… 楽しかった思い出を振り返るきっかけになります。
- 参加できなかった人にとっては… 「次は絶対に参加したい!」という強い動機付けになります。
このレポートが、次回のイベント告知における、何より強力な「実績」となるのです。
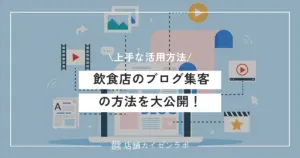
5-3. 次回イベントの予約・先行案内を出す
成功したイベントは、同じテーマ・コンセプトでシリーズ化するのも1つの手。参加者に「次回は○○な内容でやります。先行予約を受け付けています」と案内すれば、リピート率アップが期待できます。
5-4. 通常営業にもイベント要素を一部残す
イベント直後だけ盛り上がって終わるのではなく、通常時の営業でも「面白い!」と好評だったメニューや雰囲気をある程度維持しておくと、リピーターが来店しやすいです。
第6章 こんなときどうする?飲食店イベントに関するQ&A

飲食店でイベントを開く際に、多くの方が抱く疑問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
- 予算が限られていてもイベントできますか?
-
もちろん可能です。SNS割引や店内の装飾を少し工夫する程度でも、十分“面白い”演出はできます。例えば「雨の日ドリンク半額」や、フォトジェニックな小物をテーブルに置くだけでも話題になることがあります。大掛かりな機材や高級景品がなくても「参加して楽しい」「SNSに載せたい」と思わせられればOKです。
- スタッフが少ない店でも大丈夫?
-
スタッフ数が少ない小規模店は、イベントの種類や規模を調整するのがポイント。オーダーが殺到するようなゲーム要素を避け、予約制ワークショップなど“ゆるやか”な企画で回すのも手です。また、忙しい日にアルバイトを増やすか、友人や家族に臨時手伝いをお願いするケースも見られます。
- 告知しても反応が薄い…改善策は?
-
反応が薄いときは「告知期間」「媒体の使い方」「告知内容」の3点を見直します。たとえばイベントまで1週間しかないと認知が広がりにくいですし、ターゲット層が使わないSNSを中心に発信しても効果は低いです。また、「どんな面白さがあるのか」「どんな特典があるのか」を端的に伝えるコピーが重要です。
- イベント当日に欠席やキャンセルが多い場合は?
-
天候や急な体調不良などでキャンセルが出るのはある程度仕方ありません。事前予約を取る場合はキャンセルポリシーを明確にしておき、直前キャンセルには一定のキャンセル料を設定しておくことも検討しましょう。また、飛び入り参加を許容する“ゆるめ”の形式にしておくと、当日追加で来てくれる人がいるかもしれません。
- クレームやトラブル対応が心配です。
-
まずはスタッフ同士で「どんなトラブルが起き得るか」を想定し、対処方法を共有しておくと安心です。料理が遅れる場合はすぐに謝罪し、特典ドリンクをサービスするなど誠意を見せる方法もあります。大声や喧嘩など他のお客様に迷惑が及ぶ行為が起きたら、店長やリーダーが冷静に対処する姿勢を明確にしましょう。
第6章 まとめ:面白いイベントアイデアがない時はイベント企画ワークフローを活用
ここまで、飲食店のイベントを成功させるための思考法から具体的なアイデア、そして実行マニュアルまでを解説してきました。情報量が多かったかもしれませんが、最も重要なメッセージは非常にシンプルです。
6-1. 面白いイベントとは「目的を達成する手段」である
「面白いイベント」とは、単なる思いつきのアイデアや、場当たり的な賑やかしではありません。 それは、あなたの店が抱える経営課題を解決するための、極めて戦略的な「手段」です。
- 新規顧客が足りないなら、彼らが足を運びたくなる「きっかけ」を作る。
- リピーターが少ないなら、彼らとの「絆」を深める。
- 売上が低いなら、お客様が喜んでお金を払ってくれる「付加価値」を創造する。
常にこの原点に立ち返り、「何のために、誰のためにやるのか?」を問い続けること。それこそが、数多の飲食店の中からあなたの店が選ばれるための、唯一無二の答えを見つけ出す鍵となります。
この記事で紹介したフレームワークやアイデアが、あなたの挑戦の一助となり、お店に新たな風を吹き込むきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
6-2. この記事をなぞるだけ!イベント企画ワークフロー
「何から手をつければいいか分からない…」 そんなあなたのために、この記事の内容を凝縮した、「イベント企画立案ワークシート」をご用意しました。以下の質問に順番に答えていくだけで、あなたの頭の中にある漠然としたアイデアが、実行可能な企画書へと変わっていきます。
ぜひ、このワークフローを活用してみてください。
イベント企画立案ワークフロー
- [目的] このイベントで解決したい、店の最も大きな課題は何ですか?
- ( ) 新規集客 ( ) リピーター育成 ( ) 売上/客単価UP ( ) 認知度UP/ブランディング
- ( ) 新規集客 ( ) リピーター育成 ( ) 売上/客単価UP ( ) 認知度UP/ブランディング
- [ターゲット] このイベントで、最高に喜ばせたい「たった一人のお客様」はどんな人ですか?
- (例:近所に住む30代のグルメなOL、サッカー好きの40代男性グループ…)
- [アイデア] 上記の目的を達成するために、第3章のどのアイデアが最も効果的だと思いますか?
- (アイデア名: )
- [独自性] そのアイデアに、あなたの店の「強み(名物メニュー、スタッフ、空間など)」を掛け合わせると、どんなオリジナル企画になりますか?
- (アイデア × 私の店の強み = )
- [体験価値] お客様に「最高の思い出」を提供するために、どんな演出や工夫を加えますか?
- (例:シェフが目の前で調理する、生産者のストーリーを語る…)
- [拡散性] お客様が思わずSNSでシェアしたくなるような「映える」仕掛けはありますか?
- (例:巨大なオブジェ、派手なパフォーマンス、面白いハッシュタグ…)
- [イベント名] 全てを踏まえ、お客様がワクワクするようなイベント名を付けてください。
- (イベント名案: )
- [開催日時] いつ開催しますか?
- [参加費・価格] いくらに設定しますか?
- [告知方法] 誰に、どの媒体で、いつから告知を始めますか?