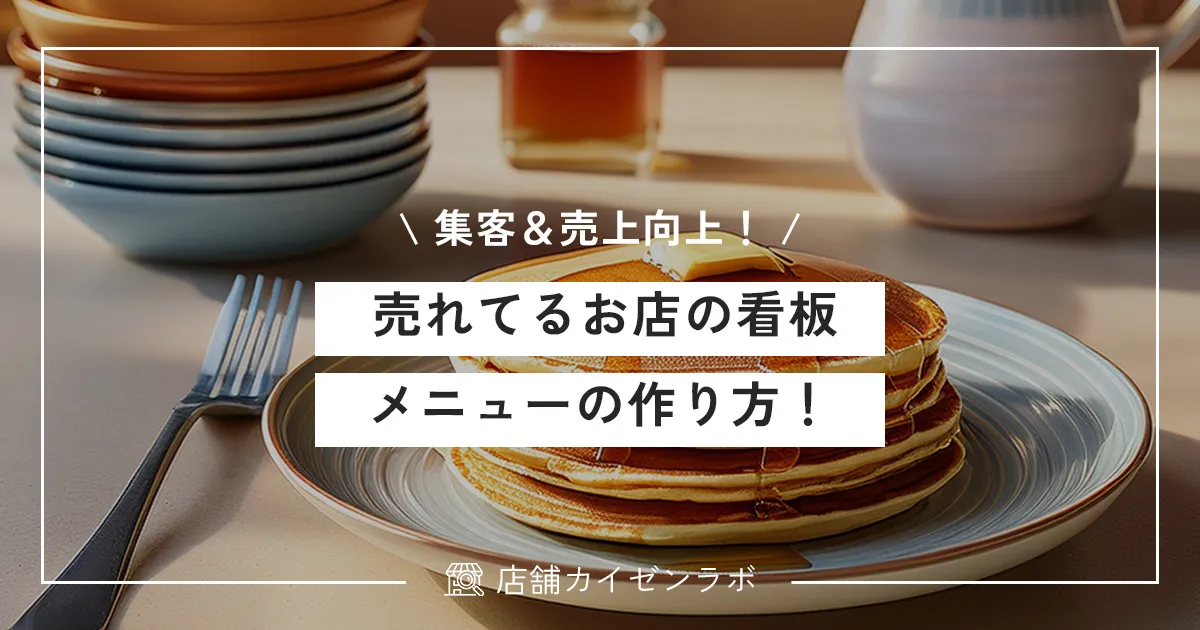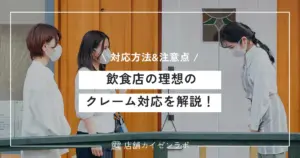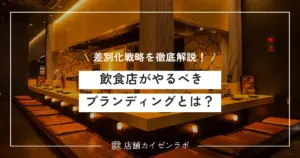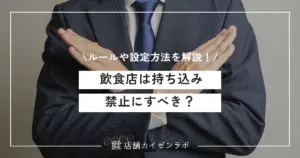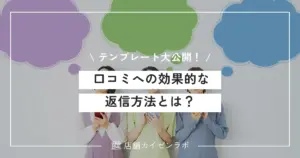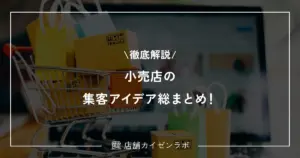第1章. 飲食店で看板メニューが必要とされる理由

飲食店にとって、看板メニューは単なる「人気料理」ではありません。来店したお客様が「ここにしかない特別な一品」を体験することで、新規顧客の獲得やリピート率の向上に直接結びつくお店の核となります。たとえば、新規のお客様は初めての訪問時に「何を頼めばいいのだろう」と迷うことが多いですが、はじめから「看板メニューを注文すれば間違いない」とわかっていれば、お店へのハードルがぐっと下がります。
さらに一度「これはおいしい」と実感していただければ、次回も同じメニューを求めてリピート来店しやすくなり、固定ファン化につながります。飲食店では当然、味やサービス、価格などさまざまな要素が重要ですが、その中でも集客面に直結するのが看板メニューの存在です。実際に筆者が関わった店舗でも、目玉となるメニューを設定していなかった頃は、月の新規来店数が伸び悩んでいました。しかし「当店特製フワトロ親子丼」と銘打った名物メニューを打ち出したところ、Web予約の段階で「看板メニューを目当てに来ました」という声が増加。看板メニューが顧客の心をつかみ、お店の知名度アップにつながった好例です。
看板メニューはブランドの象徴です。詳しくは『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』もご覧ください。
第2章. 飲食店の売れる看板メニューの作り方とポイント

2-1. コンセプトを明確化
売れる看板メニューを生み出す第一歩は、コンセプトの明確化です。どんなに魅力的なレシピでも、ターゲット層やお店の方向性とズレているとヒットしません。まずはお店の経営方針やターゲット、利用シーンを言語化し、料理がその軸から外れないように開発を進めていきましょう。
2-1-1. ターゲットや利用シーン、ニーズなどを考える
自分たちが「作りたい料理」が優先されると、実際に顧客が求めるものから外れてしまうリスクがあります。ファミリー層がメインなのか、オフィス街でビジネスランチを狙うのか、デート利用が多いのか――ターゲットと利用シーンを具体的に設定すると、どのようなメニューを看板として推すべきかが見えてきます。
- 家族連れの場合:食べやすさ、健康志向、ボリューム感
- ビジネスパーソンの場合:短時間での提供、価格の分かりやすさ
- デート利用の場合:見た目の華やかさ、シェアしやすさ
たとえば「お子様連れが多いイタリアンのお店」であれば、ピザやパスタに追加トッピングができるようにすると満足度を高められます。ここに“店独自のコンセプト”が加わると、ほかの飲食店では体験できない一皿が完成するのです。
2-1-2. ストーリー性があるか
商品名やレシピだけでなく、その背景にストーリーがあると魅力が何倍にも膨らみます。「何気なく作った看板メニュー」と「生産者との出会いで開発した特製レシピ」では、同じ材料であってもお客様の興味や満足度がまったく違います。たとえば「朝どれ野菜を農家さんから直接出荷してもらい、その日の朝に届いた食材だけで作る特製スープ」などは、会話のネタにもなりやすく、SNS投稿の際も感動が広がりやすいです。
筆者が以前、地元の食材を積極的に使う居酒屋を支援した際には、「地元漁港直送の魚を使った炙り寿司」という看板メニューを開発し、漁港や生産者との関わりをPOPやSNSで発信してもらいました。すると「漁師さんたちの熱い思いを応援したい」という地域の方も積極的に来店し、集客力が向上しました。
2-1-3. 五感を刺激する美味しさの要素があるのか
「味」だけがすべてではないのが現代の外食トレンドです。料理が提供される際の音や香り、盛り付けの色彩や高さ、さらに噛んだときの食感――こうした五感へのアプローチが、看板メニューのリピート率を飛躍的に伸ばします。
- 音:ジュージューと音が立つ鉄板料理、揚げたてのパリッとした食感
- 香り:スパイスの香り、焼きたてパンの香ばしさ
- 見た目:鮮やかな彩りやシズル感が伝わる湯気
五感を刺激しやすいポイントをまとめておくと、スタッフのプレゼンやメニュー表のPRにも活かしやすいです。
2-2. 他店との差別化
周辺に似たような競合店が多い場合ほど、明確な差別化が必要となります。とはいえ、差別化とは「完全に他店と異なる料理を作る」という意味ではありません。むしろ「よくあるメニューでも、ここのは一味違う」と思ってもらえるポイントを探すことが大切です。
たとえば、ラーメン店なら「毎朝製麺所から取り寄せる自家製麺を使う」「化学調味料を使わない」などのこだわりを看板メニューでアピールします。居酒屋なら「自社醸造のクラフトビールと相性抜群の唐揚げ」が推しとなるケースもあるでしょう。ライバル店をリサーチしつつ、自分たちのお店でしか体験できない価値を見つけることで、顧客に「これなら通いたくなる」と思ってもらえます。
筆者の実践談:ちょっとしたアイデアで
こうした差別化のポイントは「美味しさ+α」。それが独自の調理法やストーリー、盛り付け、ネーミング、価格設定でも構いません。追加の一工夫が「差別化」につながり、周囲のライバル店との差を明確化してくれます。
2-3. ネーミング

看板メニューを決定づける要素の一つに「ネーミング」があります。料理名が目に留まらなければ、お客様に記憶されにくく、SNS投稿の際に話題にもなりづらいからです。そこで、わかりやすさと特別感を同時に伝えるネーミングを心がけましょう。
- 店名+特製:「○○(店名)特製ローストビーフ丼」
- 出荷地の強調:「北海道○○産直送!濃厚ウニクリームパスタ」
- 期間・限定感:「冬だけ味わえる炙り牡蠣のグラタン」
また、料理の特徴が伝わるキャッチーな言葉を入れるのも一つの方法です。たとえば「濃厚」「ジューシー」「直送」「限定」といったワードは目を引きますが、あまりに誇大な表現はトラブルの元になりかねないので、必要以上に盛りすぎないバランスが大切です。
看板メニューの名前で惹きつけるには、キャッチコピーの工夫も有効です。参考記事は『飲食店の集客に効果的なキャッチコピーの作り方!具体的な考え方から成功事例まで徹底解説!』。
2-4. 見た目

レシピそのものが秀逸でも、見た目の魅力を活かしきれないと、お客様の心は動きにくいもの。特にSNS投稿が主流の現代では、ビジュアルを強く意識する必要があります。全体の色合い、サイズ感、盛り付けの高さや奥行きなどを調整して、最初の一瞬で「わあ!」と驚いてもらえるように工夫しましょう。
- 彩り:赤、緑、黄色などカラフルに仕上げると写真映えしやすい
- 高さ:タワー状に盛る、断面を強調するなど立体感を演出
- 器選び:料理の色味と器が相性良ければ、一枚の写真で映える
例えば、すき焼きや鍋料理などは、鍋の中身が似たような色合いになりがちです。そこへ季節の野菜をトッピングして彩りを加えたり、食材の産地表示プレートをスタンド風に添えたりするだけでも、印象に残りやすくなります。
魅力的な見た目づくりには、料理写真のクオリティも欠かせません。撮影については『飲食店で綺麗な写真撮影をする基本知識とコツ!外注する場合の注意点まで!』で紹介しています。
2-5. 目的に応じた価格設定
看板メニューの価格を決める際に、単純に「原価×何倍」で設定すると、来店動機にズレが生じる場合があります。低価格で集客を狙うのか、やや高価格でもプレミア感を打ち出すのか、目的によって最適な価格帯は変わってくるからです。
- 集客重視:¥1単位の値段調整でお得感を演出し、新規顧客を狙う
- 高付加価値重視:素材や調理法のこだわりを前面に出し、多少高くても納得感を与える
たとえば、新規顧客を呼び込む「入り口商品」として看板メニューを位置づける場合は、「初回限定」「オープン記念価格」のようなプロモーションも有効です。逆に高単価路線を狙うなら、食材の産地や栽培方法、開発秘話を丁寧に伝え、価格設定の根拠を明示することで、お客様に納得してもらいやすくなります。
平日でも来店を促すには、戦略的な看板メニュー活用がカギです。詳しくは『【完全版】飲食店で平日集客を伸ばす方法を総まとめ!無料でもできる効果的なお店への来店の増やし方!』。
2-6. 演出(スタッフトーク・メニュー表・SNS)

せっかく魅力的な看板メニューを用意しても、お客様にしっかりアピールできなければ宝の持ち腐れです。具体的には以下のような演出方法があります。
- スタッフトーク
- スタッフが実際に食べた感想や、おすすめポイントを熱意をもって伝える
- 「今日のイチ押しです」と一言添えるだけでも注文率が上がる
- スタッフが実際に食べた感想や、おすすめポイントを熱意をもって伝える
- メニュー表・POP
- 写真付きのメニュー表でシズル感を強調
- 値段のすぐ近くに「当店イチオシ」「大人気!」などのコメントを入れる
- 写真付きのメニュー表でシズル感を強調
- SNS発信
- インスタグラムなどで、ハッシュタグをつけた投稿を無料で拡散
- 店舗公式アカウントにメルマガ登録のリンクを載せ、次回のイベント告知にも活用
- インスタグラムなどで、ハッシュタグをつけた投稿を無料で拡散
演出の際には、保存が効く仕組みも大切。スタッフ間や新入社員向けに「プレゼンマニュアル」を作成し、共有フォルダに保存しておけば、ブレなく看板メニューを紹介できます。オンラインでの登録も合わせて運用し、従業員がいつでも見られるようにしておくと安心です。
SNSで魅力を伝えるには、効果的な運用方法も重要です。詳しくは『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事をご覧ください。
第3章. 繁盛店の看板メニューに共通する5つの重大ポイント

3-1. インパクトある見た目
繁盛店を訪れると、メニュー表を開かなくても「あれが有名な看板メニューだよ」とわかる場合が多々あります。その理由の一つが、圧倒的なビジュアルです。写真一枚でも人の心をつかむインパクトを持たせると、SNSなどで自然に拡散が生まれ、さらなる集客効果を高めることができます。
- 盛り付けで高さを出す:タワー状やエクストラサイズなどの迫力
- 光や熱気を見せる:鉄板やステーキのジューシー感
- 派手な彩り:カラフルな食材を使い、コントラストを際立たせる
「インスタ映え」だけが狙いでなく、実際にお客様が「つい写真を撮りたくなる」「これ、すごいね!」と感じる仕掛けが重要です。多くのお客様が料理の写真をSNSに投稿してくれれば、それ自体が無料のプロモーションとなります。
3-2. シズル感が伝わる工夫
見た目のインパクトに加え、「音」「香り」「湯気」といった要素でシズル感をプラスするのも、繁盛店のセオリーです。例えば鉄板焼きが運ばれてきた瞬間にジュージューという音が響くと、周囲のお客様も思わず「何だろう?」と注目し、次の注文につながります。
また、スープやラーメンのような湯気の立つ料理では、メニュー名に「アツアツ」「湯気たっぷり」などのフレーズを入れて、視覚だけでなく五感に訴える仕掛けが可能です。こうした演出は、味そのものを高めるだけでなく、顧客のテンションを高める効果があります。
3-3. 切り方や調理法の工夫
食材そのものを変えなくても、切り方や調理法の工夫だけで「こんな味わいがあったのか!」という驚きを与えられます。例としては、以下のようなパターンがあります。
- 断面を見せる:厚めにカットしてミディアムレアの肉断面を強調
- 真空調理で柔らかく仕上げる:時間はかかるが、ジューシーさを最大限に引き出せる
- スパイスのブレンド:同じ食材でも配合次第で風味や辛さがまったく変わる
切り方一つで見た目や食感が大きく変わるのは、料理好きな方にも受け入れられやすいポイントです。専門性やプロの技が光る要素を看板メニューに盛り込むことで、「あのお店は本格志向」という評価にもつながります。
3-4. 食べ方の提案
繁盛店では、「こうやって食べるともっとおいしい」「途中でこのソースを追加すると味変できる」といった食べ方の提案を積極的に行います。これがあると、お客様は最後まで飽きずに料理を楽しめるうえ、一皿に複数のバリエーションを感じ取れます。
- トッピングのおすすめ:チーズ、唐辛子、ガーリックなど好みでプラス
- 途中で足す調味料:タバスコ、レモン汁、和風だしなど
- 仕上げの演出:卓上バーナーで炙る、スタッフがテーブルサイドで仕上げる
こうしたアクションがあると、視覚や嗅覚に刺激を与えながら、インパクトを与える瞬間を増やすことができます。お客様同士の会話も弾み、「またこの体験をしたい」と思わせる仕掛けとなるのです。
3-5. お客様の好みに合わせてカスタマイズ
誰もが食べられる万人向けの料理よりも、自分の好みに合わせて「カスタマイズ」できるほうが、愛着が湧きやすい傾向があります。例えば「辛さレベルを選べるカレー」や「麺の硬さを選べるラーメン」など、お客様の食の楽しみ方を重視すると、リピート率もアップしやすくなります。とくに昨今は食物アレルギーや健康志向の方も多いため、油の量や塩分カット、グルテンフリー対応などのオプションがあると幅広い層に支持されやすいです。結果的に「自分に合った味を選べるお店」という好印象を持ってもらい、常連客が増える要因となります。
第4章. 看板メニュー作りに関してよくある疑問や質問

4-1. Q1:とにかく低価格にすれば看板メニューは売れる?
低価格に設定すれば、一時的に集客は増えるかもしれません。しかし、見合わない価格で赤字が出ると、長期的にはお店の経営を圧迫してしまいます。さらに安すぎる看板メニューは「原価は大丈夫なのか?」と不安に思われたり、お店の品質イメージが下がったりする恐れも。むしろ「満足度の高い価格帯」を狙い、顧客が納得できるコストパフォーマンスを整えることが大切です。たとえば、¥1単位の細かな調整でお得感を演出したり、高級食材を使うなら原産地や出荷元の情報を打ち出して価格の根拠を明確にするといった工夫が必要です。
4-2. Q2:独創的な料理であれば必ず成功する?
ユニークさは注目を集める要素ですが、独創性だけでは注文につながらないこともあります。たとえば、あまりに奇抜な料理だと顧客が味や価値をイメージしづらく、結果的に敬遠されるケースも少なくありません。大切なのは、「おいしい+話題性+お店のコンセプト」が噛み合っているか。味とネーミング、見た目、ストーリー性がバランス良く融合してはじめて、お客様が「食べてみたい」「誰かに教えたい」と感じる看板メニューが完成します。
4-3. Q3:スタッフのプレゼンをどう教えればいい?
看板メニューの魅力を十分に伝えるには、スタッフのプレゼン力が欠かせません。ポイントは「自分が食べた感想を具体的に語れるようにする」こと。たとえば、試食会を行い、味の特徴や調理のこだわりを共有すると、接客時に自然な追加トークが生まれます。また、マニュアルを作成して保存・登録し、誰でも一定のクオリティでプレゼンできるようにしておくことも重要です。特に忙しい時間帯には、短いフレーズでサッとおすすめできるよう準備しておきましょう。
看板メニューをしっかり伝えるには、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』も重要です。
4-4. Q4:SNSバズが最終ゴールなの?
SNSでバズると一気に注目度が高まりますが、それがゴールになってしまうと、一過性のブームで終わってしまう可能性が大きいです。大切なのは、飲食店として顧客が再来店したくなる理由を整えておくこと。バズで得た新規客に「もう一度食べたい」と思わせる味やサービス、店舗の雰囲気がなければ、リピートにはつながりません。SNSはあくまでも看板メニューや店舗を知ってもらう入口の一つと考え、その後の満足度を高める仕組みを持続させましょう。
4-5. Q5:定番メニューは看板になりづらいのでは?
定番メニューもアイデア次第では十分に看板にできます。むしろ、既存メニューを少しアレンジするだけでブレイクする可能性も。たとえば、カツ丼や唐揚げの“盛り付け”や“食べ方提案”を変えてみたり、特別なソースを開発するなど、小さな工夫でも大きな差別化につながることがあります。長年愛されているメニューなら、その背景や伝統をストーリー化して打ち出すと、お客様に新鮮な発見を与えられます。
第5章. 看板メニューを開発して飲食店としてのブランド力を磨こう!
看板メニューの成功には、お店のコンセプトとターゲットを明確にし、料理自体の魅力とともに名前や見た目、価格設定、スタッフのトーク、SNSなど多面的な工夫が必要です。特に印象的な見た目や、五感をくすぐる演出は集客効果が高く、新規顧客やリピーターを増やすカギになります。価格を低くするだけではなく、素材やストーリーを丁寧に伝えることで、お客様が納得する付加価値を生み出すことも大切。
さらに、「食べ方の提案」や「カスタマイズ」などのアプローチを加えれば、一皿で何度も楽しめる奥深さがプラスされ、話題性がアップします。最終的にはスタッフ全員で看板メニューの魅力を共有し、一貫性のある発信を続けることで「このお店といえばあの料理」という強固なブランドイメージを築けるでしょう。
看板メニューを中心にした販促戦略について、より詳しくは『【完全版】飲食店で効果の高い販促方法を総まとめ!売上や来店に繋がる手法を大公開!』をご覧ください。