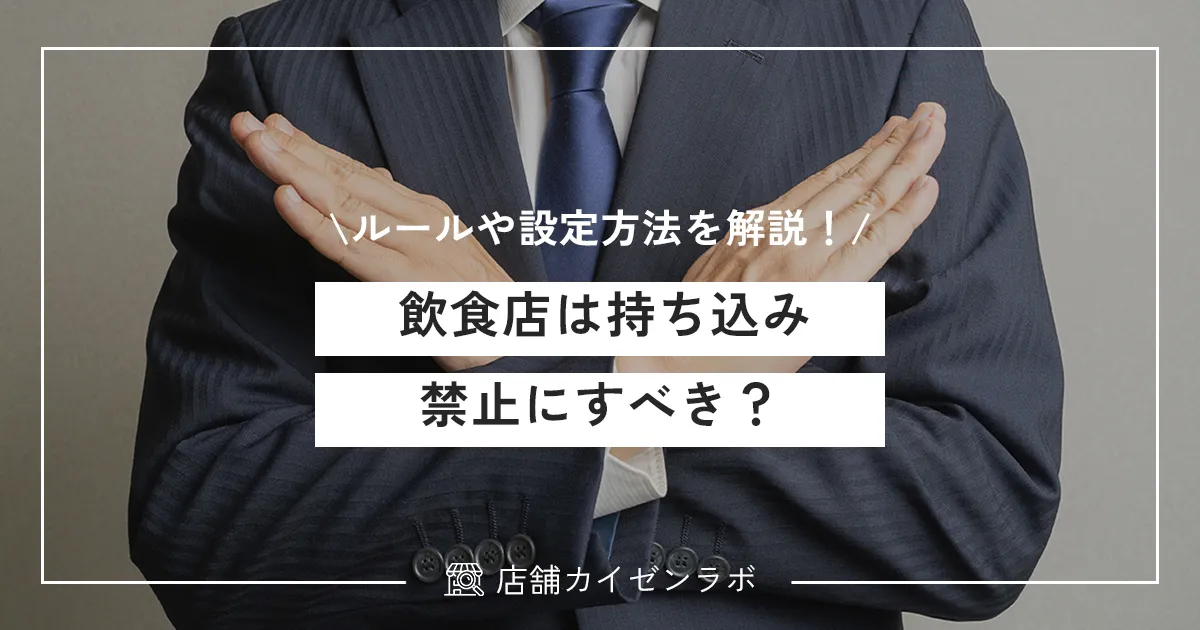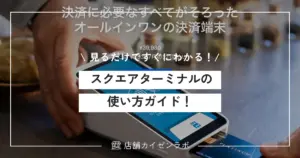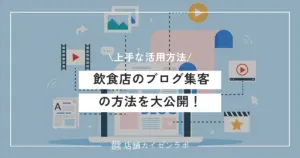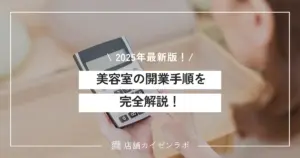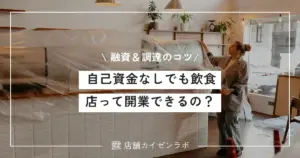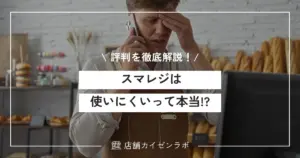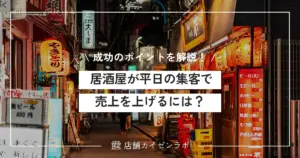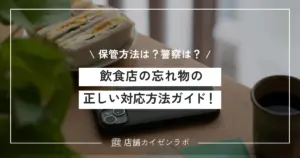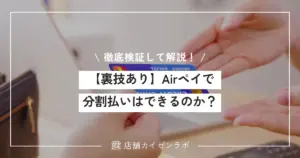第1章 なぜ飲食店は持ち込みを禁止するのか?3つの本質的リスクとは

飲食店を経営する上で、「お客様による飲食物の持ち込み」は避けては通れない課題です。多くの店舗が原則として持ち込みを禁止していますが、その背景には大きく分けて3つの本質的なリスクが存在します。持ち込み許可を検討するにしても、まずはこれらのリスクを正確に理解し、管理体制を構築することが成功の絶対条件となります。
1-1. 店の利益が低下する
飲食店が持ち込みを禁止する最大の理由は、店舗の利益構造に直接的な打撃を与える経済的リスクです。
お客様が店外から飲食物を持ち込む行為は、店舗の売上機会の損失に直結します。特に、飲食店の利益率を支えるドリンクメニュー、中でもワインや日本酒といったアルコール飲料は重要な収益源です。例えば、原価3,000円のワインを10,000円で提供している場合、1本の注文で7,000円の粗利益が生まれます。しかし、お客様が同価格帯のワインを持ち込んだ場合、この7,000円の利益は完全に失われます。
また、売上減少だけでなく、在庫管理への悪影響も無視できません。店舗側が需要を見越して仕入れた食材や飲料が、持ち込みによって消費されなければ、在庫回転率は低下します。これはキャッシュフローの悪化を招くだけでなく、賞味期限切れによる食品ロスを増加させ、結果的に原価を圧迫する要因となります。
1-2. 信頼を失いかねない衛生・安全上の問題

利益と並んで深刻なのが、衛生管理と安全性に関わるリスクです。飲食店が提供する料理や飲み物は、食品衛生法に基づき、店舗の責任において厳格な衛生基準の下で管理されています¹。しかし、外部から持ち込まれた飲食物は、その保管状況や品質を店舗側が一切保証できません。
万が一、お客様が持ち込んだ食品が原因で食中毒が発生した場合、たとえ店舗に直接的な非がなくても、「あの店で食中毒が起きた」という事実が独り歩きする危険性があります。
【飲食店コンサルタント A氏】 「持ち込み食品による食中毒は、店舗にとって最悪のシナリオの一つです。原因が外部にあると証明することは極めて困難で、保健所による営業停止処分や、SNSでの風評被害によって、築き上げてきた信頼が一瞬で崩れ去るリスクがあります。安易な許可は経営の根幹を揺るがしかねません。」
さらに、アレルギーの問題も深刻です。持ち込まれたケーキや食品に、他のアレルギーを持つお客様にとって危険なアレルゲンが含まれていた場合、コンタミネーション(意図しない混入)を引き起こす可能性もゼロではありません。
1-3. サービス品質を低下させる店舗オペレーションへの影響

持ち込みは、店舗の円滑なオペレーションにも様々な影響を及ぼします。
スタッフは、お客様が持ち込んだ飲食物と店舗のメニューを混同しないよう、常に注意を払う必要があります。これにより、配膳ミスやオーダーミスが発生しやすくなるだけでなく、持ち込み品のグラス交換やゴミの処理など、本来不要な業務が増加し、サービス全体の品質低下を招きます。
このように、一部のお客様の持ち込みを黙認すると、他のお客様から「なぜあの席は良くて、うちはダメなのか」という不満やクレームに発展しやすくなります。スタッフはその対応に追われ、本来のサービスに集中できなくなります。
店舗の限られたスペースに外部の荷物や容器が増えることで、動線が妨げられ、快適な食事環境が損なわれることも問題です。これらのオペレーション負荷は、スタッフの疲労とモチベーション低下に繋がり、長期的には店舗の評判を落とす原因となり得ます。
【本章のチェックポイント】
持ち込み許可を検討する前に、まずは「経済的」「衛生的」「運営的」な3つのリスクを自店でコントロールできるか、冷静に評価することが不可欠です。
第2章 失敗しないための「持ち込みルール」設計方法

前章で解説したリスクを理解した上で、それでもなお「持ち込み」を許可し、他店との差別化や顧客満足度の向上に繋げたいと考える経営者の方も多いでしょう。成功の鍵は、曖昧さを排除した明確なルールの設計と徹底した周知にあります。本章では、持ち込み許可を成功させるための具体的なルール設計フローを4つのステップで解説します。
2-1. 【ステップ1】持ち込みを許可する飲食物の種類を明確にする
最初に決めるべきは、「何を」「どこまで」許可するのか、という対象範囲の定義です。全ての持ち込みを無条件に許可するのはリスクが高すぎます。店舗のコンセプトや客層に合わせて、許可する品目を限定しましょう。
- 一般的な許可対象の例
- 飲料: ワイン、日本酒、焼酎など、店舗の料理と相性が良いボトル飲料。
- 食品: 誕生日や記念日のデコレーションケーキ。
- 特別な配慮: アレルギー対応食、離乳食。
- 原則として禁止すべき対象の例
- 競合する商品: ビール、ソフトドリンクなど、店舗で提供しているメニュー。
- 匂いの強い食品: 調理済みの惣菜やファストフードなど、他の客に影響を与えるもの。
- 安全性が不明なもの: 手作りの料理や加工品。
2-2. 【ステップ2】持ち込み料(コルケージ)を戦略的に設定する
持ち込みを許可する場合、売上減少を補填し、サービス対価を正当に得るために「持ち込み料(コルケージ)」の設定は必須です。価格設定は、店舗の格やサービスレベルを反映する重要な要素となります。
基本的な持ち込み料の考え方持ち込み料=サービスコスト(グラス・人件費など)+機会損失分の利益補填持ち込み料=サービスコスト(グラス・人件費など)+機会損失分の利益補填
価格設定のパターン例
| 店舗タイプ | 持ち込み料(ワイン1本あたり) | 設定の狙い |
|---|---|---|
| カジュアルなビストロ・居酒屋 | 1,000円~2,000円1,000円~2,000円 | 気軽に利用してもらい、持ち込みをきっかけに来店を促す。 |
| 中価格帯のレストラン | 2,000円~3,500円2,000円~3,500円 | サービス品質(グラス、抜栓、温度管理)に見合った対価を確保する。 |
| 高級レストラン・専門店 | 3,500円~3,500円~ もしくは 店舗提供ワインの最安値 | 高品質なサービスを提供し、安易な持ち込みを抑制。店舗のブランド価値を維持する。 |
2-3. 【ステップ3】店舗の利益を守る注文条件(ミニマムチャージ)を設定する
持ち込み料だけでは、客単価の低下を防ぎきれない場合があります。そこで有効なのが、「持ち込みをする場合の最低注文条件(ミニマムチャージ)」の設定です。
- 注文条件の具体例
- コース料理の注文を必須とする: 「〇〇円以上のコース料理をご注文のお客様に限り、持ち込みを許可します」
- 最低注文金額を設定する: 「お一人様あたり〇〇円以上のご注文をお願いいたします」
- 料理の品数で条件を設定する: 「お一人様あたり前菜・メインを各一品以上ご注文ください」
これにより、お客様は持ち込みを楽しむと同時に、店舗の料理もしっかりと注文してくれるため、客単価の安定化と料理の売上確保に繋がります。
2-4. 【ステップ4】ルールを徹底的に周知する
どんなに優れたルールも、お客様に伝わらなければ意味がありません。トラブルを未然に防ぐため、あらゆる顧客接点でルールを周知徹底しましょう。
- 周知方法のチャネル別ポイント
- 公式ホームページ/SNS: 「持ち込みポリシー」として専用ページを作成し、料金、対象品目、注文条件、予約方法を明記する。
- 予約サイト(食べログなど): 店舗情報の備考欄やコース説明に、持ち込みルールを簡潔に記載する。
- 電話/メール予約受付時: 「当店では持ち込みに関するルールがございますが、ご利用はございますか?」と一言確認する。
- 店内のPOP/メニューブック: 入り口やテーブル、メニューブックに、ルールを明記した案内を設置する。イラストや多言語表記も有効です。
【本章のチェックポイント】
「何を」「いくらで」「どんな条件で」許可するのかを具体的に設計し、お客様が予約する前にその情報を届けきることが、持ち込み戦略成功の生命線です。
第3章 持ち込み発生時の実践的オペレーションと対応術

明確なルールを設計しても、現場での対応が伴わなければ絵に描いた餅です。本章では、スタッフ全員が迷わず、かつスマートに対応できるための具体的なオペレーション手順と、トラブルを未然に防ぐコミュニケーション術を解説します。
3-1. 【ケース別】持ち込み対応の具体的なオペレーション手順
お客様の持ち込みには、ルールを理解した上での「事前申告あり」のケースと、ルールを知らない「無断持ち込み」のケースがあります。それぞれ対応フローを確立しておくことが重要です。
A)事前申告ありのお客様へのスマートな対応フロー
- 予約内容の再確認: 来店時に予約内容を再確認。「本日は〇〇(ワイン名など)をお持ち込みですね。コルケージ料として〇〇円を頂戴いたします」と料金を明確に伝える。
- 持ち込み品の受け取りと管理: お客様から丁重に預かり、適切な場所(ワインセラー、冷蔵庫、バックヤードなど)で保管する。ラベルにテーブル番号を記載し、取り違えを防ぐ。
- 最適なタイミングでの提供: お客様に「いつ頃お開けしますか?」とタイミングを伺う。料理の進捗に合わせて、最適な状態で提供する。
- プロフェッショナルなサービス: 抜栓、デキャンタージュ、グラスへのサーブなど、店舗のサービスレベルに合わせた対応を行う。
- 会計時の明記: 会計伝票に「持ち込み料」または「コルケージ」と明確に記載する。
B)無断持ち込みが発覚した際のスマートな対応フロー
- 状況の静かな確認: まずは慌てず、お客様のテーブルへ行き、小声で話しかける。「お客様、誠に恐れ入ります。そちらのお飲み物は、お持ち込みされたものでしょうか?」
- ルールの丁寧な説明: 持ち込みの事実が確認できたら、感情的にならず、お店のルールを丁寧に説明する。「大変申し訳ございませんが、当店では原則としてお持ち込みをご遠慮いただいております。もしご利用になる場合は、〇〇円の持ち込み料を頂戴しておりますが、いかがなさいますか?」
- 選択肢の提示: お客様に選択を委ねる。「①持ち込み料をお支払いいただきお楽しみいただく」「②お帰りの際までこちらでお預かりする」といった選択肢を提示する。
- 毅然とした対応: 万が一、お客様がルールに従わない場合は、他のお客様への影響を考慮し、責任者が毅然とした態度で退店をお願いすることも最終手段として必要です。
3-2. スタッフ全員の認識を統一する「対応マニュアル」の作り方
誰が対応してもサービス品質がブレないよう、具体的な対応マニュアルを作成し、スタッフ教育を徹底しましょう。
マニュアルに盛り込むべき項目例
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 基本方針 | なぜ持ち込みルールがあるのか(利益・衛生・公平性の観点から) |
| 許可品目リスト | OKなもの(ワイン、ケーキ等)、NGなもの(ビール、惣菜等)を写真付きで解説 |
| 料金体系 | 品目ごとの持ち込み料金一覧表 |
| 注文条件 | コース注文必須、最低利用金額などの条件 |
| 対応フロー | 事前申告あり/無断持ち込み別のステップバイステップの手順 |
| トークスクリプト | 「お客様、誠に恐れ入りますが〜」など、具体的なセリフ集 |
| 例外対応 | 離乳食、アレルギー対応食、水分補給用の水筒などへの対応方針 |
| トラブル発生時 | お客様が納得しない場合のエスカレーションフロー(責任者に報告するタイミングなど) |
このマニュアルを元に定期的なロールプレイングを実施することで、スタッフは自信を持ってお客様に対応できるようになります。
持ち込みルールの周知とあわせて、店舗全体のオペレーション効率化には『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事が参考になります。
3-3. トラブルを未然に防ぐための「コミュニケーション術」と「チェックリスト」

最も重要なのは、お客様に「ルールで縛られている」と感じさせるのではなく、「気持ちよく食事を楽しんでもらうためのご案内」として伝えるコミュニケーションです。
- 協力をお願いする姿勢: 「禁止です」という否定的な言葉ではなく、「より良い時間をお過ごしいただくため、ご協力をお願いできますでしょうか」という依頼の形をとる。
- 理由を添える: 「衛生管理の観点から」「他のお客様との公平性を保つため」など、なぜそのルールがあるのかを簡潔に説明すると、お客様の納得感が高まる。
- 感謝を伝える: 「ご理解いただき、ありがとうございます」という一言が、場の空気を和らげ、良好な関係を築く。
【持ち込み対応トラブル回避チェックリスト】
□ 予約時に持ち込みルールの存在を伝えたか?
□ ホームページや予約サイトにルールを明記したか?
□ 来店時に料金と条件を再確認し、同意を得たか?
□ 持ち込み品を丁寧に預かり、適切に管理したか?
□ 持ち込みが原因のトラブル(破損、食中毒等)に関する免責事項を伝えたか?
□ スタッフ全員がマニュアルの内容を理解し、同じ対応ができるか?
【本章のチェックポイント】
持ち込み対応は、店舗のサービス品質とリスク管理能力が問われる場面です。マニュアルとチェックリストを活用し、スタッフ全員が「プロフェッショナル」として対応できる体制を構築しましょう。
第4章 持ち込みを許可するメリットとデメリット

持ち込み許可はリスクを伴いますが、それを上回るリターンをもたらす可能性を秘めた経営戦略です。ここでは、具体的なデータや事例を交えながら、持ち込みを許可することで得られるメリットと、改めて認識すべきデメリットを詳細に分析します。
4-1. 【メリット】売上と顧客満足をブーストする4つの効果
持ち込み許可は、単なる顧客サービスにとどまらず、店舗の売上構造を強化し、持続的な成長を促す強力なエンジンとなり得ます。
1. 新規顧客の獲得と集客コストの削減
「好きなワインを持ち込める店」という特徴は、特にワインや日本酒の愛好家といった特定のニッチ層に強く響きます。彼らは自らのSNSやコミュニティで情報を発信するため、広告費をかけずとも質の高い口コミが広がり、新たな顧客を呼び込むきっかけになります。
2. 客単価と料理売上の向上
意外に思われるかもしれませんが、持ち込みを許可することで客単価が向上するケースは少なくありません。飲み物代が抑えられる分、お客様は「せっかくだから料理は良いものを頼もう」という心理になりやすく、高価格帯のメニューや追加の逸品料理への注文が期待できます。
3. 優良顧客の育成とリピート率の向上
自分の大切なコレクションを持ち込めるという「特別な体験」は、お客様にとって強い記憶となり、店舗への愛着(エンゲージメント)を育みます。
このようなポジティブな体験は、お客様を単なるリピーターではなく、店舗のファンへと昇華させます。ファン化した顧客は、来店頻度が高いだけでなく、友人や知人を連れてきてくれるなど、店舗にとって最も価値のある存在となります。
4. ドリンク在庫リスクの軽減
多様なニーズに応えようとワインリストを充実させると、膨大な在庫を抱えることになり、管理コストや売れ残りリスクが増大します。持ち込みを許可することで、店舗は定番や売れ筋のボトルに絞って在庫を管理でき、キャッシュフローの改善と食品ロス削減に繋がります。
4-2. 【デメリット】改めて認識すべき3つの運営リスク
もちろん、持ち込み許可には光だけでなく影の部分も存在します。これらのリスクを軽視すると、経営を圧迫する要因になりかねません。
1. ドリンク売上の直接的な減少
最も直接的なデメリットは、本来得られるはずだったドリンク売上の逸失です。特に、利益率の高いグラスワインやハウスワインの注文機会が失われることは、店舗の収益構造に影響を与えます。持ち込み料(コルケージ)の設定が低すぎると、この損失をカバーしきれない可能性があります。
2. オペレーション負荷の増大
第3章でも触れた通り、持ち込み対応はスタッフの業務を複雑化させます。
- 持ち込み品の管理(預かり、保管、返却)
- 専用グラスの準備と洗浄
- 抜栓やデキャンタージュなどの追加サービス
- 会計時の料金計算
これらの業務が増えることで、人件費という目に見えるコストだけでなく、サービス全体の品質低下という目に見えないコストが発生するリスクを常に念頭に置く必要があります。
3. 衛生・安全管理責任の曖昧化
外部から持ち込まれた飲食物に起因するトラブル(食中毒、アレルギー、瓶の破損による怪我など)が発生した場合、責任の所在が曖昧になりがちです。たとえ店舗に非がなくても、お客様との間で深刻な紛争に発展する可能性があります。事前に「持ち込み品に関するトラブルは自己責任」という旨を明記し、同意を得ておくなどの対策が不可欠です。
【本章のチェックポイント】
メリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、次章で解説する「戦略的なルール設定」が不可欠です。自店の損得分岐点を冷静に見極めましょう。
持ち込みをどう扱うかは店舗ブランディング戦略の一部です。ブランディングについては詳しくは『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』をご覧ください。
第5章 持ち込み許可の具体的な条件とルール設定

持ち込み許可を成功させるためには、感覚ではなくロジックに基づいたルール設定が求められます。本章では、店舗経営者がすぐに自店で応用できるよう、持ち込み料の相場から注文条件の具体例まで、実践的なテンプレートを提示します。
5-1. 持ち込み料(コルケージ)の相場と戦略的設定

持ち込み料は、店舗の格と提供するサービスの価値を映す鏡です。安すぎれば利益を損ない、高すぎれば顧客を遠ざけます。自店のコンセプトに合った価格帯を見極めましょう。
酒類別・持ち込み料の相場表
| 酒類 | 容量目安 | 持ち込み料の相場 | サービス内容の想定 |
|---|---|---|---|
| ワイン | 750ml | 2,000円~3,500円2,000円~3,500円 | 抜栓、グラス提供、温度管理(クーラー等) |
| 日本酒 | 四合瓶(720ml) | 1,500円~3,000円1,500円~3,000円 | 徳利・お猪口提供、冷・燗の対応 |
| ウイスキー/焼酎 | ボトル(約700ml) | 3,000円~5,000円3,000円~5,000円 | グラス、氷、割り材(水・炭酸水)の提供 |
| マグナムボトル | 1500ml | 通常料金の1.5~2倍 | 通常より手間とグラス数が増えるため |
| 記念日ケーキ | 1ホール | 1,000円~1,000円~ もしくは無料 | 預かり、皿・フォーク提供、カットサービス |
5-2. 利益を確保する「最低注文条件」の組み合わせ事例
持ち込み料と合わせて「最低注文条件」を設定することで、客単価の低下を防ぎ、安定した収益基盤を築くことができます。
- 事例1:コース料理との連動
- ルール: 「お一人様8,000円以上のコース料理をご注文の場合、ワイン1本の持ち込み料(通常3,000円)を1,500円に割引」
- 狙い: 高単価のコース料理への誘導と、持ち込み客への付加価値提供を両立させる。
- 事例2:アラカルト注文時の最低金額設定
- ルール: 「アラカルトでご注文の場合、お一人様につき料理5,000円以上のご注文をいただいたお客様に限り、持ち込みを許可します」
- 狙い: 持ち込みだけが目的の利用を防ぎ、料理もしっかり楽しんでもらうことで、店の魅力を伝える。
- 事例3:記念日利用の優遇
- ルール: 「記念日プランをご利用のお客様は、お祝いのケーキ持ち込み料を無料とさせていただきます」
- 狙い: 特別な日の利用を促進し、顧客満足度を最大化することで、リピートや口コミに繋げる。
5-3. お客様に協力を得るための「伝え方」の工夫
ルールは、ただ提示するだけでは不十分です。お客様に気持ちよく協力してもらうための伝え方の工夫が、店舗の印象を大きく左右します。
【OKな伝え方】
「当店では、お客様の大切な一本を最高の状態でお楽しみいただくため、抜栓やグラスの提供を含むサービス料として、〇〇円の持ち込み料を頂戴しております。ご理解いただけますと幸いです。」
→ 理由と提供価値を伝え、丁寧にお願いする姿勢
【NGな伝え方】
「持ち込みは有料で〇〇円です。」
→ 一方的で冷たい印象を与え、お客様を不快にさせる可能性
ホームページやメニューブックには、「持ち込みポリシー」として、背景にある想い(多様な楽しみ方を提供したい、など)を添えることで、単なる規則ではなく、店舗からのポジティブなメッセージとして受け取ってもらいやすくなります。
【本章のチェックポイント】
「持ち込み料」「注文条件」「伝え方」の3つは、持ち込み戦略の三位一体です。自店のコンセプトと照らし合わせながら、最適な組み合わせを設計しましょう。
第6章 おすすめの持ち込み料とコルケージの設定
持ち込み料(コルケージ)は、単なる売上補填の手段ではありません。価格設定そのものが、店舗のブランド価値を伝え、顧客との関係性を築くための高度なマーケティング戦略となり得ます。本章では、一歩進んだコルケージ戦略で競合と差別化し、収益を最大化するための具体的な方法論を解説します。
6-1. 利益と満足度を両立させる3つの価格設定モデル
持ち込み料の価格設定には、大きく分けて3つのアプローチがあります。自店のポジショニングに合わせて最適なモデルを選択しましょう。
1. コスト積算モデル(安定志向)
グラスの原価・破損率、サービスにかかる人件費、洗浄コストなどを算出し、そこに求める利益を上乗せする、最も堅実な方法です。
持ち込み料=(グラス代+人件費+その他経費)×利益率持ち込み料=(グラス代+人件費+その他経費)×利益率
- メリット: 論理的で価格の根拠を説明しやすい。安定した利益を確保できる。
- デメリット: 市場相場から乖離する可能性がある。サービスの付加価値が価格に反映されにくい。
2. 市場価格連動モデル(バランス志向)
周辺の競合店のコルケージ料をリサーチし、自店のサービスレベルや客層を考慮して価格を決定する方法です。
- メリット: お客様が相場観から大きく外れないため、受け入れられやすい。
- デメリット: 価格競争に陥りやすい。独自の価値を打ち出しにくい。
3. 価値提供モデル(ブランド志向)
ソムリエによる抜栓やデキャンタージュ、特別な高級グラスの提供など、他店にはない独自の付加価値を価格に反映させる方法です。
- メリット: 高い利益率を実現できる。店舗の専門性やブランド価値を高められる。
- デメリット: 提供する価値が価格に見合っているか、常にお客様から厳しく評価される。
6-2. 競合と差をつけるコルケージの差別化戦略
均一な料金設定だけでなく、柔軟な価格体系を導入することで、より多くのお客様にアピールし、利用を促進することができます。
- 2本目以降割引: 「1本目は3,000円、2本目以降は1,500円」とすることで、グループでの利用やワイン会などの需要を喚起します。
- 会員制度の導入: 年会費や月会費を支払う会員は、持ち込み料が無料または割引になる特典を付与。優良顧客を囲い込み、安定した収益源を確保します。
- 特定日・時間帯割引: 平日のディナータイムや閑散期など、集客したい時間帯限定で持ち込み料を割引し、稼働率を高めます。
- 「バイワン・ゲットワンフリー」戦略: 「当店のワインリストから1本ご注文いただければ、お客様の持ち込みワイン1本を無料にします」というルール。店のワインも楽しんでもらえ、顧客満足度も非常に高い、優れた戦略です。
6-3. ワイン持ち込みを起点とした収益モデルの構築
持ち込み客は、単にコルケージ料を支払うお客様ではありません。彼らを起点に、新たな収益機会を創出することが可能です。
- ペアリングメニューの提案: お客様が持ち込んだワインに合わせて、シェフが即興で最適な料理を提案する「持ち込みワイン専用ペアリングコース」を用意する。これは高い付加価値と顧客満足を生み出します。
- ワインログサービスの提供: お客様が持ち込んだワインのラベルや感想を記録するカードやアプリを提供。次回来店時に「前回は〇〇を楽しまれていましたね」といった会話が生まれ、顧客との関係性を深化させます。
- コミュニティ化: 持ち込み客限定のワイン会やメーカーズディナーを定期的に開催。参加費を収益に繋げると同時に、ファンコミュニティを形成し、店舗へのロイヤリティを高めます。
【本章のチェックポイント】
持ち込み料を「コスト」ではなく「投資」と捉えることで、新たな収益の柱を築くことができます。自店の強みを活かした、独自のコルケージ戦略を設計しましょう。
第7章 成功事例と失敗パターンの分析

持ち込み許可という戦略は、諸刃の剣です。成功すれば大きな武器になりますが、一歩間違えれば自らの首を絞めることにもなりかねません。ここでは、実際の店舗事例を元に、成功と失敗を分ける境界線はどこにあるのかを具体的に分析します。
7-1. 持ち込み許可で売上を伸ばした店舗の3つの共通点
持ち込みを許可し、かつ事業を成長させている店舗には、業態を問わず明確な共通点が見られます。
共通点1:明確なコンセプトとターゲット設定
成功している店舗は、「誰に、どんな価値を提供したいのか」というコンセプトが明確です。例えば、「ワイン愛好家がコレクションを披露できる特別な場所」というコンセプトのフレンチレストランは、高めのコルケージ料でも顧客が納得します。逆に「仲間とワイワイお酒を楽しむ大衆酒場」なら、安価なコルケージ料でグループ利用を促進するのが正解です。コンセプトが明確だからこそ、ルールに一貫性が生まれ、顧客にメッセージが正しく伝わります。
共通点2:持ち込みを「きっかけ」にしたアップセル戦略
成功店は、持ち込み料(コルケージ)だけで満足しません。持ち込まれたワインや日本酒を「会話のきっかけ」として活用し、料理の追加注文に繋げています。
共通点3:徹底した情報公開と期待値コントロール
成功店は、ホームページや予約サイト、SNSを駆使して、持ち込みルールをこれでもかというほど丁寧に公開しています。料金、対象品目、注文条件、サービスの範囲などを事前に明示することで、「知らなかった」「そんなはずじゃなかった」という来店後のトラブルをほぼゼロに抑えています。これは顧客満足度を高めるだけでなく、スタッフがクレーム対応に追われる時間をなくし、本来のサービスに集中できる環境を作ることにも繋がっています。
7-2. 持ち込み許可で失敗した店舗の典型的な3つのパターン

一方で、安易に持ち込みを許可した結果、経営が悪化してしまった店舗にも共通の失敗パターンがあります。
失敗パターン1:「とりあえず真似」でルールが曖昧
「流行っているから」「競合がやっているから」という理由だけで、自店のコンセプトや客層を分析せずに持ち込みを許可してしまうケースです。料金設定の根拠が曖昧で、スタッフによって言うことが違うため、顧客は不信感を抱きます。結果、不公平感からくるクレームが多発し、常連客が離れていくという最悪の事態を招きます。
失敗パターン2:持ち込み料が安すぎて利益を圧迫
売上減少を恐れるあまり、持ち込み料を極端に安く設定してしまうパターンです。一見、お客様想いに見えますが、ドリンクの利益が失われ、サービスの対価も得られないため、経営はじわじわと苦しくなります。
失敗パターン3:スタッフへの教育不足とオペレーションの崩壊
ルールだけ作って、現場のスタッフに丸投げしてしまうケースです。スタッフは持ち込み対応に慣れておらず、お客様に適切な案内ができません。持ち込まれた高価なワインの抜栓に失敗したり、予約客のボトルを取り違えたりといったミスが頻発し、店の信用を大きく損ないます。オペレーションの混乱は、サービス全体の品質低下に直結します。
7-3. 業態別(居酒屋・レストラン・カフェ)の成功パターン
持ち込み戦略は、店舗の業態によって最適な形が異なります。
| 業態 | 成功パターン例 | 狙いとポイント |
|---|---|---|
| 居酒屋・大衆酒場 | 焼酎・日本酒のボトル持ち込みを許可(料金は比較的安価に設定)。ただし「料理〇品以上の注文」を条件とする。 | グループ利用や宴会需要の獲得。ドリンクの利益減を料理の注文数でカバーする。 |
| レストラン | ワイン持ち込みに特化し、専門性の高いサービス(ソムリエ対応、高級グラス)を提供。コルケージ料は高めに設定。 | ワイン愛好家という優良顧客層の囲い込み。高い付加価値で高収益を実現し、ブランド価値を向上させる。 |
| カフェ・ダイニング | 記念日のケーキ持ち込みを許可(条件付きで無料)。ソフトドリンクや軽食の持ち込みは原則禁止。 | 誕生日会などハレの日の利用を促進。特別な体験を提供することで、口コミやSNSでの拡散を狙う。 |
【本章のチェックポイント】
他店の成功事例をそのまま真似るのではなく、自店のコンセプトと照らし合わせ、失敗パターンを回避する視点を持つことが、持ち込み戦略を成功させる鍵です。
持ち込み戦略を成功させるにはSNSでの発信も欠かせません。飲食店のSNS運用を総合的に知りたい方は『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事をご覧ください。
第8章 飲食店オーナーのための「持ち込み対応」Q&A集
8-4. テラス席ならペットボトルを開けてもいいの?
ここでは、飲食店経営者の方々から特によく寄せられる持ち込みに関する疑問について、Q&A形式で具体的にお答えします。
Q1. 持ち込みに関するルールは、法的に有効ですか?
A1. はい、有効です。 店舗が設定した持ち込みルールは、民法上の「契約」の一部と解釈されます。お客様がそのルールを認識した上で入店・注文した場合、その契約に同意したとみなされます。したがって、ルールに則って持ち込み料を請求したり、違反した場合に退店を求めたりすることは法的に正当な行為です。ただし、トラブルを避けるためにも、お客様が事前にルールを認識できる状況(ホームページへの明記、入店時の説明など)を作っておくことが極めて重要です。
Q2. 保健所への届出や特別な許可は必要ですか?
A2. 原則として不要です。 お客様が持ち込んだ飲食物を、店舗側が「調理」や「加工」をせず、単に場所と食器を提供するだけであれば、新たな営業許可や保健所への届出は基本的に必要ありません。ただし、持ち込まれた食材を店舗のキッチンで調理するような場合は、食中毒のリスク管理や衛生管理の観点から、事前に所轄の保健所に相談することをお勧めします。自治体によって見解が異なる場合があるため、確認しておくと安心です。
Q3. お客様が持ち込んだボトルを破損させてしまった場合、どうすれば?
A3. 誠心誠意の謝罪と、店舗が加入する保険での対応が基本です。 これは店舗運営における重大なリスクの一つです。まずは丁重にお詫びし、状況を正確に把握します。その上で、店舗が加入している「施設賠償責任保険」などが適用できるかを確認します。多くの保険では、業務中の対物事故をカバーしています。高価なワインを持ち込まれる可能性がある店舗は、補償の上限額などを事前に確認しておくべきです。弁償額については、お客様が購入した際の価格を証明できるレシートなどがあればそれを基準に、難しい場合は市場価格を調査し、双方納得の上で決定します。日頃からスタッフの取り扱い訓練を徹底し、事故を未然に防ぐ努力が最も重要です。
Q4. 離乳食やアレルギー対応食の持ち込みを断ったら、問題になりますか?
A4. 一概に問題になるとは言えませんが、慎重な対応が求められます。 店舗の衛生管理ポリシーとして、外部からの食品持ち込みを一切禁止するという方針も経営判断としてはあり得ます。ただし、特にアレルギー対応については、お客様の健康に関わる切実な問題です。単に「ダメです」と突き放すのではなく、「申し訳ございません。衛生管理の観点から、外部の食品をお預かりして温めるなどの対応は致しかねますが、お席でお召し上がりいただくことは問題ございません」など、できることとできないことを丁寧に説明する姿勢が大切です。画一的な対応ではなく、個別相談に応じる姿勢を見せることが、店舗の信頼を守ることに繋がります。
Q5. 持ち込み料に消費税はかかりますか?
A5. はい、かかります。 持ち込み料(コルケージ)は、抜栓やグラスの提供といった「役務の提供」に対する対価であり、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」に該当します。したがって、お客様に請求する際は、消費税込みの総額表示とするか、税抜価格と消費税額を明確に区別して表示する必要があります。会計システムの設定などを確認しておきましょう。
【本章のチェックポイント】
法務や保険など、専門的な知識が必要な場面も想定されます。いざという時に慌てないよう、顧問弁護士や保険代理店に事前に相談できる体制を整えておくこともリスク管理の一つです。
第9章 まとめ:利益と満足度を両立させるための最終チェックリスト
これまで、飲食店の持ち込みに関するリスク、ルール設計、メリット、そして具体的な戦略までを網羅的に解説してきました。持ち込み問題は、単なるルール決めではなく、店舗の理念そのものを問い直す経営課題です。
最後に、あなたの店舗が明日から行動に移せるよう、これまでの内容を実践的なチェックリストにまとめました。このリストを使って自店の現状を評価し、利益と顧客満足度を両立させる、あなただけの最適な答えを見つけ出してください。
持ち込みをきっかけにしたワイン会など、イベント企画もおすすめです。飲食店のイベントアイデアを知りたい方は『【集客アップ】飲食店の面白いイベント企画の考え方!具体的なアイデア集と成功事例を大公開!』の記事を参考にしてください。
【持ち込み戦略・実行チェックリスト】
- 自店のコンセプトとターゲット顧客は明確か?
- 持ち込みを許可した場合の経済的リスク(ドリンク売上減)を試算したか?
- 衛生管理(食中毒・アレルギー)のリスクに対応できる体制はあるか?
- スタッフのオペレーション負荷は許容範囲内か?
- 持ち込みを許可する品目と禁止する品目は明確に定義したか?
- 持ち込み料(コルケージ)は、自店の格やサービス価値に見合っているか?
- 持ち込み料の価格設定モデル(コスト積算・市場連動・価値提供)を検討したか?
- 客単価を維持するための最低注文条件(コース必須、最低金額など)を設定したか?
- スタッフ全員が共有できる対応マニュアル(トークスクリプト含む)を作成したか?
- 事前申告あり/無断持ち込み別の対応フローは確立されているか?
- 定期的なロールプレイングで、スタッフの対応スキルを向上させているか?
- 持ち込み品の管理方法(預かり、保管、破損防止策)は万全か?
- 公式サイトやSNSに「持ち込みポリシー」を分かりやすく掲載したか?
- 予約サイトの備考欄や説明文に、ルールを簡潔に記載したか?
- 電話やメールでの予約時に、持ち込みに関する確認をフローに組み込んだか?
- 店内の目立つ場所に、ルールを記載したPOPや案内を設置したか?
- 持ち込みをきっかけにしたアップセル(料理提案)の仕組みはあるか?
- 持ち込み客をファンにするための施策(ワイン会、会員制度など)を検討したか?
- 持ち込みに関する免責事項を明記し、顧客の同意を得る仕組みはあるか?
このチェックリストの全ての項目に自信を持って「YES」と答えられるようになった時、あなたの店舗は「持ち込み」という課題を、競合に対する強力な「武器」へと変えることができるでしょう。挑戦を恐れず、しかし慎重に。あなたの店舗が、お客様にとって唯一無二の価値ある場所となることを心から願っています。