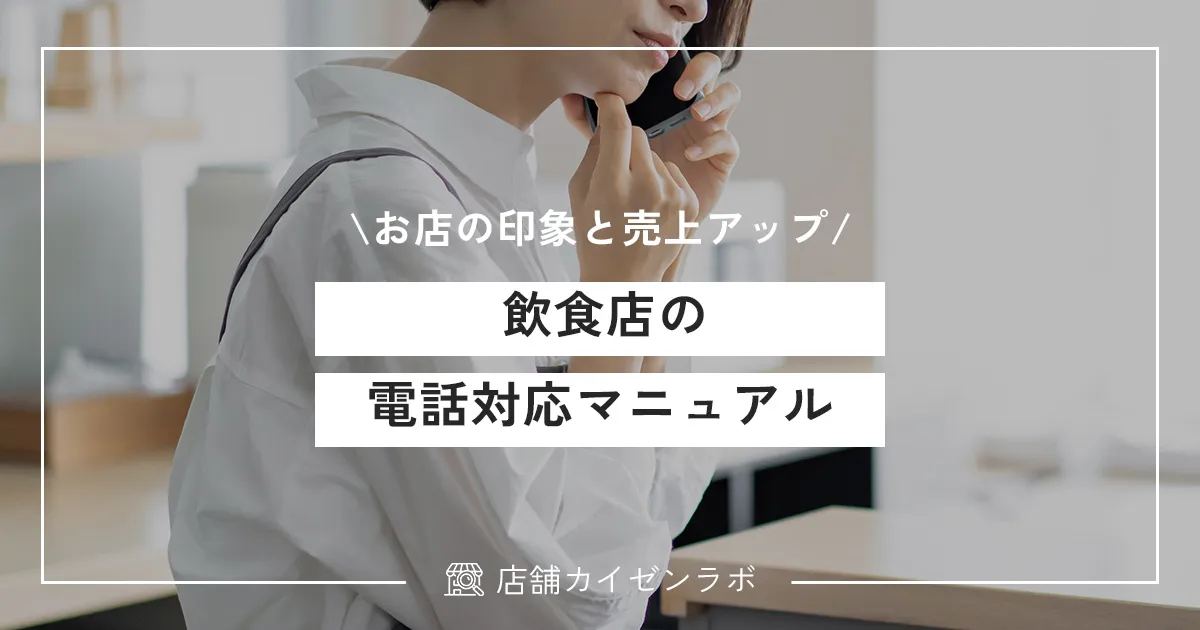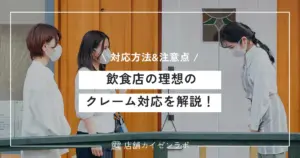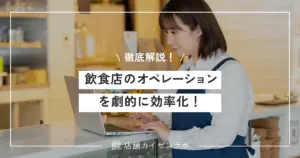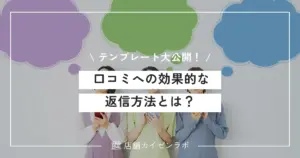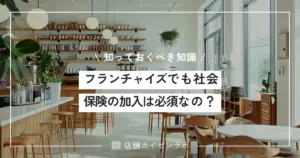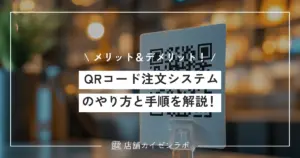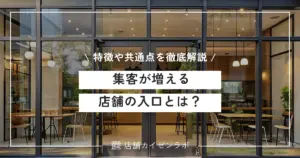第1章 電話対応が飲食店の命運を左右すると言われる理由とは?

1-1. 電話応対が重要な理由
飲食店において、電話対応は店舗の第一印象を決定づける非常に重要な業務です。特に、初めて来店を検討している顧客は、直接お店を訪れる前に電話をかけるケースが多いので、そこでの応対次第で「この店は丁寧そう」「忙しそうで不安」など、店全体の評価が一気に固まってしまうことが少なくありません。
さらに、電話では相手の表情が見えないぶん、“声や話し方”だけで雰囲気や真剣さが伝わるのが大きな特徴です。ここで雑な対応をしてしまうと、予約や問い合わせの段階で離脱される、あるいは口コミで悪評が広がる可能性も高まります。逆に、要点を的確に伝えながら、明るく丁寧に対応するだけで「このお店なら安心して利用できる」と感じてもらいやすくなります。
また、電話応対がスムーズであれば、予約受付やテイクアウトなどの業務も効率化しやすくなり、結果的に売上やリピート率にも好影響を与えます。ピークタイムにおいても、適切なフローに従った電話対応ができれば、店内接客と電話対応を両立しやすくなり、顧客満足度を下げずに済むでしょう。
1-2. スタッフに電話応対教育をするメリット
飲食店の現場では、多くのスタッフがホールやキッチンなど、それぞれ専門の持ち場で忙しく動いています。そのため、電話が鳴ったときに「あの人しか出られない」「新人だと不安」という状況が生まれやすいものです。こうした属人的な状態を脱却し、誰が電話に出ても一定の品質を保つために欠かせないのが、スタッフへの電話応対教育です。
教育を通じて、全員が共通ルール(3コール以内に出る、重要事項は復唱する、最終的にお礼を言って静かに切る、など)を把握していれば、予約ミスやクレーム発生のリスクが大幅に減少します。さらに、きちんとマニュアルを整備して定期的にロールプレイングを行うと、新人スタッフも早期に慣れるだけでなく、“顧客満足度を高める応対”を自然に身につけやすくなります。

筆者の体験談: 電話応対研修の導入
最終的に、電話応対の質の底上げは店舗全体の印象アップやリピーター増加に直結します。スタッフ教育にコストや時間をかける意義は十分にあると言えるでしょう。
第2章 シーン別で見る!飲食店の電話対応テンプレート!

2-1. 予約受付:第一印象を左右する会話テンプレート
飲食店の電話対応の中でも、圧倒的に多いのが予約受付です。ここでスムーズに対応できないと、顧客が不安になってしまうかもしれません。ポイントは、日時・人数・名前・連絡先を確実に把握し、必要ならばキャンセルポリシーを伝えること。
会話例
店舗:「お電話ありがとうございます。〇〇レストランでございます」
顧客:「明日の18時に4名で予約したいのですが……」
店舗:「ありがとうございます。明日の18時に4名様ですね。かしこまりました。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
顧客:「山本です」
店舗:「山本様ですね。ご連絡先は〇〇-〇〇-〇〇でお間違いないでしょうか?
…ありがとうございます。なお、当店は前日以降のキャンセルにつきましてはキャンセル料を頂戴しております。ご了承くださいませ。では、明日18時にお待ちしております」
筆者の体験談: 名前間違え
2-2. 店舗への道案内:わかりやすい説明がリピーターを生む

初めて来店する顧客にとって、わかりやすい道案内はそれだけで好印象に繋がります。住所だけを伝えて「Googleマップで調べてください」では味気なく、迷う可能性も高いです。
会話例
顧客:「すみません、駅からの行き方がよくわからなくて……」
店舗:「かしこまりました。〇〇駅の東口を出ていただき、すぐ右手にあるコンビニを目印に直進いただくと、2つ目の信号の角に薬局がございます。その隣のビルの3階が当店です。看板が青色なので見つけやすいかと思います」
目印となる建物や看板の色、距離感を具体的に伝えると、着実にリピーターを生みやすくなります。
電話で道案内する機会が多い店舗ほど、Googleマップ対策(MEO)が集客に効果を発揮します。詳しい施策は『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』をご参照ください。
2-3. テイクアウト・注文受付:ミスを防ぐ確認事項と例文
テイクアウトやデリバリー注文では、メニューの名前や数、受け取り時間を確実に聞き取る必要があります。特に、混雑する時間帯に相手が「あとから追加できますか?」と尋ねてくると混乱しがちです。
会話例
顧客:「テイクアウトをお願いしたいんですが、〇〇弁当を3つと唐揚げ単品4個って可能ですか?」
店舗:「ありがとうございます。〇〇弁当3つ、唐揚げ単品4個ですね。準備に30分ほどかかりますがよろしいでしょうか?」
顧客:「はい、お願いします」
店舗:「かしこまりました。合計で〇〇円になります。お支払いは店頭で現金またはクレジットカードが可能です。ご来店をお待ちしております」
受け取り時間や追加注文への対応可否をはっきり伝えることで、トラブルやクレームを事前に防ぐことができます。
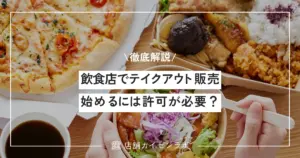
2-4. クレーム対応:最初のひと言が勝負を決める
クレームの電話がかかってくると、スタッフも気が重くなりがち。しかし、第一声で真摯に謝罪し、内容をきちんと聞く姿勢を示すだけで、相手の感情を落ち着かせやすくなります。
会話例
顧客:「先日行ったときに料理が遅くて困ったんですけど!」
店舗:「大変申し訳ございませんでした。詳しくお話を伺い、改善に活かしたいので、少々お時間いただけますでしょうか?」
顧客:「……(クレーム内容)」
店舗:「ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。今回いただいたご指摘をスタッフ全員で共有し、再発防止に努めます」
お詫びを述べつつ、改善の意思を示すことが大切。クレームの後の対応次第で、逆に好印象を残せるケースもあります。
電話でのクレームも大切ですが、ネット上の口コミ対応も見逃せません。適切な対処法は『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』から確認できます。
2-5. 営業時間外の問い合わせ:留守番電話や自動応答で取りこぼさない
飲食店では、深夜や定休日など営業時間外に電話がかかってくることもあります。スタッフが誰も出られず、折り返しの連絡を逃してしまうのは機会損失です。そこで留守番電話や自動応答システム(IVR)を活用すると、予約を受け付けたり、後からスタッフが折り返したりする体制が整います。
会話例(営業時間外の設定メッセージ)
「こちらは〇〇レストランです。本日は定休日のため、只今電話に出ることができません。ご予約希望の方は、【お名前・ご希望日時・ご連絡先】を残していただければ、翌営業日に折り返しいたします。ありがとうございます」大手チェーンや忙しい店舗ほど、自動応答システムでの一次受付が売上や顧客満足度を下げない秘訣となっています。
第3章. 飲食店の電話対応で好印象を残すための6つのポイント

3-1. 3コール以内に出る
電話が鳴り続けるのを放置すると、顧客は「対応が遅い」「スタッフが足りていないのでは」と不安になりがちです。3コール以内に出ることを意識するだけでも、相手に「忙しくてもきちんと応対してくれる」という安心感を与えられます。もし4コール以上待たせてしまった場合は、「お待たせしました」の一言を添えるようにしましょう。
3-2. 『笑声』を意識して話す
電話越しでは、声のトーンが印象を左右します。顔が見えないからこそ、笑顔で話すと声に自然な明るさが乗るのです。これがいわゆる“笑声”で、顧客は「このお店は感じがいい」と直感的に思いやすくなります。店内が忙しくても、最初のあいさつから笑声を意識するだけで、電話対応の質が一気に上がるでしょう。
3-3. ゆっくり・ハッキリ話す
飲食店は周囲が騒がしく、店員側も急ぎの対応に追われることが多いです。しかし電話では、相手の表情や唇の動きが見えないぶん、ゆっくり・ハッキリ発音しなければ伝わりにくくなります。早口でまくし立てると、相手は要件をうまく理解できずに混乱するかもしれません。少し意識してペースを落とすことで、顧客からの印象は格段に良くなります。
3-4. メモを取る

予約の日時や人数、名前、連絡先など、電話口で聞いた情報は必ずメモを取りましょう。忙しくても紙とペンを常備し、最初の対応時に素早く書き留めれば、後でスタッフ間で共有する際に「あれ、何名様だったっけ?」というミスを減らせます。電話に出る前からメモ帳と筆記具を準備しておくのがおすすめです。
3-5. 内容の復唱
聞き間違いやメモの書き損じがないよう、最後に相手の要件を復唱して確認するのが大切です。たとえば「19時に4名様、山本様でよろしいでしょうか?」と問いかけるだけで、相手が安心感を持ちやすく、こちらもミスを未然に防止できます。忙しいときこそ一秒でも早く切りたいと思いがちですが、復唱の数秒がトラブルを回避する近道になります。
3-6. 言葉遣いは敬語で、柔らかい表現を
電話対応で特に意識したいのが、柔らかく丁寧な言い回しです。
- 「〜でございます」「かしこまりました」「ありがとうございます」
- 相手の要望を断る場合も「大変申し訳ございませんが」「あいにくですが」などクッション言葉を使う
これだけで印象が変わり、顧客は「このお店はしっかりしているな」と感じやすくなります。逆にため口や命令口調が入り混じると、途端に失礼な印象を与えてしまうため注意しましょう。
筆者の店舗での成功例:録音機能の活用
筆者の経営するカフェでは、通話を録音できる電話システムを導入し、1日に数件だけスタッフ同士でレビューを行いました。最初は恥ずかしがっていたスタッフも、録音を聞き返して改善点を共有するうちに、圧倒的に予約ミスやクレーム数が減少。電話への苦手意識が消え、むしろ「自分の成長が見えるから楽しい」と言う声も聞かれました。
第4章. 飲食店の電話対応をマニュアル化して失敗ゼロへ

4-1. マニュアル化のメリットとは?
多くの飲食店では、忙しい時期ほど「誰が電話を取るか」によって対応品質がバラバラになりがちです。そこで有効なのが、電話対応をマニュアル化し、全スタッフが同じフローや言葉遣いで応対できるようにすること。
- 予約ミス・クレームの減少
必要情報(日時・人数・名前・連絡先など)を確認する手順を明文化するだけで、聞き漏れによる予約トラブルが激減します。 - 新人スタッフの早期戦力化
マニュアルを見ながらでも電話を取れば、最低限の品質は担保されるため、アルバイトや新規採用者でも不安なく応対できるようになります。 - 店舗全体のブランディング向上
どのスタッフが電話に出ても一定の丁寧さが伝われば、「このお店は教育が行き届いている」と好印象を持たれるでしょう。
店舗オペレーションと併せたマニュアル作りをしたい方は、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』をご活用ください。
4-2. 具体的にどう作る?電話対応マニュアルの基本構成
マニュアル化する際には、業務の流れや想定シナリオを整理し、箇条書きやフローチャートでわかりやすくまとめるのがポイントです。
- 基本マナー編
- 3コール以内に出る
- 第一声の挨拶例
- ゆっくり話す・笑声を意識する
- 復唱のタイミング・メモの取り方
- お礼と電話の切り方
- 3コール以内に出る
- シーン別対応編
- 予約受付(必要情報・人数確認・キャンセルポリシー)
- キャンセル・変更対応(キャンセル料の確認や変更の記録方法)
- 道案内(目印・建物の特徴)
- クレーム対応(謝罪と事実確認のステップ)
- 営業時間外の対応(留守番電話や折り返しルール)
- 予約受付(必要情報・人数確認・キャンセルポリシー)
- イレギュラー編
- 満席で断る場合(代替日や時間帯の提案文例)
- 英語対応・外国語対応の定型フレーズ
- 営業電話や取材依頼が来たらどうするかの取次ぎフロー
- 満席で断る場合(代替日や時間帯の提案文例)
- 問い合わせ先や情報共有方法
- 責任者の連絡先
- 予約台帳やシステムの場所・書き方
- 他店舗や本社が関わる場合の連絡フロー
- 責任者の連絡先
こうした情報をスタッフがいつでも参照できるよう、紙のファイルにまとめたり、デジタルツールを活用したりすると効果的です。
4-3. ロールプレイングで“使えるマニュアル”に仕上げよう
マニュアルは作っただけで満足してしまうと、スタッフが実践で使いこなせないケースが多いもの。そこで重要なのが、ロールプレイング研修による“生きたマニュアル”への落とし込みです。
- 想定シナリオを複数用意
予約、キャンセル、クレーム、道案内など、実際によく起こる状況をピックアップ。 - スタッフ同士で役割を分担
顧客役と応対役に分かれ、マニュアルを見ながら実際に声を出してやりとりする。 - フィードバックと改善
話し方のスピードや敬語の使い方、復唱のタイミングなどを他のスタッフや店長が確認し、具体的な改善点を共有。
こうしたロールプレイを繰り返すことで、マニュアルの内容を自然と覚え、現場で落ち着いて対応できるようになります。
4-4. 注意点:マニュアルは“絶対的な台本”ではない
一方で、マニュアルには書ききれないイレギュラーなケースも当然出てきます。特に飲食店では、予想外の要望や緊急のトラブル、外国語での問い合わせなどが発生するかもしれません。その際、スタッフが「マニュアルにないので答えられません」と固まってしまっては本末転倒。
- 最低限の基本ルールだけは共有し、細部は柔軟に
- イレギュラー時の判断フロー(店長に一報を入れる、折り返し対応にするなど)も決めておく
- 定期的にマニュアルを更新し、新たな事例を共有
マニュアルはあくまで土台であり、スタッフが自分の言葉で対応しつつもぶれない基準を持つためのツールと捉えると良いでしょう。
第5章. 飲食店の電話対応についてよくある質問
5-1. Q1:営業電話が多すぎて困る…うまく対処するコツは?
A: 飲食店の電話番号を公開していると、広告や勧誘などの営業電話が集中しがちです。対処法としては、まずは初動で要件を確認してから必要に応じてブロックまたは着信振り分けを行う仕組みをつくりましょう。クラウド電話なら「営業系番号」からの発信を自動認識し、別回線へ飛ばす設定が可能な場合もあります。手間やストレスを減らすには、電話代行サービスに営業電話対応を任せるのも有効です。
5-2. Q2:外国語の問い合わせが来るとスタッフが対応できずパニック…どうする?
A: まずは簡易的な英会話スクリプト(「Could you tell me your name?」「How many people?」など)を作成し、スタッフ全員が最低限使えるようにするのが第一歩。観光客が多いエリアなら、バイリンガルスタッフの採用や、翻訳アプリで一時対応する方法もあります。外国語対応の電話代行サービスを利用する飲食店も増えており、店舗規模や予算に応じて検討してみる価値があります。
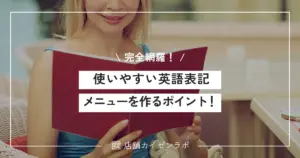
5-3. Q3:急なキャンセルや変更が頻発してしまう…何か対策はある?
A: まずはキャンセルポリシーを明確にして、予約を受け付ける段階で相手に伝えておくと、理由のないドタキャンは減ります。また、急な変更連絡が来ても混乱しないよう、スタッフ全員が共有できる予約管理表やシステムを使い、すぐに反映・通知できる体制を整えましょう。電話で受けた変更内容を即座にメモし、他のスタッフが見られる場所にまとめておくのが大切です。
5-4. Q4:営業時間外や定休日にも問い合わせが多い…対処は?
A: 営業時間外の問い合わせは、自動音声応答(IVR)や留守番電話を利用して一次受付を自動化するのが効果的です。「本日は閉店中です。ご予約の方はお名前・日時・人数を残してください」というように案内すれば、取りこぼしが減ります。翌営業日に折り返し連絡をする際にも要件がわかっているため、スムーズに対応できるでしょう。
5-5. Q5:電話口で連絡先や名前を聞き取れず、何度も聞き直すのが失礼かも…と悩む
A: 相手にとっても、後からミスが起こるほうがよほど大きな問題です。**「恐れ入りますが、もう一度お名前をお聞きしてもよろしいでしょうか?」**など、丁寧なフレーズを使えば失礼にはあたりません。特に名前の漢字や連絡先は間違いが起きやすいので、復唱での確認を必ず行うのが鉄則です。相手も「しっかり確認してくれている」と安心感を得られます。
5-6. Q6:大人数の宴会予約電話を受けると、席のレイアウトやコース説明で長時間になりがち…
A: 大人数の予約は決めることが多く、電話が長引く傾向にあります。対策としては、席レイアウト図やコース内容をまとめた案内資料をあらかじめ用意し、口頭だけでなくメールやSNSで送れるようにしておくと便利です。電話で大枠を決め、詳細は後日メールや公式LINEでやり取りする流れにすれば、スタッフ・顧客双方の負担が軽減され、聞き違いも減らせます。
第6章. 飲食店では電話対応こそ「お店の命」と理解しよう!

6-1. スタッフ全員が迷わない「マニュアル」とチェックシート
飲食店の電話対応は、属人的にせずにマニュアル化することで、誰が出ても一定水準の応対が可能になります。最低限以下の項目を含むチェックシートを作るとよいでしょう。
- 3コール以内に出る
- 名前・日時・人数・連絡先の確認を復唱
- 最終的にお礼を述べて静かに切る
- クレームや特殊問い合わせは責任者に取り次ぐフロー
ロールプレイングを組み合わせることで、新人スタッフも安心して電話対応を実践できるようになります。特に繰り返し練習することで「忙しい中でもマニュアルが頭に入っているから対応できる」と自信を持てるようになるのが大きいです。
6-2. 今すぐできるアクションプラン──1週間で変わる電話応対
以下のステップを1週間だけでも集中実行すれば、電話対応のクオリティはぐっと上がります。
- マニュアルを作成 or 更新: 「電話を受ける→復唱→メモ→席状況の確認→お礼で終わり」の具体的な流れを文章化。
- スタッフ全員でロールプレイ: 予約・クレーム・道案内など複数シナリオを想定し、交互に顧客役と電話役を練習。
- AI・IVRなどの導入検討: 繁忙期や深夜帯の一次受付を自動化する方法を調べておき、運用イメージを共有。
1週間後には実際の電話対応で「あ、これならミスが減る」「クレームも落ち着いて対応できる」といった変化を体感しやすいはず。特に人手不足が深刻な店舗ほど、電話対応のシステム化・効率化がもたらすメリットは大きいです。
忙しい時期でも電話対応の質を落とさないためには、事前準備が重要です。繁忙期の乗り越え方は『飲食店で繁忙期に必要な対策を総まとめ!忙しい時期を乗り越えて売上を最大化する方法!』で詳しく解説しています。