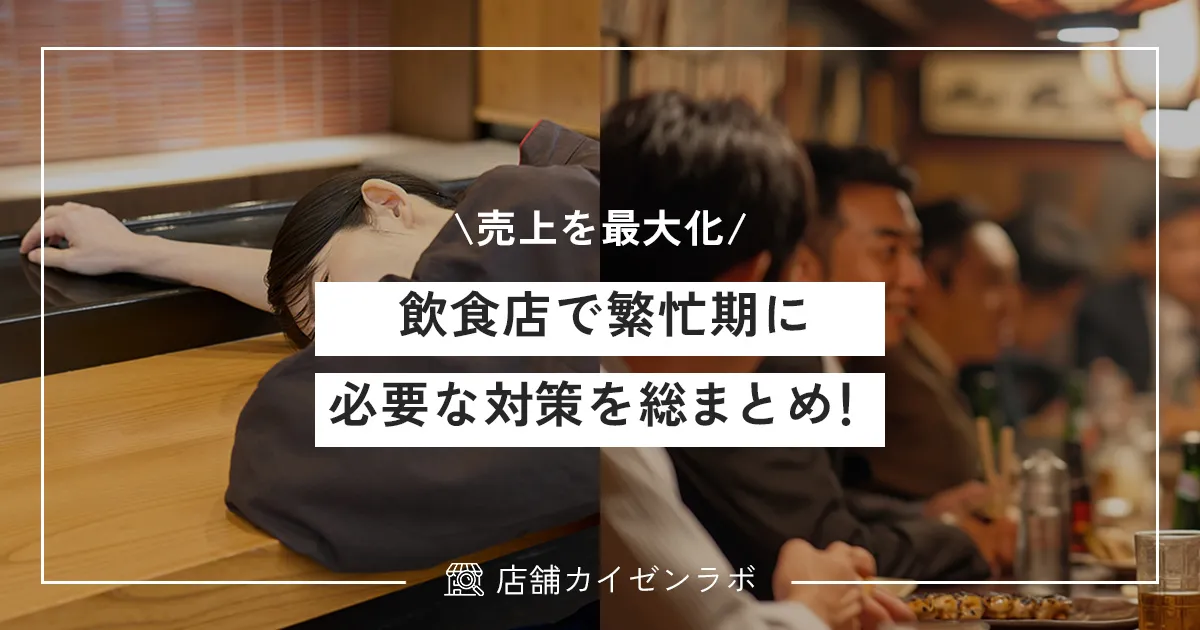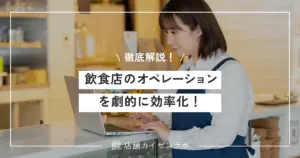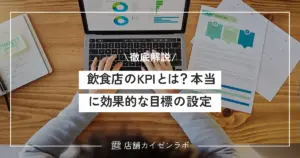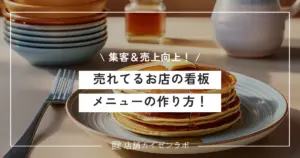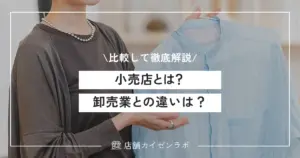第1章. なぜ今こそ飲食店が繁忙期対策を見直すべきなのか?

多くの飲食店にとって「繁忙期」は、売上を大きく伸ばす絶好のタイミングです。しかし、裏を返せばこの時期こそ接客ミスや食材管理不足によるトラブルが起こりやすく、スタッフの疲労やクレーム増加を招くリスクも潜んでいます。さらに近年は社会情勢の変化や東京都など大都市への集中に伴い、繁忙期がずれたり、閑散期が短くなったりするケースも増えているのが実情です。
「繁忙期は勝手にお客様が集まる」と楽観的に構えてしまうと、予約の取りこぼしや店舗オペレーションの混乱で機会損失が生じる可能性があります。逆に、早めに対策を講じてスタッフやメニューを最適化すれば、売上アップのみならず顧客満足度を高めるチャンスをつかむことができます。
第2章.繁忙期別で見る!飲食店がやるべき対策方法!

繁忙期とひと口に言っても、そのピーク時期や客層は店舗の立地や業態によって大きく異なります。ここでは、とくに多くの飲食店が忙しくなる代表的な時期を挙げ、それぞれの特徴と攻略のヒントを整理します。自店の売上データを照合しつつ、「いつ何を準備するか」を検討する材料にしてください。
2-1. 忘年会・新年会シーズン(12月〜1月)
12月から1月にかけては、多くの人が外食を楽しみたいと考える時期です。忘年会や新年会のほか、クリスマス会や家族会食などが集中するため、居酒屋やダイニングバーを中心に予約が殺到しやすくなります。ただしコロナ禍以降は大人数宴会が激減し、少人数や個室利用のニーズが高まっていることも特徴です。
- おすすめ対策
- 大皿料理から「個別盛りコース」への変更
- 予約管理システムの導入で電話対応の混乱を減らす
- キャンセルポリシーを明確化し、ドタキャン被害を最小化
- 大皿料理から「個別盛りコース」への変更
筆者の実践談:ちょっとした工夫で客単価アップ
2-2. 送別会&歓迎会シーズン(3〜4月)
3月は送別会、4月は新卒社員の歓迎会やクラス替え後の集まりが増える季節です。会社員や学生をターゲットにする居酒屋は、平日夜でも満席続きになるケースが多いでしょう。逆に、ファミリー層が多い店舗は季節イベントを絡めた春メニューなどで集客を図るのがおすすめです。
- おすすめ対策
- 新人スタッフが増えるため、短期集中の接客研修を計画的に行う
- 幹事向け特典を設けて、早期予約・団体予約を促進
- お花見帰り需要を見越して“テイクアウト”や“桜モチーフの限定メニュー”を投入
- 新人スタッフが増えるため、短期集中の接客研修を計画的に行う
2-3. お盆・ゴールデンウィークなど大型連休
ゴールデンウィークやお盆休みには、観光客や帰省客が一斉に動きます。観光地や商業施設内の飲食店はピーク売上を更新するチャンスですが、オフィス街など平日中心に稼ぐ店舗は逆に閑散期になりかねません。自店がどちらのタイプかを把握し、客足に合わせた仕入れや人員配置を行うことが必要です。
- おすすめ対策
- 観光客が多い地域では外国語メニューやキャッシュレス決済への対応を強化
- 地元密着型の場合は、家族連れ向けのフェアやイベント企画でリピート率アップ
- 連休中の営業時間変更をSNSで周知し、予約数をコントロール
- 観光客が多い地域では外国語メニューやキャッシュレス決済への対応を強化
第3章. 【準備編】飲食店の繁忙期対策:人員・メニュー開発・業務効率化

繁忙期で大きな成果を得るためには、実際に忙しくなる前の“閑散期”や余裕のある時期にどこまで準備を進められるかが勝負の分かれ目になります。ここでは、人材の採用や教育、メニュー開発、さらにはDXツールの導入といった側面から、準備段階で押さえておくべきポイントを順番に解説します。
3-1. 人員確保:早期採用とスタッフ教育

繁忙期に入ってから急いでスタッフを増やそうとしても、競合の飲食店も同じ時期に求人をかけているため、思うように応募者が集まらないケースが多々あります。また、新たに採用したアルバイトやパートを十分に教育する時間がなく、結果として現場でのオペレーションミスやクレームが増える原因となります。そこで閑散期など比較的余裕のあるタイミングを狙い、じっくりとスタッフ確保とトレーニングを進めるのが望ましい流れです。
3-1-1. なぜ“閑散期の採用”が有利なのか
閑散期は、人材市場自体が落ち着いているため、スタッフの確保に有利な条件が揃いやすい時期です。他の居酒屋やダイニングバーなどと求人募集のタイミングが重ならず、時給や待遇面で差をつけやすいのが実際のところ。また応募者にとっても、少しずつ仕事に慣れていける段階があるほうが定着率が高まります。東京都のような大都市圏では、競合が非常に多い分、早期採用を行う店舗ほど“人材不足”に陥るリスクを軽減できるはずです。
人材確保と教育の強化方法について知りたい方は、『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』の記事が参考になります。
3-1-2. スタッフ研修でミスを減らす
新しく採用したスタッフには、まず基本的な接客マナーや調理補助の手順、オーダー取りの流れなどを体系立てて教えることが肝心です。接客マニュアルや調理マニュアルを準備し、ロールプレイングなどの実践形式で学ばせると、実際の繁忙期にも慌てず業務に取り組めます。さらに、適性の見極めもこの段階で行うと効率的でしょう。レジ担当が得意なスタッフ、キッチン作業が得意なスタッフなど、向き不向きを考慮して配置することで、ミスマッチによるストレスやクレームを防ぐ効果が期待できます。
筆者の実践談:スタッフ教育での失敗
3-2. シフト管理:スポット求人とクラウドツールの活用
繁忙期のピーク時だけ来客数が跳ね上がる店舗では、フルタイムのスタッフを常に抱えておくと人件費の圧迫につながりがちです。一方、週末や特定の日だけ多めに人手が必要なケースも多いため、臨機応変に人員を調整できる環境を整えることが大切です。
3-2-1. スポット求人サービスで“特定日”を補強
短期バイトやスポット求人サービスを活用することで、「毎週土曜の夜だけ大幅に混む」といった変則的な需要に対応できます。固定シフトのスタッフだけではカバーしきれない日時を、その都度働きたい人とマッチングする仕組みがあれば、余計なコストをかけずに繁忙期の山を乗り越えやすくなります。また、利用者が十分に集まるエリアかどうか、事前に確かめておくことも重要です。
3-2-2. シフト作成の効率化とリアルタイム更新
近年はクラウド型シフト管理ツールが充実しており、スタッフがスマホやPCから希望シフトを入力すれば、店長やマネージャーが一覧画面で確認・調整ができるようになっています。従来のように紙ベースのシフト表を使っていると、急な変更や追加募集が生じた際に混乱しやすく、ダブルブッキングや漏れが発生するリスクが高まります。ツールを導入しておけば、勤務希望の変更やキャンセルなどがあってもリアルタイムで反映され、誰がいつ働けるかを明確に把握できるため、繁忙期のオペレーションが安定しやすくなるでしょう。
3-3. メニュー開発:時短調理と季節の演出
繁忙期には提供スピードが遅れがちですが、メニューそのものを「仕込みがしやすい料理」や「大量に作っておいても味を損なわない料理」にシフトすることで、ピーク帯の混雑を大幅に緩和できます。同時に季節感を出した限定メニューを用意すれば、お客様から“手抜き”の印象を与えずに済むだけでなく、売上を上乗せできるチャンスにもなります。
3-3-1. 大量調理&仕込みの効率化
たとえばカレー、シチュー、牛すじ煮込みなど、煮込み系の料理は長時間じっくり煮込むほどコクが出るので、仕込み段階で調理を済ませておけばピーク時には温めるだけで提供可能です。また、前菜やサラダ類はあらかじめ盛り付けを完了し、冷蔵庫で保管しておけば、お客様からオーダーが入ったらすぐに出せます。これによりスタッフの調理負荷を下げると同時に、配膳スピードを高速化できる点が魅力です。
3-3-2. 季節メニューと少人数プラン
冬であれば鍋やポトフ、夏なら冷製パスタや冷しゃぶサラダなど、季節ごとの定番メニューを“繁忙期限定フェア”として打ち出すと、広告宣伝にも活用しやすくなります。また近年は大人数宴会が減少し、2〜4名の小グループで来店するケースが増えているため、大皿料理のコースだけでなく、個別盛りで見栄えを意識した“小人数プラン”を並行して用意するのがおすすめです。こうした柔軟なメニュー構成がリピーターや口コミの増加にもつながります。
3-4. 業務効率化:POSレジ・在庫管理・予約システム
繁忙期の混雑は、スタッフだけでなくお客様にとってもストレス要因になりがちです。しかし、ITやDXツールを上手く導入することで、会計から在庫チェック、予約管理までをスムーズにし、ヒューマンエラーや待ち時間を最小限に抑えることが可能になります。
3-4-1. POSレジで会計の混雑を解消
従来のレジ操作は現金のやり取りが多く、忙しい時間帯にミスが起きやすい上に会計待ちの行列ができてしまうこともありました。POSレジを導入すれば、売上データやメニュー別の注文数をリアルタイムで集計でき、キャッシュレス決済を活用すればお釣りの間違いといったトラブルを大幅に減らせます。また、日次や時間帯別の売上ピークを可視化しやすい点も、繁忙期のシフト配置や仕入れ計画に役立ちます。
おすすめのキャッシュレス対応オールインワン決済端末を知りたい方は、『【2025年最新版】オールインワン決済端末を徹底比較!コスパ最強のおすすめ端末8選もご紹介!』の記事でまとめています。
3-4-2. オーダー&在庫管理の連動
タブレットオーダーやQRコード注文を導入すると、ホールスタッフが走り回らずともキッチンへオーダー情報が届き、混雑時の聞き間違いや二重発注も防ぎやすくなります。さらに在庫管理システムと連携しておけば、特定の食材が不足した段階でオーダーを自動停止に設定するなど、品切れによるクレームや売り損じを最小限に抑えられます。東京都のように利用者数が多い地域では、こうしたDXツールの導入が当たり前になりつつあるため、競合店に遅れをとらないためにも検討が必要です。
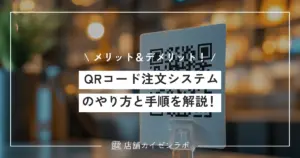
3-4-3. オンライン予約・事前決済のメリット
繁忙期には、電話予約の取りこぼしが大きな課題となります。スタッフが接客中で電話に出られない間に競合店へ流れてしまうケースは少なくありません。オンライン予約システムなら24時間受付ができ、顧客が空き状況を見ながら自分で予約を確定できるため、機会損失を防ぎやすいのが魅力。また、宴会コースやパーティープランを事前決済にすれば、当日の会計処理をスピーディに済ませられるため、ホールが混雑するピーク時に余裕を生み出せます。
第4章. 【実践編】飲食店の繁忙期対策:販促・衛生管理・クレーム対応

準備を万全に整えたうえで、いざ繁忙期が始まると、今度は「どう集客と満足度を最大化するか」「トラブルやリスクをいかに抑えるか」がポイントになります。ここからは、幹事特典やSNSを活用した販促策、衛生管理の徹底やクレーム対応マニュアルの整備といった“本番期”に必要な実践的なアプローチを掘り下げます。
4-1. 販促強化:幹事特典・SNSキャンペーン・リピーター育成
繁忙期は基本的に来客数が見込める時期ですが、逆に言えば「他店も同様に繁忙期」であるため、より効果的な販促を打ち出した店舗に客が集中する可能性があります。そこで重要なのが、“一見さん”をリピーターに変える仕掛け作りや、幹事を味方につけるイベント企画などの取り組みです。
4-1-1. 幹事特典&イベント企画で大人数を呼び込む
送別会や歓迎会、忘年会など、大人数の予約は幹事が店を選ぶケースが大半です。幹事向けの無料特典や割引を設定して「ここを選ぶと得する」というイメージを作っておけば、Google検索やSNSなどで情報収集している幹事に見つけてもらいやすくなります。さらに、サプライズ演出やメッセージプレートなどの付加サービスが充実していれば、幹事としても盛り上げやすく、利用しやすい店舗として認識してもらえるでしょう。
繁忙期に人を呼び込むイベントの企画例は、『【集客アップ】飲食店の面白いイベント企画の考え方!具体的なアイデア集と成功事例を大公開!』の記事を参考にどうぞ。
4-1-2. SNSと連携した限定クーポンや投稿企画
近年はInstagramやTwitterを通じて情報を得る消費者が増えています。繁忙期には新作メニューや限定フェアをSNSで告知し、フォロワー向けに特典クーポンを配布するなどの施策が有効です。たとえば「ストーリーズで当店の紹介をしてくれたらドリンク1杯無料」といったキャンペーンを展開すれば、自然とお店の知名度や口コミが広がります。また、ハッシュタグを独自に作り、顧客が投稿しやすいように工夫すると、一見さんの集客力が一段と高まるでしょう。

4-1-3. リピーター促進のためのポイントカード&メール配信
繁忙期に初めて来店した顧客が、そのまま一度きりで終わるのはもったいない話です。ポイントカードやアプリ登録を促し、次回の来店で使えるドリンク無料券や割引特典を提供しておくことで、閑散期にも再訪してもらいやすくなります。メールマガジンやLINE公式アカウントを活用し、「◯月限定の新メニューができました!」とプッシュ通知を送れば、タイミングよく顧客の関心を引けるはずです。
筆者の実践談:繁忙期に合わせた施策
4-2. 衛生管理を徹底し、信頼をキープする
繁忙期こそ店内が混み合い、スタッフも忙しくなるため、衛生管理や食材管理がおろそかになりやすいのが実情です。しかし、万が一食中毒や大きな衛生トラブルが起これば、SNSで評判が一気に広まり、売上が激減するリスクを抱えます。忙しいときほど“基本”を徹底し、店内を清潔に保ち、安全な食材を提供することが欠かせません。
4-2-1. 店内清掃・除菌のルーティン
客席、ドアノブ、メニュー表、トイレなど、不特定多数が触れる箇所は定期的に拭き掃除やアルコール除菌を行う必要があります。混雑時でも担当者を決め、交代で店内を巡回しながら清潔を維持できる体制を作っておきましょう。最近はお客様自身がSNSに店内写真を投稿するケースも多く、「忙しそうだったけどテーブルが常に綺麗だった」といったポジティブな口コミが広がることは大きなアドバンテージになります。
4-2-2. 食材の温度管理と調理基準
冷蔵庫・冷凍庫の温度を定期的に確認し、記録しておくことは、繁忙期だからこそ重要度が増します。加熱が必要な食材の適正温度や賞味期限は、あらかじめ明確なマニュアルを作成し、スタッフ全員が同じルールで調理するように徹底します。また、設備の故障が起きないように閑散期のうちにメンテナンスを済ませ、万が一不具合が発生した場合にすぐ対応できる業者の連絡先を共有しておくと安心です。
4-3. クレーム対応マニュアル:先手を打って混乱防止
オーダーミス、料理の提供遅延、席の配分ミスなど、繁忙期にはどうしてもトラブルが起きがちです。しかし、クレームへの初動がスムーズで誠実さを感じられるものであれば、お客様の不満が深刻化する前に解決し、かえって「きちんとした対応をしてくれるお店」と好意的に捉えられる可能性すらあります。
4-3-1. クレーム発生ポイントを明確にする
飲食店のクレームの大半は、(1) 提供スピードが遅い、(2) 注文が伝わっていない、(3) 席の案内や配席がスムーズでない、といった要因から発生します。あらかじめ「これらの状況が起きた場合、誰が対応するか」「店長にエスカレーションする基準はどこか」を定め、スタッフ全員に周知しておくと、現場が混乱しづらくなるでしょう。特に新人スタッフも繁忙期に投入される場合は、クレーム処理のやり方をロールプレイングで練習しておくと効果的です。
4-3-2. 店内動線の見直しとクレーム専任担当
繁忙期は席数をフル活用し、しかも回転率を上げるためにホール内が忙しなくなります。その際、スタッフ同士がぶつかったり、通路が狭すぎて料理の提供に時間がかかったりすることが、クレームにつながる恐れがあります。そこで店内動線を見直し、スタッフがスムーズに行き来できるレイアウトを整備するのがおすすめです。また、余裕があればベテランスタッフを“クレーム専任”としてホールに配置しておくと、初期対応のスピードが上がり、大きなクレームに発展しにくくなります。
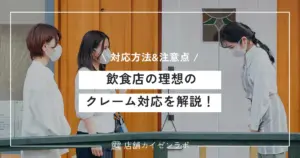
4-4. 全体最適を目指す:スタッフ疲労と予約管理への注意点
繁忙期に、ただひたすら“忙しいから残業を増やす”という形で乗り切ろうとすると、スタッフの疲労やモチベーション低下によって離職が急増する可能性があります。一度スタッフが大量に辞めると、回らなくなった業務がさらに既存メンバーに負荷をかける悪循環に陥るため、事前に休憩とシフト管理を見直す必要があります。
4-4-1. スタッフの休憩とメンタルケア
「休憩どころか食事を取る暇もない」という状況が数日続けば、どんなに意欲の高いスタッフでも限界を感じるものです。繁忙期でも短いスパンで休憩を挟み、シフトを組む段階から“負担が集中しすぎない”よう工夫しましょう。特に週末や祝日など、最も忙しい日程に複数のベテランを配置し、パートやアルバイトがサポートに回りやすい体制を敷くのが効果的です。
4-4-2. 予約重複とオーバーブッキング対策
オンライン予約と電話予約を併用している店舗では、同じ時間帯に複数の大人数予約が重なる「オーバーブッキング」が深刻な問題となりがちです。予約管理システムを導入し、空席の数と予約状況をリアルタイムに同期させることで、予約可能枠の制限をかけて無理のない受け入れ体制を整えるようにしましょう。顧客が当日来店して「席がない」という事態を避けることができれば、トラブルやSNSへの不満投稿を防ぎ、店舗の評判を保つことにつながります。
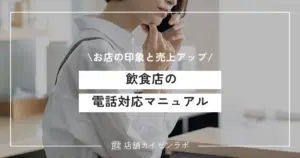
第5章. 見落としがちな繁忙期でよくある飲食店の落とし穴

飲食店の繁忙期は売上増のチャンスであると同時に、スタッフ疲労や予約管理ミスなどのリスクが高まる時期でもあります。目の前の業務に追われていると、長期的な店舗運営に負の影響を及ぼしかねない要素を見落としがちです。この章では、売上を伸ばす裏で起こりやすい代表的な“落とし穴”を取り上げ、具体的な対処法を紹介します。
5-1. スタッフの疲労・モチベーション低下
- 連日の長時間シフトが離職を招く
繁忙期にシフトが集中すると、スタッフが連日残業を強いられ、疲労やストレスが溜まりやすくなります。疲弊したスタッフが一気に離職すると、さらに人手不足が深刻化し、悪循環に陥る恐れもあります。 - 対策:適度な休憩とシフトバランス
ピーク時間帯にスタッフを厚くし、それ以外は薄くするなどメリハリをつけた編成が大切です。また、“休憩を必ず取らせるルール”を徹底し、体力的にも精神的にもケアを図りましょう。繁忙期特別手当など、金銭的インセンティブを用意するのも有効です。
口コミ引用:アルバイトスタッフの投稿
5-2. オーバーブッキングや予約管理の混乱
- 一度に複数の予約が集中しがち
電話予約・オンライン予約・直接来店など、さまざまな経路で同じ時間帯に席が重複してしまう「オーバーブッキング」は繁忙期に起こりやすいトラブル。せっかくお客様が来店しても席が用意できない場合、クレームに発展するだけでなく、機会損失にもつながります。 - 対策:予約管理システムの一元化
前章でも述べたように、オンライン予約システムを使いこなして予約枠を適切に制限し、電話予約や飛び込み客も含めて一括管理する方法がおすすめです。スタッフ間で「今どの席が空いているか」を即時に共有できる仕組みを整えましょう。
5-3. 店舗設備の故障・不足
- 繁忙期に限って起こるトラブル
調理器具や冷蔵庫、エアコンなどがフル稼働し、負荷がかかった結果、急な故障が起こるケースがあります。対策を怠ると「冷凍庫が止まって大量の食材が廃棄に…」といった最悪の事態もあり得ます。 - 対策:閑散期のうちにメンテナンスを済ませる
繁忙期直前に設備点検や簡易修理を行い、トラブルを未然に防ぎましょう。急な故障に対応できる業者の連絡先をスタッフ間で共有しておくのも重要です。
筆者の実践談:予約の取りこぼし改善
第6章. 飲食店の繁忙期に関してよくある悩みと質問

飲食店における「IT化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、もはや一部の先進的な店舗だけの取り組みではありません。SNSや予約システムを含むさまざまなDXツールが普及し、繁忙期と閑散期の落差をコントロールする手段として注目されています。ここでは、具体的な活用事例やメリットを紹介していきます。
6-1. 繁忙期をチャンスに変えるITツール「ビジネスチャット」
ここでは、よくある“繁忙期対策の勘違い”や“ちょっとした疑問”についてQ&A形式で取り上げます。忙しい時期にこそ浮上しやすい課題を整理し、正しい解決策を再確認してみましょう。
6-1. Q1:電話予約だけで十分だと思うのですが、オンライン予約の体制は本当に整えた方が良いですか?
A. 電話予約のみだと、ピークタイムにスタッフが出られない電話が増え、見込み客を逃すリスクがあります。オンライン予約を導入すれば24時間受付でき、顧客自身が空き状況を見て予約日時を設定できるため“電話対応の手間”を減らせます。特に東京都や大都市のように競合店が多い地域では、オンライン予約を備えている店舗が支持されやすい傾向があるので、導入を検討しましょう。
6-2. Q2:スタッフを増やしたいけど、閑散期はそんなに人が必要ありません。無駄になりませんか?
A. 繁忙期こそ人手が欲しいものの、閑散期はシフトが削られがちでアルバイト定着率が下がる、という悩みは多いです。短期スポット求人サービスやパートタイム採用を組み合わせて、繁忙期の週末だけ複数人を増やせる柔軟な体制を構築する方法があります。逆に、閑散期を“教育期間”と割り切り、新人スタッフをじっくり育てる戦略も有効です。
6-3. Q3:クレーム対応は店長が出て謝れば十分ですよね?
A. 店長が矢面に立つのはもちろん一つの方法ですが、現場のスタッフが初期対応を誤ってしまうと、大きなクレームに発展する可能性があります。クレーム対応のマニュアルを作成し、全員で共有・ロールプレイングしておくことが不可欠です。迅速な対応と誠意ある謝罪ができれば、逆に顧客の信頼度が上がる例も少なくありません。
6-4. Q4:DXツール導入はコストがかかる印象があります。小規模店舗では不要ですか?
A. 最近は月額数千円程度から導入できるPOSレジや予約システムも増えています。小規模店舗ほどスタッフの頭数が限られており、“人力で補えない”部分をITでカバーするメリットは大きいといえます。特に繁忙期には電話対応や会計作業などが集中するため、DXツールを導入することで長い目で見るとコスト削減につながるケースも多いです。
第7章. 次の繁忙期へ向けてしっかりと準備を始めよう
飲食店の繁忙期は売上を大きく伸ばすチャンスである一方、スタッフ不足や提供の遅れ、クレーム増加などリスクも高まる時期です。対策としては閑散期のうちに人員採用と教育を進め、メニューを仕込み重視の構成に見直し、オンライン予約やPOSレジなどDXツールを導入して予約取りこぼしや会計業務の混乱を減らすことが重要です。
また、実際の繁忙期には幹事特典やSNS販促で新規客を呼び込みつつ、衛生管理やクレーム対応マニュアルを徹底して信頼を守ることが欠かせません。さらにスタッフの休憩やオーバーブッキング対策など細部までケアを行い、短期的な売上と長期的な顧客満足の両立を目指すことで、繁忙期を機に安定した経営基盤を築くことが可能になります。