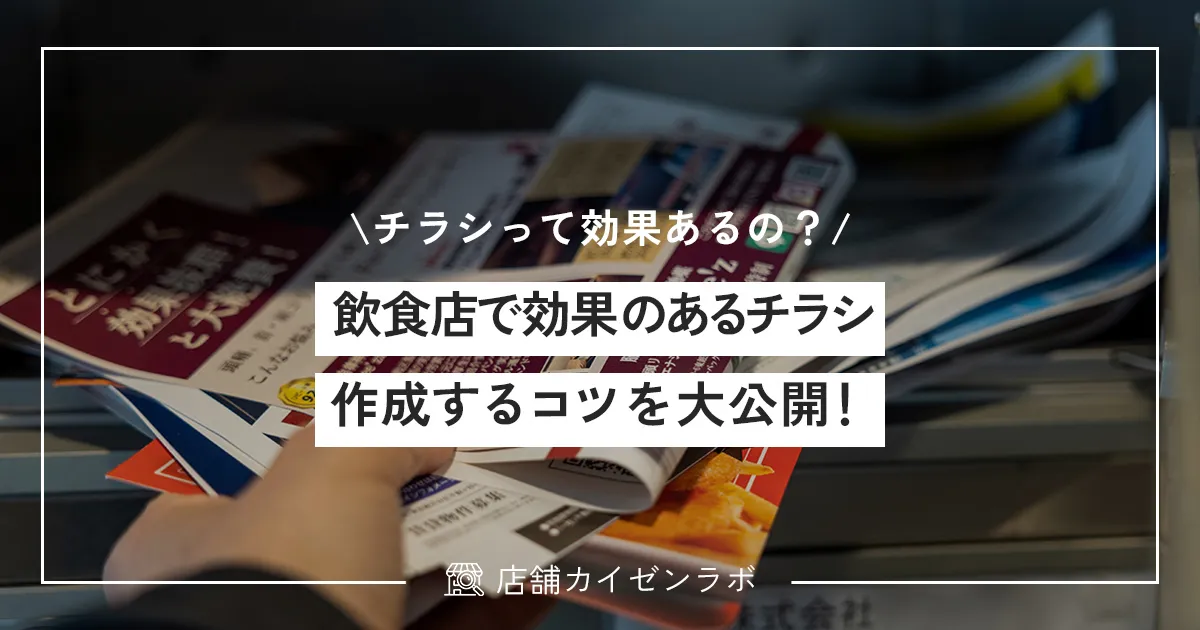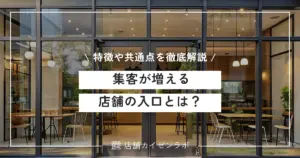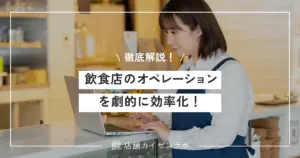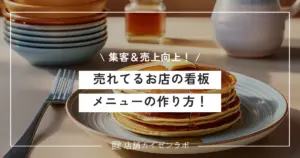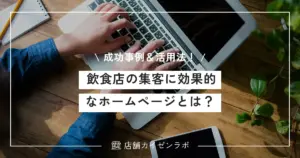第1章. 飲食店がチラシを活用してポスティングをするメリットとは?

1-1. 店舗周辺から新規見込み客を獲得できる
飲食店の主要ターゲットは、店舗周辺の居住者や通勤者が中心です。ポスティングはその商圏内に「ピンポイントでチラシを届ける」手法として効果が高く、わざわざ遠方を狙うよりはるかに短期間で見込み客を獲得しやすいのがメリット。いわゆる“フライヤー(チラシ)”を配布するだけで、地域の住民が“あ、こんなお店があったんだ”と認知してくれるため、無駄なコストを抑えながら集客できます。
一方、新聞折込やWeb広告は広く拡散する強みがある反面、近隣以外の層にもリーチしてしまい、費用対効果が下がるケースがあります。ポスティングはあらかじめ配布エリアを限定しやすいので、徒歩圏内や自転車圏内など、“実際に来店可能性が高い人”に焦点を絞れます。ターゲットがはっきりしている店舗ほど、ポスティングの真価を発揮できるでしょう。
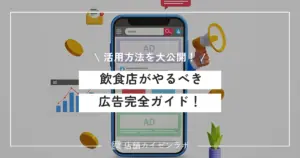
1-2. 低予算でも効率良く集客が期待できる
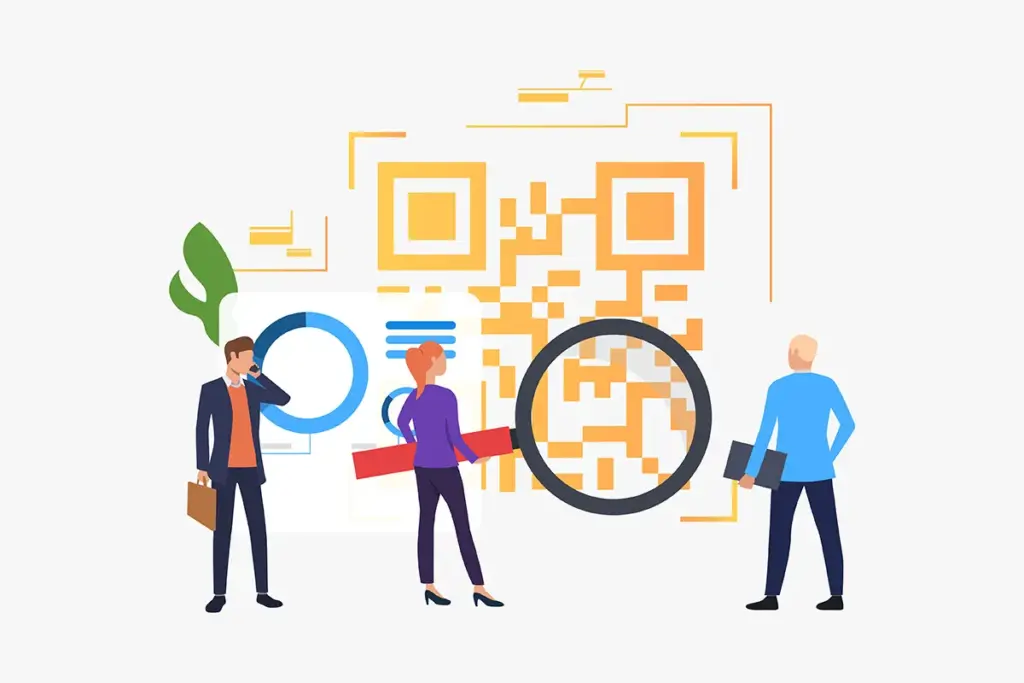
大がかりなテレビCMやラジオCM、あるいは大手ポータルサイトへの広告出稿と比べると、ポスティングははるかに低コストで始められます。大量に印刷するフライヤーほど単価は下がりやすくなり、用紙のサイズや印刷加工(たとえば特色インクやミシン目など)を必要最低限に抑えれば、予算の範囲内で十分な枚数を確保しやすいのも魅力です。
さらに、必要な地域や世帯を絞ることで“薄く広く配る”のではなく、“濃く狭く配る”戦略を取りやすいのもポイント。オフィス街のランチ需要、学生街のボリューム志向など、ターゲット別にメッセージを変えてチラシを作成すれば、同じ予算でも高い反応率が得られます。
1-3. 自分の店舗だけを“独占的に”アピールできる
新聞折込やポータルサイトの広告枠に載せると、どうしても複数の広告と並列で比較されがちです。ユーザーの目に留まりにくい場合もあり、折り込み広告だと他店のチラシと一緒に捨てられてしまう可能性も否めません。
一方、ポスティングの場合は、ポストに投函されたチラシが単独で見られるため、“自分の店舗だけ”をアピールしやすい利点があります。裏を返せば、デザインや文字情報が不十分だと一瞬で捨てられるリスクもありますが、それはデザインと作成方法を工夫してカバーすればOK。しっかり写真や文字を整え、魅力的なオファーを打ち出せば、“オンリーワン”の存在感を示せるでしょう。

第2章. はじめてでも安心!飲食店のチラシの簡単な作成方法!

2-1. 作成の全体フローを理解する
チラシ(フライヤー)をゼロから作成するには、ざっくり以下のステップがあります。
- コンセプト決め:ターゲット層や目的(新商品告知、オープン告知、リニューアルなど)を明確化
- デザインレイアウトの作成:テンプレートを使う or プロに依頼する
- 印刷仕様の決定:サイズ(A4、A5など)、用紙(コート紙、マット紙など)、特色使用や折り加工の有無
- 印刷の注文と納期確定:オンライン印刷サービスのご利用や地元の印刷会社へ依頼
- 配布方法の選択:ポスティング、新聞折込、手配りなど
初心者の場合は、無料でダウンロードできるテンプレートや、オンラインデザインツール(Canvaなど)を活用してレイアウトを組むのがおすすめです。慣れてきたら、一部だけプロのデザイナーに外注して完成度を高める方法もあります。
筆者の実践談:プロへの依頼
2-2. 印刷会社を選ぶポイント
印刷会社を選ぶ際には、以下のような点が重要です。
- 見積もりの透明性:印刷サイズ、用紙グレード、色数、特色の有無、折り加工やミシン目加工など、それぞれの費用が明確になっているか
- 納期:イベントやオープン告知など“いつまでに欲しいか”を事前に伝え、必ず余裕を持ってスケジュールを組む
- 対応範囲:デザイン修正や写真加工までサポート可能か、データ入稿だけでOKかなど、希望に合わせて柔軟に対応してくれるか
第3章. 飲食店のチラシ作成において大切な8つのポイント

3-1. ターゲットを決める
飲食店チラシで最も重要なのは「誰に向けて発信するか」を明確にすること。たとえば、ファミリー層向けならキッズメニューや個室の有無、ビジネスマン向けならランチの速さやコスパを強調するなど、伝えるべき情報が異なります。ターゲットを具体的にイメージして作成すると、内容がブレにくくなり、反応率が大きく変わってきます。
3-2. 掲載する情報を絞る
せっかくのチラシだからといって、メニューやクーポンを大量に詰め込むと、逆に見づらくなりがち。人はひと目で何を訴求されているのかが分からないと、そのまま読むのをやめてしまいます。そこで大切なのが「情報の優先順位づけ」。店舗名・ロゴ、メイン写真、特典などを前面に打ち出し、補足的な情報は裏面や小枠にまとめるのがおすすめです。
3-3. 映える&食べたいと思わせる写真を用意する

飲食店チラシで最も重要といっても過言ではないのが“料理写真”です。明るさや彩度、角度を少し変えるだけで「美味しそう!」と思われる度合いが大きく変わります。できれば自然光が入る場所や、専用ライト・レフ板を使うのが理想。加工ソフト(Photoshopや無料ツール)で色味を調整し、シズル感をアップさせるのも手です。
- ポイント:
- 背景はシンプルにして料理を際立たせる
- 器や食材の色を合わせて統一感を出す
- 同じアングルの写真ばかり並べない
- 背景はシンプルにして料理を際立たせる
チラシ効果を高める、美味しさを引き立てる写真撮影には専門の業者に依頼することをおすすめします。優良業者は、『飲食店が写真撮影を依頼する際の業者の選び方のコツと注意点!料理撮影に強いおすすめな会社も厳選してご紹介!』の記事にまとめていますので参考にどうぞ。
3-4. 季節感を出す
季節限定のメニューや季節カラーを取り入れたデザインは、それだけで特別感を演出できます。春なら桜やパステル系、夏なら涼しげなブルーやガラス器、秋冬は暖色系の写真と背景色を用いるなど、「今しかない雰囲気」をアピールするのがコツ。チラシを手に取った瞬間、「シーズンごとに違うメニューがあるんだ」と興味を持ってもらえます。
3-5. 暖色系の色を使用する
赤やオレンジなどの暖色系カラーは、人間の食欲を刺激しやすいといわれています。全面を赤にするのは逆効果の場合もあるので、メインビジュアルの一部や文字装飾に取り入れると良いでしょう。特にスープや肉料理などは赤系の背景やアクセントを使うと、より美味しそうに見える傾向があります。
3-6. 料理のジャンルに合わせた配色でデザインする
和食なら和風の落ち着いた色味(茶、黒、紺など)を基調にしたり、居酒屋なら少しにぎやかな色使いで楽しさを演出するなど、業態ごとの“世界観”を表現します。イタリアンなら国旗カラーの赤・緑・白を差し色に使う方法も定番。ジャンルに合わない配色を選んでしまうと、店のイメージが伝わりにくくなるので注意が必要です。
3-7. 反響率を計測できるようにする
チラシを作るだけで満足してしまうのはもったいない。必ず「クーポン」「QRコード」「キャンペーンコード」など、反響を測定できる仕掛けを入れましょう。たとえば、QRコードを読み取ってもらうとオリジナル特典ページに飛ぶようにしておけば、配布エリアごとのアクセス数を追えるうえ、SNSやLINE公式アカウントへ誘導しやすくなります。
3-8. ロゴや店名を大きく配置して“覚えてもらう”
チラシの表面にロゴや店名をしっかり配置することで、“どんな店か”を一瞬で理解してもらえるようになります。店名やロゴが目立つと、繰り返し目にするうちに読者の潜在意識に刷り込まれ、将来的な来店にもつながりやすいのがメリット。特に開業まもないお店ほど、ロゴと店名の認知度を高めることが大切です。
第4章. 飲食店への来店に繋げるチラシの効果的な配布方法3選!

4-1. ポスティング:地域に“直接アタック”できる鉄板手法
ポスティングは、飲食店のチラシ配布で最もポピュラーな方法のひとつ。マンションや戸建て住宅のポストへ直接投函するため、ターゲットの居住層にダイレクトにアプローチできます。「実際に足を使って届ける行動力」が伝わりやすく、地域の信頼獲得にもつながるのがポイントです。
- メリット
- 範囲の選定が自在:駅周辺、大学近くなど特定のエリアだけを集中的に攻められる
- 他広告と競合しない:新聞折込のように、ほかのチラシと混在することが少ない
- 低コスト運用が可能:スタッフが空き時間に回れたり、外注のポスティングサービスも比較的安価
- 範囲の選定が自在:駅周辺、大学近くなど特定のエリアだけを集中的に攻められる
- デメリット / 注意点
- 手間と時間がかかる:自社スタッフが配る場合、広範囲だと数日かかるケースも
- 投函できない物件がある:オートロックマンションなど、管理人の許可が必要な場合
- 手間と時間がかかる:自社スタッフが配る場合、広範囲だと数日かかるケースも
4-2. 新聞折込:シニア層へのアプローチに効果的
新聞を購読している世帯がターゲットに多い場合、新聞折込が選択肢に入ります。折込チラシは朝刊・夕刊に織り込まれるため、比較的高齢者層やファミリー層が目にする機会が多いです。地域密着のローカル紙を活用すれば、ポスティング以上に広範囲へアプローチしやすいメリットがあります。
- メリット
- 確実に配達される:新聞を手に取る際、ほとんどの人が折込チラシを目にする
- 費用感が明確:折込料は新聞社や地域ごとに相場が決まっており、配布エリアを細かく選べる
- 安定した読者層:新聞を読む習慣のある中高年層に適しており、リピート狙いにも使いやすい
- 確実に配達される:新聞を手に取る際、ほとんどの人が折込チラシを目にする
- デメリット / 注意点
- 若年層へのリーチが限定的:新聞を取っていない一人暮らしの学生や社会人はカバーできない
- 他のチラシと競合:大量の折込チラシの中に埋もれるリスクがある
- 若年層へのリーチが限定的:新聞を取っていない一人暮らしの学生や社会人はカバーできない
4-3. 店頭配布・駅前配布:狙った時間帯に直接手渡し
駅前や店舗付近でチラシを手渡しする方法は、ターゲットを見極めやすいのが特徴。平日の朝なら通勤客、夕方なら仕事帰りのビジネスパーソンといった形で、欲しい層に絞って声をかけられます。接触回数は少ないかもしれませんが、「対面コミュニケーション」が強い信頼感を生み出します。
- メリット
- 直接の会話が可能:チラシ配布と同時に店のアピールや簡単な説明ができる
- 時間帯でターゲットを変えられる:朝と夜で配る相手が違うため、複数メニューの訴求が可能
- 即時反応が分かる:受け取り拒否の割合やチラシを見ながら質問される内容など、現場感がつかみやすい
- 直接の会話が可能:チラシ配布と同時に店のアピールや簡単な説明ができる
- デメリット / 注意点
- 人件費がかかる:立ち配りに人を割けるだけの余裕が必要
- 天候に左右される:雨や猛暑で配布効率が極端に下がる恐れ
- 人件費がかかる:立ち配りに人を割けるだけの余裕が必要
イベントと連動させた配布戦略を知りたい方は、『【集客アップ】飲食店の面白いイベント企画の考え方!具体的なアイデア集と成功事例を大公開!』の記事が参考になります。
第5章. チラシ配布を集客に繋げるために大切な3つのポイント

5-1. 集中的なポスティングの効果を最大化
ポスティングは「ある狭いエリアに集中して短期間で配布する」と、チラシを受け取る頻度が上がり、認知度が一気に高まる傾向があります。特に、エリア選定が重要。たとえば、単身者向けメニューを推すなら大学やオフィスが近い地域、ファミリー向けなら学校や大型スーパー周辺を重点的に攻めるなど、狙いを明確にすれば予算対効果が上がります。
筆者の実践談:ポスティング一点集中法
5-2. 配布エリアとターゲットのマッチング
同じ“ファミリー層”でも、駅前高層マンション群と郊外の戸建て住宅街ではライフスタイルが異なります。地域の特性に精通した“権威のある”店舗と思ってもらうためには、配布エリアの属性をリサーチすることが欠かせません。自治体の人口統計や住宅地図、周辺の学校や商業施設の情報などを調べ、店のコンセプトと整合する場所を優先的に狙いましょう。
- チェック項目
- 周囲の施設:学校、企業ビル、スーパー、銀行など
- 住人の世帯構成:子育て世帯、学生、単身ビジネスマンなど
- 競合店舗の位置:同業他店との距離や価格帯を把握
- 周囲の施設:学校、企業ビル、スーパー、銀行など
5-3. 効果的な配布タイミングを見極める
「曜日」「時間帯」を工夫するだけで、チラシの反応率は劇的に変わります。金曜の夜にポスティングすれば「週末どこで食事しよう?」と考えている家庭やビジネスマンの目に留まりやすい。給料日後のタイミングを狙えば、外食意欲が高いタイミングを直撃できます。最も店が忙しくなる直前に配っても余裕がないので、むしろ狙い目はその前週や週の初めです。
- 事例
- 金曜夕方〜土曜朝の配布:週末外食を検討するファミリー層やカップルを捉える
- 給料日翌週の配布:財布が潤っている時期にクーポンが刺さりやすい
- イベント前に重ね配布:花見シーズンやクリスマス時期などに合わせる
- 金曜夕方〜土曜朝の配布:週末外食を検討するファミリー層やカップルを捉える
チラシ配布と併せて、他の販促策を取り入れることで集客効果を最大化できます。『【完全版】飲食店で効果の高い販促方法を総まとめ!売上や来店に繋がる手法を大公開!』の記事にまとめていますので併せてご活用ください。
第6章. 飲食店のチラシ配りで失敗しないための注意点
6-1. むやみに配布範囲を広げない
「数打ちゃ当たる」とばかりに遠方まで一気にチラシをまき散らすと、費用ばかりかさんで実際の来店が少ないという残念な結果に。商圏や客単価の見込めるエリアを丁寧に調べるのが大切です。特に開業まもない頃は、店舗近隣の狭いエリアに集中配布を行い、反応が取れたら徐々に範囲を広げるステップがおすすめ。
筆者失敗談:エリア選定ミスの結果
6-2. オファーやクーポン内容が魅力的か再チェック
チラシを受け取った人に「行ってみようかな」と思ってもらうには、“お得感”や“興味を引くフック”が欠かせません。まったく割引率が低かったり、クーポン内容が複雑すぎると、せっかくのチラシがスルーされる原因に。地元で評判の料理の無料トッピングや「○○円OFF」など、シンプルかつインパクトある特典を検討しましょう。
- 注意点
- 割引率が大きすぎて収益が合わない場合は期間限定にする
- 料理写真やクーポン部分をしっかり目立つ配置に
- 割引率が大きすぎて収益が合わない場合は期間限定にする
6-3. デザインや写真の質を妥協しない
とにかく安上がりで済ませたいからといって、画像が粗いまま印刷したり、文字の配置を適当にすると「この店、なんだか怪しいな……」と敬遠されるリスクがあります。メインビジュアルや文字の読みやすさ、配色の統一感などは妥協せずに仕上げるのが鉄則。プロのデザイナーに部分的に依頼するだけでも、見た目の印象はガラリと変わります。
6-4. 反応率を見ずに次の施策を進めない
チラシ配布後の反応が芳しくなかったのに「まぁいいか」と放置していると、同じ失敗を繰り返してしまいます。クーポンの回収率やSNSフォロー率、アンケートを通じた店舗認知度など、具体的な数字やお客様の声を集め、次回のチラシ作成に反映しましょう。
集めたアンケートやお客様の声から顧客満足度を高めるためのオペレーション施策は、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事に詳しく説明しています。
第7章. 飲食店で実際に効果が出たチラシの成功事例

7-1. 居酒屋A:ビジネスマン向け“二次会クーポン”が大ヒット
デザイン要点
- 配色:落ち着いたネイビー背景+黄色のアクセント文字で視認性UP
- サイズ:A4両面フライヤーで、お得な宴会コースとドリンクメニューを大きく紹介
- 特色:ミシン目を使った切り取りクーポン。二次会利用時にドリンク1杯無料
ターゲットへの刺さり方
職場の歓送迎会や飲み会後の“二次会需要”を狙い、近隣のオフィスビルを中心に配布。「2軒目どこ行く?」と悩むタイミングでクーポンを思い出し、利用率が高まったとのこと。「仕事帰りのビジネスマン目線を熟知した専門性」が評価され、サクッと追加注文を促す仕掛けが好評でした。
7-2. 和食店B:季節限定メニューのみを大胆に打ち出す
デザイン要点
- 表面:季節の食材(春なら桜鯛、秋なら松茸など)を大きく写した料理写真を一面に配置
- 裏面:店舗ロゴと地図、営業時間をシンプルにまとめ、文字情報を最小限に
- 用紙:上質なマットコート紙+特色印刷で高級感を演出
ターゲットへの刺さり方
対象は比較的年齢層が高めのシニア・ミドル世代。新聞折込とポスティングの併用で「ご年配でもすぐに見やすい」大きめ文字と落ち着いた色味を採用し、信頼度がアップ。店主の経歴や和食の伝統技法を少しだけキャッチコピーに混ぜたことも効果的だったそうです。
第8章. 飲食店のチラシについてよくある勘違い
8-1. Q1:1回配れば十分じゃない?
A:チラシ施策は1回きりで終わらせるのはもったいないです。複数回配布することで「この店、気になる」と再認識してもらいやすく、専門家としての存在感がアップします。特に新メニューや季節限定メニューが変わるたびに配布すると、定期的な認知を獲得できます。
8-2. Q2:チラシよりWeb広告のほうが今風じゃない?
A:確かにWeb広告やSNSも有効ですが、紙のチラシは“物理的接触”による訴求力があります。Web広告が得意な層だけでなく、紙媒体を好む年齢層にもアプローチできる点が大きな強み。「デジタルだけでは捉えきれない層をカバーする」のが戦略的です。
8-3. Q3:デザインは無料テンプレートで適当に組めばOK?
A:確かにコスト削減にはなりますが、“見やすさ”や“写真の美しさ”を軽視してはいけません。無料テンプレートでも十分きれいなフライヤーを作れますが、用紙サイズの塗り足し設定や印刷データの解像度など、細かいスジのチェックが必須です。専門知識を多少取り入れると仕上がりが格段に向上します。
8-4. Q4:クーポンをつけると常連の客単価が下がりそう…
A:一時的な割引はあるものの、クーポンで新規客を増やし、リピートしてもらえれば十分ペイできます。また、「サービス精神のある店」という印象が好感度を高め、口コミや評判向上につながります。期間限定にすれば常連客が不満を抱くケースも最小限に抑えられます。
8-5. Q5:高齢者向けならデザインは無難に…?
A:無難にまとめるだけでなく、大きめ文字や写真で見やすさを確保するのは大事です。メニューのこだわりポイントや食材選びのプロセスなどをしっかり入れておくと、むしろシニア層から高い評価を得られます。情報量ゼロのデザインより、安心できる根拠を示す方が効果的です。
8-6. Q6:配布後の反応がイマイチ。どうすれば?
A:まず“どこで、いつ、どんな内容で配ったか”を詳細にデータ化し、改善点を洗い出しましょう。エリアが広すぎる、クーポン内容が弱い、写真が暗いなど、問題点はいくつも考えられます。失敗原因を分析し、アドバイスを受けられる専門家や印刷会社との相談も視野に入れるといいでしょう。
第9章. チラシにこだわれば地元の人気飲食店になれる!
飲食店のチラシを活用したポスティング施策は、単発で終わるものではなく、配布と改善のサイクルを継続して回すことが肝心です。ターゲットや季節に応じてデザインやクーポン内容を見直し、配布エリアやタイミングを変えることで効果を安定的に高められます。実績や口コミを重ねていけば、地域住民からの信頼が蓄積し、リピーターも増加。
紙のチラシとSNSなどのオンライン施策を組み合わせれば、“手元に残る安心感”と“拡散力”の相乗効果を狙えます。最終的には、周辺の人々に「よく知っている店」として認識され、安定した集客が期待できるでしょう。成果が出るまで試行錯誤を繰り返し、得られたデータを次の施策に反映する地道な積み重ねこそが、飲食店チラシを大きな武器に変える鍵となります。