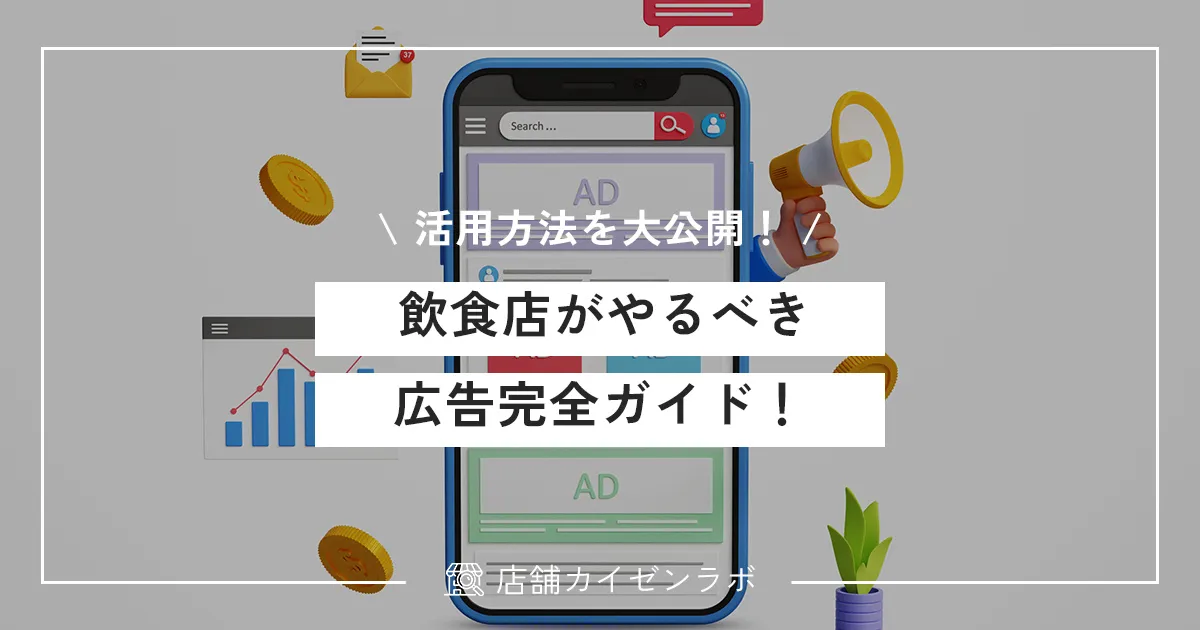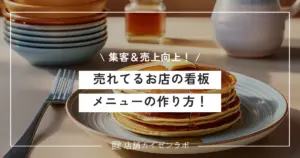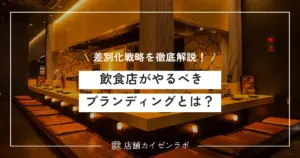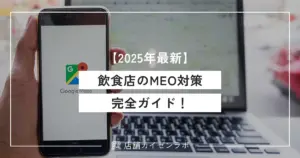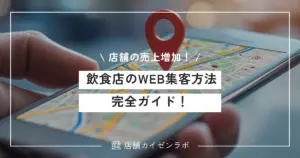第1章. 飲食店が広告を行う重要性とメリット

1-1. 集客だけじゃない!飲食店に広告を打つ真の価値
飲食店における広告といえば、新規顧客を増やすための手段として考えられがちです。もちろん、それは大きな目的の一つですが、広告によって得られるメリットはそれだけではありません。具体的には「認知度向上」「リピーター育成」「ブランディング向上」「スタッフモチベーションアップ」など、さまざまな副次的効果が期待できます。
たとえば、チラシやSNSによって自店舗の強みを外部に発信することで、スタッフが「当店にはこんな良いところがあるのだ」と再認識でき、サービス向上につながることも少なくありません。広告を単なる販促ではなく「お店の魅力を再発見し、磨くツール」として捉えると、より多くの可能性を引き出せるのです。
1-2. リアル店舗が重視すべき「認知×信頼」の方程式
広告には、単に「店を知ってもらう」以上の効果として、店の“信頼感”を高める役割もあります。広告を見ると、多くの人は「あ、この店はきちんと運用・管理をしているんだな」「広告を出すほど本気なのだな」と無意識に感じやすいものです。
特に飲食店の場合、食品衛生や接客品質などに対してユーザーは慎重になりがち。そのため、“しっかり告知されているお店”=“安心して利用できそうなお店”という心理的効果が働く点は見逃せません。広告を出すことで認知だけでなく信頼度も獲得し、最終的に集客や売上アップにつなげられるのです。
1-3. 広告がトリガーになる!新メニューや企画のテストマーケティング

新メニューや新サービスを投入するとき、広告をうまく活用すれば“テストマーケティング”としても機能します。たとえば、SNS広告を使って「期間限定の新メニュー」を周知すれば、反響や予約数からリリース前におおまかな需要をつかむことができます。広告の費用対効果を見ながら、顧客層・時間帯・地域性などのデータも蓄積できるので、次の施策に生かしやすいのがメリットです。
こうした情報は、ただ店頭で新商品を出して様子を見ているだけでは得られません。「新しいチャレンジをする際、広告を併用することで短期間で広く意見を集める」—飲食店が広告を活用する大きな醍醐味といえるでしょう。
第2章. 地元客をがっちり掴む!飲食店がやるべきアナログ広告10選

2-1. チラシのポスティング:狙い撃ちで新規客を獲得
2-1-1. ポスティングのメリットと費用感
チラシのポスティングは、特定エリア内の住民を“狙い撃ち”できる集客方法として根強い人気があります。新聞をとっていない若年層や共働き家庭にも直接リーチでき、配布単価も1枚数円〜数十円と比較的安価です。
印刷費を含めても数万円規模で数千枚を配れるため、うまくターゲットエリアを絞れば費用対効果が高いといえます。地域イベントに合わせて時期を調整すると、さらに目に留まりやすくなるでしょう。
2-1-2. 高反応率につなげるデザインとタイミング
夜の飲食店なら、夕方以降にポスティングすることで「今日は外食にしようかな」と思っている世帯を取り込めます。視認性の高いデザインや限定クーポンを載せると、反応率アップが期待できます。
ポスティングについてさらに深く学びたい方は『飲食店のポスティング成功完全ガイド!最も集客効果が高い方法を大公開!』をご覧ください。
筆者の実践談:居酒屋での施策
2-2. 新聞折り込みチラシで広範囲にアピール
2-2-1. “新聞購読層”への一斉周知が可能
新聞折り込みチラシは、新聞を定期購読している世帯に一斉配布できるため、シニア層や主婦層へのアピールに有効です。さらに配布エリアを細かく指定可能なので、店舗から徒歩圏内に限定して広告費を抑えることもできます。
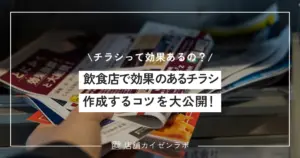
2-2-2. コンバージョンを高めるクーポン連動のポイント
紙クーポンはデジタルに慣れていない層にも好まれ、「折り込みチラシを見た」と持参してもらうことで効果測定がしやすいメリットがあります。
「◯月限定」「◯枚限定」といった期限や枚数を設けると、興味を持った人の“早めの来店”を促せるでしょう。
2-3. ダイレクトメール(DM)とFax DMで特定ターゲットを刺激
2-3-1. DMの“個別感”でリピーターを呼び戻す
DMやFax DMは、封書やFaxを使って特定の家庭・企業へダイレクトにアプローチします。たとえば過去の宴会利用がある企業に「団体予約特典」をDMで送れば、再来店につながる可能性が高いです。
誕生日月や記念日に合わせたDMを送るなど、パーソナライズドな内容を工夫すれば一段と効果が上がります。
2-3-2. 法人向けFax DMの活用事例
オフィス街の飲食店で有効なのがFax DMです。週替わりランチや会食プランをFaxで送ると、ビジネスマンからの予約が増えやすくなります。
口コミ:各企業の実状を知ろう
2-4. デリバリーサイト登録で新しい収益源を確保
2-4-1. ウーバーイーツや出前館など、主要サイトの特徴
近年はテイクアウトやデリバリー需要が拡大しており、ウーバーイーツや出前館などに登録していないと損をする時代ともいえます。忙しい平日夜や在宅ワーク層の利用が見込め、店に足を運べない顧客層からの注文も取り込みやすいです。
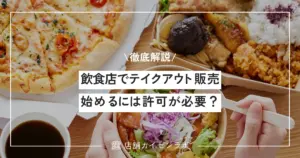
2-4-2. 掲載プランと手数料を見据えた採算計算
一方で、デリバリーサイトの手数料はやや高め。プランやオプションを慎重に選び、どの程度の利益を確保できるかを試算しましょう。デリバリー経由で知名度が上がり、後日来店につながるケースもあるので“広告投資”として考えるのも一つの方法です。
2-5. テレビCM・地域紙・プレスリリースで一気にブレイク!
2-5-1. ローカルTVや地域紙への広告出稿
ローカルテレビ局の深夜枠や地方の情報番組などは、意外と費用が抑えられる場合があります。地域紙に関しても、主要読者が限定されているからこそ費用対効果が高いケースがあります。地元ならではの話題で取り上げられれば、爆発的に認知度が上がる可能性も。
2-5-2. プレスリリース配信でメディア取材を狙う
プレスリリースを作成し、地元メディアやWebメディアに送付すれば、特集コーナーなどで紹介されるチャンスが生まれます。そうしたメディア露出はSNSや口コミサイトで瞬く間に話題化する可能性があり、広告費以上の反響を得られることも珍しくありません。
2-6. 看板やのぼりで通行客の足を止める
2-6-1. 店前看板のデザインで印象が変わる
「料理写真が美味しそう」「本日のおすすめが気になる」—そう思わせる看板デザインは、店頭でお客様の足を止める大きな要因になります。文字のサイズや配色、魅力的な写真など視認性にこだわると、ふらっと立ち寄る客を増やせます。
2-6-2. のぼり旗で視線をキャッチ
ロードサイドの店なら、車で通り過ぎる人にも見つけてもらいやすい「のぼり旗」が有効です。色使いやキャッチコピーは太め&短めにし、遠目からでも内容がわかるデザインを意識しましょう。
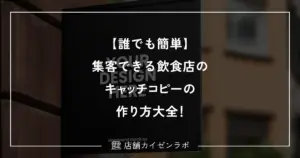
2-7. 駅看板出稿で“通勤客”を取り込む
2-7-1. 駅広告の種類と選び方
駅の看板広告には、改札周辺の壁面ポスターからデジタルサイネージまで様々な形態があります。費用や掲出期間は駅ごとに大きく異なるため、まずは最寄り駅や狙いたい沿線の広告代理店へ問い合わせることがスタートになります。
2-7-2. 朝夕のラッシュ層に効果的なメッセージ
通勤・通学中に目にする広告は、時間が限られている人へのアピールになります。たとえば「朝活メニューで1日をスタート」「仕事帰りの一杯割引」など、具体的なシーンを想起させるコピーを入れると誘導率が高まります。
2-8. 地域紙などへの広告出稿で“地元読者”を逃さない
2-8-1. タウン誌やフリーペーパーの強み
フリーペーパーやタウン誌には地域のニュースを熱心に追う読者がおり、“生活圏内の新店情報を集める”ためによく読まれます。大手新聞ほどではないにせよ、狭い範囲で高い閲読率を誇るものも少なくありません。
2-8-2. 掲載料金と枠サイズの相場
カラー1ページ全体を使う場合や、1/2ページ、1/4ページなど区画で費用が変わります。配布部数だけでなく、配布エリアや読者層をよく確認し、自店に適した枠を確保しましょう。毎月定期的に載せる契約をすると、単発よりも割安になることがあります。
2-9. ケーブルTVや地域チャンネルで動画CMを狙う
2-9-1. ローカル放送なら費用が抑えられる可能性大
地上波全国放送のCMは莫大な予算が必要ですが、ケーブルTVや地域チャンネルなら放送エリアが限定される分、比較的手軽な料金でCMを流せます。視聴者の多くが近隣住民なので、店舗の実質的な商圏とマッチしやすいメリットもあります。
2-9-2. 15秒〜30秒の動画づくりのポイント
短い時間で店の魅力を伝えるには、看板メニューのビジュアルや店内の雰囲気を第一に見せるのがおすすめ。テロップやナレーションで「駅から徒歩◯分」「人気の週替わりランチ」といった情報をシンプルに盛り込むと印象に残りやすくなります。
2-10. プレスボードや地元イベントへの協賛で地域認知を確保
2-10-1. プレスボードへの掲示を活用
地元の商工会や自治体施設などに設置された“プレスボード”にチラシやリーフレットを掲示できるケースがあります。市役所や観光案内所など、多くの人が行き交う場所に情報を載せられれば、地元住民だけでなく観光客にもアピールが可能です。
2-10-2. 地域イベント協賛でブランドを訴求
商店街の祭りや運動会、ローカルマラソン大会などに協賛し、イベント運営側のパンフレットやノベルティに店舗情報を載せる方法もあります。来場者の口コミを通じて、「あのイベントを支えてくれた店なんだ」と好感度アップにつながりやすいのが魅力です。
第3章. 飲食店で効果が出やすいデジタル広告10選

3-1. ローカルSEO・MEO:Googleビジネスプロフィール&Yahoo!プレイス活用
3-1-1. 地域検索で存在感を高めるMEOの基本
ローカルSEO、つまりMEO(Map Engine Optimization)は、GoogleマップやYahoo!検索で上位表示を狙う手法です。「○○駅+居酒屋」「△△市+カフェ」といった検索ワードに合わせて、地元ユーザーへ直接アプローチできます。
MEOをさらに深く知りたい方は『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』もご覧ください。
3-1-2. Googleビジネスプロフィールの魅力と管理ポイント
Googleビジネスプロフィールに自店を登録すれば、営業時間や口コミ評価、写真が検索結果やGoogleマップ上に表示されます。定期的な写真投稿や口コミ返信を行うことで、店舗イメージが向上しやすく、検索順位にも良い影響を及ぼすといわれています。
3-1-3. Yahoo!プレイスで幅を広げる
Yahoo!プレイスはYahoo! JAPANが提供する店舗情報サービスで、独自のクーポン発行機能やイベント告知が可能です。Yahoo!ユーザーが検索や地図機能から店を見つけやすくなるため、GoogleだけでなくYahoo!利用者も取り込みたい場合は登録を検討してみましょう。
3-2. SNS運用:LINE・Facebook・Instagram・Twitterでファンを作る
3-2-1. SNS別の特徴とおすすめの活用法
- LINE:リピーター育成向き。友だち追加でクーポン配布がしやすい。
- Facebook:30代以上のビジネスパーソンが多い。文章量の多い投稿に向く。
- Instagram:写真や動画で“映え”を重視した若者向け。ビジュアル重視の訴求が得意。
- Twitter(X):拡散力が高く、一気に話題になる可能性がある。
3-2-2. 投稿頻度と内容で信頼を育む
SNSアカウントは、更新が止まると存在感が薄れます。週1回でもいいのでメニュー紹介や店内の雰囲気をアップし、ストーリーズやリールなどを活用すればリーチが伸びやすいです。
SNSの活用方法についてより詳しく知りたい方は『飲食店がSNS運用をするデメリットと注意点!リスクを把握して炎上やトラブルを回避!』も参考になります。
筆者実践談:イタリアンバルの場合
3-3. Web広告:ジオターゲティング広告・リスティング・GDN・SNS広告
3-3-1. 地域限定で費用を絞れるジオターゲティング広告
特定のエリア内だけに配信できるジオターゲティング広告は、無駄なクリックを減らし、広告費を抑えながら地元客を集中して狙える手法です。「半径◯km以内」「主要駅周辺」に絞って効果を高められます。
3-3-2. 検索行動を直撃するリスティング広告
「○○駅 居酒屋」「△△市 ランチ」など具体的なキーワードで検索するユーザーに、検索結果上部や下部に広告を表示するのがリスティング広告。クリック課金型なので、興味のある人だけを取り込める点がメリットです。
3-3-3. GDN(Google Display Network)とSNS広告の違い
GDNは提携サイトにバナー広告を出す仕組みで、広く認知を拡大したいときに有効。一方、FacebookやInstagramなどのSNS広告はビジュアル中心で潜在顧客に訴求できます。どちらも年齢・性別・興味関心などでターゲット設定が可能なので、費用対効果の管理がしやすいです。
3-4. グルメポータルサイト・飲食店集客アプリで予約と口コミを同時獲得
3-4-1. 食べログ・ぐるなび・ホットペッパーなど主要サイトの特徴
グルメ情報サイトは全国的に利用者が多く、口コミ機能やオンライン予約機能を兼ね備えているのが特徴です。新規顧客が店を選ぶ際、「とりあえず食べログ(or ぐるなび)で見てみる」という行動パターンは定着しており、掲載するだけで検索流入が期待できます。
3-4-2. 飲食店専門のキュレーションサイトへの出稿
最近増えているのが“こだわり食材”や“話題のスイーツ”といったテーマ特化型のキュレーションサイト。特定ジャンルに強いコアユーザーが集まるため、他店と差別化しやすい場合があります。掲載料や読者数をチェックして、自店に合った媒体を選びましょう。
3-4-3. 自店サイト・ウェブメディア掲載の相乗効果
自店の公式サイトやブログを作り込み、グルメポータルから誘導すればファン化しやすくなります。ウェブメディアで特集してもらえれば、自然検索によるアクセスも増え、SNSシェアを通じてブランド力を高める好循環が生まれることが多いです。
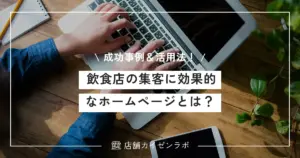
自店メディアを活用した集客なら『飲食店のブログ集客の方法を大公開!来店や売上に繋げる上手な活用方法!』も併せておすすめです。
3-4-4. メールマガジンで定期的に訴求
メールマガジンは古いイメージがありますが、根強い効果を発揮します。新メニューやクーポン情報を定期的に送信すれば、来店タイミングを逃しやすい忙しい顧客にも効果的なリマインドが可能です。
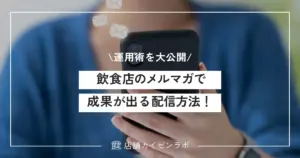
第4章. 飲食店が使う広告費の目安とは?

4-1. 売上比5〜10%はあくまで目安。その内訳が大切
多くの飲食店では、広告費を「売上の5〜10%」程度と設定するケースが一般的です。しかし、実際には店舗の立地や客単価、競合状況によって最適な広告費は変動します。たとえば繁華街の路面店ならば、通行客による自然な集客が期待できるのでWEB広告に大金をかけなくても十分に成果が出る場合があります。一方で、郊外型のレストランなど車移動が多いエリアでは、看板やローカルCMなどオフライン広告に一定の予算を組む必要があるかもしれません。
つまり「5〜10%」はあくまで初期設定の目安。実際は“どの媒体に、どのタイミングで、どんな目的で”お金を使うのか、内訳をしっかり検討することが重要です。新規顧客獲得を重視するのか、リピート向上を重視するのかでも、予算配分は大きく変わります。
- SNS広告・リスティング広告:ターゲットを細かく絞れるため、比較的少額からスタート可能。
- チラシ・ポスティング:まとまった印刷費や配布費がかかるが、地元客への直接アピールが強い。
- 看板・駅広告:契約期間やサイズによっては高額。認知度向上が目的の施策に向く。
このように、各媒体ごとに費用対効果と狙える顧客層が異なるため、自店の状況と狙いに合ったプランを立てましょう。
4-2. 年間プランで繁忙期と閑散期にメリハリをつける
飲食店には、忘年会や歓送迎会シーズン、お花見シーズンなど、客足が増えやすい時期が存在します。これらの時期に合わせて広告を集中的に打つことで、大きな売上アップが見込めるでしょう。逆に、閑散期に広告を強化して来店促進を狙うという方法もあります。
たとえば年間広告予算を「120万円」と仮定すると、繁忙期の直前にはWeb広告とチラシを組み合わせて集中投下し、閑散期にはSNSでキャンペーン情報をこまめに発信するといったメリハリのあるスケジューリングが可能です。結果として、広告費を同じ総額で使っていても、売上に対する効果は大きく変わります。
4-3. 資金調達・助成金を活用して“攻め”の広告戦略を
広告にしっかり投資したいものの、資金面で不安があるという場合は、小規模事業者持続化補助金などの助成金・補助金制度を検討してみましょう。店舗の販路拡大や新規顧客獲得に関連する取り組みの場合、広告宣伝費の一部を補助してもらえる可能性があります。
専門家コメント:補助金申請
第5章. 飲食店が広告で成功するための6つのポイント

5-1. 発信の目的を明確にする:新規客かリピーターか
広告で成功を収めるためには、まず「何を目的とするのか」をはっきりさせる必要があります。たとえば、「今月は新規顧客を増やしたい」「夏のビアガーデンをPRして売上を伸ばしたい」「平日のランチ利用を増やしたい」など、明確にゴールを設定すると、選ぶ広告媒体や配信時期、訴求内容も変わります。
目的が曖昧なまま広告を打ってしまうと、結局どんな層に届いたのか、どれだけの成果があったのかが把握できなくなることが多いのです。
「新規客を10%増やす」「リピーター来店数を月間100件にする」など、数値化したゴールと期限を設定すると、広告効果が測定しやすくなります。単なる“感覚”に頼ると広告費が無駄になりがちなので、必ず目標を定量的に管理しましょう。
広告成果を数字で把握するなら『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』もぜひお読みください。
5-2. コンセプト&ターゲットに合う戦略を徹底する
店舗のコンセプトや想定客単価、ターゲット層と広告手段が合わない場合、思ったような反響が得られないことは珍しくありません。たとえば家族連れが多い郊外型のレストランなのに、若者向けのInstagram広告ばかりに偏っていたら真のターゲットに届きにくいでしょう。
ターゲット層を性別や年齢層だけでなく、利用シーンや好み、SNSの使用状況などで細分化し、それにマッチする広告媒体を選ぶことが成功の近道です。
お店の雰囲気や世界観が大事な飲食店ほど、“宣伝感”の強いコピーだとブランドイメージを損なうリスクがあります。高級フレンチなら上質感を、カジュアルバーなら気軽さを打ち出すなど、広告コピーやビジュアルにもコンセプトとの一貫性を持たせましょう。
5-3. オンラインとオフラインを使い分け、効果測定で改善
多角的に集客したいなら、アナログ(チラシ、看板、DMなど)とデジタル(SNS、MEO、Web広告など)を使い分けるクロスメディア戦略が効果的です。たとえば駅看板で店の認知度を上げ、そこからQRコードでSNSアカウントへ誘導すると、定期的な情報発信につなげられます。
効果測定は広告戦略の成否を分ける大切な作業です。オフラインのチラシや看板にもQRコードやクーポンコードを付けると、どの媒体を見て来店したのかが把握しやすくなります。SNS広告やリスティング広告でも、配信用の特別URLを使うことでクリック数や予約数を追跡可能です。
5-4. 広告費の配分と口コミ活用でコストを抑える
広告はどうしても費用がかかりますが、口コミやSNSでの自然拡散はほとんどお金をかけずに集客できる可能性があります。「広告で話題の種を作り、口コミ拡散で一気に知名度を上げる」という流れを意識することで、コストを大幅に抑えつつ集客力を高めることができます。
口コミは返信することでさらに多くの口コミを呼ぶことができます。そのための有効な返信例については『口コミへの効果的な返信方法とは?印象の良い例文やテンプレートを大公開!』の記事を参考にどうぞ。
SNSでの拡散を促すには「ハッシュタグキャンペーン」「写真投稿で割引」など、お客様が自然に投稿したくなる仕掛けを用意するのが効果的です。良質な口コミは広告以上の説得力を持つことが少なくありません。
第6章. 集客施策で飲食店が見落としがちな3つの注意点

6-1. 安易な割引はNG!中長期的視点でブランディングを
割引クーポンや値下げキャンペーンは、短期的には集客に効果があるかもしれません。しかし安易に大幅割引を繰り返すと、常に安くなければ来店しない「割引目当てのお客様」ばかりが集まってしまい、単価が下がり続けるリスクがあります。
理想は、“まずは割引でお店に興味を持ってもらい、その後は通常メニューで満足してもらう”という流れを確立すること。中長期的に継続して利益を出すためには、価格以外の部分(雰囲気・サービス・品質)で選ばれるお店づくりを同時に進める必要があります。
6-2. デジタルとアナログのクロスメディアで最大効果を狙う
デジタル広告だけに注力している店は、紙媒体や看板で見込み客を取りこぼす可能性があります。反対に、アナログ施策しかやっていないとWeb上の広い顧客層に届かないリスクが生まれます。
両者を組み合わせると、たとえば「チラシでQRコードを読み取らせてSNSへ誘導→SNSフォロワーを増やし、再来店を促すクーポン配布」というクロスメディア戦略が可能になります。
6-3. 「エリアを知る」ことで費用対効果が大幅に変わる
飲食店が店舗ビジネスである以上、地理的要素は無視できません。エリア特性(住宅街なのか、オフィス街なのか、観光地なのか)や競合の数、来客の時間帯などを把握しないまま広告を打つと、的外れな層へ無駄に広告費を費やす結果につながります。
駅周辺のサラリーマン向けに出す広告なのか、ファミリー層の多い郊外向けか、大学生が住む街なのかによって、媒体選択や打ち出すメニューは変わるはずです。
第7章. 飲食店の広告に関してよくある疑問6選

7-1. Q1:チラシを1万枚配っても反応が薄いのはなぜ?
A:デザインが単調、配布エリアや時期がずれている可能性があります。ターゲット層に響く魅力的なコピーやクーポンを付け、曜日や時間帯に合わせて配布すれば、反応率が上がりやすくなります。
7-2. Q2:割引クーポンを乱発しても問題ない?
A:過度な値引きは「安くなければ行かない客」を増やし、利益を圧迫するリスクが大。特別感を演出しつつ、期間や利用条件を限定して店舗の価値を守る施策にとどめましょう。
7-3. Q3:SNS広告に予算を集中させたいけど、大丈夫?
A:SNSはターゲットを狙いやすい反面、使う層が偏ることも。オフライン施策や他のデジタル広告とも併用し、多様な客層へアピールするバランスを意識するのがおすすめです。
7-4. Q4:広告代理店に頼むか、自力でやるかの基準は?
A:予算や時間に余裕があれば代理店に任せる利点大。ノウハウの習得と運用時間が確保できるなら自力でも可。ただし開店直後は代理店を活用し、早期に集客を安定させる選択も検討しましょう。
7-5. Q:口コミだけに頼っても大丈夫?
A:口コミは強力ですが、拡散スピードや到達範囲に限界があります。広告と組み合わせることで認知拡大のペースを上げ、好意的なクチコミが生まれやすい土壌をつくるほうが得策です。
7-6. Q:スタッフ不足の状況で広告を打つのは危険?
A:集客増でサービス品質が落ちると逆効果に。キャンペーン期間や席数調整などでオペレーションを最適化し、無理なく対応できる範囲で広告を活用しましょう。
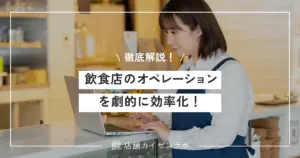
第8章. 集客を増やした飲食店は広告に挑戦してみよう!

広告は飲食店の成否を左右する大きな要素ですが、そのやり方は店ごとに正解が異なります。まずは小さな施策から試し、効果を測定して改善していけば、無駄なコストや時間をかけずに成果を積み上げられるでしょう。たとえスタッフ不足や立地の弱みがあっても、ターゲットを絞ったオンライン施策や、地域を意識したオフライン施策で十分に巻き返すことが可能です。
大切なのは、自店ならではの魅力をどう広告で表現するか。その本質を見失わず、試行錯誤を続ければ、きっとお客様に選ばれる店づくりができるはずです。応援しています。