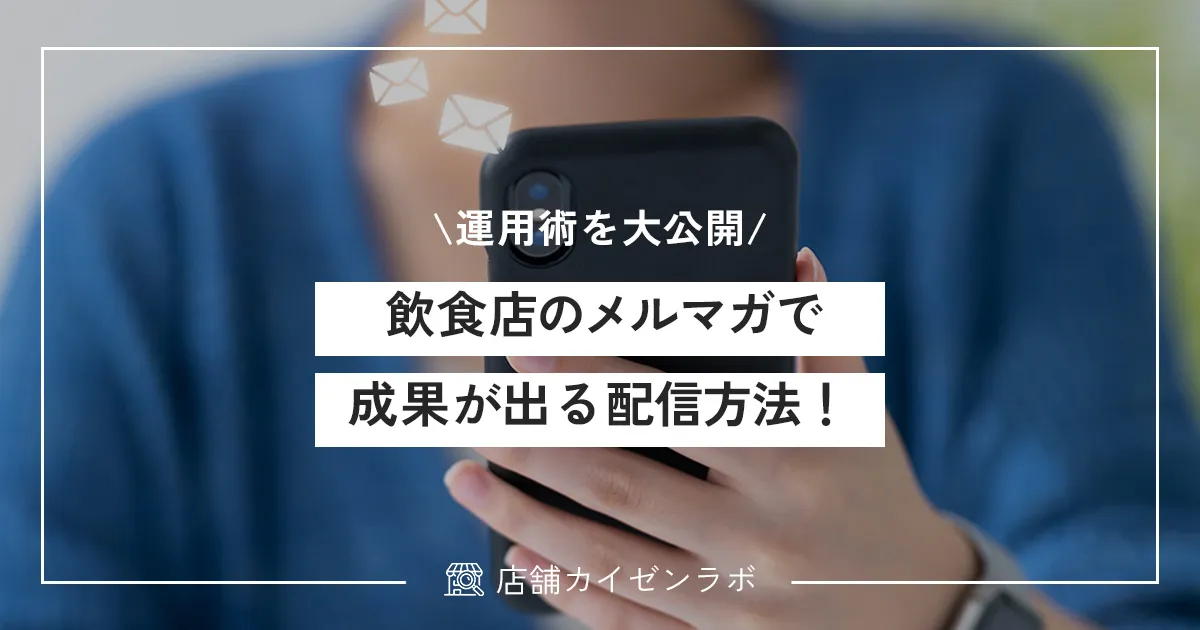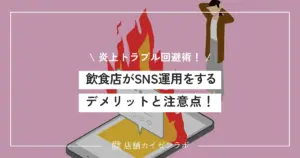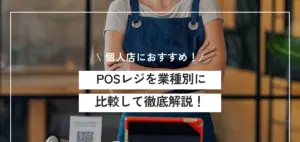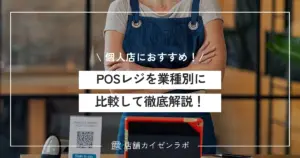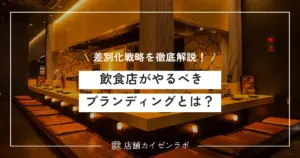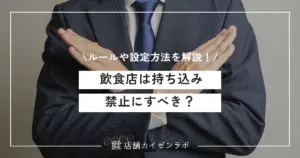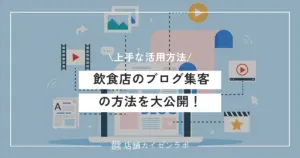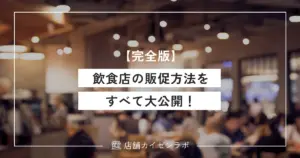第1章. 飲食店のメルマガを導入する前に知っておきたい基礎知識

飲食店がメルマガ(メールマガジン)を使って“顧客”へ定期的に情報を届ける手法は、SNS全盛の時代でも根強い“集客”効果を発揮する“マーケティング”方法です。具体的には、店舗のイベント告知、新メニューの案内、クーポン配布などを“メール”で配信することで、既存顧客との接点を維持し、来店意欲を高めます。SNS投稿は拡散力に優れている一方、タイムラインに埋もれてしまいがちなのが弱点。その点、メルマガはプッシュ型で“顧客”の受信トレイに直接届くため、“開封”される可能性が高く、リピーターづくりに有効とされています。

第2章. 飲食店がメルマガで得られる5つのメリット

2-1. リピーターの確保で安定した売上を狙う
飲食店の“集客”において、リピーターの存在は非常に重要です。新規顧客を追いかけ続けるよりも、一度来店した“顧客”に繰り返し利用してもらうほうが売上の安定につながります。メルマガを通じて定期的にクーポンやイベント情報を“配信”すれば、店舗の記憶が薄れかけた頃に「そういえば、あの店がクーポン送ってきたから行ってみよう」と思い出してもらいやすくなるのがポイントです。
リピーターを増やす施策としては、『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』の記事でも紹介してますので併せてご確認ください。
2-2. コストが安く始められるデジタルツール
チラシや雑誌広告の場合、印刷費や掲載費がかかり、1回の施策にまとまった予算を必要とします。一方メルマガは、メール“システム”の月額料金や通信費程度で運用でき、印刷物のように継続的な刷り増しコストが発生しません。店舗の経費削減という観点でも、“デジタル”ツールによる“マーケティング”が注目を集めています。
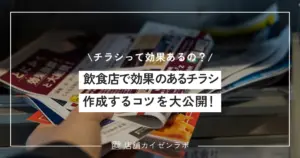
2-3. プッシュ型の情報発信で確実に届く
SNS投稿は拡散力がある反面、「フォロワーが多いのに見られていない」「投稿がタイムラインに埋もれて流れてしまう」といった課題に直面しやすいです。メルマガの場合、読者の受信トレイへ直接情報を届けられるため、“開封”される確率が相対的に高くなります。プッシュ型で確実に“登録”者へ“配信”できる手段は、飲食店の安定した集客基盤づくりにおいて重宝されます。
2-4. セグメントを絞ったマーケティング展開が可能
メルマガの“システム”には顧客リストを属性ごとに整理し、異なる内容を配信できる“機能”があります。たとえば「ランチ利用が多い20代女性」「家族連れでの利用が多い30〜40代」「記念日利用がメインのカップル層」などをセグメント化すれば、それぞれに合わせたメール本文を作成可能です。これにより、興味関心が高い情報のみを届けられ、顧客満足度が上がります。
筆者の実践談:最適なタイミングの効果
2-5. 独自の強みをアピールしやすい
SNSでは文字数や投稿サイズに制限がある場合も多く、一度に深い情報を伝えきれないことがあります。メルマガなら、長文でも問題なく、“写真”や“資料”PDFのリンクを設置するなど、より詳しい解説が可能です。飲食店のメニュー開発ストーリーやシェフのこだわり、産地直送の食材背景など、興味深いエピソードを盛り込むことで、一気に店舗のブランディング力が高まるでしょう。
店舗のブランディングに悩む方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』の記事が参考になります。
第3章. 飲食店がメルマガを配信するデメリットと注意点

3-1. SNSと比べて拡散力が劣る
メルマガはプッシュ型で届きやすい一方、読者が“友人や知人へシェアする”ハードルはSNSより高くなりがちです。たとえば「このクーポンをみんなで共有しよう」と考えた場合、SNSの投稿はボタン一つで一気に広がるのに対し、メルマガは基本的に個人のメールボックスに収まるものなので、バイラル効果が生まれにくいのが弱点です。
そのため、新規“顧客”の獲得においてはメルマガ単独で大成功を狙うのは難しく、SNSやポータルサイト、口コミなどと組み合わせて“集客”効果を最大化させる必要があります。メルマガは「既存顧客のリピート促進と深い関係性構築」、SNSや広告は「新規認知拡大・拡散」という役割分担が理想的と言えるでしょう。
3-2. 作成・配信の手間が思いのほかかかる
メルマガは低コストで運用できるメリットがあるものの、継続的に“配信”するにはそれなりの時間と労力が必要です。本文を書く、写真を用意する、クーポンコードを発行する、配信後に結果を分析する…など、月に数回でもスタッフの手が取られます。特に飲食店では、繁忙時間帯と事務作業を両立しなければならないため、「気づけば1カ月まったく配信していなかった…」という事態になりがちです。
この問題への対処として、ステップメールや自動配信機能のあるメルマガ“システム”を導入し、ある程度先の“方法”までまとめてコンテンツを作り置きするのがおすすめ。そうすれば、忙しい時期にも定期的に“配信”でき、“顧客”との接点を途切れさせずに済みます。
3-3. メルマガ配信システムとの契約が必要
多くの読者に一括でメールを送る場合、通常のメールアドレス(GmailやYahooメールなど)では制限に引っかかってしまう恐れがあります。そこで、専用のメルマガ配信“ツール”を契約し、リスト管理や配信予約、開封率分析などの“機能”を活用するのが一般的です。無料で使えるものもあれば、有料で高度な分析機能が付いているものもあり、価格帯やサービス内容はさまざま。
3-4. 登録者を集めるハードルがある
メルマガは読者が“登録”してくれないことには始まりません。ところが、昨今はSNSやLINE、アプリ通知などコミュニケーションツールが増え、メールの重要度が下がりつつあります。特に若年層はメールを常用しない人もいるため、「わざわざメールアドレスを登録するのは面倒」と感じる顧客がいるのも事実です。
したがって、店頭で「メルマガ登録で○○サービス!」という特典を提示したり、会計時のレシートにQRコードを掲載して「簡単登録」を促したり、分かりやすいメリットを訴求する施策が欠かせません。登録後に届くクーポンやイベント情報が魅力的であればあるほど、登録ハードルは低くなります。
第4章. 飲食店がお客様にメルマガ登録をしてもらうためのコツ

4-1. 接客やテーブルPOPで自然に誘導する
飲食店でメルマガの“登録”者を増やすには、実店舗の強みである「スタッフとの直接コミュニケーション」を活かすのが近道です。たとえば会計時に「当店のメルマガ登録で次回ドリンク1杯無料になります」とひと言添えるだけでも、多くのお客様が興味を示すものです。また、テーブルPOPやレジ横のカウンターにQRコードを配置し、「スマホですぐ登録できます」と視覚的に分かりやすく誘導する方法も有効。
筆者体験談:登録への誘導施策
4-2. 明確な登録特典で“メリット”を見せる
お客様が「わざわざメールアドレスを登録する」理由を作るには、特典の活用がいちばん手っ取り早い方法です。クーポンやドリンク無料券などの具体的メリットがあれば、「ちょっと試しに登録してみようかな」という心理が働きます。一方で、割引率が大きすぎると利益を圧迫しかねないため、値引き幅の設定や配布タイミングは慎重に考えましょう。
具体データ:ルール設定の是非
4-3. メルマガの概要をわかりやすく伝える

「いつ配信されるのか」「どんな内容が届くのか」を明確にするほど、読者は安心して登録できます。例えば「月2回のペースで新メニュー情報やクーポンをお届けします」と最初に言っておけば、「頻繁にメールが来て煩わしいのではないか」という不安を取り除けます。逆に情報が少ないと「どれくらい送られてくるのか不明」「本当にお得なのかわからない」と思われ、登録のハードルは上がります。
4-4. 登録フォームはシンプルに
新規登録ページで入力項目が多いと、途中で離脱する人が増えがちです。メールアドレスや氏名など最低限の情報だけで“登録”を完了できるようにしたほうが、登録率は格段に上がります。後からステップメールやアンケートで追加情報をヒアリングする方法をとれば、最初の敷居を低く抑えつつ必要データを集めることが可能です。
4-5. 属性情報も上手にヒアリングする
誕生日や好きなメニューなど、ある程度の顧客属性を把握できれば、セグメント配信でさらに“効果的”なアプローチが可能となります。生年月日を聞いておけば、誕生日月に特別メールを送れるほか、小学生以下の子連れ顧客向けにキッズイベントを告知するなど、細かいターゲット設定ができます。
4-6. SNSや予約サイトを使ったオンライン誘導
店頭だけでなく、SNSや食べログ・ぐるなびなどの予約サイトでも「当店のメルマガ登録はこちら!」と案内を出すことで、より多くの見込み客を取りこめます。SNSには拡散力があるため、「登録すると特典があるよ」という告知を定期的に行い、フォロワーをメルマガ読者へ転換するのも有効な“方法”です。オンラインとオフライン両方の導線を用意すれば、潜在顧客を網羅的にカバーできます。
専門家コメント:SNSとの使い分け
また地域集客を強化するにはMEO対策も必須です。『【2025年最新】飲食店のMEO対策完全ガイド!Googleマップからの集客・売上を最大化する方法を大公開!』の記事で詳しく解説してますのでご活用ください。
第5章. 読者を飽きさせない!飲食店の効果的なメルマガ配信の具体的な方法!

5-1. 配信の頻度とスケジュールを決める
メルマガを「どれくらいの頻度で配信するか」はとても重要なテーマです。週1配信〜月1配信まで幅がありますが、飲食店の場合は月2〜4回程度がちょうど良いバランスとされます。頻繁すぎると読者が「しつこい」と感じ、“解除”につながる恐れがあり、逆に少なすぎると店舗の情報や魅力を発信しきれません。
筆者運用例:ターゲットへの効果的なタイミング
5-2. セグメント配信でパーソナライズを狙う
多忙な読者に送るメルマガは、自分に関係のある情報であればあるほど“開封”率が上がります。そこで活きてくるのがセグメント配信です。登録時に集めた属性情報や過去のクリック履歴をもとに、内容を分けることで「興味のある人にだけ、より深い情報を配信する」ことが可能となります。
5-3. タイトル(件名)を見直すだけで開封率が変わる
メルマガが届いても、まず件名を見て「読むか、読むまいか」を判断するのが読者心理です。タイトルは短めにまとめ、「何が得られるのか」を具体的に示すと“開封”されやすい傾向にあります。例として「【限定3日】夏の新メニューと特別クーポンのご案内」「週末は家族で楽しむ○○フェア開催!」など、メリットやイベント要素をタイトルに盛り込むのが王道の方法です。
5-4. メルマガ経由の来店を計測する仕組みづくり
せっかくメルマガを配信しても、「どれくらい来店につながったか」や「どのクーポンが最も利用されたか」を把握できないと改善のしようがありません。そこで、クーポンに固有コードを割り振ったり、予約時に「メルマガを見た」と伝えてもらう仕組みを作るなど、成果計測が可能な運用フローを整備する必要があります。
専門家コメント:計測の仕組み化
5-5. 飲食店ならではの最適配信時間を考える
飲食店のメルマガ“配信”では、読者がメールを開いてすぐ「行ってみよう」「予約しよう」と思いやすい“時間”帯を選ぶのがポイントです。ランチ需要がある店舗なら、午前中~昼前に配信すれば「今日のお昼はどこで食べよう?」と考えるタイミングを狙えます。逆にディナーや飲み会需要が高い店舗なら、夕方の退勤時間や金曜の午後に配信し、「明日の夜、どこ行こうかな」という潜在ニーズにアプローチ可能です。
5-6. 曜日別の開封率を意識しよう
曜日によって、人々の行動パターンは大きく変わります。たとえば、月曜日は仕事の立ち上がりで忙しくメールを開く余裕がない人が多い一方、週末前の木曜・金曜はレジャーや外食の計画を立てるタイミングになりがちです。店舗として「週末の集客を伸ばしたい」と考えるなら、木曜または金曜の朝にメルマガを配信し、特別メニューやクーポンを告知すると“効果的”でしょう。
第6章. メルマガ配信で発生しうるトラブルを防ぐための3大チェックポイント

6-1. オプトインでの同意を確実に取る
メルマガを“配信”する際には、読者本人の同意(オプトイン)が法律上重要になります。飲食店に限らず、勝手にメールを送りつけるのは特定電子メール法等に抵触するリスクがあるので要注意。登録フォームに「当メルマガの配信に同意しますか?」とチェックボックスを設ける、店頭で口頭同意を得たあと確認メールを送るなど、確実に“顧客”の意思を確認するプロセスを整えましょう。
事例:苦情やクレーム
6-2. セキュリティ対策を怠らない
メルマガの“登録”リストには個人情報が含まれているため、不正アクセスや情報漏えいなどのセキュリティリスクと常に隣り合わせです。スタッフが退職する際にパスワードをそのままにしていないか、紙に印刷した顧客リストを放置していないかなど、店舗内部で管理体制を見直しましょう。また、配信システムを選ぶ際も、セキュリティやサーバーの安定性に定評があるサービスを選ぶと安心です。
6-3. 購読解除(オプトアウト)の導線を用意
読者がメルマガを不要と感じたとき、スムーズに解除できる仕組みを整備するのも大切です。メール文面の末尾に「配信停止はこちら」というリンクを設置し、一目でわかるようにしましょう。購読解除を拒否したり手続きが複雑だと、クレームにつながるだけでなく、法律面でも問題になる可能性があります。
第7章. 実際の運用で迷いがちな飲食店のメルマガに関する疑問

7-1. Q:どれくらいの頻度で送るべき?
A:月2〜4回程度が目安ですが、業態や情報更新の頻度によっても変わります。あまりに多すぎると“解除”されやすくなり、少なすぎると存在感が薄れがちです。週1配信でクーポンや新メニュー情報を紹介するパターンや、月1回だけ濃い内容を届けるパターンなど、店舗のペースに合わせてテストしながら最適化しましょう。
7-2. Q:解除されにくい件名・内容ってある?
A:解除されにくいかどうかは、件名の工夫以上に「配信内容が読者の役に立っているか」が大きく影響します。例えば毎回セール情報だけを送っていると、お得感より“しつこさ”が目立つことも。一方、ストーリー性やスタッフ紹介などを織り交ぜて「このメールが来ると読んでしまう」という状態を作れれば、解除率は下がります。
7-3. Q:手作業で配信は無理…どんなシステムが良い?
A:読者が増えるほど、手動でメールを送るのは現実的ではありません。そこで、メルマガ配信システムを利用し、リスト管理・一斉送信・ステップメール・開封率測定などを自動化する必要があります。料金や機能は幅広いため、初期コストを抑えたいなら無料プランや低額プランがあるツール、ステップメールや詳細な分析を重視するなら有料プランを検討する形が一般的です。
7-4. Q:SNS全盛の時代にメルマガは古い?
A:SNSの拡散性や手軽さは確かに強力ですが、メルマガには「プッシュ型で確実に読者の受信トレイへ届く」という強みがあります。SNSだと投稿がタイムラインに埋もれたり、アルゴリズムの影響で全員に表示されないリスクも。一方、メルマガは自分から取りに行かなくても情報が届くため、一定の開封率を期待しやすいのが利点です。理想は両方を上手に使い分けること。
7-5. Q:ステップメールって本当に必要?
A:ステップメールは、登録から一定期間後や誕生日の直前など、あらかじめ設定した“シナリオ”通りに自動配信してくれる機能です。忙しい飲食店では、人手を割けないときでも定期的にメールを送れるため、読者との接点を途切れさせません。特に、新規読者向けのウェルカムメールや誕生日クーポン配信など、繰り返し使うパターンを自動化するのに適しています。
第8章. メルマガを導入して飲食店の魅力を効果的に発信しよう
本記事では、飲食店がメルマガを導入する意義やメリット、注意点などを通して、リピーターを増やす効果的な手法を解説してきました。特に、頻度・配信時間の最適化やセグメント配信、タイトルの工夫など小さな改善を積み重ねることで、開封率や来店率を高めることが可能です。一方で、法的手続きやセキュリティ面、適切なツール導入など、意外な落とし穴も少なくありません。
飲食店のマーケティング施策として、メルマガはコストを抑えながら確実に顧客へアプローチできる有力な選択肢です。SNSやオフライン集客との併用で新規・既存客双方を効率よくカバーし、店舗全体の売上とブランド力を底上げする戦略に生かしてください。以上を踏まえ、今後の飲食店運営において、メルマガを強力なコミュニケーションツールとして活用し、顧客満足度と収益の向上を目指しましょう。