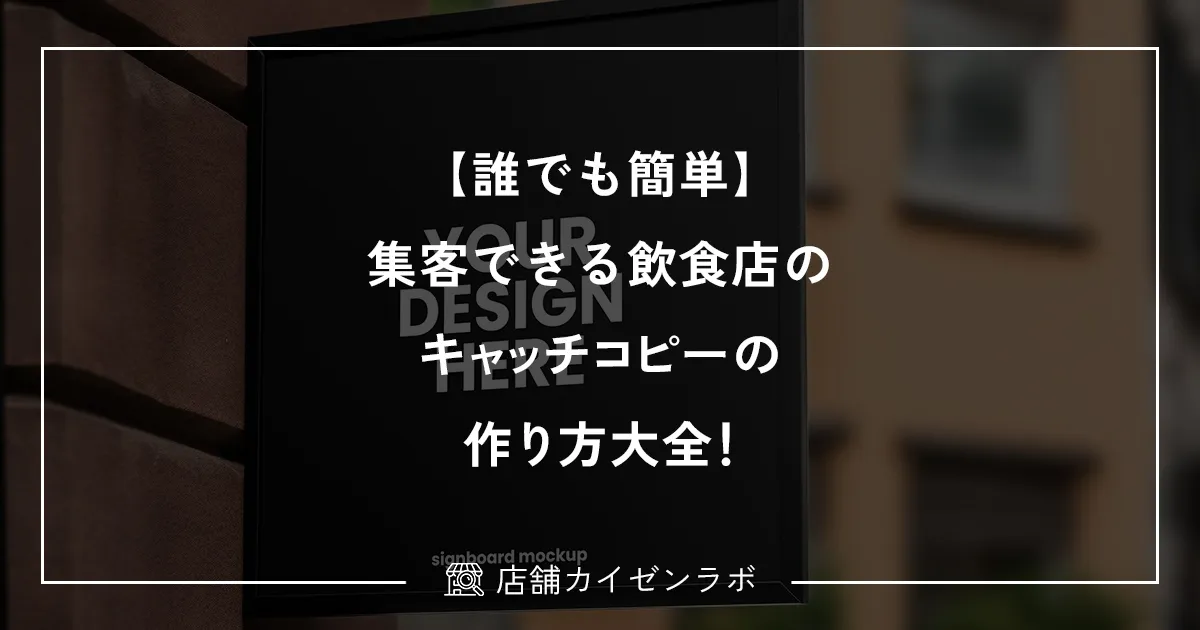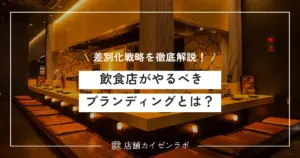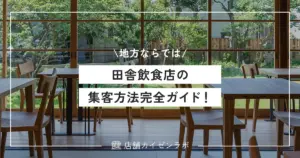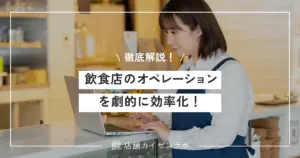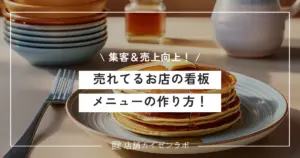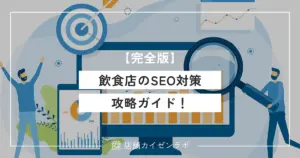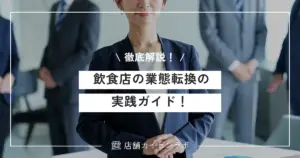第1章. なぜ飲食店にとってキャッチコピーが重要なのか?

近飲食店の魅力を伝えるうえで、キャッチコピーは「一瞬でお客様を惹きつける」大きな武器になります。スマートフォンやSNSの普及により、情報があふれる現代。たとえば30秒以内に人が目にする情報量は、ひと昔前の数倍とも言われています。こうした状況下で、長々とした説明文は最後まで読まれずに流されてしまいがちです。そこで、ターゲットに刺さる“ひと言”を準備しておくことが重要になります。
つまり、飲食店のキャッチコピーは幸せやワクワク感を直感的に伝え、数秒で「ここが良さそうだ」と感じさせる提案として機能します。逆に言えば、その“ひと言”が適当だと、せっかくの美味しい料理や素敵な空間が埋もれてしまうのです。
第2章. 【事例から学ぶ】キャッチコピーがもたらす飲食店の成功と失敗

2-1. 成功事例1:親しみ系ワードで電話予約が2倍に
ある地方のイタリアンレストランから相談を受けた際、最初は「厳選素材の本格イタリアン」という硬い言葉をキャッチコピーに使っていました。料理の実績はあるものの、なんとなく高級店らしく敷居が高いイメージになり、実際にお客様へアンケートをとると「ちょっと入りづらい」と感じる人が多かったのです。そこで、コピーを「お腹も心も満たす、ほっとするイタリアン」に変更したところ、翌月から電話予約が2倍に増加しました。
ポイントは「ほっとする」というワードを入れて、親しみやすいイメージをアピールしたこと。実は人は「どんなシーンで食事を楽しみたいか」を想像したとき、堅苦しい雰囲気よりもリラックスできる空間に魅力を感じがちです。専門家のコメントでも「キャッチコピーはターゲットの気持ちに寄り添う言葉選びが大切。とくに飲食店では『温かみ』を伝えると反応が良い傾向がある」と言われています。
2-2. 成功事例2:高級路線を徹底して客単価アップ
一方、「うちは安っぽい店だと思われたくない」という飲食店オーナーもいるでしょう。実際に、都内で高級食材を扱う和食店の事例では、「少しでも高級感を演出したい」というオーナーの要望を踏まえ、“贅沢の限りを尽くした一品”というフレーズをキャッチコピーに採用しました。結果、客単価が平均500円アップし、特に接待や記念日利用の予約が増えたのです。
この店では、元々「和の伝統が息づく逸品」というコピーを使っていましたが、もう少しインパクトを強めたいと検討し、あえて「贅の限り」という強めの言葉を使ったのが決め手でした。過度な煽りではなく、「高級食材と熟練シェフの技術を駆使した特別感」を端的に示すことで、顧客の「記念日に相応しい」と思わせる心理を刺激したのです。
2-3. 失敗事例:煽りコピーでクレーム続出
成功例ばかりではありません。過度な煽り表現や誇大広告による失敗も多々見受けられます。ある焼き肉チェーン店では「絶対に幸せになれる究極の特選肉!」というフレーズを大きく掲げたところ、「実際にはそこまで美味しくなかった」「大げさすぎる」とSNSで批判が上がり、クレームが相次いだのです。これにより店の信用が一時的に低下し、来店数も減少しました。
ここで問題なのは、“絶対”や“究極”といった言葉が過剰に期待を煽り、食事体験とのギャップを生んだことです。飲食店のキャッチコピーは、基本的に幸いな体験を提案するものであっても、あまりにも誇大な言葉や違法スレスレの表現は逆効果になります。最悪の場合、景品表示法などの法規制に抵触するリスクも考えられます。専門家によれば、「『世界一』や『絶対』という言葉は根拠不十分だと誇大広告とみなされる恐れが高い」とのことです。
結果として、このチェーン店は看板を改訂し、より具体的に「A5ランクのブランド牛を直送、香りまでご馳走する特選焼肉」と表現を変えることでクレームも減りました。「香り」という五感に訴えるワードを盛り込み、尚且つ誇張を控えめにしたのが功を奏したのです。
3章. 【飲食店向け】キャッチコピーの作り方:今すぐ実践できる5ステップ
3-1. キャッチコピーの目的を決める
キャッチコピーは、「お店の魅力」を短い言葉で端的に伝え、ターゲットの興味を引き出すための“提案”です。来店の後押しをするために「売上アップを狙う」「新メニューを周知する」など、まずは目的を明確に設定しましょう。目的が曖昧だとコピー自体がブレやすくなり、結果的に実績にもつながりにくくなります。
3-2. キャッチコピーのターゲットを明確にする
「誰に向けた言葉なのか」を明確にするだけで、キャッチコピーの表現はガラッと変わります。たとえば「若年層を狙うなら個性的な言葉」「ファミリー層には安心感・お得感」を強調するといった具合に、相手の属性を具体的にイメージするとブレなくなります。ここでいう“ターゲット”は「年齢・性別・ライフスタイル」などを細かく設定すると効果的です。
3-3. 独自のウリ・他店との差別化
飲食店は数多く存在するため、「ここだけの魅力(USP)」をコピーで打ち出す必要があります。たとえば「国産野菜直送」「創業◯年の秘伝タレ」「手作りスイーツ専門」など具体的なフレーズがあれば、“他店にはないここだけの食事”をイメージしやすいでしょう。
3-4. お客さんが今すぐ行動すべき動機を組み込む
お店に足を運んでもらう、あるいは電話で予約をしてもらうためには「行くなら今!」と思わせる工夫が大切です。たとえば「期間限定」「数量限定」「割引クーポン配布中」のように、“急がないと損”と感じさせる言葉は効果的。筆者が支援したカフェでも「今だけ◯%OFF」というキャンペーンを検討し、SNSで発信したところ問い合わせが急増しました。
3-5. お客さんの「次の行動」を誘導する
最後に、「次に何をしてほしいか」を具体的に伝えるのがポイントです。例として「お席のご予約はお電話がお得です」「Instagramをフォローで1ドリンク無料」など、行動を明記するとターゲット=お客さんは次のステップに移りやすくなります。
4章. 【心を動かす】キャッチコピー作成で今すぐ使える5つのポイント

4-1. オノマトペの魔法:食感・香りを言葉で伝える
| オノマトペの例 | ||
|---|---|---|
| 「サクサク」 | 「ジュワッ」 | 「とろ~り」 |
オノマトペは、料理の魅力を一瞬でイメージさせる強力な方法です。とくに飲食店では、お客様が実際に口に運ぶ前に「この料理は美味しそうだ」と思ってもらうことが重要になります。たとえば「カリッと香ばしい焼き餃子」と書くだけでも、食感と香ばしさが頭に浮かびやすく、注文率が上がったという実例があります。
筆者が以前サポートした定食屋では、からあげを「衣サクサク、ジュワッと肉汁!」とメニュー表に記載したところ、注文が全体の2割以上増えました。お客様からは「この表現を見たら無性に食べたくなった」という声があったほどです。五感を刺激するオノマトペは、「思わず食べたい」気持ちを引き出す大きなカギといえます。
4-2. “限定”を活かす:期間・数量・イベントで緊急感UP
| 限定感を強調するフレーズ | ||
|---|---|---|
| 「今だけ」 | 「1日5食限定」 | 「季節限定」 |
限定感を強調するフレーズは人を行動に駆り立てる王道テクニックです。とくに「春限定のイチゴパフェ」や「この時期しか食べられない旬の牡蠣フェア」のように、時期や数量を絞ることで「早く行かなきゃ損」と感じさせられます。
4-3. 数字×実績で信用を得る:レビュー点数や受賞歴を明示
| 数字×実績 | ||
|---|---|---|
| 「年間◯万人が来店」 | 「創業50年以上の老舗」 | 「口コミ評価4.0以上」 |
数値や実績は、キャッチコピーに説得力を持たせる典型的な手段です。初めて行くお店でも、数字が明記されていると「ここなら間違いないかも」という安心感を与えやすいのです。
4-4. 読者の感情をくすぐる:ワクワク・懐かしさ・特別感
キャッチコピーでお客様の感情を揺さぶると、「なんとなく気になる」から「絶対行きたい」へ、一気に心理が変わることがあります。たとえば「子どもの頃に戻れる懐かしのナポリタン」と書かれていると、多くの人が「どんな味だろう」「懐かしい思い出があるかも」と興味をそそられます。
4-5. 過剰表現NG!違法リスクを回避するフレーズ例
「世界一うまい!」「絶対痩せる!」など、根拠のない強すぎる表現は景品表示法のリスクだけでなく、クレームを招く可能性があります。「絶対」「完全に」「史上最強」などの断定ワードは、使用に注意が必要です。
5章. 飲食店のキャッチコピーの制作を外注するには?
5-1. 費用相場の目安:プロコピーライターと自作の差
キャッチコピーを外注すると、専門家への依頼料が数万円から数十万円かかるケースもある一方で、自作なら初期費用はほぼゼロ。しかし後者は試行錯誤に時間がかかることもあるため、コストと労力のバランスをよく考える必要があります。
5-2. 予算を抑えて成果を出す4つの工夫
- SNSを活用する
InstagramやTwitterで写真+コピーを発信。こまめな投稿とハッシュタグ選定で、広告費ゼロでも集客できる可能性は十分。 - 店内POPや手書きボード
細かい費用をかけず、スタッフのアイデアで温かみあるキャッチコピーを作成。お客様にも親しみやすい印象を与えられます。 - クラウドソーシングの活用
ライターやデザイナーを募集すれば、複数案を比較可能。契約時に機密保持契約を結んでおけば安心です。

筆者もクラウドソーシングで複数のコピーを試したことがありますが、優秀なコピー案に出会えたときは投資額をはるかに上回る成果を得られました。大切なのは、費用対効果を意識しながら、柔軟に試行錯誤を続けることです。
6章. 作って終わらない!飲食店でキャッチコピーの効果を測定する方法

6-1. どこを見る?来店数・予約率・SNS拡散など主要KPI
キャッチコピーが本当に役立っているかどうかを判断するには、「数字」で見るのが一番わかりやすいです。具体的には、以下のような指標(KPI)を設定して定期的にチェックするのがおすすめです。
- 来店数・売上
看板やSNSでコピーを変えた後、来店者数や日別売上がどう変化したかを確認する。 - 予約率(電話・ネット予約)
キャッチコピーによって「今すぐ予約したい」と思わせられているか。電話やオンラインフォームからの問い合わせ数を比較しよう。 - SNSでのいいね数・シェア数
写真とコピーをセットで投稿し、どのくらい拡散されたかを把握する。ターゲット層に刺さるかどうかの指標になる。 - 口コミサイトの評価やレビュー数
口コミ件数が増えた、評価が上がったなど、継続的にモニタリングするとキャッチコピーの効果を見逃さずに済む。
筆者が支援したカフェでは、看板を刷新してから一週間で土日の来店数が10%増加。あわせてInstagramのフォロワーも1.2倍になりました。こうした複数のKPIを見ながら、キャッチコピーが実際に集客・売上アップに貢献しているかを冷静に判断できます。
KPIの考え方については『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』の記事でより詳しく解説してますので併せて参考にどうぞ。
6-2. 成果を上げるPDCA:小さな変更を繰り返す重要性
キャッチコピーは一度作って終わりではなく、改善を繰り返すことでより高い成果を生む。そこで役立つのが「PDCAサイクル」です。
- Plan(計画)
どんな顧客層を狙い、どのような言葉を使うか考える。 - Do(実行)
実際に看板やメニュー表を変更してみる。SNSにも投稿する。 - Check(検証)
設定したKPIをもとに数値を測定。来店数や予約率をチェック。 - Act(改善)
うまくいかなかった点を修正し、別の言葉や表現を試す。
7章. 飲食店のキャッチコピーに関するQ&A
- どのくらいの長さがベスト?
-
結論から言うと、看板など一瞬で目に留まる媒体では「短くキレを重視」。逆にメニューやSNSの投稿文なら、ある程度「味や雰囲気を詳しく描写」した方が響く場合があります。どちらが正解というわけではなく、「場所と目的」に応じて使い分けるのがポイント。
- 誇大広告にならないラインは?
-
「世界一」「絶対」「完全に」など、根拠が薄い断定表現は避けるのが無難。景品表示法や薬機法に抵触するリスクがあるだけでなく、お客様の期待値を必要以上に上げてしまい、実際の体験とのギャップが大きくなる恐れがあります。
安全策としては、「◯◯の調査で高評価!」など、数字や第三者の評価を一緒に示すと効果的。ただし、その数字が真実であることは当然重要です。 - 英語やカタカナ表記、入れたほうがいい?
-
結論としては「店のコンセプト次第」。和風居酒屋が無理にカタカナを多用するとイメージに違和感が出たり、逆に洋食店なら軽快な英語表現がハマることもあります。
筆者が見た成功例として、アメリカンスタイルのカフェが「Satisfy your sweet tooth!」など英語フレーズを添えていていて外国人客が増加したケースがあります。一方、和食店で過剰に英語を使うと「どんなお店?」と混乱を招いた事例もある。客層や雰囲気に合わせた自然な導入が大切です。
8章. キャッチコピーの効果をさらに向上させるために

8-1. 看板・POP・SNSを連動させるメリット
実は、同じキャッチコピーやフレーズを複数の媒体で繰り返すと「記憶に残る」効果が高まる。たとえば、看板に書かれた言葉とまったく同じコピーをSNSでも頻繁に使えば、お客様は「あの言葉のお店だ」と結びつけやすくなります。
8-2. 店員の声かけも“キャッチコピー化”する
意外な盲点ですが、スタッフの接客トークにもキャッチコピーの要素を入れられます。たとえば「本日のおすすめは、じゅわっと肉汁あふれる特製ハンバーグです」と口頭で伝えるだけで、メニューに書かれたフレーズがもっと鮮明に伝わります。

筆者が研修を行った居酒屋では、店員さんに「おすすめを聞かれたら、オノマトペと感情ワードを必ず入れる」というルールを設けた結果、実際に単価アップにつながった。口頭での“生きたキャッチコピー”は、お客様との距離を一気に縮める効果があります。
9章. キャッチコピーはお店の特徴を一瞬で伝える魔法の言葉

9-1. キャッチコピーの重要性
キャッチコピーは、単なる飾り文句ではなく「お客様の心を動かす導線」です。ここまで紹介してきたテクニックや事例を踏まえ、自分の店に当てはめてみると、思わぬ集客アップやファン獲得につながる可能性があります。最後に、すぐに実践できるチェックリストを用意しました。
- ターゲットの明確化
若年層・ファミリー層・ビジネスパーソンなど、狙う客層に合わせた言葉選びをしているか? - 自店の強みの棚卸し
“こだわり素材” “老舗の歴史” “駅チカ” など、自分の店ならではの魅力を一言で言い切れるか? - オノマトペや感情ワードの活用
サクサク、ジュワッ、ほっこり、ワクワク……五感や気分を刺激する表現を入れられているか? - 限定感・数字で説得力を増す
「数量限定」や「創業◯年」といった具体的データを盛り込んでいるか? - 法的リスクへの配慮
「絶対」「完治」「世界一」など、根拠がない過剰表現は避け、誇張しすぎないようにしているか? - 効果測定とPDCA
変更後の売上や予約件数、SNS反応などを記録し、良いコピーほど継続して使う仕組みはあるか?
9-2. 次にあなたがやるべきアクション
- 店頭看板やSNSのコピーを「すぐに」変えてみる
まずは小さな部分からでも構わないので、短いフレーズをひとつ刷新し、どんな反応があるか観察しましょう。 - PDCAを回すためのシートやアプリを用意
来店者数、売上、口コミ数などを週単位・月単位で計測し、キャッチコピー変更との関連をチェックする。 - スタッフとの情報共有
キャッチコピーの意図や使いどころをスタッフと共有し、声かけや接客トークにも生かしてもらう。 - 定期的に季節イベントを取り入れる
季節ごと・行事ごとにコピーを更新して、新鮮な驚きと限定感を提供するとリピート率が上がりやすい。
言葉は無料の武器です。小さな工夫と継続的な改善が、大きな成果をもたらす可能性を秘めています。ぜひ自店ならではのキャッチコピーを追究し、「一度行ったら忘れられない」そんな存在感を手に入れてください。