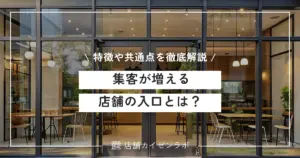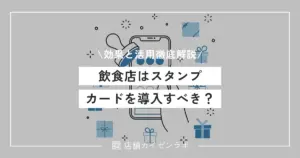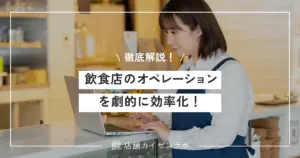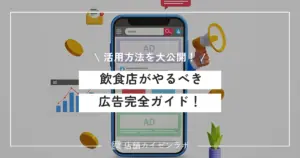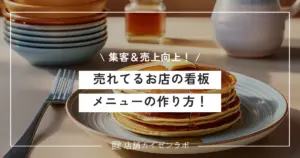第1章. ポスティングとは?費用の目安はどれくらい?

1-1. 新規客を掴む鍵となる「ポスティング」の基本
飲食店がポスティングに取り組む理由は、ずばり“地域密着型の集客”にあります。新聞折込やWeb広告とは異なり、配布したいエリアやターゲットをかなり絞り込んで実施できるのが大きな特徴です。たとえば、店舗の半径1km内に集中してチラシを投函すれば、「すぐ行ける距離」「近所だから気軽に立ち寄れる」という心理的ハードルが下がり、来店のきっかけを作りやすくなります。
筆者の体験談:配布戦略の実例
1-2. 必要になる費用の内訳と相場を一気に解説

ポスティングを実施するうえで発生する費用は、大きく(1)チラシ作成費(デザイン)、(2)印刷代、そして(3)配布代の3つに分類できます。
- デザイン費
- 相場感:片面A4サイズで約1万〜3万円程度が平均的。
- 飲食店の場合は、料理写真や店内の雰囲気を効果的に見せたいので、プロのデザイナーやカメラマンに依頼するケースが多いです。
- 節約ポイント:テンプレートを利用したり、自社で写真を用意することでコストを下げることも可能。
- 相場感:片面A4サイズで約1万〜3万円程度が平均的。
- 印刷代
- 相場感:A4チラシを5,000部印刷するなら、両面カラーで1部あたり数円〜10円前後。
- 紙質やサイズ、片面・両面、モノクロ・カラーによって金額が上下します。
- 大量部数(1万枚以上)をまとめて発注すると、単価は下がりやすいです。
- 相場感:A4チラシを5,000部印刷するなら、両面カラーで1部あたり数円〜10円前後。
- 配布代
- 相場感:1枚あたり数円〜10円程度。
- 依頼する地域や形態(一戸建て限定、集合住宅込み、セット配布など)によって変わります。GPSでの配布管理や報告書を提供する業者はやや単価が高め。
- 相場感:1枚あたり数円〜10円程度。
たとえば、A4チラシを5,000枚、片面カラーでデザイン〜配布まで業者に一括依頼した場合、合計5万〜10万円程度になることも珍しくありません。最近では、オンライン印刷でチラシを安く刷ったうえで、配布だけ業者に依頼する「二段階方式」も見られます。これはデザインが自作できる飲食店や、比較的シンプルなメニュー案内チラシを作る場合に向いています。
ポスティングに加えた効果的なチラシの作り方・集客例を知りたい方は、『飲食店がチラシで集客するには?効果の出るデザインの作成方法と配布のコツを大公開!』の記事もあわせてご覧ください。
いずれにせよ、配布部数×反応率×客単価による売上増が費用を上回れば投資回収できるため、費用対効果を意識したポスティング計画を立てることが重要です。初期費用ばかりに目が行きがちですが、ターゲットを絞れば意外と少ない部数でも十分な効果を得られるケースもあります。
第2章. 飲食店がポスティングするメリットとデメリット

2-1. 低コストでターゲットを絞りやすい「ポスティングの利点」
飲食店にとってポスティングの最大のメリットは、費用対効果の高さと精密なターゲット設定です。たとえば、
- 費用を抑えやすい
Web広告や大手グルメサイトへの掲載は月額料金が高額になりがち。ポスティングなら比較的少ない予算からスタートできます。 - 商圏を限定できる
駅チカでなくても、半径1km圏内の一戸建てやマンションだけを狙うなど、細かなエリア設定が可能。住民がピンポイントで自分の店を認知してくれます。 - 他の広告に埋もれない
新聞折込やポータルサイトでは他社と並列になることも多いですが、単独ポスティングなら飲食店のチラシだけに注目してもらいやすいです。 - クーポンや特典を直接届けられる
チラシを手に取った瞬間、**「クーポンがあるなら行ってみようかな」**と行動へつなげやすい。特にテイクアウトやデリバリー併用店舗はシームレスな注文導線を作れます。
▼筆者の実践談:限られた予算の中で
- 要因分析:二段階のクーポン(初回→ドリンク1杯サービス/2回目→フード1品無料)を用意しておき、初回だけでなくリピートを誘導する仕組みが奏功。
- 費用対効果:デザイン・印刷・配布トータルで約4万円ほどかかったが、初月だけで十分回収できた。
こうした事例からも分かるように、ポスティングは狭い地域であっても一定の反響を得られ、効果が分かりやすいというメリットが大きいです。
2-2. 配布漏れ・クレームなど、気をつけるべき「落とし穴」
一方で、ポスティングにはデメリットやリスクもあります。特に注意したいのが以下のポイントです。
- クレームリスク
- 禁止物件や「チラシ不要」ステッカーのある家への誤配。
- 大規模マンションでは管理組合がチラシ投函を禁じている場合も多く、発覚すると苦情を受けやすい。
- 禁止物件や「チラシ不要」ステッカーのある家への誤配。
- 配布漏れや誤配
- 配布スタッフによっては、誤って別のエリアに投函していたり、配るべき場所を飛ばしているケースも。
- 業者選定の際に、GPS追跡や投函写真レポートなど管理体制が整っているかを確認する必要があります。
- 配布スタッフによっては、誤って別のエリアに投函していたり、配るべき場所を飛ばしているケースも。
- 投函タイミングのミスマッチ
- 昼間に留守が多い地域だと、ポストが満杯になる夕方までに他のチラシと埋もれてしまう恐れ。
- 飲食店の場合、週末の夜や給料日直後など、「購買意欲が高まる時期」に合わせる工夫が必要です。
- 昼間に留守が多い地域だと、ポストが満杯になる夕方までに他のチラシと埋もれてしまう恐れ。
- 広告効果の短期的な限界
- チラシは見た瞬間に判断されるため、反応が出る期間は配布後1週間〜2週間程度がピークになりやすい。
- 継続して定期的に配布しないと忘れられてしまうリスクがある。
- チラシは見た瞬間に判断されるため、反応が出る期間は配布後1週間〜2週間程度がピークになりやすい。
クレーム対策においては、「管理組合へ事前に相談」「ポストの表示をしっかり確認する」といった配慮が欠かせません。また、少し面倒でも戸建てと集合住宅で異なる配布計画を練ると、配布漏れや無駄を減らせます。ポスティング業者に任せる場合は、事前に配布禁止リストやエリア選定のすり合わせをしておくと安心です。
第3章. 作成から配達までの流れは?飲食店のポスティングの実施方法!

3-1. チラシを作るまで:デザイン・写真・コピーのこだわりポイント
ポスティングの成果を左右する要因として、まず挙げられるのがチラシそのものの“完成度”です。飲食店の集客においては、とりわけ料理写真とキャッチコピーが肝になります。
- 料理写真
- 撮影のコツ:自然光を活かした明るい写真、背景をシンプルにしてメインの料理を際立たせる。
- プロのカメラマンに依頼しなくても、最近のスマホカメラは十分高性能。照明やアングルを工夫するだけで印象が大きく変わります。
- 飲食店の場合、“おいしそう”なビジュアルはそのまま来店意欲を刺激する最大の武器です。
- 撮影のコツ:自然光を活かした明るい写真、背景をシンプルにしてメインの料理を際立たせる。
- コピーライティング
- ポイント:「どんな店か」「どんな味や特徴があるか」を一瞬で伝える。
- 例:「このチラシ持参で自慢のローストビーフ半額!」「木の温もりに包まれた個室居酒屋でゆっくり過ごしませんか?」など、具体的なメリットを明示。
- 長々と書かない:文字が多すぎると読みにくく、捨てられやすくなります。
- ポイント:「どんな店か」「どんな味や特徴があるか」を一瞬で伝える。
- クーポンや特典を添える
- 飲食店の強みの一つが「来店時にすぐ使える特典」を提供できる点です。
- 例:ドリンク無料券・ランチ100円引き・デザートサービスなど。期限をあえて短く設定すると来店を急がせる効果が期待できます。
- 飲食店の強みの一つが「来店時にすぐ使える特典」を提供できる点です。
- レイアウト(デザイン全体)
- ごちゃごちゃ詰め込まず、余白を残して料理写真を大きく配置したほうが目を引きます。
- 地図を目立つ位置に入れると「ここなら行ける」とすぐ判断してもらえます。
- ごちゃごちゃ詰め込まず、余白を残して料理写真を大きく配置したほうが目を引きます。
お客様の心を動かすキャッチコピーの作り方をもっと深掘りしたい方は、『飲食店の集客に効果的なキャッチコピーの作り方!具体的な考え方から成功事例まで徹底解説!』もぜひ参考にしてください。
チラシ作成時のポイントまとめ
- 料理写真は光とアングルを意識
- キャッチコピーで店の特徴を端的に伝える
- クーポンや特典をわかりやすく提示
- 地図や営業時間をはっきり明記
この段階で、「どんな客層を狙うか」が明確になっているほどチラシの完成度は高まります。ファミリー層が多い地域ならキッズメニューや家族割、オフィス街向けならランチやテイクアウト強調、といったターゲット別の差別化が必須です。
「美味しそう!」と感じさせる写真でチラシ効果を高めたい方は、『飲食店で綺麗な写真撮影をする基本知識とコツ!外注する場合の注意点まで!』の記事で撮影手法も紹介してますので参考にどうぞ。
3-2. 印刷~配達:業者依頼と自力配布、どちらがいい?
チラシが完成したら、次は印刷と配布のステップに移ります。ここでの大きな選択肢が「自力配布か、業者委託か」。どちらにもメリット・デメリットがあるので、店舗のリソースや配布部数に合わせて判断するとよいでしょう。
1. 自力配布
- メリット
- コストが低い:外注費がかからず、印刷代だけで済む。
- エリアや投函先を細かく把握できる:実際に歩いて配るため、立地感覚がつかめるし、お客様と直接コミュニケーションが生まれる場合も。
- コストが低い:外注費がかからず、印刷代だけで済む。
- デメリット
- 時間と手間がかかる:数百〜数千部を配るのは想像以上に大変で、スタッフのシフトなども圧迫。
- クレームリスク管理が難しい:配布禁止物件やステッカーを見落とす可能性がある。
- 時間と手間がかかる:数百〜数千部を配るのは想像以上に大変で、スタッフのシフトなども圧迫。
2. ポスティング業者に依頼
- メリット
- プロのノウハウ:地域別の特性や効果的な投函時間など、業者が持つデータを活用できる。
- 配布の正確性:GPS管理や投函報告書を提供してくれる業者も増え、配布漏れや誤配を防ぎやすい。
- 時間節約:飲食店のスタッフは接客や調理で忙しいため、外部委託で本業に集中しやすい。
- プロのノウハウ:地域別の特性や効果的な投函時間など、業者が持つデータを活用できる。
- デメリット
- 費用:配布だけで1枚数円〜10円程度の単価がかかり、大量配布だと予算がかさむ。
- 業者任せでエリア分析を誤ると、思ったほど反響が出ない可能性も。
- 費用:配布だけで1枚数円〜10円程度の単価がかかり、大量配布だと予算がかさむ。
実際に、試しに1,000部ほど自力で配るところから始めて、効果や手間を実感したうえで次回以降の本格的な配布は業者委託、という段階的アプローチも有効です。特に飲食店の場合、開店前後は仕込みや接客で人員が必要になるため、無理にスタッフが配布を担当するとサービス品質に影響が出ることもあります。
第4章. 飲食店のポスティング効果をさらに上げるための4つのポイント

4-1. 目的とターゲットを明確にし、配布エリアを徹底分析する
まず最も大切なのが、「どんな人に来店してほしいか」を具体的にイメージしてターゲットを絞ってポスティングを行うことです。ファミリー層か単身者か、学生向けかビジネスマン向けかによって、チラシの内容やクーポンの訴求点が大きく変わります。
また、配布エリアの特性を理解するために、事前に商圏内の人口統計や世帯構成、周辺に競合が多いエリアなどをチェックしておきましょう。たとえば、マンション集中地域は効率よくチラシを投函できる反面、クレーム対策や禁止物件チェックが欠かせません。逆に一戸建て中心の地域は配り切るのに時間がかかりますが、ターゲット属性をさらに細かく絞ることができます。
このように事前準備を徹底し、目的・ターゲット・エリア特性を明確にしておけば、後のチラシ作成から配布戦略までブレずに進めやすくなります。
4-2. 配布タイミングを工夫し、繰り返し実施する
ポスティングは“いつ配るか”で反応率が大きく変わります。特に週末に行うと、在宅率の上昇や週末の外食ニーズと重なり、チラシに目を留めてもらいやすい傾向があります。一方、平日ランチを狙いたいなら、あえて平日朝〜昼の時間帯に投函するなど、ターゲット層の生活リズムに合わせた配布が効果的です。
さらに、大切なのは継続してポスティングすること。1回だけで終了してしまうと、「前にチラシを見たけど行かなかった」という層を取りこぼす可能性が高まります。定期的にポスティングを行うことで、地域住民の頭の片隅に店名を刷り込む効果が期待できます。季節のイベントや新メニューに合わせて何度か投函すれば、「次こそ行ってみよう」と思う人が徐々に増えていくはずです。
4-3. チラシデザインは視認性と魅力を両立させる
ポストに投函されたチラシは、受け手にとって数多ある広告の一つにすぎません。そこで効果的なチラシデザインを心がけることで、ひと目で「なんだろう?」と興味を持ってもらえる確率が上がります。具体的には、料理写真を大きく配置し、店の名前やクーポン特典、アクセス情報などを見やすい位置にまとめるとスムーズです。
「何がどれだけお得か」「どんな雰囲気の店なのか」がサッと伝わるかどうかが、購買意欲を刺激できるかの分かれ道。文字ばかりがぎっしり詰まったレイアウトは読む気を失わせるため、余白を作り、視認性を高めるのがポイントになります。
4-4. プロの知見を活かすため、ポスティング業者を活用する
自力で配布する方法もありますが、店舗運営で忙しい場合はポスティング業者へ依頼するのも有効な選択肢です。業者によっては、ターゲット層の多い集合住宅のリストを保有していたり、GPS管理や投函写真レポートなどで配布の正確性を担保してくれるところもあります。
また、担当者が地域の需要やクレーム回避策に詳しいケースも多く、プロのアドバイスを受けながら配布エリアやタイミングを設定できるメリットがあります。チラシのデザイン・印刷を一括で行う業者もあり、スピーディに実施しやすくなるでしょう。
第5章. 飲食店のポスティングに関してよくある質問
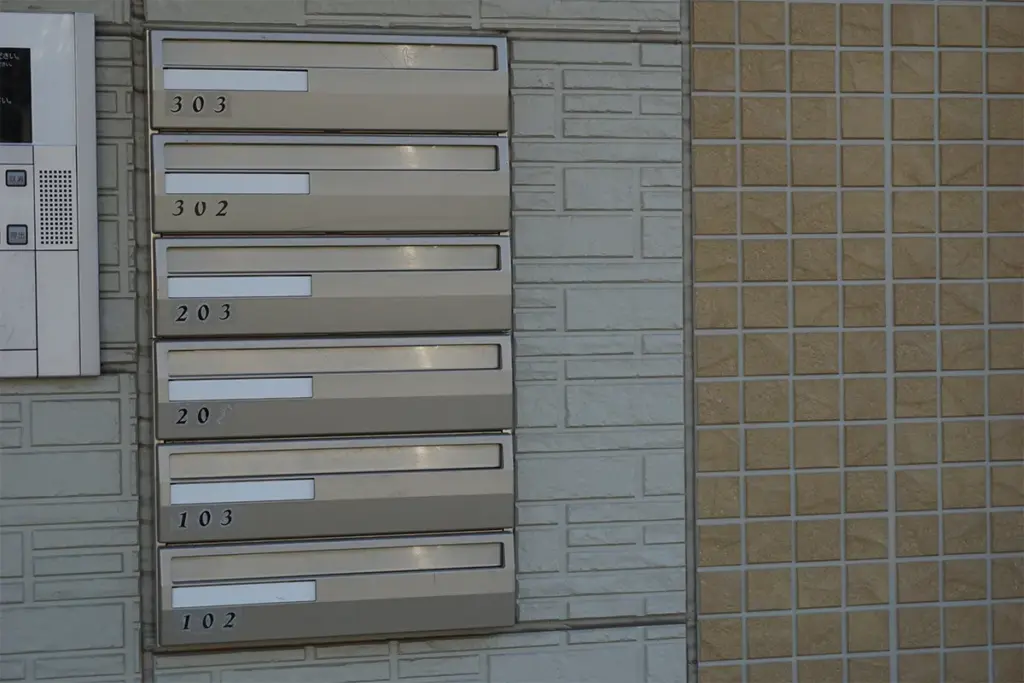
5-1. Q1「チラシは結局、捨てられない?」
A: 確かにポスティングされたチラシの一部は捨てられてしまいます。ですが、ターゲットにマッチしたデザインやクーポンを作成すれば、意外と多くの人が目を通し、冷蔵庫などに保管してくれるものです。マグネットタイプやカレンダー付きのチラシなら、「すぐ捨てずに貼っておく」人も一定数います。
▼口コミ
5-2. Q2:どのくらい反応率が出れば成功?
A: 一般的には0.1〜0.5%といわれています。たとえば1万枚配れば10人〜50人の新規来店が得られればまずは合格ライン。ただし、飲食店は客単価とリピート率で採算が大きく変わります。
- 客単価3,000円 × 3回リピートすれば、1人あたり9,000円の売上に相当するため、ポスティング費用をすぐに回収できる。
- 高級店の事例:反応率0.1%でも1回あたりの客単価が1万円を超えるため、十分に費用対効果を達成しているケースがある。
5-3. Q3:Web広告と比べてどっちがコスパいいの?
A: ターゲットや目的によります。広範囲に訴求したい場合はSNS広告などが有利ですが、近隣住民の“リアルな”利用を狙うならポスティングが非常に効果的です。
- Web広告の特徴:24時間オンラインでアクセスを集められる反面、エリアや世代を完全には絞れない場合がある。
- ポスティングの強み:半径数百mなど物理的にエリア限定できるので、“徒歩や自転車で行ける店”を探す層にダイレクトに刺さりやすい。
筆者の経験談:駅遠の店の戦略
5-4. Q4:配布禁止エリアやクレームはどう回避する?
A: 投函を嫌がる世帯や管理組合が存在するのは事実。これを無視するとクレームのもとになります。対策としては、
- 「チラシお断り」や管理組合ルールを事前調査
- ポスティング業者は独自に禁止物件リストを持っていることが多い。契約前に共有してもらいましょう。
- ポスティング業者は独自に禁止物件リストを持っていることが多い。契約前に共有してもらいましょう。
- 丁寧なマニュアル・教育
- 自力配布なら、スタッフに「禁止物件には絶対投函しない」よう徹底する必要がある。
- 自力配布なら、スタッフに「禁止物件には絶対投函しない」よう徹底する必要がある。
- トラブル発生時は速やかに謝罪対応
- 印象を悪くしないため、問い合わせ先をチラシに明記しておく。
5-5. Q5:自力配布 vs. 業者依頼、結局どちらがおすすめ?
A: 予算やスタッフ状況により異なります。
- 自力配布
- メリット:コストは印刷代のみ/エリア把握ができる
- デメリット:人手と時間を取られる/クレーム対応を全部自力で行う
- メリット:コストは印刷代のみ/エリア把握ができる
- 業者依頼
- メリット:配布クオリティや迅速性が高い/クレームリスクをある程度業者がカバー
- デメリット:外注費がかかる/業者選定を誤ると配布精度にばらつきあり
- メリット:配布クオリティや迅速性が高い/クレームリスクをある程度業者がカバー
おすすめは、「まず少部数を自力配布して反響を確かめ、効果が見込めれば業者へ拡大委託」という二段階方式。実際に小規模のカフェなどは、自力で500枚を試しに配って確かな手応えがあった後に、本格配布3,000部を業者に依頼し大きな売上増につなげた例があります。
5-6. Q6:どれぐらいの頻度で配るべき?
A: 飲食店のメニュー更新やイベントに合わせる形が王道です。月1回や季節の変わり目、またはボーナス時期に合わせるなど、継続的に配るほど認知度向上が期待できます。
- 一度配布して終わりにしない:配布直後は反応があっても、その後しばらく配布がないと忘れられてしまいがち。
- メニュー刷新や新メニュー発売時:新商品が出たタイミングで再びチラシを配ると、「また新しい情報を教えてくれている」と注目されやすい。
- イベント告知:クリスマスやお正月、地元の祭りなどに合わせてスペシャルメニューを打ち出すと、“タイミングが合った”人の来店を促しやすいです。
第6章. ポスティングを継続して地域に愛される飲食店を目指そう!

ポスティングは単なる一回きりの広告手段というより、地域住民との“コミュニケーションツール”として継続するのが重要です。新メニューやイベント情報を定期的に届ければ、「あの店はいつも新しい提案をしている」と印象づけられ、複数回目のチラシで「今度こそ行ってみよう」と踏み切る人も増えます。リピーターに対しても「そろそろ行こうかな」と足を運ぶきっかけを与えられるでしょう。
まずは小規模に配ってクーポン回収率や売上をチェックし、効果が出れば部数やエリアを拡大する方法ならリスクを抑えられます。あわせてポスティング業者や飲食コンサルなど専門家に相談し、エリア特性やチラシデザインをブラッシュアップすれば、さらに安定した地域密着の集客が実現しやすくなります。