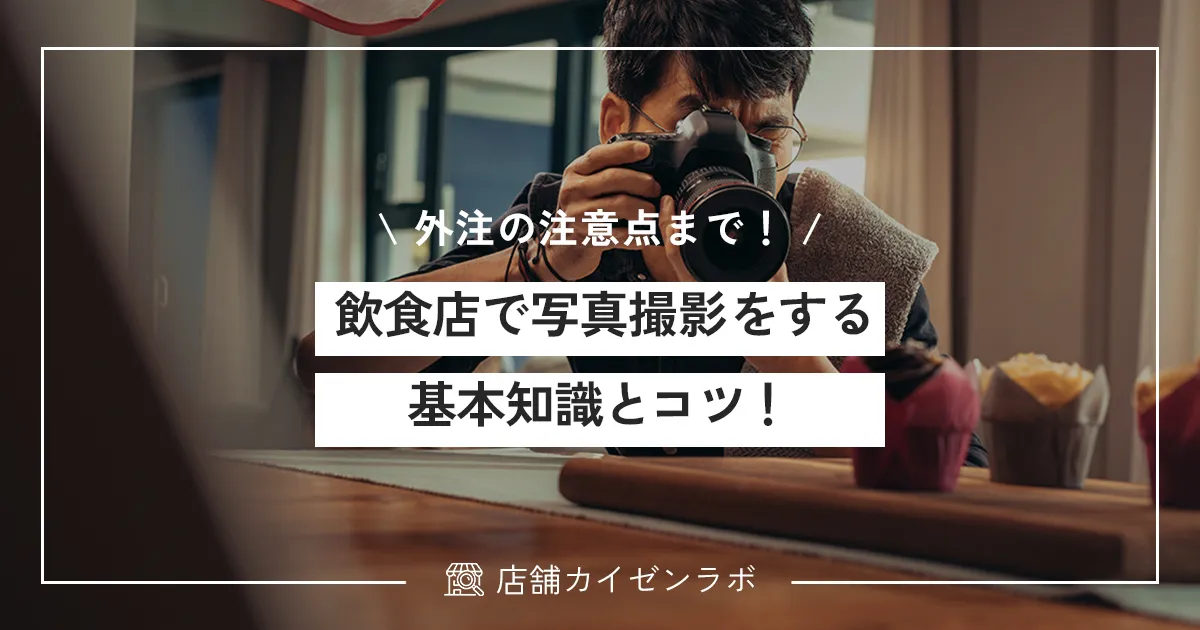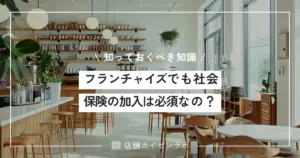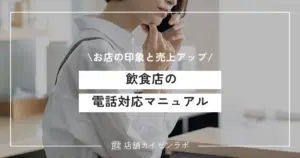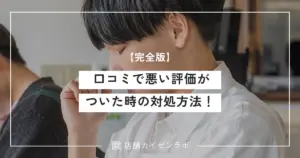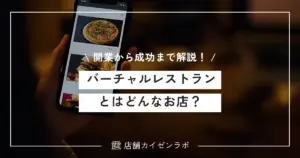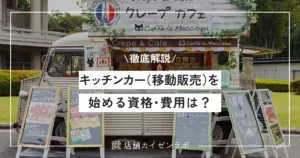第1章. 飲食店は”写真”の印象で売上が変わる!

飲食店において「料理写真」や「店舗の外観・内観写真」は、ただの飾りではなく“売上を左右する重要要素”です。SNSで発信した写真が魅力的だと拡散や口コミを呼び、新規客の来店きっかけにつながります。一方、ブレていたり暗い写真では、「このお店は料理もイマイチなのかも…」と誤解されかねません。ビジュアルが先行する時代だからこそ、飲食店ほど写真の「質」が命綱になるのです。
写真が集客に与えるインパクト
- SNSやグルメサイトの第一印象:テキストより先に目に入る写真が来店意欲を左右
- 実際の料理との差:写真と実物のギャップが大きいとクレームにつながる
- ブランドイメージ確立:統一感のある写真で店舗の雰囲気を印象づける
SNSを活用した集客については『飲食店がSNS運用をするデメリットと注意点!リスクを把握して炎上やトラブルを回避!』でも詳しく解説しています。
筆者の体験談:素人写真→プロに変更
こうした事例からも、写真が売上に直結するといっても過言ではありません。
第2章. 内製か外注か?飲食店の最適な写真撮影方法とは?

2-1. 内製に向いている飲食店と外注が向いている飲食店
写真撮影を「自店で行うか(内製)」それとも「専門のカメラマンや制作会社に任せるか(外注)」は、店舗規模や更新頻度、予算などで選択が分かれます。ここでは、どんなタイプの飲食店がどちらに向いているかを整理してみましょう。
内製が向いているケース
- 撮影頻度が高い:
例)毎月、新メニューや季節限定料理を入れ替えるお店
→撮影ごとに外注するとコストがかさむため、スタッフが機材やノウハウを習得するメリットが大きい - SNS運用に力を入れたい:
投稿時に細かい写真を多数アップしたい/動画やリールも取りたい
→ふと思い立ったときに撮影できる機動力が欲しい - 小規模予算、低コストで始めたい:
カメラや照明など初期投資はあるものの、長期的には外注費を抑えられる
外注が向いているケース
- ハイクオリティを最優先する高級店や特別なイベント用:
高級レストラン、ホテル内のレストラン、記念日向けのスペシャルメニューなどは失敗が許されない
→プロのカメラマンや制作会社へ依頼し、ライティングやディレクションをフル活用 - 撮影に割く人員や時間がない:
調理や接客で手一杯になりがちな現場
→任せられる撮影業者を見つけ、まとめて依頼したほうが効率的 - 大規模リニューアルや複数店舗分の撮影:
一気に内装・外観・メニュー撮影を行い、ブランディングを統一したい
→外注により短期間で大量カットを高品質に仕上げられる
2-2. 両者のメリット・デメリット比較表
下記のような比較表で「内製」と「外注」の特徴を整理すると、自店にベストな撮影方法が見えてきます。
| 項目 | 内製 | 外注 |
|---|---|---|
| 初期コスト | カメラ・照明機材を揃える投資が必要 | カメラマン・制作会社への依頼料 |
| 品質の安定度 | スタッフの技量次第で差が出る | プロの実績とノウハウで基本的にハイレベル |
| 撮影スピード | いつでも撮れる | スケジュール調整が必要 |
| トータル費用 | 長期運用なら安く済むことも | 初回は割高だが質と効率が高い |
| 柔軟性 | メニュー変更時も即対応可能 | 撮り直しや追加撮影は有料オプションになる場合も |
筆者の体験談:スタッフによる撮影
第3章. 飲食店の写真撮影の基本①:外観や店舗空間を魅せる

3-1. 外観撮影の基本:昼と夜の見せ方を押さえよう
外観写真は、通りがかりの人や初めてSNSで店を知る人に「どんなお店だろう?」と興味を持ってもらう絶好のチャンスです。昼と夜、それぞれの時間帯で意識するポイントを抑えると、店の魅力がしっかり伝わります。
昼間は斜め正面から
- 斜め正面で奥行きを強調:建物の側面も適度に見えるよう撮ると、立体感が出て「入りやすい雰囲気」が演出できる
- 看板やロゴを大きく映す:店名をはっきり写し込むだけでも、ブランドイメージを覚えてもらいやすい
- 夕暮れ時のマジックアワー:空にグラデーションがかかる時間帯は外観が一気にドラマチックに見える
夜間はライトアップと看板を活かす
- 照明や電飾をONに:店名やロゴが暗がりでも目立つようにし、電飾ライトも効果的に配置
- 外壁・入口周りを整頓:ゴチャゴチャしたポスターや段ボールがあるとイメージが下がりやすい
- 実例:焼肉店で来店アップ
- 夜の看板を鮮やかに撮り直してSNSに掲載したところ、飛び込み来店が翌月に15%増加
- 夜の看板を鮮やかに撮り直してSNSに掲載したところ、飛び込み来店が翌月に15%増加
外観で第一印象を良くしたい方は『集客が増える店舗の入口とは?入りたくなる飲食店の外観の特徴や共通点を徹底解説!』の記事もぜひ参考にしてください。
3-2. 内観撮影の基本:空間を広く雰囲気よく伝える
店内を撮影する際は、「広さ」と「雰囲気」が両立した写真を撮ることが大切です。視野が狭いと圧迫感を与えてしまいますが、ちょっとした工夫でお店全体の魅力をぐんと引き出せます。
広角レンズやアングルで空間を演出
- 広角レンズ(スマホ対応機種も増加):テーブルやカウンター席が連なる様子をワイドに捉え、奥行きを感じさせる
- 45度の斜めから:カウンターやテーブルの配置を俯瞰するのに最適。店内動線がわかりやすく、写真映えしやすい
- 低めの位置で撮る:テーブルや椅子が浮き立ち、視線を引き込む効果がある
照明と小物の使い方
- 自然光を取り入れる:窓際があれば、蛍光灯の黄ばみを抑えて色味を自然に再現しやすい
- 片側が暗い時はレフ板で補光:なければ白い紙ボードで代用して、店内を全体的に明るく
- 小物や装飾を部分的に入れる:植物やメニュー看板をフレームインし、世界観を強調する
口コミ:店長B氏
店舗の世界観を伝える写真を撮りたい方は『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』もご覧ください。
3-3. 撮影時の事前準備:自然光や整頓で店の魅力UP
撮影前にひと手間かけるだけで、店内外の写真クオリティは大きく変わります。特に自然光の取り入れ方や不要物の整理などは、どんな店舗でもすぐに実践できるので要チェックです。
自然光を上手に扱う
- 窓のない厨房だけで撮らない:電球色で黄ばみやすく、新鮮さが伝わりにくい
- 窓際に簡易撮影スペースを確保:小さなテーブルを置き、日中は自然光で明るく撮る
- ビフォーアフター例:筆者実践
- 窓なし厨房で撮った料理は黄ばんで見える→窓際へ移動したら本来の色味やツヤが綺麗に出てSNSの反応が向上
- 窓なし厨房で撮った料理は黄ばんで見える→窓際へ移動したら本来の色味やツヤが綺麗に出てSNSの反応が向上
店内の片付けと統一感
- 段ボールや配線などをフレーム外に:生活感が映り込むとお店のクオリティが落ちる印象に
- テーブルや床の掃除も念入りに:後で Photoshop などで消せるかもしれないが、手間もコストも増える
- 装飾のテイストを揃える:テーブルクロスや小物がバラバラだと写真が散らかった印象になる
プチ裏ワザ:ライティング
第4章. 飲食店の写真撮影の基本とコツ②:メニューや料理撮影の準備と手順

4-1. 撮影スペースと照明セッティング
「どこで撮るか」「どんな光を使うか」は、メニュー写真のクオリティを左右する重要ポイントです。店内の蛍光灯は色味が黄ばみやすく、料理の新鮮さが伝わらないことも多いため、簡易的なセットを作るだけでも効果は絶大です。
- 撮影専用スペースを確保
- 小さなテーブルや台をひとつ用意し、バック紙(白・木目など)を敷く
- 調理場と客席の間に設置すれば、温かい料理のまま素早く撮影できる
- 小さなテーブルや台をひとつ用意し、バック紙(白・木目など)を敷く
- 照明セッティング
- 自然光が入りづらい店舗は、定常光やソフトボックスを1灯でも導入すると影のコントロールがしやすい
- 厨房の蛍光灯と白熱電球が混在すると色温度が乱れ、食材が緑がかりになるので注意
- 自然光が入りづらい店舗は、定常光やソフトボックスを1灯でも導入すると影のコントロールがしやすい
プチ裏ワザ:料理の色
4-2. アングルと盛り付け:おいしそうに見せる基本
同じ料理でも、撮る角度や盛り付け次第で売上に影響するほど印象が変わるのが飲食店写真の面白いところ。以下の3つの定番アングルを使い分ければ、主要メニューはほぼカバーできます。
- 俯瞰(真上)ショット
- ワンプレートや彩り豊かな料理に最適
- 全体の配置やトッピングが見やすく、カフェ飯やパスタにおすすめ
- ワンプレートや彩り豊かな料理に最適
- 斜め45度ショット
- ハンバーガーや焼肉など、立体感を強調したい料理に効果的
- 湯気やソースのテカリを捉えやすい角度
- ハンバーガーや焼肉など、立体感を強調したい料理に効果的
- 真横ショット
- パフェやドリンクの層、グラスデザインなど高さや断面を際立たせたい場合に活用
- パフェやドリンクの層、グラスデザインなど高さや断面を際立たせたい場合に活用
盛り付けチェックリスト
- 皿の縁が汚れていないか
- メイン食材が隠れていないか
- 彩りを加える野菜やハーブをのせる余地はあるか
専門家コメント:映える盛り付け
4-3. 撮影フローを管理:温かい料理やアイスを優先
すべての料理を一気に用意すると冷めたり溶けたりして、写真映えが大幅に損なわれます。撮影順を工夫し、ベストなタイミングを逃さないようにしましょう。
- 時間経過に弱い料理から撮る
- アイスクリームやスープは、できたてor盛り付け直後を狙う
- 湯気が立っているうちにシャッターを切る
- アイスクリームやスープは、できたてor盛り付け直後を狙う
- 見た目の崩れやすい揚げ物・パスタなどを続ける
- カリッと感や麺のツヤが重要
- カリッと感や麺のツヤが重要
- 冷製・常温メニューは後回し
- サラダや前菜は比較的いつでも撮りやすい
- サラダや前菜は比較的いつでも撮りやすい
筆者体験談:撮影の失敗
4-4. 撮影後のレタッチ:スマホアプリ or PCソフト
撮った写真をどこまで修正するかで、クリック率や売れ行きが変わると言っても過言ではありません。過度なレタッチは実物とのギャップを生みますが、適度な補正は料理の魅力を際立たせます。
- スマホアプリ(無料)
- Snapseed, Lightroom Mobile, VSCOなど
- 露出・彩度・シャープネスをサクッと調整
- Snapseed, Lightroom Mobile, VSCOなど
- PCソフト(有料)
- Adobe Photoshop, Lightroomなど
- カット数が多い場合の一括レタッチや合成・文字入れがしやすい
- Adobe Photoshop, Lightroomなど
注意点
- 料理本来の色を変えすぎない
- 色温度の微調整で黄ばみや赤みを除去
- 不自然なテカリを加えすぎるとサンプル写真感が強くなる
第5章. 飲食店の写真撮影の基本とコツ③:構図と演出でワンランク上の写真を作る

5-1. 湯気・照りを強調する逆光&レフ板活用
「湯気」「ソースの照り」が表現できると、“アツアツ感”や“ジューシー感”を訴求でき、写真を見る人の食欲を大きく刺激します。逆光または半逆光で撮ることで、湯気やテカリが輪郭を描きやすくなるのがポイントです。
- 背後から光を当てる:ラーメンや鉄板焼きなど、湯気が上がるメニューで有効
- 手前が暗くなる場合はレフ板を使う:白いボードやアルミホイルで光を反射し、料理の正面を明るくする
筆者実践レポ:シズル表現
5-2. 三角構図・対角線構図で視線を誘導
構図を変えるだけで、「写真を見た人がどこに目を引き寄せられるか」が大きく変わります。特にメイン料理へ視線を集めたい時、以下の2パターンが分かりやすい効果を発揮します。
- 三角構図
- 料理や小物を三角形に配置し、安定感とまとまりを演出
- 副菜や飲み物を配置してもゴチャゴチャせずリズムが生まれる
- 料理や小物を三角形に配置し、安定感とまとまりを演出
- 対角線構図
- 皿の対角線を意識して主役を置く
- 左上から右下へスッと視線が流れるため、写真映え度が高い
- 皿の対角線を意識して主役を置く
5-3. 背景・小物でブランド感を底上げ
料理の見た目だけでなく、器や背景紙、ナプキンなどの小物が写真全体のトーンを決定づけます。和食なら陶器や木目、洋食やスイーツなら淡い色紙や大理石風背景を使うだけで、ガラッとイメージが変わるのです。
- 器の選び方:白皿がベーシックだが、彩りが多いメニューでは黒皿や和皿が映える
- 背景紙の活用:木目調や大理石柄など、1~2種類常備するとシーンごとに使い分け可能
- 小物配置:箸置きやカトラリー、ドライフラワーなどを置いて“写真にストーリー”を与える
専門家コメント:背景紙の活用
5-4. シズル感が決め手:とろけるチーズやアイスの“瞬間”を逃さない
チーズを引き伸ばすシーンやアイスが溶け始める瞬間など、“動き”や“温度”を感じさせる演出はSNSで特にバズりやすいです。成功のカギは、短時間勝負と連射モードを駆使してベストショットを逃さないことにあります。
- 連射モードで数十枚撮り
- あとで一番良い表情や伸びを選べる
- あとで一番良い表情や伸びを選べる
- スタッフやモデルとの事前リハーサル
- ピザを切り分けて持ち上げるタイミングや、デザートをスプーンですくう角度など
- ピザを切り分けて持ち上げるタイミングや、デザートをスプーンですくう角度など
- 動画撮影も検討
- InstagramリールやTikTok用に数秒の動画を撮り、そこから静止画を切り出す手もあり
- InstagramリールやTikTok用に数秒の動画を撮り、そこから静止画を切り出す手もあり
成功談:チーズハットグの“びよ〜ん”動画
第6章. 機材別で見る!カメラと照明の上手な活用方法!

6-1. スマホでの撮影:手軽さと機動力を活かす
近年のスマホカメラは高性能化が進み、日中の店内撮影なら十分綺麗な写真が撮れます。SNS主体の運用や、更新頻度の高い店舗では、スマホ撮影の機動力をフル活用するメリットは大きいでしょう。
- HDR機能:逆光や明暗差が激しいシーンも自動補正
- 露出補正&ポートレートモード:被写体(料理)を際立たせやすい
- 暗所撮影やズームには限界がある:ホワイトバランスが狂いやすいので注意
筆者体験:iPhoneのポートレートモード
6-2. 一眼レフ(ミラーレス)で狙う高クオリティ
本格的なメニュー写真を追求するなら、一眼レフやミラーレスカメラの強みは無視できません。ISO感度や絞り、シャッタースピードの調整が細かくできるため、照明環境が厳しい店内でも美しく撮れます。
- ISO感度は低め(100~400):ノイズを極力抑え、料理の質感をクリアに
- 絞り(F値):F2.8~F4.0でピントを料理に合わせ、背景を程よくボカす
- シャッタースピード:1/60秒以上を目安にし、ブレを防ぐ。暗所では照明追加or三脚使用を検討
専門家コメント:撮影テクニック
6-3. 照明機材:ストロボ&定常光を使いこなす
暗い店内や夜間撮影で自然光を期待できない場合、外付けストロボや定常光(LED・ソフトボックス)は救世主になります。初期投資はかかりますが、安定した光を得られるメリットは非常に大きいです。
- ストロボ(外付けフラッシュ)
- 一瞬だけ強い光を発し、動きのある料理もブレにくい
- バウンス(天井や壁への反射)やディフューザーで光を柔らかく
- 一瞬だけ強い光を発し、動きのある料理もブレにくい
- 定常光/ソフトボックス
- ライトの当たり具合をリアルタイムで確認でき、初心者でも扱いやすい
- 大きめのソフトボックスなら光が拡散され、影が柔らかくなる
- ライトの当たり具合をリアルタイムで確認でき、初心者でも扱いやすい
第7章. 飲食店の写真撮影を外注するときの基本と注意点

7-1. カメラマン選びで注目すべき3大ポイント
飲食店が外注で写真撮影を依頼する場合、単に価格だけで選ぶと「イメージと違う仕上がり」「納品が遅い」「リテイク料金が高額」などのトラブルにつながることがあります。そこで、カメラマン・撮影業者を比較する際に必ず押さえておきたい3つのポイントを見ていきましょう。
- 撮影実績(ポートフォリオ)
- フォトグラファーや制作会社のWebサイトやSNSに登録されている過去作品をチェック
- 和食メインか、洋食やスイーツに強いかなどジャンルが明確に分かるか
- 実際の飲食店撮影のサンプルを見て「自店スタイルと相性がよさそうか」を判断
- フォトグラファーや制作会社のWebサイトやSNSに登録されている過去作品をチェック
- ディレクション体制
- 撮影だけでなく、構図の提案や盛り付けアドバイス、必要なら動画制作まで対応できるか
- 事前打ち合わせ(ヒアリング)がどれくらい丁寧か。要望やコンセプトのすり合わせが重要
- 撮影だけでなく、構図の提案や盛り付けアドバイス、必要なら動画制作まで対応できるか
- 料金や納期の明確さ
- カット数や時間制、機材費や交通費など、料金体系が細かく明示されているか
- インボイス対応など、支払い方法や経理処理上のやりとりがスムーズか
- カット数や時間制、機材費や交通費など、料金体系が細かく明示されているか
口コミ:和食店オーナーB氏
「安さ優先でフリーランスを探したら、仕上がりは悪くなかったけど納品が2週間遅れました。もう少しディレクションがしっかりしている方を選べば、お店のこだわりを写真に反映できたかもしれません。」
7-2. お金の話は重要!料金相場と見積書サンプル徹底解説
プロカメラマンに依頼する際、料金相場がはっきりしないまま契約してしまうと、撮影後に追加費用で驚くケースも。下記のように見積書の内訳を把握しておくと、トラブルを避けやすくなります。
- 基本撮影料:カット数×○○円、あるいは半日拘束○万円など
- レタッチ・色補正料:1カットあたりいくらか、どこまで含まれているか
- 交通費・出張費:東京など主要都市内は無料の場合もあれば、県外移動で加算されることも
- 機材費:ドローン撮影や大型ストロボなど、特殊機材使用時に追加されることがある
- オプション:スタッフ・モデル手配やディレクション費用、動画編集など
サンプル見積書(例)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 撮影基本料金(半日) | 50,000円 | 料理15カット+内観・外観数カット込み |
| レタッチ料(20カット) | 20,000円 | 明るさ調整・色味補正 |
| 交通費(都内) | 0円 | 東京23区内は無料 |
| モデル手配(オプション) | 25,000円 | サービス風景で男女モデルを起用 |
| 合計 | 95,000円 | 税抜表示 |
7-3. 打ち合わせ~当日の段取り:プロ任せでいい?どこまで口出しすべき?
外注先が決まったら、事前の打ち合わせで自店のイメージや撮りたいカットをしっかり共有しておくことが重要です。プロだからといって「お任せ」にすると、仕上がりが抽象的になり、後から「こんなはずじゃなかった…」と感じるケースも。
おすすめの進め方は以下の通りです。
- 撮影コンセプト作り
- 「落ち着いた雰囲気で撮りたい」「元気でカジュアルに見せたい」など店舗の特徴を言語化
- 参考になる写真やSNSのスクショ、雑誌の切り抜きを用意する
- 「落ち着いた雰囲気で撮りたい」「元気でカジュアルに見せたい」など店舗の特徴を言語化
- メニューリスト&優先順位
- 主力メニューや季節限定、売りたい料理を最初に撮影
- ドリンクやデザートは後回しにしないと冷めたり溶けたりする恐れがある
- 主力メニューや季節限定、売りたい料理を最初に撮影
- タイムテーブル共有
- 何時から準備し、どの順序で撮るか
- 営業時間や仕込みのスケジュールとも調整しておく
- 何時から準備し、どの順序で撮るか
専門家コメント:プロカメラマンS氏
7-4. プロ外注の成功・失敗談+対応策まとめ
成功談
- SNS用写真を大量に撮り下ろし、週ごとに順番に投稿→フォロワー増→ランチタイムの客足が1.5倍に
- メニュー表にきれいな写真を載せたら、単価の高いメニューの注文率がアップ
失敗談
- 外注費用を抑えたくて低価格業者を探したら、レタッチは別料金かつカット数制限で思ったより高くついた
- 撮影当日にシェフが複数の料理を同時進行で作り、時間管理が甘くなる→カメラマンが業を煮やして撮れないメニューが出た
第8章. 飲食店の写真撮影に関してよくある疑問
8-1. Q1:撮影した写真の著作権は店側にあるの?
A:一般的にはカメラマンに著作権が帰属し、飲食店は使用権を得る形です。別用途で使う場合は追加費用が発生する場合があるので、契約前に利用範囲を明確化しましょう。
8-2. Q2:肖像権トラブルを防ぐにはどうすればいい?
A:スタッフやお客様が映る場合、事前に撮影同意を得ておくのが基本です。イベント撮影時はポスターやSNSで周知し、NGの方がいればフレーム外に配慮しましょう。
8-3. Q3:撮影後の修正や追加撮影は無料?
A:契約内容次第ですが、色調補正は数回まで無料でも別アングルの再撮影は有料が一般的です。リテイク範囲を最初にしっかり確認しておきましょう。
8-4. Q4:メニュー写真を他の広告にも流用したい場合は?
A:契約時に二次利用の許可や追加料金の有無を明記してもらいましょう。後で想定外の費用を請求されないよう、転用範囲をはっきりさせることが大切です。
8-5. Q5:カメラマンに撮影データを全部もらえないのはなぜ?
A:RAWデータや未編集カットの提供は別途費用だったり、カメラマンの著作管理上NGの場合もあります。不要トラブルを防ぐため交渉時に要確認です。
8-6. Q6:料理写真が実物と違いすぎると言われたら?
A:過度なレタッチはクレームを招く恐れがあります。実際の色味から大きく逸脱しないよう注意し、メニュー表やSNS上で誤解が生まれない調整にとどめましょう。
第9章. 飲食店こそ写真撮影に力を入れて取り組もう!
飲食店にとって写真は単なる「見た目」ではなく、集客や売上に直結する大きな武器です。魅力的な料理写真は新規客の来店を後押しし、常連客には再訪のきっかけを与えます。外観や内観の雰囲気づくりも撮り方ひとつで印象が変わるため、こだわりを持つほどブランドイメージが強化されるでしょう。
さらに、動画やSNS拡散による相乗効果も期待できます。自力での撮影ノウハウと外注活用の両面を押さえ、法務・契約面のトラブルを避ける体制を整えれば、写真は単なる記録から“お店の売れる仕掛け”に大変身します。
写真を含めたWeb全体での集客戦略を考えたい方は『飲食店のWEB集客方法完全ガイド!効果的なマーケティング施策で店舗売上を増加させよう!』をご覧ください。