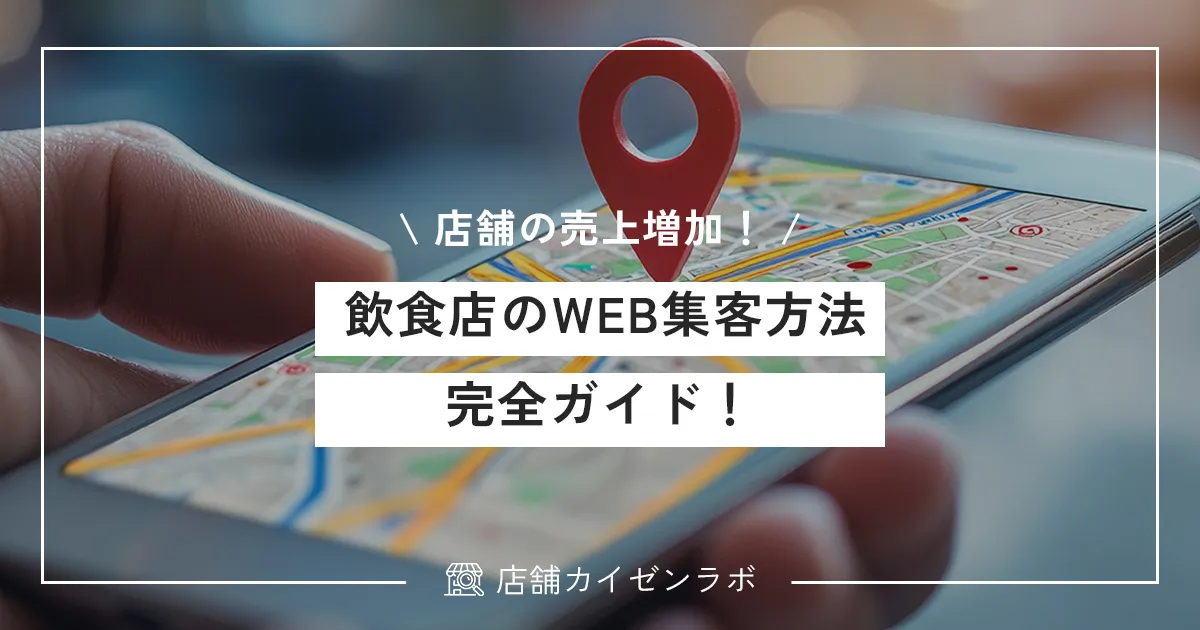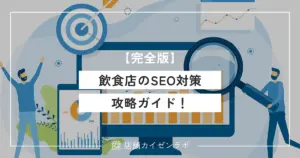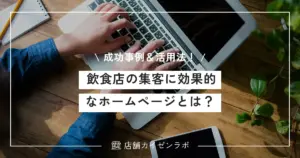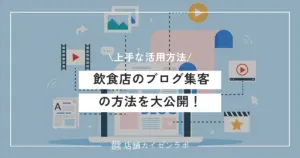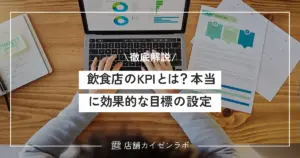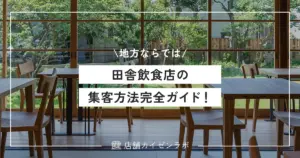第1章. なぜ今、飲食店にWEB集客が求められるのか?

インターネットが普及し、スマホ一台ですぐに近くのお店の評判を調べられる時代になりました。実際、総務省の調査によると「飲食店を利用する際、まずはスマホで検索する」というユーザーは増加の一途をたどっています。これまで飲食店の集客といえば、チラシ・ポスティング・看板といった“オフライン”中心でした。しかし、情報収集の主戦場がデジタルへ移りつつある現在、Webを活用するかしないかで大きく売上に差が生まれやすくなっています。
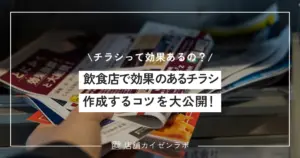
加えて、グルメサイトやSNSが台頭してからは、「口コミ」の重要性が急激に増しました。どれほど素晴らしい料理を提供していても、ネット上で情報が見つけにくいと新規来店のきっかけになりにくいのです。一方で、Web集客をしっかり実践すれば、ローカルSEO(MEO)やSNS投稿経由で潜在顧客を効率的に呼び込めます。つまり、今や飲食店においてWeb活用は“追加の販促手段”というよりも、“欠かせない経営戦略の1つ”だと言えるでしょう。
第2章. 飲食店がWEB集客する上で押さえておくべき4つのポイント

2-1. 自店の数字を知るだけで売上アップにつながる?
飲食店でのWeb集客をスタートする際、大前提として「お店の経営指標」を正しく把握する必要があります。代表的なものとして「売上」「客単価」「原価率」「来客数(客数)」が挙げられ、これらを数値で捉えるだけでも、やみくもに施策を打つよりはるかに効率的に集客が可能です。
店舗運営で重要なKPIの設計方法は『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』で解説しています。
- 売上: 日々の合計売上だけでなく、曜日・時間帯別の推移を見てみると「いつ来客が少なくて困っているか」が分かりやすくなるでしょう。
- 客単価: 1回の来店で平均いくらの注文をしているか。もし極端に低いなら、アップセルの仕組み(セットメニューや限定ドリンクなど)を検討できます。
- 原価率: 食材にかかったコスト÷売上×100で算出します。料理へのこだわりと利益率のバランスを保つ指標です。
- 客数(来客数): 実際に何人の顧客が来店したかの延べ人数。売上や客単価と合わせて分析することで、どの施策が “集客数” に寄与しているかを見極めやすくなります。
筆者の実践談:集計から施策に繋げる
2-2. ターゲット層と市場ニーズを徹底的に掘り下げる

Web集客を含めたマーケティングで重要なのが「どの客層に向けて情報を発信するのか」をはっきりさせることです。お店の価格帯や雰囲気、メニューの種類を明確に伝えるためにも、まずはターゲット層を絞り込みましょう。
- 学生や若年層: SNS慣れしているのでインスタやTikTokをチェックしがち。リーズナブルかつ映える写真を重視。
- ビジネスパーソン: 時短やコスパを重視。Googleマップやグルメサイトでの情報検索が多い。
- ファミリー層: 子連れでも気兼ねなく入店できる雰囲気、座席配置などを確認しようと検索。
加えて、市場ニーズの把握も欠かせません。たとえば地域で働く人が多ければ「ランチテイクアウトを充実させる」「注文がスムーズにできるオンライン予約を導入」などが有効になります。逆に観光客の多いエリアなら、英語メニューや地図連携を充実させるだけで、外国人客や旅行者が来やすくなるでしょう。
2-3. 知っておくと便利な事前準備ツール
- エクセルやGoogleスプレッドシート: 日々の売上・客単価・客数を記入するだけでも、傾向がわかりやすくなります。
- SNSハッシュタグリサーチ: InstagramやTwitterで地域名や料理ジャンルで検索し、どんな投稿が人気かチェックする。
- Googleトレンド: 地域名+業態(例:「神田 カフェ」)の検索ボリューム推移を確認して、アピールすべき切り口を見つける。
第3章. 飲食店のWEB集客施策①:公式WebサイトとSEO

3-1. 公式サイトがブランディングの要に!飲食店サイトで抑える3要素
自前のWebサイトを持つ飲食店はまだ少数派ですが、実は「お店のファンを増やす」うえで非常に有効な戦略です。SNSやグルメサイトと違い、公式サイトではお店の世界観やコンセプトを自由に表現しやすいという強みがあります。単にメニューや店舗情報を載せるだけでなく、以下の3点を押さえるとブランディング効果が高まります。
- スマホ対応のデザイン(UI/UX)
今やほとんどのユーザーがスマホでWebを閲覧します。文字が小さすぎて見えない、タップしにくいボタン配置などは大きな離脱要因です。特に予約フォームへの導線は、タップしやすい位置に配置しましょう。 - 高品質な写真や動画
飲食店の魅力は何といっても料理のビジュアル。公式サイトには、プロカメラマンが撮影したような写真をふんだんに使用することをおすすめします。店内の雰囲気やシェフの調理風景などもあると、ユーザーが「行ってみたい」と思いやすくなります。 - 予約・問い合わせのしやすさ
電話予約だけでなく、オンライン予約フォームやLINE公式アカウントへのリンクを設置しておくと、顧客の来店ハードルがぐっと下がります。とくにビジネスパーソンは業務時間中にサッと予約できると便利なので、「24時間予約受付OK」のフォームを作っておくのも手です。
筆者体験談:WEB集客効果
3-2. 飲食店向けSEO対策の実践ステップ
公式Webサイトを作っただけでは、検索エンジンからの集客はすぐに得られません。上位表示を狙うためのSEO(検索エンジン最適化)に取り組む必要があります。とはいえ、高度な専門知識が不可欠というわけではなく、以下のステップを意識すれば成果が出やすくなります。
- キーワード選定は「地域名+業態」を基本に
例:「渋谷 和食 ランチ」「博多 居酒屋 個室」など、ユーザーが実際に検索しそうなキーワードを意識します。自店の強み(駅近、コスパ重視など)を付け足してもOKです。 - コンテンツ強化と内部リンクの整備
「メニュー紹介」「季節の限定料理」「店舗のこだわり」といったコンテンツを公式ブログなどで定期的に更新し、関連ページ同士を内部リンクでつなぎます。たとえば新メニューの記事から予約ページへ誘導するリンクを貼るなど、ユーザーが次の行動を取りやすい設計が大切です。 - ページ表示速度の向上
大きすぎる画像や不要なプラグインでサイトが重いと、ユーザー離脱や検索順位の低下につながります。画像圧縮やキャッシュ活用など、基本的な対策を行いましょう。 - ローカルSEO(MEO)との連携
Googleビジネスプロフィールなどに登録している店舗情報と公式サイトを相互リンクすると、地域検索での上位表示に寄与しやすくなります。SNSでも同じ店舗名を使い、情報を一貫させることがポイントです。
飲食店向けSEO対策をさらに詳しく知りたい方は、『【完全版】飲食店のSEO対策攻略ガイド!店舗への集客効果や具体的な施策まで徹底解説!』もご参照ください。
第4章. 飲食店のWEB集客施策②:グルメサイトや口コミサイト

4-1. 正確な店舗情報とメニュー写真が勝負を決める!
食べログ・ぐるなび・ホットペッパーなどのグルメサイトに情報を掲載するのは、飲食店のオンライン集客において非常に効果的な方法です。これらサイトは検索エンジンの上位に表示されることが多く、ユーザーが“お店探し”をするときの入り口になりやすいのが特徴。
- 基本情報を正確に
店名・住所・電話番号・営業時間・定休日などをしっかり更新し、古い情報を放置しないことが大切です。間違った情報だとクレームにつながったり、信用を失ったりする恐れがあります。 - メニューと写真は魅力を最大限に伝える
グルメサイト内の写真は、ユーザーが「美味しそう」「行ってみたい」と思うきっかけ。特にメイン料理だけでなく、店内風景・ドリンク・デザートなども複数載せて、店の雰囲気が伝わるようにします。 - クーポン機能や限定情報を活用
ぐるなびやホットペッパーでは、期間限定クーポンや予約特典を設定できます。Web上で「今だけお得」「会員限定」と打ち出すことで、来店を即決する動機になるのです。
4-2. 口コミへの神対応で評価UP!マイナスをプラスに変える接し方

グルメサイトにおける口コミは、飲食店にとって“広告以上に効果がある”と言われています。多くのユーザーが星評価やコメントを参考にするため、口コミを軽視するのは非常にもったいない。
- 好意的な口コミにはお礼を
良いコメントに対して感謝の意を伝えたり、今後の来店を楽しみにしていることを書くだけで「やっぱりこのお店はいいな」という印象を与えられます。 - ネガティブな意見こそ真摯に対応
味や接客への不満が書き込まれた場合も、言い訳をせずに謝意と改善の意志を示すと、ほかのユーザーから「誠実な店だ」と評価されることが多いです。放置すれば残念な印象を与え続けてしまうので要注意。
第5章. 飲食店のWEB集客施策③:GoogleマップとMEO

「地域名+飲食店」などで検索すると、上部に地図とともにお店の情報が表示されることがあります。ここを制するのが、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の最適化(MEO対策)です。
- 正確な店舗情報を登録
住所・電話番号・営業時間・WebサイトURLはもちろん、休業日や臨時変更などもこまめに更新します。Googleの検索結果やGoogleマップ上でユーザーが確認する情報のため、誤りがあると大きな機会損失になるでしょう。 - 写真を豊富にアップ
お店の外観、内装、看板メニュー、スタッフの笑顔などを定期的に投稿することで、「実際に訪れる前から雰囲気を感じ取れる」状態を作ります。 - 口コミへの丁寧な返信
グルメサイト同様、口コミが増えると表示順位に良い影響があるとも言われています。評価が低い口コミであっても、誠実に対応することで店の印象をプラスに変えられます。
筆者の実践談:MEO対策結果
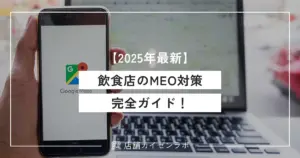
第6章. 飲食店のWEB集客施策④:SNS(Instagram・LINE・X・Facebook…)

飲食店のWeb集客においてSNSは欠かせない存在です。とはいえ、一言に「SNS」といっても特徴やユーザー層が異なるプラットフォームが複数あり、それぞれで発信の仕方や狙うべきターゲットが変わってきます。ここでは代表的なSNSをひと通り紹介しつつ、飲食店ならではの活用ポイントをまとめていきましょう。
6-1. Instagram:写真の“映え”を軸にファンを作る
主な特徴
- ビジュアル重視:料理写真や内装の雰囲気を「映え」要素で魅力的に見せやすい
- ハッシュタグ検索:地域名や料理ジャンルで検索するユーザーが多く、潜在顧客を呼び込みやすい
- ストーリーズで24時間限定コンテンツ:仕込みシーンやスタッフ紹介など“裏側”を気軽に発信可能
活用パターン
- 商品・メニュー紹介投稿
定番料理はもちろん、季節限定メニューや新作デザートを綺麗な写真と一緒に紹介。調理中の動画やシェフのコメントがあると“人柄”が伝わり、親近感が生まれます。 - ストーリーズで仕込みやスタッフの魅力を発信
24時間で消える気軽さを活かし、日常感をリアルタイムに共有。フロアスタッフや店長のキャラクターが見えやすいほどフォロワーとの距離感が縮まりやすいです。 - キャンペーン・イベント告知
「週末限定テイクアウト割引」「新メニュー試食会」など、期限や特典を明記した投稿で来店を即決してもらいやすくします。
成功例談話(筆者の知人店より)
6-2. LINE公式アカウント:リピーターを逃さない“1対1”コミュニケーション
主な特徴
- 既存顧客とのつながり強化:お友だち登録しているユーザーに直接クーポンやメッセージを配布できる
- 高い開封率:プッシュ通知が届くため、メールマガジンよりも反応率が高い場合が多い
- セグメント配信:誕生日特典やランチ利用者向け割引など、ユーザー属性別に情報を切り分けて配信しやすい
活用パターン
- バースデークーポン:誕生日月や記念日に割引クーポンを送ると、特別感を演出できて来店率が上がる
- 予約リマインダー:予約日前日にリマインドメッセージを送ることで、無断キャンセルや忘れを防ぎやすい
- 限定オファー:LINE登録者だけに提供する割引や先行メニューなど、会員の優遇感を高める
6-3. X(旧Twitter):旬の話題や限定情報をリアルタイムに拡散
主な特徴
- 瞬発力が強い:トレンドやイベントに合わせて投稿すると拡散されやすい
- 140文字(または280文字)で気軽に投稿:細かなニュースや空席情報など、思い立ったらすぐ発信できる
- ハッシュタグで話題を共有:季節イベントや地域のお祭りと絡めることで、フォロワー以外にも届く可能性がある
活用パターン
- 今晩限定割引の告知:当日限定サービスやゲリラセールを投稿→リツイートで知人に広がる
- 営業時間変更のお知らせ:突然の臨時休業や短縮営業など、リアルタイムに知らせたい情報をすばやく伝えられる
- 地域ハッシュタグ+写真:#○○市 #イベント名 などをつけて料理写真を投稿すれば、興味を持つ層への可視性が高まる
6-4. Facebook:地域コミュニティで信頼を築く
主な特徴
- 30代以上のユーザー比率が高め:ビジネスパーソンやファミリー層が多いイメージ
- グループ機能やイベント機能が充実:ローカルコミュニティとの連携がしやすい
- 文章量を多めに載せてもOK:背景ストーリーや店舗コンセプトを詳しく書くのに適している
活用パターン
- 地元グループへの参加:地域のFacebookグループでイベント案内やキャンペーンをシェアすると、地元密着で拡散されやすい
- Facebookページで限定ライブ配信:新メニューの試食会をライブ動画で流すと、ユーザーとのリアルタイムな交流が生まれる
- 商店街や観光協会とのコラボ:Facebook上で相互に告知し合うことで、別のファン層にもリーチ可能
6-5. TikTok:ショート動画で若年層の行列を生む
主な特徴
- 短尺動画中心:15~60秒程度の動画がメインで、スピード感のある映像が好まれる
- 若年層に爆発的に浸透:学生や20代を狙いたい店舗には特に有効
- バズると一気に数万~数十万再生も:拡散による高い宣伝効果を狙える
活用パターン
- 厨房シーンの“シズル感”動画:仕込みや調理の様子をテンポ良く編集し、“見るだけで食欲が湧く”映像を目指す
- スタッフ出演のエンタメコンテンツ:コミカルな踊りやトレンドの音源に合わせたパフォーマンスがハマればバズりやすい
- イベントハッシュタグへの参加:TikTok独自のチャレンジやハッシュタグを活用して、多くのユーザーにリーチする
6-6. YouTube:長尺動画と“物語”でブランドを深く伝える
主な特徴
- 長尺動画OK:調理工程や食材のストーリーを丁寧に見せられる
- 検索エンジンとしての機能:Google検索とも連動し、意外なキーワードで動画がヒットする場合がある
- チャンネル育成型:継続的に動画を投稿することで、根強いファンコミュニティが形成される
活用パターン
- 調理過程のフルバージョン公開:あえて詳しくレシピや工程を見せることで、“料理へのこだわり”を伝え、店のブランド力を高める
- 食材生産者への取材動画:地元農家や漁業関係者を訪れ、仕入れ先の魅力を紹介。飲食店の裏話が好きなユーザーには刺さりやすい
- 定期的な投稿でチャンネル登録者を増やす:週1回や月数本などペースを決め、イベント動画・新作メニュー紹介などを継続的にアップ
6-7. Threads:Instagram連携で“コミュニティ会話”を広げる新星SNS
主な特徴
- Meta社が提供するテキスト中心のSNS:Instagramとの連携が強みで、初期フォロワーを引き継ぎやすい
- 500文字まで投稿可能:X(旧Twitter)の文字数制限と比べ、少し長めのトークができる
- 画像・動画を一度に10件まで投稿可:複数の料理写真やイベントオフショットをまとめて載せるのに便利
活用パターン
- Instagramとの併用:既存のインスタフォロワーをThreadsにも誘導し、よりライトなコミュニケーションを展開。メニュー開発の舞台裏トークなど、会話ベースで発信する
- リアルタイム交流とファン意見の募集:店の改善アイデアや新メニューのアイデア募集などをして、コミュニティを巻き込む
- ハッシュタグやトレンドへの柔軟対応:XやInstagramほどの拡散力はまだ未知数だが、トレンドを押さえると多くの人の目に留まる可能性大
SNS運用の基本から応用までをまとめた『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』の記事も参考になります。
第7章. 飲食店のWEB集客施策⑤:広告・オンライン予約・テイクアウト
7-1. Google広告やSNS広告でピンポイントに狙う
自然検索(SEO)だけで集客しようとすると、上位表示まで時間がかかったり、競合が強いと埋もれてしまう可能性があります。そのため、Google広告やSNS広告を活用して、エリアやユーザー属性を絞り込んでアプローチするのも一つの戦略です。
- 検索連動型広告(リスティング広告)
「地域名+業態」(例:銀座+フレンチ)で検索したユーザーに対して自店の広告を表示できます。今まさに飲食店を探している“顕在顧客”を直接取り込める強みがあります。 - SNS広告
InstagramやFacebookでは、年齢・性別・興味関心・居住地域などを細かく設定できるため、「週末に外食する人」「昼食にスイーツを食べるのが好きな人」などをピンポイントで狙えます。少額から出稿できるのも魅力です。
飲食店向け広告の種類や選び方については『飲食店がやるべき広告完全ガイド!集客につながる効果的な活用方法を大公開!』の記事で詳しく解説しています。
7-2. 「オンライン予約システム」で顧客体験を向上
電話予約だけでは取りこぼしている顧客を補う手段として、オンライン予約システムの導入が注目されています。空席状況をリアルタイムで確認できれば、忙しいユーザーほど「手軽に予約できる店」を優先しやすいです。
- 導入の利点
- 24時間いつでも予約受付が可能
- 入力された顧客データを分析でき、リピーター施策につなげやすい
- キャンセルや人数変更もオンラインで完結
- 24時間いつでも予約受付が可能
- 実装方法
- 自社サイトへの予約フォーム設置
- グルメサイトの予約機能(ホットペッパー、ぐるなびなど)のプラン利用
- LINE公式アカウントのリッチメニューから予約誘導
- 自社サイトへの予約フォーム設置
実例(筆者サポート事例):予約システムの導入
7-3. テイクアウトやデリバリーで客層を広げる
コロナ禍を経て、多くの飲食店がテイクアウトメニューを強化しています。これをWeb集客と組み合わせると、新たな顧客セグメントを取り込む機会が格段に増えます。
- オフィス需要・在宅需要の取り込み
近隣オフィスや在宅勤務が多い地域なら、ランチテイクアウトや宅配サービスが重宝されます。SNSや公式サイトで「事前注文→時間指定で受け取り」などの手間を軽減する施策を発信すれば、忙しいビジネスパーソンに刺さりやすいです。 - メニュー設計のポイント
店内と同じメニューをすべてテイクアウト対応するのは難しい場合があるので、テイクアウト専用に工夫した「冷めても美味しい」「汁もれしにくい」構成が喜ばれます。
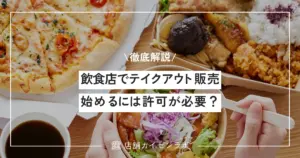
第8章. 飲食店のWEB集客に関してよくある質問
8-1. Q:SNS投稿は毎日やらないとダメ?
A:毎日投稿が理想とは限りません。質の低い投稿を量産してもフォロワーが飽きたり、逆に“宣伝臭”が強すぎると敬遠されるケースもあります。目安としては、週2〜3回をコンスタントにアップしつつ、フォロワーとのコメントやDMのやり取りを丁寧に行うことがポイントです。
8-2. Q:広告にいくらかければ効果が出る?
A:一概には言えませんが、まずは月1〜3万円程度の少額予算からテスト運用し、クリック数や予約数を見ながら調整する店舗が多いです。効果測定(どのキーワード・クリエイティブで反応があったか)を定期的に行い、費用対効果の高い領域に予算を集めるのが定石です。
8-3. Q:公式サイトなしでもSNSだけで大丈夫?
A:SNS運用だけでも一定の集客効果はありますが、プラットフォームの仕様変更やアカウント凍結リスクを考えると、公式サイトを併設しておくのが安全です。SNSと公式サイトを連携させることで、予約導線や店舗の詳しい情報を整理できるメリットも大きいです。
8-4. Q:グルメサイトに掲載しているから他はやらなくてもいい?
A:グルメサイトでリーチできる層は確かに多いですが、そこに掲載している競合店も数多く存在します。一方、InstagramやGoogleビジネスプロフィールなど“自前でコントロールできる媒体”を併用することで、より多角的なアプローチが可能です。相乗効果を狙いましょう。
第9章. Web集客を活用して飲食店の認知度を高めよう!
ここまで、多角的な視点から飲食店のWeb集客について解説してきました。オフライン施策との併用やターゲット分析、SNS・グルメサイト活用、広告やオンライン予約導入など、成功へのルートは実に多彩です。大切なのは、どの施策が自店の強みと相性が良いかを見極め、少しずつ試しながら調整を続けること。
地道に改善し続け、自店のブランド力を継続的に磨いていけば、必ずや“ファンに愛されるお店”として選ばれ続けることでしょう。