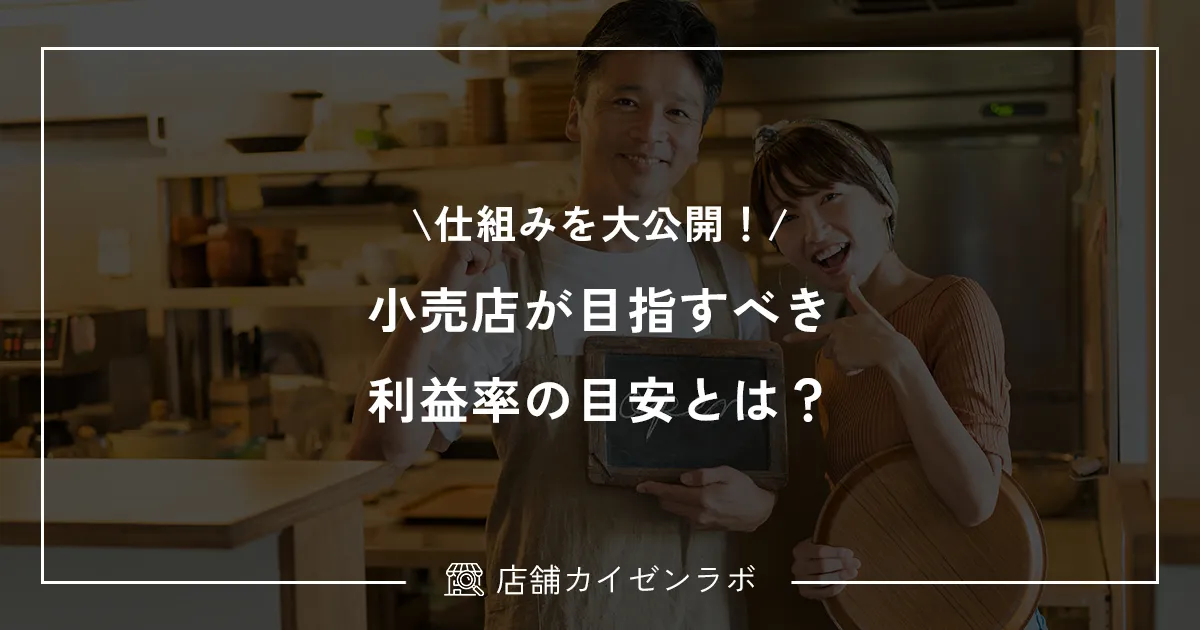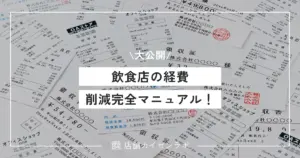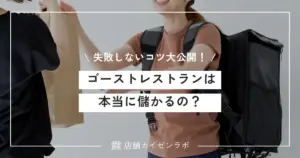第1章. 小売店の「利益率」とは?なぜ重要なのか?

1-1. 売上増=利益増ではない理由
小売業に携わっていると、「月間売上が伸びれば利益も伸びて当然」と感じてしまう場面が多いかもしれません。けれど実際には、仕入れや販促、人件費、在庫ロスなどのコストが増えれば、売上高と利益が比例しないことがしばしばあります。
小売業では「どれだけ売ったか」だけでなく、「売った商品にかかった原価や諸経費を引いたうえで、最終的にいくら残るのか」を意識することが非常に重要です。特に食品やアパレルの場合、値下げや廃棄などで想定外のコストが発生しがちなので、売上ばかり追いかけると思わぬ落とし穴にはまってしまうでしょう。
1-2. 「粗利率(売上総利益率)」と「営業利益率」をセットで見る
小売店の利益率を語るうえで欠かせないのが、「粗利率(売上総利益率)」と「営業利益率」です。
- 粗利率は、仕入れ原価を引いただけの金額(粗利)が売上全体の何%かを表す指標。
- 営業利益率は、さらに人件費や家賃、光熱費、広告費などを差し引いた営業利益が売上高の何%かを示す指標です。
たとえば仕入れ原価が60万円、売上が100万円のときは粗利が40万円。粗利率は40%になりますが、そこから家賃や人件費を引いて最終的に残る額(営業利益)が10万円だったとすると、営業利益率は10%です。
どちらか一方だけを見ると、店舗運営のどこに問題があるかを見落としがちです。「粗利率はそこそこ高いけど、販管費を引いた後の営業利益率が低迷している」といったケースもよくあります。
第2章. 小売店の平均利益率はどれくらい?業種・規模ごとの相場と目安

2-1. 食品スーパー・アパレル・日用品で利益率はこんなに違う
小売店と言っても、業種や扱う商品によって利益率の平均は大きく異なります。食品スーパーやコンビニなどは、消費期限の短い商品を扱うため値下げや廃棄が発生しやすく、結果として粗利率は20%前後、営業利益率に至っては2〜3%程度という企業が珍しくありません。
逆に、アパレルや雑貨は商品単価を比較的高めに設定できるため、粗利率が30〜50%となることもあります。ただし、シーズン切り替えや流行の変化でどうしても在庫が残り、値下げセールに頼る場面が出てくるので、最終的に営業利益率をどこまで保てるかが鍵を握ります。
2-2. 大手チェーンと個人経営で異なる固定費の構造
また、店舗の規模が大きいか小さいかでも、利益率は変わってきます。大手チェーンのように多店舗展開している場合、大量仕入れで原価を抑えられる反面、広告費や統括人件費などの固定コストもかさんで、結局は営業利益率が意外に低いことも多いのです。
いっぽう、個人商店や中小規模店の場合、仕入れ原価は少し高めになるかもしれませんが、家賃や人件費を抑えやすく、独自色を打ち出すことでそれなりの粗利率を確保できます。
第3章. これさえ見ればOK!小売店の利益率の計算方法!

3-1. 必要な数字は「売上・仕入れ原価・販管費」の3つ
小売店の利益率を計算するときに、まず最初に押さえておきたいのが以下の3つの数字です。
- 売上高
その月や期間における商品販売の総額。 - 仕入れ原価
売った商品を仕入れるために実際にかかったコスト。
- 食品や雑貨の場合、発注額+送料なども含める。
- 廃棄や値下げ分もできるだけ把握して、正確な原価計上を。
- 食品や雑貨の場合、発注額+送料なども含める。
- 販管費(販売管理費)
人件費、家賃、光熱費、広告宣伝費など、店舗運営全般にかかる費用。
「仕入れ原価は商品が売れた分だけを計上する」のが理想ですが、在庫の棚卸しが不十分だと、不要に多く仕入れた分も丸々かさんでしまう恐れがあります。つまり、正しい在庫管理をしていないと、利益率の計算がズレるという点には注意が必要です。
3-2. 粗利と粗利率の計算
- 粗利 = 売上高 − 仕入れ原価
- 粗利率(%) = ( 粗利 / 売上高 ) × 100
たとえば売上高100万円、仕入れ原価60万円なら粗利は40万円。粗利率は(40万円 / 100万円) × 100 = 40%です。
これで「商品を売って得た利益」がざっくりわかりますが、販管費の存在を考慮しないため、最終的に本当に残るお金はもう少し減っていきます。
3-3. 営業利益と営業利益率の計算
- 営業利益 = 粗利 − 販管費
- 営業利益率(%) = ( 営業利益 / 売上高 ) × 100
上記の例で粗利が40万円あっても、販管費(家賃・人件費・広告費など)に30万円かかっていれば、営業利益は10万円。
営業利益率は(10万円 / 100万円) × 100 = 10%となります。粗利率とセットで見ないと、「原価は高くないけれど販管費が大きい」場合などを見落としてしまうことになるのです。
3-4. 実践的な計算例:在庫と値下げを踏まえたケース
よりリアルなシミュレーションとして、在庫や値下げ状況を踏まえた例を見てみましょう。
- 月間売上高:100万円(商品A 70万円、商品B 30万円)
- 仕入れ原価:
- 商品A:仕入れ原価 40万円 → 値下げや廃棄はほぼなし
- 商品B:仕入れ原価 25万円 → うち5万円分は売れ残り、最終的に半額セールで売ったため実質原価率がやや上昇
- 全体として原価合計 40万円 + 25万円=65万円(※本来は仕入れ単価×売れた数量で計算)
- 商品A:仕入れ原価 40万円 → 値下げや廃棄はほぼなし
- 販管費:家賃10万円、人件費15万円、広告費5万円、その他3万円 → 合計 33万円
この場合、
- 粗利=100万円 – 65万円=35万円(粗利率35%)
- 営業利益=35万円 – 33万円=2万円 → 営業利益率2%
一見、売上が100万円もあるのに、最終的に2万円しか残らないという結果になっています。その原因をさらに掘り下げるには、「商品Bの在庫ロスや半額販売による想定外の原価上昇」「思ったより高かった広告費」などを細かく分析する必要があるでしょう。
3-5. 利益の計算ミスとよくある落とし穴
- 在庫を把握していない
売上に対する仕入れ原価を正しく計算するためには、倉庫や店頭在庫、廃棄などをきちんと管理する必要があります。 - 値下げ損失を加味しない
値下げで売れた商品も、理想的な利益率で計算してしまい、実際の粗利率が低くなるケースが多い。 - 人件費などの販管費を細かく分けない
仕分けが曖昧なまま大まかに計上していると、どのコストが増えすぎているかを掴めない。
計算を楽にするコツ
- 月単位または週単位で棚卸しして、在庫と仕入れコストを把握する。
- POSレジや会計ソフトなどを活用してデータ化し、エクセルにまとめる習慣を作る。
- 必要なら専門家(税理士やコンサル)に定期的に見てもらうことで、数字の誤差を最小限にする。
「売上高 ー 仕入れ原価ー 販管費」だけのシンプルな式に見えますが、実は在庫ロスや値下げ、様々な費用が絡むので、正確な計算には店舗オペレーション全体を見直す必要があるのです。
第4章. 今すぐできる!短期間で小売店の利益率を上げる方法

4-1. 価格を見直して、過度な値下げを改める

- ステップ1:過去3か月の値下げ回数・金額を洗い出す
「つい値下げで客を呼んでいた」頻度を数えて、どれくらい粗利率を下げていたかを振り返りましょう。たとえば週間チラシや月間セールを何度実施したのか、値下げ率は平均どのくらいか、ざっと表にしてみるだけでもOKです。 - ステップ2:値下げ対象品を分類し、必要性を検証
すべての商品を一律に割引していないか、あるいは売れ筋までも値下げしていないか確認します。「なぜこの商品を安くしたのか」「本当に割引が不可欠だったか」を振り返ると、不要な値下げが見つかることが多いです。 - ステップ3:セール頻度を1〜2回減らす
いきなり完全撤廃が怖い場合は、週2回やっていた値引きセールを週1回に減らすなど、小さく始めます。ポストカードやSNSで案内する商品を「通常価格でも魅力があるもの」にシフトしてみるのも一案です。 - ステップ4:値下げしなくても売れる“仕掛け”を考える
POP(商品説明カード)や店頭ポスターで「商品が持つストーリー」「品質の良さ」「期間限定のセット割引(安売りではなく価値の追加)」などを強調。安さ以外の“購入理由”を提供することで、客単価を維持しやすくなります。
4-2. 在庫管理を徹底してロスを減らす
- ステップ1:週ごとの売れ残りを記録する
食品小売なら消費期限切れによる廃棄数、アパレルならシーズン切れ商品、雑貨なら長期在庫化しがちなアイテムをリスト化。「どの商品が、どれくらいロスに直結しているか」を見える化することが大切です。 - ステップ2:棚卸し頻度を増やす
月1回しかやっていなかった棚卸しを、まずは週1回にして在庫をこまめに数えます。ロスが早期に発見できれば、値下げ前に“売り場の目立つ位置”に移すなどの対策が可能になります。 - ステップ3:仕入れ数量を“週単位”でコントロール
これまで月単位でまとめていた発注を、週ごとに見直す。売れ筋が想定より伸びていれば早めに追加発注し、不調な商品は発注を減らすなど、柔軟に動きましょう。 - ステップ4:数値化ツールを活用(POSやエクセルなど)
在庫管理システムがなくても、日々の売上データをエクセルでまとめれば、3~4週分の売れ数を比較して次回仕入れを調整しやすくなります。
POSレジがある店舗なら、商品別に売上集計・在庫残数を把握し、発注担当が週1回でもデータをチェックするとロス率を低下させやすいです。
4-3. まとめ:短期でも着実に利益率を向上するコツ
- 値下げ頻度を減らす
- 「いつでもセール」は利益を圧迫しがち。POPや商品ストーリーで付加価値を訴求して売る工夫を。
- 「いつでもセール」は利益を圧迫しがち。POPや商品ストーリーで付加価値を訴求して売る工夫を。
- 在庫チェックを細かくする
- 週単位で棚卸し、発注サイクルをこまめに調整。ロスになりそうな商品を早期に販促すれば値下げ回避が期待できる。
- 週単位で棚卸し、発注サイクルをこまめに調整。ロスになりそうな商品を早期に販促すれば値下げ回避が期待できる。
- 小さな改善を毎月積み重ねる
- セール削減や在庫管理をやりながら、粗利率と営業利益率の変化を確認。手応えを感じたら次の施策に踏み込み、失敗時も原因を分析するPDCAを回す。
「売上を落とさず利益を上げる」というのは小売店にとって理想ですが、まずは“無駄な値下げ”と“在庫ロス”を減らすだけでも、粗利率はぐっと改善されるはず。短期的に取り組めることから始めて、少しずつ店舗全体の利益率を上げる体質づくりを目指しましょう。
集客力アップで利益率を改善する方法を知りたい方は、『小売店の集客アイデア総まとめ!来店効果が高い売上増加施策を徹底解説!』の記事も参考にどうぞ。
第5章. 中期〜長期で小売店の利益率を底上げしていく方法

5-1. 仕入れ先の交渉・見直し

売上総利益率(粗利率)を高める王道手段のひとつが、仕入れコストの削減です。複数の仕入れ先から小分けに仕入れているなら、どこか1社に発注を集約してまとめ買い割引を狙えないか検討してみましょう。もっとも、「安い=質が悪い」となるとリピーター離れの原因にもなり得るため、仕入れ先の変更や集約には品質・納期なども含めたバランスが重要です。
長期的な契約で値下げしてもらう方法もありますが、当然相手先との信頼関係が不可欠です。実際に、筆者がサポートした小型スーパーでは複数の農家との取引を一本化し、収穫量に応じて定期的にまとめ買いする契約を締結したことで仕入れ原価が安定し、廃棄ロスも減少。結果的に営業利益率が1ポイント以上アップしています。
5-2. ネットショップやサブスクの導入で販路を拡大
オフラインだけで完結していると、在庫が売れ残った場合に値下げか廃棄しか手段がなくなりがちです。しかしネットショップと連携することで、地域外の顧客にも売り込めるようになり、在庫の回転率が上がる場合があります。さらに、定期購入(サブスク)制度を設けると、ある程度需要が読めるため、過剰在庫を減らしやすいというメリットも考えられます。
もちろんネット販売には手数料や配送費など新たなコストが発生します。が、値下げに回すよりも利益率が維持できるなら、結果としてプラスになる可能性があります。SNSやライブコマースなどと掛け合わせることで、小さな店舗でも思わぬヒット商品が生まれるケースもあるので検討してみる価値は十分にあるでしょう。
第6章. 実際に小売店の利益率を改善した成功事例

6-1. 値下げを半減して粗利率が5ポイント向上したスーパー
地方の小型スーパーで、競合の大手チェーンが近隣に進出してきたため、毎週末のセールを打ち続けた結果、ほぼ全商品を値下げで捌くような状態に陥っていました。そこで店長が思いきって、「週末セールは月1回に抑える。かわりにPOPや店内アナウンスで鮮度と地元産のこだわりをアピールする」という戦略に切り替えたところ、客数は一時的に落ちても客単価が確実に上がって月間粗利率が5ポイント近く改善。結果として営業利益率も以前より高い水準で推移するようになりました。
店長いわく、「安さ以外の価値を明確に打ち出すことで、お客さんの購買理由が“安いから”だけじゃなくなった」とのことです。これは、とくにローカルで独自性を強く出せる店舗だからこそできた施策ともいえます。
6-2. アパレル店が在庫ロスを抑えて営業利益率アップ
アパレル系は粗利率が高いぶん、売れ残ったときの値下げが痛手になりやすい業態です。ある小規模アパレル店では、過剰在庫に悩んでいたところ、POSデータを細かく分析し、追加発注サイクルを短くする仕組みを導入。シーズン前に大量発注せず、売れ筋を見極めながら小ロットで仕入れを増やす形に変えました。すると、シーズン終わりのセール品が激減し、結果として営業利益率が2%向上。顧客満足度も下がらず、リピーターがむしろ増えたといいます。
オーナーは「ITに投資するのは最初抵抗があったけれど、値下げロスの削減分だけでも十分元が取れました。継続的に売れ筋データを見る習慣ができたのも大きな収穫です」と語っています。
第7章. 小売店の利益率に関するよくある質問
7-1. Q1:値下げを減らすと客数が減りませんか?
A:一時的には減る可能性がありますが、代わりに“通常価格でも買う理由”を明確にすれば、客単価や利益率が向上します。POPや接客で「セール以外の魅力」を伝えることが重要です。
7-2. Q2:在庫を削減すると品切れしそうで心配…
A:仕入れ先との連携を強化し、週2回、3回など小分けに納品してもらう仕組みを作れば「多めに仕入れるリスク」を減らせます。アパレルなら小ロット発注+追加発注をこまめにやるのが鍵です。
7-3. Q3:粗利率と営業利益率、どちらを重視すべき?
A:両方セットで見るのが基本。粗利率が高いのに営業利益率が低い場合は販管費が重い、逆に営業利益率がそこそこでも粗利率が低いのは値下げ頻度が多いなど、それぞれ違う原因が見えてきます。
7-4. Q4:ネットショップの費用がかかりそうで踏み切れません…
A:手数料や配送コストは確かに発生しますが、在庫ロスや安売りによる損失を考えると、オンライン販売で補える分でペイできる例もあります。まずは少数アイテムからでもテストを始めてみるのがおすすめです。
7-5. Q5:売上ばかり気にしてた過去のデータはもう使えない?
A:売上高だけでも商品別の傾向をつかむヒントになります。今後は仕入れ原価や販管費の詳細も合わせて記録・分析し、「どの商品が利益率を引き下げているのか」を段階的に探っていきましょう。
第8章. 小さなステップから始めて、小売店の利益率を底上げしていこう!

8-1. 小さな戦略から始めてみる
大掛かりな仕入れ先変更やネットショップ導入をすぐに始めるのが難しい場合、まずは「値下げ回数を少し減らす」「週1回の棚卸しを増やす」「売上・原価・販管費を月ごとに見える化する」など、目の前で実行できるアクションから取り組むのがおすすめです。
これだけでも「今まで気づかなかったロスに早めに手を打てる」「セール依存度が減って客単価が上がる」といった成果が出ることがあります。特に接客や商品陳列の工夫は、コストも少なくて済むうえ効果が出やすいので、優先的に試してみる価値は高いでしょう。
8-2. 最後に:利益率の向上が小売店にもたらすもの
利益率が上がれば、店舗運営が安定し、スタッフや設備に投資できる余力が生まれます。顧客にとっても、安易な値下げに頼らず“品質や独自の価値”で勝負する店舗が増えるのは歓迎すべきことではないでしょうか。
小売店の魅力とは、物理的な商品を通じて日々の生活や気持ちを豊かにすること。利益率を適正に確保できれば、より質の高い接客や商品ラインナップに再投資できるため、長期的なファン作りにもつながります。
「売上ばかり気にして、結局は利益が出ていない…」と悩んでいるなら、ぜひ今回の内容を参考に、まずは自店の利益率を見える化してみてください。そして、値下げや在庫、仕入れの見直しを少しずつ進めながら、自店舗の最適な利益体質を目指してみましょう。