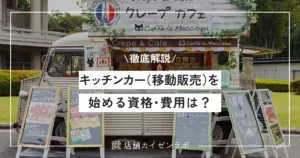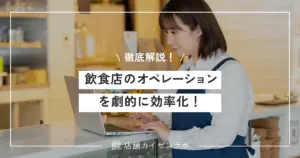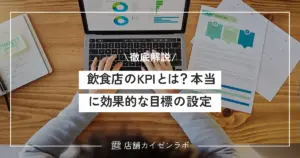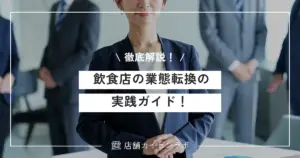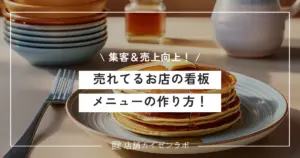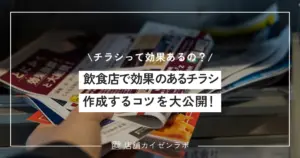第1章. 飲食店がECサイトを持つことの重要性

飲食店のEC化とは、実店舗での提供に加えて、パッケージ化・冷凍化などを施した商品をオンライン上で販売し、自宅など遠方の顧客にも届ける仕組みを指します。従来は雑貨や衣料品など物販のネット通販が中心でしたが、近年は食品分野のEC(ECサイトやモールへの出店など)が急速に成長しており、専門的な料理や地域の特産品を扱う飲食店も続々と参入しているのが大きな特徴です。
飲食店がEC化を考える主な背景
- 商圏拡大: 実店舗だけでは地域住民・近隣客に限られていた顧客層が、オンライン展開で全国に広がる
- 売上補填・リスク分散: 店舗が休業したり客足が減ったりする状況下でも、ECから収益が得られる
- ブランディング強化: 独自のストーリーやこだわりをECサイトで発信し、ブランド認知を高められる
- ネット通販技術の進歩: 決済機能やモール出店など、比較的手軽にオンライン販売を始められる環境が整った
こうした要因から、飲食店にとって「ECを始めるかどうか」はもはや検討事項として外せない時代になってきています。
第2章. 実店舗でもECサイトでも“売れる”商品ジャンルの選び方

2-1. どんな品が選ばれやすい? 冷凍総菜からギフト向けまで
飲食店がECサイトを立ち上げる際には、「どんな商品を作ればいいのか」悩む人も多いでしょう。ポイントは、店舗の強みと“オンライン受け取り”の性質を融合させることです。冷凍できる料理なら賞味期限を延ばして全国配送できるし、ソースやスープのレトルトパックなら遠方の顧客でも開封してすぐ調理可能です。
具体的には以下のようなジャンルが、実店舗・EC問わず販売しやすい傾向があります。
- 冷凍総菜・弁当
- ハンバーグやカレー、煮物など、加熱するだけで完成
- 様々な食材の組み合わせセットで単価を上げやすい
- ハンバーグやカレー、煮物など、加熱するだけで完成
- レトルト・瓶詰めソース
- カレーソース、パスタソース、鍋の出汁など、味を安定させやすい
- 料理初心者でも手軽に使いやすい点が魅力
- カレーソース、パスタソース、鍋の出汁など、味を安定させやすい
- 焼き菓子・パン
- 保存が効き、ギフト需要も狙いやすい
- パンは冷凍で長期保存できるものもある
- 保存が効き、ギフト需要も狙いやすい
- 高級食材&ギフトセット
- ブランド牛、地元の海産物、季節限定の食材など、希少性をアピール
- オリジナルラッピングやメッセージカードで付加価値をつける
- ブランド牛、地元の海産物、季節限定の食材など、希少性をアピール
2-2. 筆者の体験談:小規模パン屋の冷凍パンECでリピート率を上げた話
筆者が過去にサポートした例として、地方で営業している小規模のパン屋さんがあります。地元では朝から行列ができるほど評判でしたが、「客数の伸びに天井が見えた」とのことで、冷凍パンのネット通販を始めることにしました。元々のパン作り技術が高く、バゲットから甘めのフルーツパンまで種類が豊富だったため、「焼き立て状態に近い品質を維持できる冷凍技術」を導入することで、全国配送を実現したのです。
- 冷凍パンセット: バゲット・クロワッサン・あんパンなど詰め合わせ
- アプリで焼き方ガイドを配信 → 美味しく焼ける温度と時間を通知
- ギフト向けにラッピング&メッセージカードのオプションを用意
結果的に、SNSで話題になりリピーターが大幅に増え、「月間のEC売上が実店舗と同水準に達した」そうです。鍵になったのは、店舗人気の商品をうまく通販向けにアレンジし、保存性を高め、さらに美味しさを伝えるフォロー(焼き方ガイド)を入れた点です。
このように、何気ない強みを“オンラインでも価値が伝わる形”に再編集することで、ECサイトでの販売が成功しやすくなります。
第3章. 飲食店がECサイトを始める4つのメリットと注意点

3-1. メリット①:店舗外の売上を確保してリスク分散
飲食店がECをスタートする最大のモチベーションとして、まず考えられるのが「店舗以外の売上が得られる」ことです。たとえば台風や大雪など、天候不良で来客が激減するケースや、社会情勢の変化で営業時間が短縮されるケースなど、実店舗だけに依存していると売上が大幅に落ちるリスクがあります。
しかし、ECサイトでの販売を並行していれば、全国からの注文を受け付けることが可能であり、「倒産リスクの軽減」や「収益源の多角化」に繋げられます。特に地方の飲食店が繁忙期と閑散期の差を埋めるためにオンライン化する事例は年々増えており、観光客やリピーターを中心に通販を根付かせることで、オフシーズンも一定の売上を得ている店舗もあります。
3-2. メリット②:遠方の顧客獲得
実店舗での販売は、基本的に「来店できる人」限定となりますが、EC化すれば日本全国(場合によっては海外)まで顧客層が広がります。知名度のあるご当地グルメや、普段は地元民しか食べられなかった隠れた名店の味を「自宅で味わいたい」という人にとって、オンライン注文は大きなメリットです。
3-3. メリット③:認知度アップで実店舗集客にも好影響
ECを始めると、顧客との接点がオンライン上でも増えます。商品ページやSNS、レビューサイトなどで店舗名が露出すると、自然と実店舗の知名度も上がるのです。特に、メディアやインフルエンサーが「このお店の◯◯が自宅でも食べられる」と紹介してくれれば、それをきっかけに「次はお店に行ってみたい」と思う人が出てきます。
3-4. メリット④:ブランディング強化や新業態開拓
最後の理由として、「ブランディング強化」や「新業態の開拓」も挙げられます。たとえば、実店舗で出しているメニューとは異なる新商品を通販向けに開発することで、自社の新たな一面を打ち出すチャンスになるのです。高級路線の商品を試しに販売してみたり、コラボ商品を展開したりと、オンラインならではの企画もしやすい利点があります。
3-5. 注意点:始めれば儲かるわけではない
上記のようにメリットは多いものの、実際にECサイトを構築して成功するには、いくつかの注意点があります。ここでは代表的な4項目(+独自情報)をざっくりとまとめます。
- コストがかかる
- ショッピングカートサービス利用料、モール手数料、梱包資材、人件費…などさまざまな経費が発生
- 無料プランから試しても、結局拡張機能や物流費用などで出費が増えるケースが多い
- ショッピングカートサービス利用料、モール手数料、梱包資材、人件費…などさまざまな経費が発生
- EC担当が必要(マンパワー拡充)
- ご注文対応・発送作業・在庫管理・お問い合わせ対応など、手間のかかるオペレーションが膨大
- 店舗スタッフが兼任するには限界があるため、専門の担当を置いたり外部委託を検討する必要がある
- ご注文対応・発送作業・在庫管理・お問い合わせ対応など、手間のかかるオペレーションが膨大
- 集客が難しい
- ネット通販はライバルも多く、ただECサイトを作っただけでは売れない
- 広告やSNS活用などのマーケティングが欠かせない
- ネット通販はライバルも多く、ただECサイトを作っただけでは売れない
- ネットリテラシー・セキュリティ面の課題
- アプリ開発や決済システム導入では、個人情報保護や不正利用対策が必要
- ウェブ管理の知識不足でトラブルを起こすと信用を失うリスクがある
- アプリ開発や決済システム導入では、個人情報保護や不正利用対策が必要
EC化のメリットを享受するためには、どのようなコストとリソースが必要になるのかをしっかり試算したうえで、運営体制を整えることが大切です。
第4章.飲食店のECサイトの始め方!必要な開設準備6つのステップ

4-1. 目的やコンセプトを明確に
ECサイト構築に取りかかる前に、まずは飲食店として何を目指すか、その「目的」や「コンセプト」をはっきりさせることが必要です。なぜなら、EC化を進めるうちに「本当にこの商品は売れるのか?」「そもそも誰に買ってほしいのか?」といった疑問が浮上しがちだからです。事前にコンセプトを固めておくと、迷いが生じたときに判断基準となり、ブレずに一貫性を保てます。
コンセプトの決め方がわからないという方は、『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』の記事が参考になります。
目的の具体例
- 店舗外での売上を伸ばす:実店舗が休業状態でも継続収入を得る
- 遠方のファンを取り込む:地方にいても購入したいという顧客を逃さない
- ブランド価値を高める:独自のストーリーやこだわりを全国にアピール
- 新業態へトライ:たとえばデザート専門のEC限定商品をテスト販売する …など
これらの目的を明確にしたうえで、次は「どんな食品を、どのように、いくらで売るのか?」を考えます。EC化のゴールを定義しておけば、導入後の迷走を防ぎ、成功までの道筋を描きやすくなるでしょう。
4-2. 必要な許可申請と店舗環境の整備
飲食店がネット通販(EC)で食品を扱う際、想像以上に必要な許可や設備があるケースがあります。既に実店舗の営業許可(飲食店営業)を持っていても、製造形態が変わると別の営業許可が追加で求められることがあるため、事前に保健所に相談しておくのがおすすめです。
たとえば「かん詰又はびん詰食品製造業」や「菓子製造業」が典型例で、真空パックや瓶詰めにして販売する場合、許可が必要となります。また、食品ラベルの作成や表示も法律で厳格に定められており、原材料や賞味期限、保存方法などを適切に記載しなければ違反リスクが生じます。
許認可まわりのチェックリスト
- 飲食店営業許可:すでに取得済みか再確認
- 製造業の許可:菓子製造、缶詰製造、食肉製造など、商品特性に応じて必要か
- 食品衛生責任者:実店舗を運営している場合は既にいるはずだが、追加の資格が要るか確認
- 食品ラベル:表示項目(名称、原材料、賞味期限、アレルゲンなど)を満たしているか
もしEC向け食品の加工設備が既存の店舗内では要件を満たさない場合、別途施設工事が必要となることもあります。早めに保健所と協議し、「どの製造形態ならOKか」を把握しておくことで、スムーズにECサイトオープンへ進めるでしょう。
4-3. ECサイト制作:独自サイトorショッピングモール
ECサイトを立ち上げる方法として、大きく2つが挙げられます。
- 自社ECサイトを構築する(Shopify、BASEなどのASPを利用/WordPress系プラグインを利用/フルスクラッチで開発 など)
- モールへ出店する(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなど)
自社ECサイトのメリット・デメリット
- メリット
- デザインやブランディングの自由度が高い
- 顧客情報を自社で管理しやすく、リピーター施策を打ちやすい
- 売上に対する手数料が比較的低い(ASP月額やクレカ決済手数料程度)
- デザインやブランディングの自由度が高い
- デメリット
- 集客を自力で行う必要があり、マーケティングにコストがかかる
- 初期構築の手間やシステム管理が面倒(セキュリティ対策含む)
- 集客を自力で行う必要があり、マーケティングにコストがかかる
モール出店のメリット・デメリット
- メリット
- もともと大勢のユーザーが集まるため、露出しやすい
- ショッピングモール独自のキャンペーンや検索流入が見込める
- テンプレートが整っているので構築が比較的簡単
- もともと大勢のユーザーが集まるため、露出しやすい
- デメリット
- 販売手数料や固定費が高めの場合がある
- デザインやプロモーション手法に制約が多い
- モール内の競合が多く、価格競争に巻き込まれやすい
- 販売手数料や固定費が高めの場合がある
飲食店の場合、「まずは認知度を上げたい」ならモール、「ブランドづくりや独自ファンを育てたい」なら自社ECサイトといった選び方をすることが多いです。もちろん、両方を併用する店舗もあります。実店舗の認知度や予算、スタッフのWEBスキルなどに応じて最適な形を選ぶと良いでしょう。
4-4. EC用の設備・アイテムをリスト化
ECサイトを作っても、実際に食品を発送するには備品や機械が欠かせません。たとえば「真空パック」「冷凍保存」「自動シーラー」など、商品ジャンルに応じた設備の導入が必要になるケースがあります。
- 冷凍庫・冷蔵庫:温度帯別に在庫を管理
- 真空包装機:煮込み料理やソース類を長期保存しやすくする
- 梱包材:クール便や常温便用の段ボール、保冷材、ラッピング用品など
- 宅配伝票やラベル印刷システム:ミスなく発送するための管理ツール
特に冷凍や真空パックは「美味しさ」と「衛生面」を両立するためのキーポイントです。鮮度を保ちやすく、顧客が自宅で調理しやすい形にまとめられます。ただし保健所からの設備要件がある場合もあるため、事前に許認可と連動して準備するとスムーズです。
4-5. 宣伝・告知の導線づくり
ECサイトを構築しただけでは、ほとんどの人に存在を知られず埋もれてしまいます。そこで「いつ、どこで、どう告知するか」を考えることが必要です。SNS(Instagram、Twitter、Facebookなど)で新商品をアピールしたり、実店舗でレシートやチラシにECサイトのQRコードを載せるなど、幅広いチャネルを使って告知しましょう。
- SNSの活用:店舗の料理写真、メニュー開発秘話、スタッフの想いなどを発信→ファンづくり
- 実店舗での誘導:来店客に向けて「オンラインでも買えます!」と明示。テーブルPOPやレシートにURL掲載
- PR方法:プレスリリース配信、インフルエンサーへのサンプル提供、ローカルメディアとの提携 …など
特に飲食店はビジュアルが重要なので、SNSとの相性が良いです。食欲をそそる写真や動画、店舗のストーリーをうまく演出すると、ネット通販へのアクセスが一気に増える可能性があります。

その他の販促全体戦略については『【完全版】飲食店で効果の高い販促方法を総まとめ!売上や来店に繋がる手法を大公開!』の記事をご覧ください
4-6. 在庫管理システムやリピート販売戦略
いざECが軌道に乗って注文が増えると、次に直面するのが「在庫管理」と「リピート販売施策」の課題です。人気商品ほどあっという間に在庫切れを起こしやすく、「受注したのに在庫がなかった…」というトラブルに繋がるリスクがあります。これを防ぐには、注文データと在庫数をリアルタイムで連動させる仕組みが望ましいでしょう。
- 在庫管理ツール:Shopify等のASPであれば在庫管理アプリと自動連携が可能
- リピート戦略:定期購入コースを設定、リピート買いで割引やポイント付与、メールマガジンやLINEで再購入を促す
筆者が過去にコンサルした和食店では、「頒布会」の仕組みを導入して“月ごとに違う惣菜セット”を送る定期プランをスタートしました。すると、毎月の商品開発が大変ではあるものの、顧客は飽きにくく、リピーター率が大幅に向上したという結果が得られました。飲食店のECサイトが安定して売上を確保するには、このようにリピート前提の運営体制を築くことが重要です。
まとめ
ECを始めるための6ステップは「コンセプト設定→許認可→サイト制作→設備準備→宣伝→在庫・リピート運用」
第5章. 飲食店のECサイト運営で見落としがちな5つの落とし穴
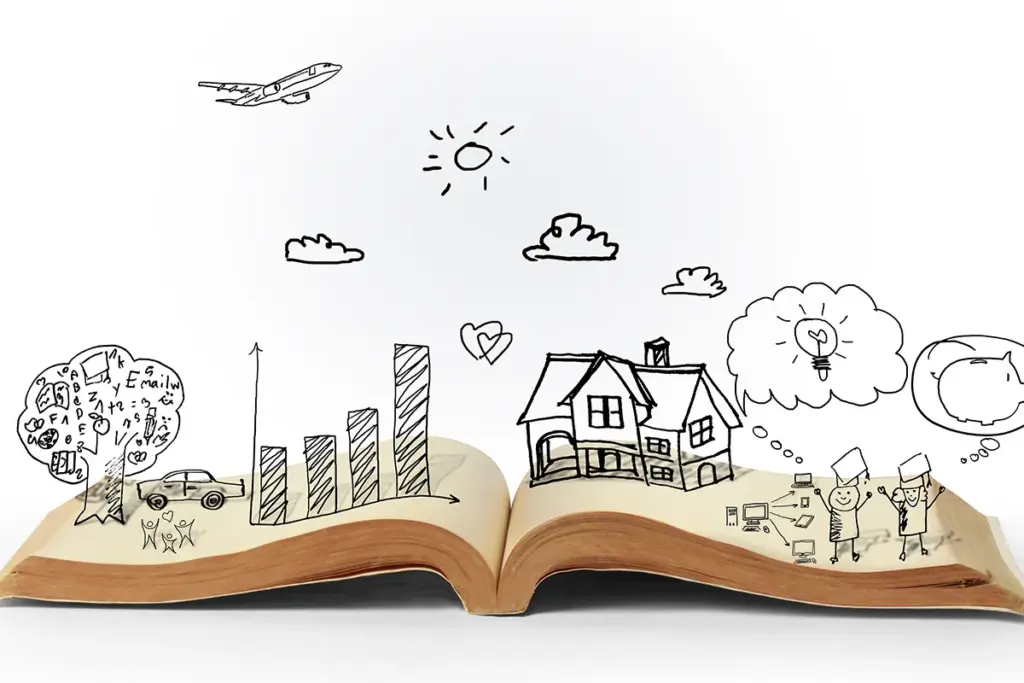
5-1. 設備投資や手数料などコスト面の把握不足
「ネット通販は無料サービスもあるからコストがかからない…」と考えていると、大きな落とし穴にはまる可能性があります。たしかにBASEなどのASPは無料プランが用意されていたり、モールによっては初期出店費用が安い場合もあります。しかし、実際に運営を続けると以下のような費用が積み重なってきます。
- ASPの手数料・月額費用:無料プランでも決済手数料が高めに設定されていることがある
- モールの販売手数料:売上の○%を取られるため、思った以上に利益が残らないケース
- 梱包資材・配送費:クール便やドライアイスなどは特にコストがかさむ
- 広告宣伝費:SNS広告や検索連動型広告で集客を図るときに予算が必要
- システム連携費用:在庫管理や顧客管理を効率化するには、有料ツールを導入する場合がある
5-2. EC担当のマンパワー不足
ECの運営は意外と手間が多く、片手間ではまわりません。商品の登録や価格調整、顧客からの質問対応、在庫管理、発送準備、梱包、配送手配など、細々とした作業が毎日発生します。これらを実店舗のスタッフだけで兼任すると、疲弊してクオリティが下がる可能性が高いです。
理想はEC専任の担当者を置くこと。予算的に難しければ、外部のEC運営代行サービスや物流代行、あるいはアルバイト採用などでマンパワーを補填する方法も検討してみましょう。「ECの立ち上げ時に人手をケチったばかりに、トラブル続きで悪評が立った」という例は少なくありません。ネット通販は一度クレームや低評価が広まると、巻き返しに大きな努力が要る点に注意してください。
5-3. 思うように集客できないジレンマ
ECサイトを始めたばかりの頃は、顧客を集めるのが最も難しい課題です。特に、モールを利用しない独自のECサイトは、検索エンジンで上位表示されるまで時間がかかり、その間にアクセスが全然来ない…という状況が発生しやすいです。飲食店のECに限らず、オンラインで売上を上げるには広告やSNSマーケティングが必要不可欠といえるでしょう。
- SNS広告(Instagram, Facebookなど):料理写真との相性が良く、特にターゲットを絞りやすい
- リスティング広告(Google Ads):具体的なキーワードで検索する見込み客にアプローチ可能
- SEO対策:商品名や地域名を絡めた検索対策を地道に施す
- 口コミ誘導:購入者に「SNS投稿するとクーポン」などの特典を設け、自然拡散を促す
SEO対策で検索上位に押し上げるテクニックなどは、『【完全版】飲食店のSEO対策攻略ガイド!店舗への集客効果や具体的な施策まで徹底解説!』の記事で解説しています。
マーケティングに予算をかけられない場合でも、実店舗の来客をECに誘導するだけでもスタートダッシュが可能です。店頭でECチラシを配ったり、レシートにQRコードを載せたりして、既存客のネット通販利用を促してみましょう。
5-4. 返品・クレーム対応
食品を扱うECは、衛生面や温度管理などの要因でトラブルが起きやすいのが実情です。「冷凍便なのに溶けていた」「真空パックが破損してソースがこぼれていた」といったケースでは、苦情処理や返品交換が発生します。実店舗なら店員がその場で対応できますが、ECでは配送に時間差があるため、問題の原因が特定しにくいのも難点です。
クレーム対策のポイント
- 返品ポリシー・交換ルールを事前に明文化する
- 商品到着後すぐに確認してもらうようアナウンスする(「問題があれば○日以内にご連絡ください」など)
- 運送会社との連携を密にし、配送温度帯の確認や破損リスクを最小化する
- SNSやレビューサイトで悪評が広がる前に、迅速に誠意ある対応をする
誇大表現は避け、商品の実態を正確に伝えることも大切です。クレーム対応が丁寧だと、むしろ好印象を残せる可能性もあるため、「トラブルが起きたときこそチャンス」と捉えて、マニュアル化を検討するとよいでしょう。
クレーム対応を含めた飲食店オペレーション整備のヒントは『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事をご覧ください。
5-5. セキュリティと個人情報保護
ECサイトで顧客の氏名・住所・クレジットカード情報などを扱う以上、セキュリティ対策を怠ると大問題に発展する恐れがあります。たとえ個人情報が流出しなくても、「個人情報保護方針が曖昧」「SSL(暗号化通信)が導入されていない」といった不安材料があると、顧客が購入をためらうことも少なくありません。
- SSL証明書の導入:サイトURLがhttpsになり、通信が暗号化される
- 個人情報保護方針の明記:プライバシーポリシーをわかりやすく提示
- 信頼できる決済代行会社の利用:大手の決済サービスを使うことで、セキュリティ面が向上
- アプリや顧客管理システムで権限設定をしっかり行う
飲食店が多忙な中でセキュリティ対策を後回しにすると、悪意のある攻撃や情報流出に遭遇するリスクが高まります。「面倒だから大丈夫だろう」と軽視せず、早めに専門家やシステム会社と連携することを検討しましょう。
第6章. 飲食店のECサイト運営に関してよくある質問

6-1. Q:テイクアウトとECって何が違うの?
A:テイクアウトは“すぐ食べられる”店頭受け取り、ECは全国発送や贈答用など“冷凍・常温”で保存できる商品がメインです。両方とも店舗外販売ですが、ターゲットや利用シーンがまったく異なります。ECは日持ちやパッケージデザインが重視され、客単価を上げやすいのも特徴です。
6-2. Q2:広告費にどれくらい投資すべき?
A:まずはSNS広告や検索連動型広告に小額からテスト出稿し、費用対効果を測るのがおすすめです。月3~5万円程度でもアクセス解析を行い、CPA(獲得単価)を見ながら調整すると良いでしょう。黒字が見込めたら徐々に増やすスタンスでリスクを抑えられます。
6-3. Q3:賞味期限が短い商品でもECは可能?
A:冷凍や真空パックなど加工を工夫すれば、賞味期限が短い総菜でも販売できます。また、配送スピードを上げたり、製造・発送日を限定する“予約販売”を導入する方法も。事前に保健所と相談し、衛生面と表示ルールをしっかり守れば問題ありません。
6-4. Q4:ECサイト制作を外注すると高額になりませんか?
A:本格的なデザイン制作やカスタマイズを依頼すると費用は数十万円~かかることも。ただしShopifyやBASEの標準テンプレートを使えば低予算で始められます。まずは最小限の投資からスタートし、売上に合わせて段階的に拡張する方法がおすすめです。
6-5. Q5:顧客情報の取り扱いで気をつけることは?
A:クレジットカードや住所など個人情報を扱うため、SSL証明書導入やプライバシーポリシーの明示が必須です。システム管理の権限は必要最小限に設定し、定期的にセキュリティ更新を行いましょう。万が一の流出事故が起きると信用回復が大変です。
6-6. Q6:イベント時の限定商品は効果ある?
A:クリスマスや母の日、お中元など季節イベント向け商品を打ち出すと注目されやすく、単価アップや新規顧客獲得に繋がります。SNSで事前告知し、数量限定販売やギフトセットを用意すれば“特別感”が生まれ、リピーターも増える可能性大です。
第7章. 飲食店こそ通販を上手に活用して売上アップを狙おう!
飲食店がECに挑戦する意義は、単なる売上補填にとどまりません。日本全国あるいは海外にまで商圏を拡げ、リスク分散や新たなファン層の開拓、ブランド価値の向上といった多面的なメリットが得られます。成功のカギは、まず目的や商品コンセプトをしっかり固めること。そして、保健所の許可や食品表示など法的要件をクリアしつつ、EC担当や在庫管理などの運営体制を整える点が不可欠です。
さらに、オーナー自らのストーリー発信やSNS・広告での集客、顧客データを活かしたリピート施策を積み重ねることで、安定したEC売上と実店舗への相乗効果が生まれます。補助金や代行サービスを活用しながら、小さく始めて大きく育てる――それこそが飲食店EC成功への最短ルートです。