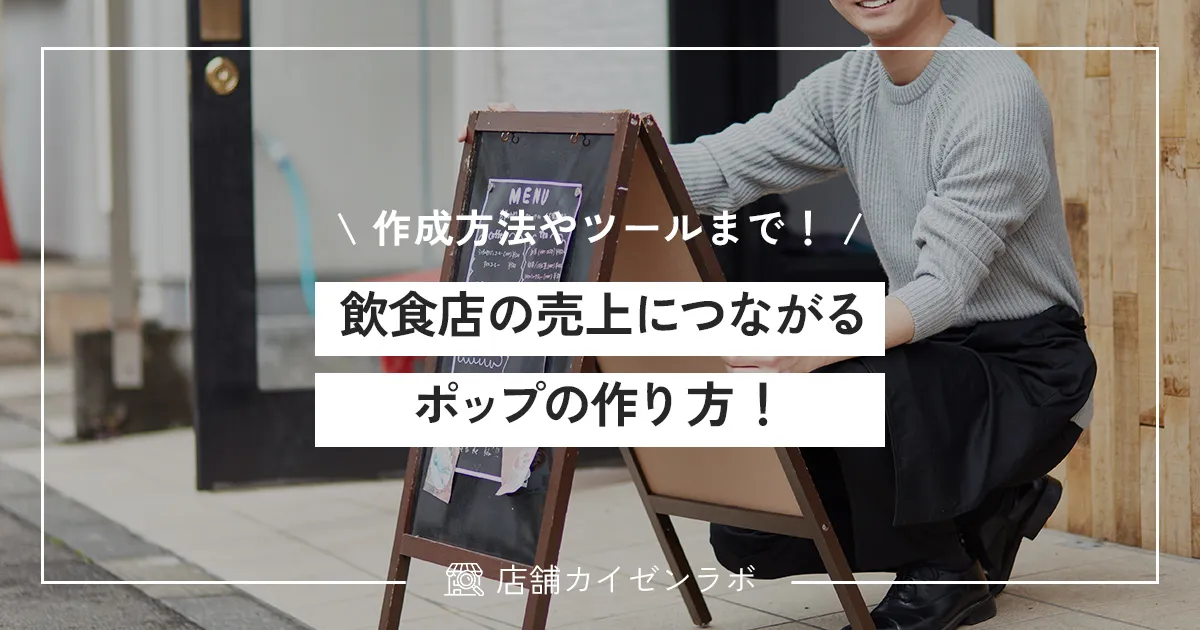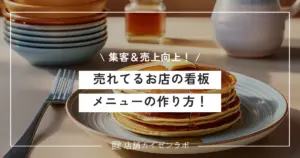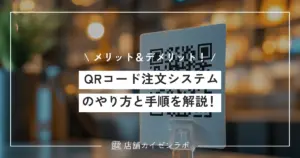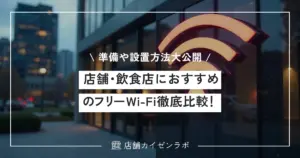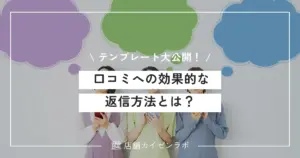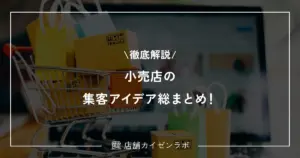第1章. 飲食店がポップを活用することの意義とメリット

1-1. 小さな投資で大きな集客効果が狙える
飲食店ポップは、広告費を最小限に抑えながら集客効果を高められる手段です。例えば、店頭でポップを見つけた通行客が「思わず気になって入店する」「人気メニューの存在を知って注文する」といった流れにつなげやすいのが最大のメリットです。
さらに、SNSやチラシなど外部メディアを使う場合と比較して、設置費用や維持コストが低い点も魅力。店舗内外の空きスペースを活用すれば、すぐにでも始められるため「まずはお試しで作成する」という飲食店にも最適です。
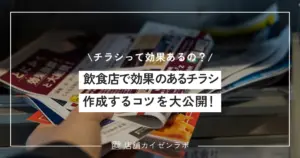
小さな立て看板や卓上POPだけで、客足が5%増えた事例もあり、わずかな初期投資でも十分に成果を期待できます。
ポップとSNSを連動させたい方は『飲食店がSNS運用をするデメリットと注意点!リスクを把握して炎上やトラブルを回避!』もぜひご覧ください。
口コミ事例:都内カフェ経営・Aさん
1-2. 客単価アップにもつながる“もう一品”の心理
飲食店ポップを店内に設置すると、追加注文を促す効果が大きく高まります。特に卓上POPは、席に座っている顧客の目に留まりやすいので「もう一品いかがですか?」とさりげなく誘導できるわけです。
たとえば、デザートやドリンク、季節限定メニューなど、あらかじめおすすめしたい商品の価格や写真をポップで見せておくと、「食後のデザートも頼もう」「今日はちょっと贅沢してみよう」といった心理をくすぐります。実際、卓上POPを導入した結果、デザートの注文比率が2割ほど伸びた飲食店も珍しくありません。
こうした“もう一品”の意識づけが、トータルの客単価アップにつながります。
第2章. 飲食店におけるポップの種類と最適な配置

2-1. 卓上POP・店頭POP以外にもある5つのバリエーション
飲食店ポップと聞くと、まず「卓上POP」や「店頭POP」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、壁面やメニュー表、さらには大型ポスターや吊り下げ型ポップなど、多彩なバリエーションが存在します。
- 壁面POP:壁に貼り付けることで、店内装飾も兼ねるタイプ。空き壁を使って季節メニューを紹介すると注目度がアップ。
- メニュー表POP:メニュー自体に写真やシズル感のあるキャッチコピーを入れ込んで、読ませる仕掛けを強化。
- 吊り下げ型POP:天井から吊り下げて視線を誘導。大きめのサイズで遠くからでも目立ちやすい。
- ポスターパネル型:入口やレジ周辺で、キャンペーンやイベントの存在を強くアピールできる。
- スタンド看板型:店舗前の歩道や商業施設内で、通行人に向けて直接アプローチする手段として有効。
それぞれの用途や置き場所によって、訴求力やターゲット層が異なるため、メニューの特徴や客単価、導線に合わせて使い分けるのがポイントです。
店頭での集客を強化したい方は『集客が増える店舗の入口とは?入りたくなる飲食店の外観の特徴や共通点を徹底解説!』もご参照ください。
筆者体験談:注文増加テクニック
2-2. 効果を2倍にするポップの置き方と時間帯別の差し替えテク

ポップの種類を決めたら、次に重要なのが「具体的な置き方」と「差し替えタイミング」です。店頭POPは通行客を呼び込みやすく、卓上POPは追加注文を促す効果が高いといった役割分担を理解したうえで配置を考えましょう。
実際に、ある和食チェーン店ではランチタイムとディナータイムで卓上POPを切り替えています。昼は日替わり定食やお得セットをアピールし、夜はお酒やおつまみ系を強調するデザインに変更。その結果、ランチタイムの定食追加率と夜のドリンク注文数がともに10%以上伸び、店舗全体の売上アップに成功しました。これが時間帯別ポップ戦略の典型的な成功例といえます。
「ポップを変えるのは手間…」と感じるかもしれませんが、一度運用ルールを決めてしまえば慣れてくるものです。POPの効果を最大化するために、時間帯ごとのターゲット層や客層を整理し、必要に応じて使い分けるようにしましょう。
ポップだけでなく接客も強化したい方は『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』もぜひ。
第3章. 飲食店が効果的なポップを作成する5つのステップ

3-1. 宣伝するメニューの魅力とターゲットを明確化する
飲食店ポップの作成において最も重要なのは、「何を、誰に向けて訴求するのか」を明確にすることです。おすすめメニューの魅力を最大限に伝えたいのか、キャンペーンの告知で集客したいのか、目的によって伝え方は変わります。さらに、ターゲットが女性客なのか、ファミリー層か、ビジネスパーソンかによっても最適な言葉やデザインは異なります。
例えば、筆者が働いていた店舗では、女性向けの低糖質スイーツを導入した際に、店内ポップで「体にやさしい」「砂糖不使用」を大きく打ち出しました。その結果、健康志向の方からの注文が増え、一部地域からわざわざ買いに来るリピーターも獲得。ターゲットを明確化し、それに即した訴求ポイントを強調することで成果は大きく変わります。
推しメニューを打ち出すなら『売れてるお店の看板メニューの作り方!集客や売上向上に繋げるには?』も参考になります。
3-2. 逆ピラミッド法とシズルワードで視線を奪うコピーライティング
ポップを作るうえで、「短く」「強く」「わかりやすい」コピーが欠かせません。まずはキャッチとなる大見出しで目を引き、その下に補足情報を簡潔に入れる“逆ピラミッド法”がおすすめです。
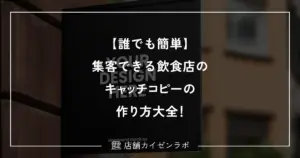
また、「香ばしい」「とろける」「ジューシー」といった五感を刺激するシズルワードを使うことで、文字だけでも食欲や興味をかき立てやすくなります。ただし、誇大表現は逆効果となる場合があるので、事実をベースにした表現を心がけましょう。
3-3. 写真・イラストで“おいしさ”を伝えるビジュアルづくり
人は視覚情報から受ける印象が非常に大きいため、写真やイラストの活用は必須です。美味しそうな写真があれば、一目で「食べてみたい!」と興味を引きつけられます。写真撮影が難しい場合も、フリー素材やイラストをうまく使ってポップを彩ると、メニュー自体の魅力をアップさせられます。
最近では「Canva」など無料のデザインツールで簡単に画像を加工できます。お店の雰囲気やブランドイメージを保ちつつ、一貫したテイストを意識するとクオリティが高く見えるでしょう。
ポップで統一感を出したい方は『飲食店がやるべきブランディングとは?成功事例から学ぶ店舗の差別化戦略を徹底解説!』もご一読ください。
3-4. わかりやすい価格表示と限定性を強調して行動を後押し
価格設定はお客が最も気にするポイントの一つです。あえて価格を大きく表示することで「こんなに安いんだ!」と驚かせたり、「期間限定・数量限定」などの限定性を加えると「このタイミングを逃せない!」という心理を動かせます。
たとえば、「本日限定!先着20食だけ特別価格」といったポップを出したお店では、開店直後から注文が集中し、早い時間帯に完売する事例もあります。限定性は強力な武器になるため、活用できるシーンがあれば積極的に盛り込みましょう。
3-5. 配置場所の最終確認と継続的な効果検証
ポップが完成しても、置く場所を間違えると台無しです。店内導線を考慮し、あえてレジ横に小さいポップを置くことで「会計前に気付いてもらう」戦略をとる店舗もあります。特に卓上POPは、テーブルが狭すぎると邪魔になるので大きさとのバランスが重要です。
また、ポップを設置して終わりではなく、「実際に追加注文は増えたか?」「新規客は増えたか?」などをデータで検証し、必要があれば内容や配置を変えていきましょう。継続的に試行錯誤を続けることで、効果がどんどん高まっていきます。
ポップ管理も含めた業務効率化には『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』が役立ちます。
第4章. 飲食店のポップ作成で使える!無料&有料ツールまとめ!

4-1. パソコンでイチから作る人向けのおすすめソフト4選
「飲食店ポップ」を自作するには、まず定番のPCソフトを使いこなす方法があります。WordやPowerPointは操作が比較的簡単で、文字や画像を配置するだけでそこそこのクオリティに仕上がるのが利点です。さらにPhotoshopやIllustratorは、有料ながら高度なデザイン機能や豊富なフォントを使えるため、よりプロっぽい仕上がりを追求する方に向いています。
- Word
文章編集に特化しており、表や画像の挿入も容易。無料テンプレートを追加することで簡単にポップを作ることができます。 - PowerPoint
スライド制作ソフトですが、自由度が高くレイアウトの整理がしやすいのが特徴。アニメーション機能をオンにすれば、デジタルサイネージ的な活用も視野に入ります。 - Photoshop
写真加工が得意なので、料理写真の明るさや色味の調整に役立ちます。SNS映えするビジュアルが欲しい飲食店におすすめ。 - Illustrator
ロゴやイラスト制作、文字装飾が得意。こだわりのブランドイメージを追求したいときに最適です。
これらソフトは機能が豊富ゆえに、最初は戸惑うこともあるかもしれません。とはいえ、ネット検索すれば多数の操作ガイドが見つかるので、独学でも十分習得可能。店舗のオリジナリティを打ち出したいなら、時間をかけてマスターする価値があります。
4-2. デザイン初心者でも即戦力!POP無料テンプレート5選
一方、あまり時間をかけたくない方やデザインに自信がない方には、無料テンプレートを活用するやり方がおすすめです。ここでは代表的な5つのサービスを取り上げます。
- Canva
豊富な無料デザイン素材とフォントを備えたクラウド型ツール。ドラッグ&ドロップで簡単にポップを作れます。 - POPKIT
イラストや文字素材を「組み合わせるだけ」でポップが完成。筆者もいちど使った際は、初回登録から10分未満でデザインを仕上げられました。 - BuzzFood
飲食店向けのテンプレが充実しているのが強み。メニューPOPや卓上POPのひな形があり、そのまま書き換えるだけで即戦力に。 - でき太
日本語フォントや手書き風デザインに力を入れており、温かみのあるポップを出したいときに相性抜群。 - Picky-Pics
素材のバリエーションが豊富で、写真加工機能も充実。料理写真をおいしそうに見せる工夫がしやすいと口コミで高評価。
これらツールは無料プランでも十分実用的ですが、追加で有料素材を購入できるショップラインも用意されていることが多いです。まずは無料範囲で試してみて、自分のお気に入りを見つけてみましょう。
口コミ事例:Bさん・レストラン経営
4-3. 外注を検討するなら?デザイン会社・印刷会社選びのポイント

もし時間やスキルの問題で自作が難しい場合は、専門のデザイン会社や印刷会社へ外注する方法もあります。プロの視点でコンセプトからサポートしてもらえるため、クオリティが高く、納期も最短スケジュールで仕上げてもらえるケースが多いのがメリットです。
- 価格と納期を事前に確認
見積もり時にデザイン費や印刷費、送料などを詳細にチェックしましょう。一部地域への配送が対象外となることもあるので注意が必要です。 - ポートフォリオや口コミを参考に
依頼したいデザイン会社が、飲食店ポップやメニュー表の実績を多数持っているかどうか、事前に事例を見せてもらうと安心です。 - 打ち合わせで狙いを明確に
「どんな顧客層にアピールしたいのか」「店舗の雰囲気はどうか」「具体的な商品の特徴は?」などを整理し、デザイン会社と共有しておくことで、イメージのズレが大幅に減らせます。
印刷物をオーダーした後、実際のPOP設置までのスケジュール管理や在庫調整なども発生するため、飲食店の繁忙期を避けて早めに依頼するのがベター。長期的なパートナーとして付き合える会社が見つかれば、季節のキャンペーンごとに新しいポップを依頼するなど、継続的な販促強化が期待できるでしょう。
第5章. 飲食店のポップに関してよくある疑問6選

5-1. Q1:お客の目を引くために文字を多く入れすぎましたが、逆に読まれません。
A:情報量が過多だと視線が散り、読む前にスルーされがちです。要点を整理し「大見出し+短い説明+写真」の構成が理想。価格など重要項目を強調し、シンプルな配色でデザインすると伝わりやすくなります。
5-2. Q2:インパクト重視でカラフルな配色にしたら、逆にポップがごちゃついて見えます。バランスのコツは?
A:メインカラーを1~2色に絞り、文字色や背景色にコントラストを持たせると読みやすくなります。背景と文字の色が似ていると印象がぼやけるため避けましょう。客単価アップを狙う商品ほど配色に注意し、要点が目に飛び込むレイアウトを意識してください。
5-3. Q3:店舗入口に派手な看板を設置しているのに、なぜか注文につながりません。原因は?
A:入口のポップは通行客を呼び込む効果は高いものの、店内メニューとのつながりが曖昧だと注文増に直結しません。店頭POPで興味を持った人が、店内で同じメニューをさらに詳しく知れるよう、卓上POPや壁面ポップで連携を取るのがカギです。
5-4. Q:朝と夜の客層が全く違うのに、同じポップを使い回してしまっています。やはり問題ありますか?
A:時間帯ごとにニーズが変わる飲食店では、ポップを差し替えるほうが効果的です。たとえば朝はサンドイッチやコーヒー、夜はアルコールやおつまみ系を強調するとスムーズに追加注文が期待できます。小さな手間で、売上へのインパクトが大きく変わります。
5-5. Q:新メニューの宣伝ポップを置いたのに全然売れません。なにが足りないのでしょう?
A: 料理写真やイラストが不足していると“魅力”が伝わりにくいです。さらに、価格や量など具体的な情報が明示されていない場合も、注文に踏み切れない原因になります。シズル感のある写真とわかりやすいコピーを一緒に配置し、試してみたい気持ちを刺激しましょう。
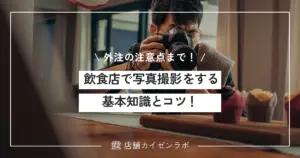
5-6. Q:同じポップをずっと置きっぱなしでいいですか?面倒なので変えていません。
A:見慣れたポップは“そこにあるだけ”になり、訴求力が下がります。新鮮味を与えるには定期的なデザイン更新が効果的。季節やイベントに合わせて小さな変更を加えるだけでも再注目され、リピーターの来店意欲を高められます。
第6章. POPを上手に活用して飲食店の売上を高めよう!
飲食店ポップは、集客から追加注文、リピーター獲得まで多面的に効果を発揮する便利な販促ツールです。しかし最大限の成果を出すには、ターゲットに合わせて内容や配置を柔軟に変え、客の動向を常に検証し続けることが重要になります。特に卓上POPと店頭POPの連動や、時間帯別・季節別の差し替えが売上拡大のカギ。
さらに自作ツールや無料テンプレートの活用、専門家への外注など、状況に応じた手段を選ぶことで、デザインや導入コストを最適化できます。新メニューやキャンペーンの情報はもちろん、キャッシュレス決済OKの案内やスタッフ用オペレーションマニュアルとしての活用など、応用範囲は広がる一方。自店ならではの創意工夫をこまめに盛り込み、継続的な改善を図ることで、飲食店ポップの力を最大限に引き出しましょう。
キャッシュレス対応をわかりやすく伝えたいなら『【2025年最新版】オールインワン決済端末を徹底比較!コスパ最強のおすすめ端末8選もご紹介!』もご覧ください。