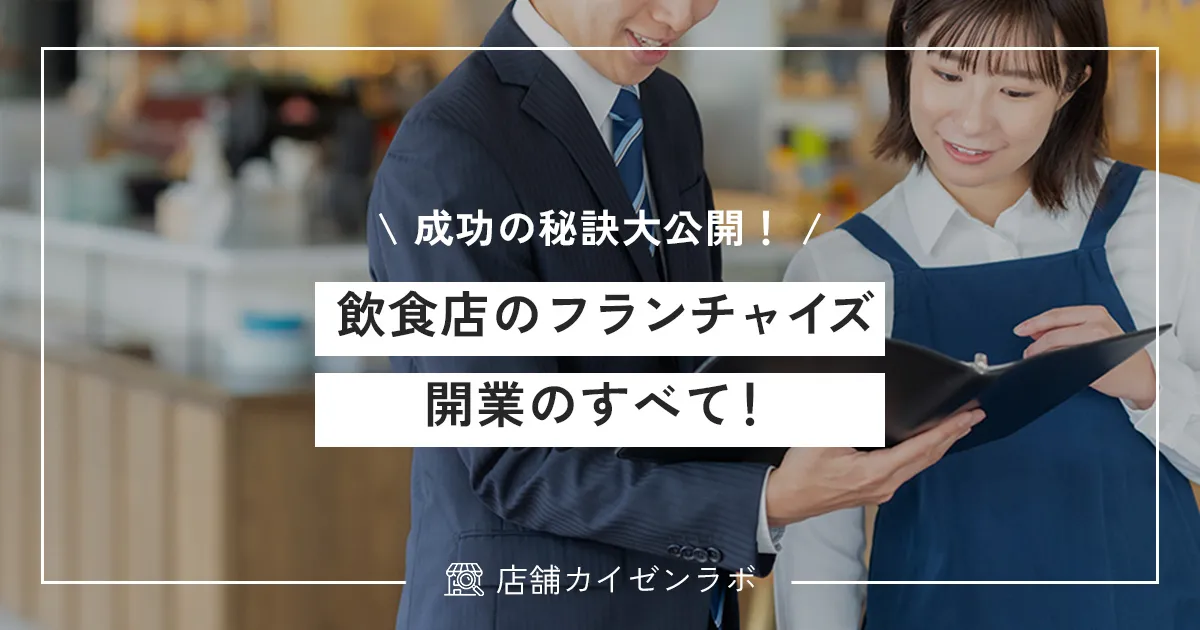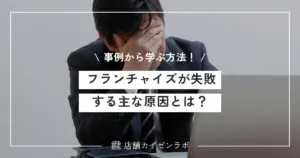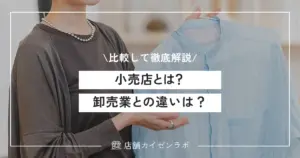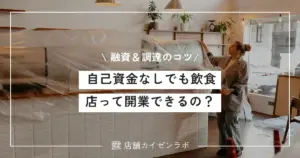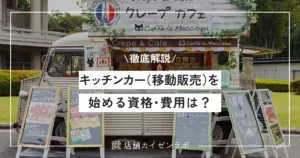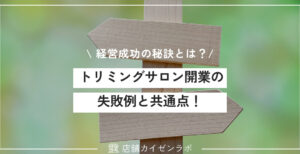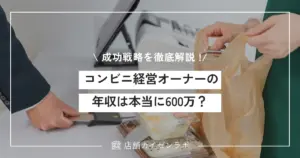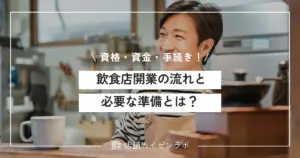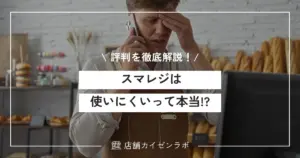第1章. 飲食店フランチャイズの基本と概要

1-1. フランチャイズとは何か?基本的な仕組み
フランチャイズ(FC)とは、本部が培ったブランドやノウハウを独立した加盟店に提供し、加盟店オーナーは一定のロイヤリティや加盟金を支払う代わりに本部の看板やマニュアルを使って飲食店を運営するモデルです。
飲食店フランチャイズでは、具体的なレシピや衛生管理、接客マニュアルなどが用意されているため、業界未経験でも比較的スムーズに開業できるメリットがあります。本部としては、加盟店の資金を活用して全国展開を加速しやすく、加盟店側は成功実績のあるブランドに乗ることで顧客を獲得しやすい、いわゆる“Win-Win”が期待できる仕組みです。
1-2. フランチャイズの歴史と海外事例
フランチャイズの起源としては、アメリカでのハンバーガーチェーンやフライドチキンチェーンが有名です。1950年代から一気に普及した背景には、都市化や車社会の発展と相まって、同じクオリティの料理をどこでも食べたいという需要が高まったことが挙げられます。
日本へは1970年代ごろから外食チェーンのフランチャイズが浸透し始めました。コンビニエンスストアのFC化でノウハウが蓄積され、続いて飲食店も多種多様なジャンルが参入。現在ではラーメン、居酒屋、ファーストフード、カフェなど、幅広い業態がフランチャイズで展開されるまでに成長しています。
1-3. 飲食店フランチャイズが伸びる背景

飲食店のフランチャイズが伸び続けるのは、衛生管理や調理工程など専門的なノウハウを本部が整えられるからです。個人で独立開業すると、仕入れルートやメニュー開発、接客マナーまでイチから構築しなければなりません。
一方、フランチャイズではすでに完成度の高いメニューとマニュアルを使えるため、開業リスクが低減しやすいのが特徴です。さらに本部による大規模な広告展開や共同仕入れも、加盟店にとって強力な後押しとなり、“小資本で早期に軌道に乗せたい”と考える経営志向と合致しやすいのです。
第2章. チェーン店の種類とは?レギュラーチェーンとフランチャイズチェーンの特徴と違い!

2-1. レギュラーチェーン(直営店)の特長と投資リスク
レギュラーチェーンとは、企業(本部)が資金を出して店舗を運営する形態です。ブランド統一や品質管理の徹底がしやすく、マニュアルや販促企画も一元管理で行うため、店舗ごとのバラつきが少ないのが利点。
しかし、投資リスクは本部が全面的に負うことになるため、急速な店舗拡大は資金面のハードルが高くなる傾向があります。特に飲食店は内装費や厨房機器など初期コストが大きく、直営のみで全国チェーンを実現するには莫大な資金が必要です。
2-2. フランチャイズチェーンの特徴 — 投資分散とオーナーの独立支援

フランチャイズチェーンでは、本部がブランドとノウハウを提供し、店舗投資や日々の運営資金は加盟店オーナーが負担します。そのため、資金負担が分散されることで短期間で多店舗展開を狙いやすいメリットがあります。
加盟店にとっては、認知度の高いブランド看板と、接客や調理など各種マニュアルを活用できるため、ゼロから始めるよりリスクが低め。飲食店のフランチャイズでは、本部がスーパーバイザー(SV)を派遣して定期的に経営指導を行い、オーナーの独立支援を行うところが多いです。
2-3. 直営からフランチャイズへ転換するケース
一部の外食企業では、最初は数店舗の直営でブランドを育て、その後にフランチャイズ化する流れが一般的です。ある大手ラーメンチェーンも、最初は十数店舗の直営のみでしたが、知名度向上を受けてフランチャイズ展開へ踏み切り、今では数百店舗を超えるチェーンに成長しました。
このように、直営で培った“メニューの安定性”や“ブランドイメージ”を武器に、加盟希望者を募集する戦略は、飲食店ではよく見られる成功パターンです。
筆者の体験談:マニュアル整備は必須
筆者のような失敗を防ぐには、『フランチャイズオーナーが失敗する主な原因とは?事例から学ぶ悲惨な結末を避ける方法!』も参考にしましょう。
第3章. 飲食店におけるフランチャイズ契約とライセンス契約の違いとは?

3-1. 契約期間・更新条件のチェックポイント
フランチャイズ契約は、一般的に3〜10年程度の契約期間が設けられます。期間満了時には「更新料が発生する」「更新しなければ看板やメニュー名を変更しなければならない」など、契約書に詳しい条件が定義されている場合がほとんどです。
また、飲食店においては店舗改装のスパンや衛生基準の変更など、追加投資が必要になるタイミングがあるため、契約時に更新条件や解約時のルールを念入りに確認しておくことが大切です。
3-2. 開業後のサポート範囲 — 研修・SV制度の有無
フランチャイズ契約では、本部が事前研修やオープン後のスーパーバイザー巡回など手厚い支援を提供するのが一般的。飲食店フランチャイズの場合、食材発注やスタッフの教育マニュアル、オペレーション改善など、細かな部分までサポートしてもらえるところが魅力です。
対照的にライセンス契約は「商標の使用権」を得るのがメインで、本部による研修や販促支援が限定的なことが多いです。飲食の現場で細かいノウハウを求める場合は、手厚いサポートを期待できるフランチャイズ契約のほうが無難でしょう。
本部の研修以外にも、『飲食店の新人教育の完全マニュアル!店舗スタッフに必要な接客や仕事の研修方法を徹底解説!』を押さえておくと安心です。
3-3. ライセンス使用料とロイヤリティの差
ライセンス契約は、一度の使用料(あるいは期間ごとのライセンスフィー)を支払えば、ブランド名や商標を使える形が一般的。本部としても細かい経営介入は行わないため、オーナーにとっては経営の自由度が高い一方、集客やメニュー開発などを自力で工夫しなければなりません。
フランチャイズ契約では、毎月ロイヤリティを払う代わりに、広告・マーケティングやメニュー開発、共同仕入れなどのサポートが受けられるのが大きな違いです。飲食店では仕入れコストが利益を左右するため、本部が共同調達で食材を安く提供してくれる場合、ロイヤリティを払ってもトータルで得になることが少なくありません。
3-4. 経営自由度とブランド統一性のバランス
ライセンス契約だと「内装」「メニュー開発」「営業時間の設定」などである程度自由が利きますが、フランチャイズでは本部が決めたブランドルールを守る必要があります。飲食店で大事なのは、店ごとの味やサービスレベルが大きくブレないこと。ブランドイメージの統一が集客力に直結するため、オーナー独自の変更が難しい面もあるでしょう。
ただし、FC契約でも一部メニューは地域限定で開発OKなど、裁量を与える本部も存在します。結局は、オーナーがどこまで自由度を求めるかと、本部が提示する契約条件が合致するかどうかがポイントです。
第4章. フランチャイズの加盟金とロイヤリティの仕組み

4-1. 加盟金の内訳と相場 — 何に使われる費用なのか
飲食店フランチャイズに加盟するとき、最初に大きく支払うのが加盟金です。一般的には、ブランドの使用権や研修費、マニュアル作成のコストなどが含まれ、本部が長年かけて構築してきたノウハウを活用する権利を得るための費用と考えられます。
相場としては、居酒屋チェーンで100〜300万円程度、カフェ系で50〜150万円程度が目安ですが、同じ業態でも企業ごとに大きく変わります。また、加盟金とは別に物件取得費や内装費、厨房機器などの設備投資が必要となるため、トータルの初期資金を把握しておくことが肝要です。
4-2. ロイヤリティで受けられるサポート — 広告や運営指導

加盟後、毎月支払うロイヤリティは、本部のサポート費や広告費に充てられることが多いです。特に飲食店フランチャイズでは、季節ごとの新メニュー開発やレシピ改良、テレビCMやSNS広告などが継続的に行われ、本部と加盟店が共同でブランド力を向上させる仕組みを持っています。
また、店長向けの研修会やスーパーバイザー(SV)の巡回指導などもロイヤリティでまかなわれるケースが一般的。飲食店経営で必須の衛生管理や接客マナーのチェックも含め、本部の定期サポートが得られる点は大きなメリットです。
4-3. 保証金や違約金が発生するケース
契約時に保証金の支払いが求められるフランチャイズもあります。これは、本部が加盟店の契約トラブルや、設備の原状回復費などに備えて預かる形。契約満了や解約時に返金される場合もあれば、解約タイミングや違約内容次第で差し引かれることもあるので、契約条項をしっかり確認しておきましょう。
違約金に関しては、途中解約した場合や契約不履行があった際に発生する可能性があります。特に内装や備品はブランドイメージを統一するため、本部指定の業者や規格で施工していることが多く、解約後の原状回復費用が大きくなる例も珍しくありません。
月々の負担を軽くするには、『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』も参考にしてください。
4-4. 加盟金・ロイヤリティを抑えるコツ
最近では「ロイヤリティ無料」を看板にするフランチャイズが注目を集めていますが、仕入れマージンや広告費など、別の形で本部が収益を確保しているケースが多々あります。加盟金やロイヤリティが低いという理由だけで飛びつくと、トータルコストで逆に高くつく可能性もあるため要注意です。
また、本部が期間限定キャンペーンを行っている場合、加盟金や研修費の一部が割引になることがあります。少し時期をずらすだけで数十万円お得になるケースもあるので、契約時期の見極めも飲食店開業の大事なポイントです。
開業資金が不安な方は、『自己資金なしでも飲食店って開業できるの?融資・調達のコツや費用を抑える方法まで!』をチェックしましょう。
第5章. 飲食店フランチャイズにおける5つのロイヤリティの種類
5-1. 売上歩合方式 — 繁忙期ほどロイヤリティが上がる?
売上歩合方式では、月間売上に対して数%のロイヤリティを本部に支払う形です。売上に比例するため、売上が低いときには負担も軽く済む一方、繁忙期や特別キャンペーンで売上が跳ね上がるとその分ロイヤリティ額も増えてしまいます。
飲食店は季節や立地条件で売上が大きく変動することが多いです。特にイベントが集中する観光地や飲食街で売上ピークを迎えるオーナーは、「急にロイヤリティ負担が増えた」と感じやすいので、繁忙期の資金繰りを念頭に置くことが大切です。
5-2. 定額方式 — 売上が伸びるほどオーナーが得をする
定額方式は毎月○万円といった固定ロイヤリティを支払うため、売上が上がれば上がるほどロイヤリティ比率が下がり、オーナーの利益拡大につながりやすい形式です。
一方、売上が不調の月でも同額を支払わなければならないため、開業初期の立ち上げが安定しない時期は負担感が大きい可能性があります。定額方式が向いているかどうかは、自店舗の売上が季節変動に強いか弱いか、平常時の集客力がどの程度見込めるかによって変わってきます。
5-3. 粗利分配方式 — 食材コストが命運を握る
粗利分配方式は、売上から原材料費を差し引いた粗利額を基準にロイヤリティを計算します。飲食店の粗利は食材相場や仕入れルートによって上下するため、加盟店側が原価管理をしっかりできればロイヤリティを抑えられるメリットがあります。
ただし、食材価格が急騰したとき、オーナー負担が増えるのか本部負担が増えるのかは契約内容次第。飲食店においては、原価率が1〜2%変化するだけで年間利益に大きな差が出るため、粗利分配方式を選ぶなら細部まで契約を確認しましょう。
5-4. ロイヤリティフリー — 表面的には安いが注意!
ロイヤリティフリーのフランチャイズ本部も一見魅力的ですが、食材仕入れで上乗せしている場合や、広告費・システム使用料という名目で別途徴収しているケースが多いです。
飲食店は仕入れコストの比率が高いので、もし仕入れ価格が相場より割高だと、長期的には通常のロイヤリティ方式より負担が大きくなる恐れもあります。表面的な無料をアピールしていても、実質どれだけコストがかかるのかをきちんと試算するのが賢明です。
5-5. 複合方式・特例 — メーカータイアップや変動制ロイヤリティ
メーカーの協賛を受けたタイアップ型フランチャイズや、一定売上を超えたら追加の歩合が発生する“変動制ロイヤリティ”を採用している本部もあります。こうした特殊モデルは、業態やエリア特性にマッチすれば非常に有利に働きますが、契約書の細部を読み違えると不利になるリスクがあります。
加盟前には、実際に同じモデルで運営しているオーナーや先輩店舗にコンタクトを取り、実状や収益構造を聞いておくことをおすすめします。
第6章. 種類別に見る!飲食店のフランチャイズ業態を比較!

6-1. 併設型のポイント — 複数メニューで客単価UP
併設型とは、一つの店舗でメイン業態+サブ業態を組み合わせる形です。たとえばラーメン店とからあげコーナーを併設したり、居酒屋とカレー専門コーナーを併設するといった具合。
メリットは、客層を広げて単価アップや回転率向上を狙いやすい点。しかし、調理動線が増えてオペレーションが煩雑化するデメリットもあるため、マニュアル化やスタッフ教育が欠かせません。
6-2. フリーネーム型 — 自由度を活かして地域密着
フリーネーム型は、本部のノウハウや食材供給を受けながらも、店舗名やロゴをオリジナルで展開できる方式です。全国的に画一的な看板を出す従来型とは異なり、地域ならではの名前やメニューを前面にアピールできるのが魅力。
ただし、「本部のブランド力を利用した集客」が得にくいという弱みもあります。看板の自由度が高い分、地元客をどう引き込むかがオーナーの腕の見せどころになるでしょう。
6-3. テイクアウト特化・キッチンカー
ここ数年で、飲食フランチャイズの中でもテイクアウト専門やキッチンカーの案件が増加中です。コロナ禍によって持ち帰り需要が高まり、固定店舗だけでなく移動販売で売上を稼ぐスタイルが脚光を浴びています。
キッチンカーは、飲食店を構えるよりも低初期費用で始められる一方、天候やイベントの有無で売上が大きく左右されるデメリットがあります。本部が仕入れや調理マニュアルを整備してくれる分、未経験者には参入ハードルが下がりますが、移動先のリサーチや許認可手続きに注意を払う必要があります。
キッチンカーの開業に興味がある方は、こちらの『キッチンカー(移動販売)を始めるには?開業に必要な資格・費用など準備の方法を徹底解説!』も参考にしてください。
6-4. 新たなトレンド業態 — カフェ×スイーツ、バー×デリバリー
昨今は、昼夜で異なる客層を取り込む“複合業態”も増えています。たとえば昼はカフェタイムでスイーツを提供し、夜はバーとしてお酒と軽食を提供する形です。こうした業態を想定したフランチャイズ本部もあり、どちらの時間帯でも売上を確保する戦略が取れるのが特徴。
ただし、運用オペレーションは当然複雑になりますし、スタッフのシフト管理や内装設備も二面性を意識したものが必要です。マニュアルがある程度柔軟に対応できる本部かどうかを見極めることが、複合業態の成功を左右します。
第7章. 飲食店のフランチャイズが向いている人の特徴とは?
7-1. 素直に本部ノウハウを吸収できる人
飲食店フランチャイズでは、調理手順や接客方法を細かくマニュアル化している本部が多いため、その内容を素直に実践できるオーナーが成功しやすい傾向にあります。
「自分のやり方が絶対だ」というタイプよりも、まずは本部の指導をきちんと受け止め、軌道に乗ってからオリジナル要素を加えていくような柔軟性がある人が向いています。スタッフの教育やメニュー展開なども、本部の指示に忠実に再現すれば、比較的早期に売上が安定しやすいでしょう。
7-2. 強い責任感 — クレームやスタッフ管理を乗り切る
飲食店は長時間営業やクレーム対応など、日々の運営でトラブルが発生しやすい業種です。特に衛生面のトラブルはブランド全体を揺るがす可能性もあるため、オーナーとして高い責任感が求められます。
スタッフ採用や教育においても、アルバイトが短期で辞めてしまうケースが少なくありません。そうした人材確保・人材育成を怠らずに取り組める、粘り強いオーナーが最終的に店舗を軌道に乗せやすいと言えます。
7-3. 学習意欲と経営改善力 — データ分析が成功を呼ぶ
本部のマニュアル通りに運営していると、ある程度安定した売上は見込めます。しかし、周辺競合や季節の変化など、飲食店を取り巻く環境は常に動いています。そこで必要となるのが、売上データや顧客動向を自ら分析して改善する力。
たとえば客単価が伸び悩んでいれば、サイドメニューを追加するのか、割引キャンペーンで回転率を上げるのかといった戦略を練って本部に提案・相談できるオーナーが成果を出しやすいです。筆者が知る成功オーナーは、月次レポートを熟読し、本部のアドバイスを受けつつも自店の創意工夫を欠かしません。
成功するFC経営にはKPIの運用も重要です。詳しくは『飲食店が設定すべきKPIとは?本当に効果的な目標や指標の設定方法と活用術を徹底解説!』をご覧ください。
7-4. 人材マネジメントを楽しめる人
飲食店は接客業であると同時に、多くの場合はアルバイトやパートスタッフが店舗の要となります。スタッフが気持ちよく働ける環境を整え、意欲的に仕事へ向かってくれるよう仕組みを作れるオーナーは、結果として離職率を下げて業績を安定させることができます。
フランチャイズのマニュアルで業務フローは標準化されても、スタッフ同士のコミュニケーションやモチベーション管理まではオーナーの力量次第。人材マネジメントを苦に感じず、一緒に店舗を盛り上げる喜びを見いだせる人が、飲食店フランチャイズでは成功しやすいと言えます。
7-5. あなたに合ったフランチャイズを見つけるには?
フランチャイズビジネスは、本部ごとに契約内容やサポート体制が大きく異なります。自分に合った業態・ブランドを見つけるためには、複数のフランチャイズ本部を比較検討することが成功への第一歩です。
BMフランチャイズでは、100件以上の優良フランチャイズ本部を簡単に比較でき、資料請求は何件でも無料。商工会議所が運営する「ザ・ビジネスモール」から派生したサービスで、信頼性の高い情報を提供しています。
- 飲食店だけでなく、多様な業種から選択可能
- 無料で複数社の資料を一括請求
- 専門コンサルタントによる起業セミナーも開催
まずは気になるフランチャイズの資料を取り寄せて、初期投資やロイヤリティ、サポート内容を具体的に比較してみましょう。
➡︎フランチャイズ比較をしてみる第8章. 飲食店のフランチャイズに関してよくある疑問

8-1. Q1:未経験でも飲食フランチャイズに参入できますか?
A:飲食業の経験がなくても、マニュアルや研修制度が整ったフランチャイズなら十分参入可能です。特に調理や接客を細かくガイドしてくれる本部を選べば、ゼロからでもオペレーションを学べます。ただし、資金面やスタッフ管理など経営者としての責任は重いので、事前に研修や本部サポートをしっかり確認しましょう。
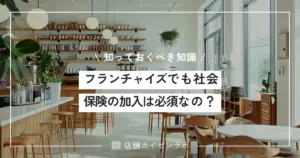
8-2. Q2:ロイヤリティが高いと感じたらどうすればいい?
A:ロイヤリティは一見コストに見えますが、広告やメニュー開発など本部が担う業務を分担できるメリットがあります。もし高いと感じるなら、共同仕入れで食材原価が下がっているか、ブランド力向上による売上増が見込めるかを再検討しましょう。トータルでプラスなら、むしろ投資と考える方が賢明です。
8-3. Q3:テイクアウト特化型のFCは儲かる?
A:テイクアウト特化は初期投資が比較的抑えられ、少人数でも運営しやすい利点があります。持ち帰り需要が増えた今の市場では有望ですが、立地選定や商品パッケージのクオリティが重要です。集客力を維持するためにも、本部の販促支援やSNS活用のノウハウをうまく利用すると安定した売上を見込みやすくなります。
8-4. Q4:フランチャイズを解約したい場合、どんなリスクがありますか?
A:契約期間内の途中解約には違約金が発生することが多く、また内装や看板の原状回復費用を負担しなければならない場合もあります。さらに本部ブランドを即時に使えなくなるため、店舗継続が難しくなるケースも。契約前に解約条件をよく確認し、リスクを把握しておくことが大切です。
8-5. Q5:人材不足が心配ですが、対策はありますか?
A:飲食店はアルバイトやパートの入れ替わりが多い業界です。フランチャイズであれば、本部による求人支援やマニュアル化された研修プログラムを活かせるメリットがあります。定期的にスタッフとコミュニケーションを取り、働きやすい環境づくりを進めることで離職率低下につなげられます。
8-6. Q6:独自メニューは出せるのでしょうか?
A:本部が定める基本メニューを遵守しつつ、地域限定メニューや季節の特別メニューを開発できるFCもあります。ただし、ブランドイメージを守るためのガイドラインがある場合が多いです。事前に“どこまで自由に作れるか”を確認し、独自メニューが認められるフランチャイズを選ぶのがおすすめです。
第9章. 飲食店フランチャイズの知識を学んで成功させよう!
飲食店フランチャイズは、本部が磨き上げたノウハウとブランド力を活かして比較的早期に安定収益を得られる一方、月々のロイヤリティやマニュアル遵守など制約も伴います。特に、衛生管理や調理オペレーションの標準化が売上や口コミに直結しやすい飲食業だからこそ、本部の支援が大きな武器となるのです。加盟金や保証金、解約時のルールなど契約面を事前にしっかり把握し、総合的なコストメリットを考慮することが肝心。
FC後の運営では、『飲食店のWEB集客方法完全ガイド!効果的なマーケティング施策で店舗売上を増加させよう!』も収益拡大に不可欠です。
また、オーナー自身がローカルイベントやSNSを積極的に活用し、地域密着やテイクアウト対応など多面的に収益を伸ばす工夫を重ねることで、競合が多いエリアでも差別化を図れます。最後に、店舗運営を成功させる最大のカギは、人材マネジメントと日々の改善意欲。フランチャイズだからといって全てを本部任せにせず、自ら学び続ける姿勢を持ち、ブランドの恩恵を最大限に引き出しましょう。