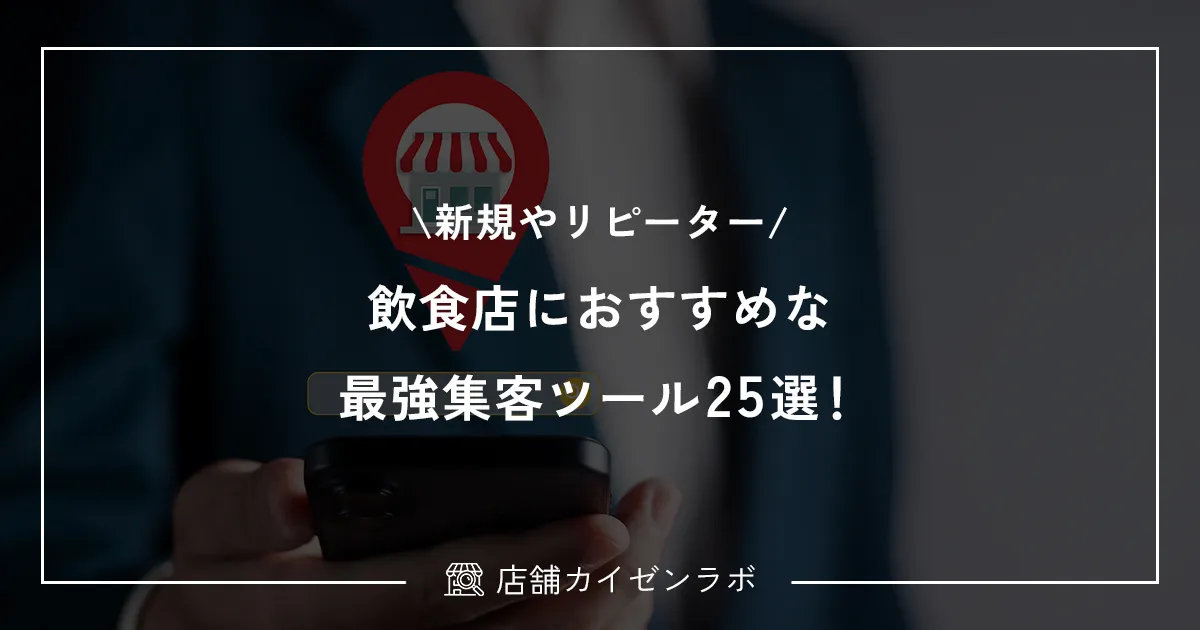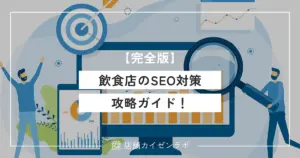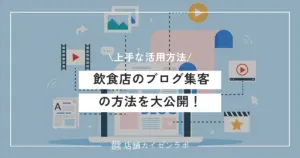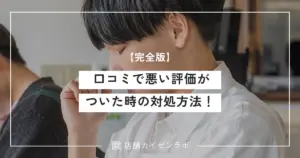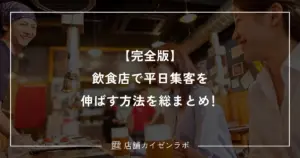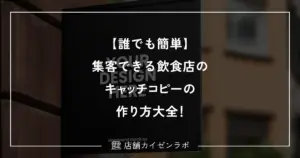1. 飲食店が集客ツールを導入する重要性
飲食店の経営では、いかに安定して集客できるかが大きな課題です。特に近年は、SNSの普及やスマートフォンの利用増加により、顧客が飲食店を探す方法が大きく変化し続けています。そこで、飲食店が導入すべき集客ツールの種類や使い方も多様化しているのです。こうしたツールの活用により、新しい顧客を獲得し、継続的に来店してもらう仕組みを整えることができます。ここでは、まずなぜ飲食店に集客ツールが必要なのか、その背景と意義を整理していきましょう。
1-1. 変化する市場環境への適応
スマートフォンの爆発的普及とともに、顧客が飲食店を選ぶ際の情報源は多種多様になりました。たとえば、グルメサイトでメニューや価格を確認するだけでなく、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSで「このお店が気になる」「料理写真が美味しそう」といった情報をリアルタイムで入手することが当たり前になっています。
加えてデリバリーサービスやネット予約が普及し、店舗を訪れなくても自宅や職場で料理を楽しむ消費スタイルが当たり前になりました。飲食店側から見ると、「店内に足を運んでもらう来店型ビジネス」だけでなく、「オンラインでオーダーを獲得して販売するビジネス」にも対応する必要があります。こうした大きな市場変化に取り残されないためには、従来のチラシや看板といったオフライン販促だけでなく、SNSやグルメサイトを通じて顧客を呼び込むツールが不可欠です。
さらに、Google検索やGoogleマップによる地域検索も激しく競合する時代です。特に地元の住民やオフィス街のビジネスパーソンに向けて「近くにある良い飲食店」として見つけてもらうには、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)を活用することが大きな効果を発揮します。実際に検索結果で上位表示されれば、多くの潜在顧客に気づいてもらえるため、集客のチャンスを逃しにくくなるでしょう。
1-2. 多様化する顧客ニーズへの対応

飲食店が使用する集客ツールは、単に新規顧客を呼び込むためのものにとどまりません。最近では「いかにリピーターを増やすか」「いかに継続的に売上を上げていくか」という視点がとても重要です。顧客一人ひとりの好みに合わせたクーポンを配布できるアプリやSNSを運用すれば、再来店につながる販促施策を打ち出しやすくなります。
また、若年層やファミリー層、あるいはビジネスマンなど、どのターゲットを主に狙うのかによって、利用するツールや発信する情報が変わるのもポイントです。SNSであればInstagram中心でビジュアル重視、あるいはX(旧Twitter)中心で拡散力重視、といった運用の違いもあります。こういった「多様な顧客ニーズ」に対応するには、複数の集客手段をうまく組み合わせることが必要になってきます。
そして、多くの顧客が「今すぐ予約したい」「すぐに注文したい」といった欲求を持っています。いわゆる即時性ニーズが高まっているので、オンライン予約システムやデリバリーアプリを導入しておけば、顧客が手軽にアクセスできるようになるでしょう。電話予約だけでは対応しきれなくなった時代だからこそ、幅広いツールの導入が飲食店には欠かせないのです。
ここまでの内容からわかるように、飲食店が市場の変化や多様な顧客ニーズに対応するためには、オンライン・オフライン両面での販促戦略が必要です。そして、適切にツールを導入すれば、新規顧客の獲得だけでなくリピーターの継続来店にもつなげることが可能となります。
2. お店に来店してもらうための基本戦略

飲食店が安定した売上を実現するには、ツールの導入だけでなく、そもそもの基本戦略がしっかりしている必要があります。いくら便利なSNSやグルメサイトを利用しても、「どんな顧客にどんな魅力を訴求したいのか」が曖昧だと効果を上げにくいでしょう。そこで、ここでは顧客を呼び込むために欠かせない基本戦略を紹介します。
2-1. ターゲット設定と店舗コンセプトの明確化
まず何よりも大切なのは、ターゲットを具体的にイメージし、それに合わせた店舗コンセプトを固めることです。たとえば、「ランチタイムに会社員がサクッと食事できるお店」「家族連れがくつろぎながらディナーを楽しめるレストラン」「デートや記念日に利用されるようなおしゃれな雰囲気の飲食店」など、具体的にターゲットを絞ると、おのずと集客方法も明確になっていきます。
もし漠然と「いろんな層に来てほしい」と考えてしまうと、情報発信の軸がぶれてしまい、結局どの層の顧客にもアピールしにくくなります。逆に「ランチを中心にビジネスマンの来店を獲得したい」と決めておけば、SNSの投稿内容やグルメサイトのキャッチコピーにおいて「ヘルシーかつ時短」「リーズナブルな価格帯」「ビジネスランチに最適」などの表現がしやすくなります。
ターゲット設定を行う際には、店舗周辺の環境調査や競合店のリサーチも欠かせません。競合がどんな集客ツールを使い、どんなメニューや価格帯で勝負しているのかを把握することで、自分の店舗ならではの強みを見つけやすくなるでしょう。それこそが本当に必要な「店舗コンセプトを明確にする」プロセスです。
ターゲットに響くキャッチコピーの作り方は『【誰でも簡単】集客できる飲食店のキャッチコピーの作り方大全!具体的な考え方から成功事例まで徹底解説!』を参考にしてください。
2-2. 効果的な情報発信の基礎
ターゲットが定まったら、その人たちが日常的に見る媒体やSNS、検索エンジンを通じてアプローチする必要があります。たとえば若い女性が多い地域であればInstagramが中心になるでしょうし、ビジネスマンがメインの地域ならばX(旧Twitter)やFacebookのページ、あるいはGoogle検索への露出を強化する方法が有効かもしれません。
情報を発信する際には、ただメニュー写真を投稿するだけでなく、ターゲットが「このお店に行ってみたい」と感じる要素をしっかり伝えることが重要です。たとえば、「季節限定の新メニューが登場」「ランチセットで無料のドリンクサービス実施中」「予約限定でデザートをプレゼント」など、思わず顧客が行動を起こしたくなるような情報が求められます。
また、グルメサイトに掲載する情報やSNSの投稿内容は常に最新を保つことが大切です。営業時間や定休日、メニューが変わったのに放置されていると、「実際にはもう販売していない料理が載ったまま」というように顧客にとって混乱の原因になります。最新の情報発信を続けることで、顧客の来店意欲を下げずに済むだけでなく、検索エンジンからも更新頻度の高いサイトとして評価を受けやすくなる可能性があります。
効果的な情報発信を実践することで、店舗の魅力がターゲットに伝わり、新規顧客の獲得とリピーターの育成を同時に狙えます。大切なのは「誰に」「どんな価値を伝えるか」という軸を常にぶらさないことです。
3. 目的に応じた飲食店の集客ツールの選び方

飲食店向けの集客ツールは多岐にわたりますが、導入にはコストや手間がかかります。そこで、まずはツール選定の前に「何を目的として導入するのか」をはっきりさせることが大事です。「新規客を呼び込みたい」「予約を取りやすくしたい」「リピーターを増やしたい」など、目的によって最適なツールは変わります。ここでは、主に3つの目的別にツール選定のポイントを紹介します。

3-1. 新規獲得用ツールを選択するポイント
広く情報を行き渡らせることが鍵
新規顧客の獲得を最優先に考えるなら、まずは「多くの人にお店の存在を知ってもらう」ことが必要です。ここで強力な手段となるのが、グルメサイトやSNS広告など、広いユーザー層にアプローチできるツールです。グルメサイトであれば食べログやぐるなびといった有名サービスが代表的で、特定の地域やジャンルで検索した際にお店が表示されやすくなります。これらのプラットフォームは無料掲載枠もありますが、より上位表示を狙うなら有料プランやリスティング広告の検討が必要です。
SNS広告はターゲットを絞り込みやすいのが魅力。たとえばInstagram広告で20〜30代の女性に向けて写真映えするメニューをアピールすれば、高い訴求力が期待できます。また、X(旧Twitter)のプロモーション機能を使って、店舗周辺エリアのユーザーだけに広告を配信する方法もあります。こうした広告ツールの活用は、比較的短期間での集客に効果的です。
エリア訴求と口コミの重要性
地域密着型の飲食店なら、Googleビジネスプロフィール(GBP)も欠かせません。GBPに店舗情報を詳細に登録しておくと、Googleマップで「近くの○○」と検索されたときに表示されやすくなります。たとえば「近くの焼き鳥屋」「駅名+カフェ」など、ユーザーが欲する情報に合致すれば、クリックからの来店につながりやすいです。さらに口コミや写真の数が増えれば増えるほど、検索結果での露出が高まり、信頼感も得やすくなります。
新規顧客を獲得し続けるには、広い範囲での露出と、実際に訪れた人が好意的なレビューを投稿してくれる仕組みが大切です。そのためには、キャンペーンで口コミ投稿を促す、お礼メールやSNSメッセージで感謝を伝えるなどの工夫が役立つでしょう。

3-2. 予約導線を強化するツールの活用
電話だけでは取りこぼす時代
電話予約が中心だった時代は終わりを迎えつつあります。今では多くの飲食店がオンラインでの予約システムを導入し、24時間いつでも予約可能な環境を整えています。グルメサイトに予約ボタンを設置したり、独自の予約ページを作ったりすることで、顧客がふと食事の予定を立てたときに「今すぐ予約できる」状態をつくるのです。
オンライン予約ツールには無料から有料までさまざまありますが、有料版を導入すると「予約枠管理」「ダブルブッキング回避」「自動リマインドメール」といった機能が使えるため、店舗側の負担を大幅に削減できます。また、グルメサイト経由で獲得できた予約には手数料が発生することもあるため、コストとメリットのバランスを考慮することが必要です。
予約データから新たな販促へ
オンライン予約を導入すると、どの時間帯にどんな顧客が予約しやすいか、データが自動的に蓄積されていきます。たとえば、平日夜は男性の一人予約が多い、週末は家族連れが多いなど、予約者の情報が貴重なマーケティングデータとなるのです。こうしたデータを分析すれば、空いている時間帯に合わせたクーポン配信やプラン作成など、新しい販促施策を検討する材料になります。
電話予約だけでは得られない「顧客の属性」や「予約日時の傾向」を可視化することで、より戦略的に販促が可能になります。具体例を挙げると、20代が多く予約する時間帯にはSNSで新メニューを告知し、40代が多い時間帯には落ち着いた雰囲気のディナーコースを用意するといった使い方が考えられます。
3-3. リピーター化を目指すアプリやSNS施策
再来店につなげる鍵
新規顧客の獲得だけでなく、「一度来店した人に何度も通ってもらう」仕組みづくりは売上を安定させるうえで欠かせません。そのために有効なのが、LINE公式アカウントや自社アプリといった、ダイレクトに顧客とつながれるプラットフォームです。これらを導入すれば、一斉クーポン配信やポイント管理が簡単に行えるので、リピート率を高められるでしょう。
実際、LINE公式アカウントを使えば、誕生日月に特典を送ったり、新メニュー情報をタイムリーに通知したりといった施策を低コストで実施できます。アプリを自社で開発する場合、ある程度の初期投資が必要ですが、スタンプカード機能や、ユーザーの来店履歴を蓄積できる機能があれば、よりパーソナライズされた販促が可能になります。
SNS運用でファンを醸成
InstagramやFacebook、X(旧Twitter)といったSNSは、新規顧客開拓だけでなくリピーター育成にも使えます。たとえば、季節のメニュー紹介やイベント告知を定期的に投稿することで、お店をフォローしている顧客が「また行きたい」「友人を誘ってみよう」と思うきっかけをつくれます。コメント欄でのやり取りやDMへの返信を丁寧に行うと、店舗と顧客の距離が近くなり、ファン化が進みやすくなるでしょう。
さらに、リピーターの多い店舗では「SNS投稿をしてくれたら割引」などのキャンペーンを行い、自然と口コミを増やす取り組みを積極的に行っています。SNSを利用して写真や動画が拡散されれば、新規顧客の獲得にも波及しやすく、結果的に大きな集客効果を得られる可能性があります。

4. 目的別!飲食店におすすめな集客ツールを一挙紹介!

飲食店の集客では、新規顧客を獲得しつつリピーターを増やす施策が欠かせません。なかでも「SNS」「MEO(Googleマップ対策)」「デリバリーサービス」「グルメサイト掲載」など、目的に合わせて選べるツールは多岐にわたります。以下では、これらのツールを 目的別 に整理しながら、できるだけ多くの方法をまとめてみました。自店舗に合ったツールを選んで、効果的な販促と売上向上を目指しましょう。
4-1. グルメサイト&ポータルサイト(集客の基本)
4-1-1. aumo Biz
- 特徴:Googleマップでの上位表示やSNS運用、広告配信などを一元管理できるマーケティングツール。無料プランからスタートでき、幅広い集客施策をまとめて実施可能。
- おすすめの店舗:コストを抑えつつ、グルメサイトやSNS、MEOなど複数チャネルで認知度を上げたい店。
4-1-2. 食べログ
- 特徴:掲載店舗数85万件以上を誇る大手グルメ検索サイト。口コミや写真投稿機能が充実しており、新規顧客が店舗情報を検索するときの定番。
- 注意点:ユーザー投稿の口コミは原則削除できないため、ネガティブな書き込みにも真摯に対応する姿勢が必要。
4-1-3. ぐるなび
- 特徴:複数言語対応が可能で、インバウンド集客にも有利。楽天ポイントと提携しているため、予約時にポイントが貯まるのが強み。
- おすすめの店舗:都市部に多い居酒屋や観光客向けの飲食店に特に相性が良い。
4-1-4. Retty
- 特徴:実名登録制で信頼度の高い口コミが集まるグルメサービス。ユーザー同士のフォロー機能により口コミが拡散されやすい。
- メリット:GoogleやSNS、インバウンド対策などを一括で強化できる「Rettyお店会員」サービスあり。
4-1-4. favy
- 特徴:飲食店向けサブスクリプション「favyサブスク」を展開。割引や無料サービスを月額料金制で提供し、継続来店を促す仕組み。
- おすすめの店舗:リピーター獲得のためにサブスクを導入してみたいお店。
4-1-5. 地域のポータルサイト
- 特徴:特定エリアの飲食店やイベント情報が集まるサイトで、近隣住民や訪問客へのアピールに有効。
- メリット:無料で掲載できるケースも多く、地域に密着した集客を実現しやすい。
4-2. デリバリー&テイクアウト(売上向上)
4-2-1. Uber Eats
- 特徴:世界10,000以上の都市で展開されるフードデリバリーサービス。国内でもコロナ禍で広く普及し、注文のハードルが低い。
- 導入メリット:既存客だけでなく、エリア内の新たな顧客にもリーチしやすい。配達委託が可能で、追加の人件費を抑えられる。
4-2-2. 出前館
- 特徴:日本最大級のデリバリーサービス。成果報酬型の手数料のみで導入しやすく、スタッフが接客態度や運転技術の基準を満たしている点も安心。
- メリット:出店サポートが充実しているため、デリバリー初挑戦でも導入しやすい。
4-2-3. Wolt
- 特徴:フィンランド発のデリバリーサービスで、日本でも対応エリアを拡大中。初期費用や掲載料は不要で、注文がなければコストがかからない成果報酬型。
- おすすめの店舗:比較的新しいサービスを活用しながら、地域での認知度を上げたい店。
4-2-4. menu
- 特徴:国内発のテイクアウト・デリバリーサービス。24時間注文が可能で、深夜帯の売上拡大にも対応。
- メリット:アプリからのサポート窓口が充実しており、テイクアウトとデリバリーの両方をまとめて強化できる。
4-3. SNS&MEO集客(認知度向上&リピーター獲得)

4-3-1. Instagram
- 特徴:写真や動画投稿を通じて料理や店内の魅力をダイレクトに訴求できるSNS。ハッシュタグ検索を利用するユーザーが多く、拡散力が高い。
- おすすめの店舗:映えるメニューやおしゃれな内観があるお店。若年層の利用者が多く、新規集客につなげやすい。
4-3-2. Facebook
- 特徴:実名登録が基本のSNSで、企業ページをホームページ代わりに運用可能。投稿やイベント告知などを通じて中高年層にも訴求しやすい。
- メリット:広告出稿機能やアクセス解析を利用することで、細かなターゲティングが可能。
4-3-3 X(旧Twitter)
- 特徴:拡散力が高く、短い文章や写真をリアルタイムで発信しやすいSNS。リポスト機能で話題が瞬く間に広がる可能性大。
- おすすめの店舗:キャンペーンやタイムセール情報を即時拡散し、短期的な集客を狙う際に有効。
4-3-4. LINE公式アカウント
- 特徴:国内ユーザーの多さが圧倒的。クーポン配信やスタンプカード機能、1対1のチャットなどでリピーターを確保しやすい。
- メリット:プッシュ通知で高い開封率が期待できる。誕生月特典やポイント付与など、リピート施策が簡単。
4-3-5. Googleビジネスプロフィール
- 特徴:Googleマップ上で店舗情報を無料で掲載可能。MEO対策(Map Engine Optimization)により、地域名×飲食ジャンルの検索で上位表示を目指せる。
- 注意点:口コミに対する返信や情報更新を怠ると評価が下がり、集客効果を損ねるリスクがある。
4-3-6. Googleストリートビュー
- 特徴:店内や外観を360度パノラマで表示し、来店前に雰囲気を確認してもらえるツール。Googleビジネスプロフィールと連動可能。
- メリット:視覚的に店舗の魅力を伝えられ、初めて訪れるお客様の不安を軽減。
SNSで重要な映える写真を撮るコツは『飲食店が写真撮影を依頼する際の業者の選び方のコツと注意点!料理撮影に強いおすすめな会社も厳選してご紹介!』を参考にしてください。
4-4. Web広告&自社ホームページ(長期的な集客戦略)
4-4-1. Web広告(リスティング広告・ディスプレイ広告など)
- 特徴:検索キーワードやユーザー属性を指定して広告を出稿できるため、短期間で効果を得やすい。
- おすすめの店舗:すぐに集客を伸ばしたい、ターゲットを絞った訴求を行いたい場合に有効。
4-4-2. 自社ホームページ
- 特徴:公式サイトとして自由にレイアウトやコンテンツを作成できる。ブランドイメージや世界観を深く伝えるのに最適。
- 注意点:制作や保守に時間とコストがかかるが、長期的なSEO対策や情報発信の拠点として機能する。
4-5. オフライン集客(地域密着型の施策)
4-5-1. ポイントカード
- 特徴:来店頻度に応じて特典を付与し、リピート率向上を狙う方法。コストが低く導入しやすい。
- メリット:スマホアプリやLINE公式アカウントとも連携可能で、紙からデジタルに移行すれば管理も簡単。
4-5-2. チラシ
- 特徴:高齢者層など、ネットをあまり使わない層への訴求に有効。新聞折り込みやポスティングを活用して、エリアを絞った集客もできる。
- 注意点:印刷・配布のコストがかかるため、販促費を事前に計画しておくことが重要。
4-5-3. 看板
- 特徴:通行人の目を引き、思わぬ飛び込み来店を生み出す。視認性が高いほど集客効果が期待できる。
- メリット:古くから使われている手法だが、デジタル施策と併用することで相乗効果を狙いやすい。
4-6. 新しい集客施策(デジタル×リアル)
4-6-1. ECサイトの活用
- 特徴:自店オリジナルの調味料や冷凍商品をオンラインで販売し、売上拡大と店舗アピールを同時に実現。
- メリット:メディアやSNSで話題になれば広告費を抑えつつ全国展開も狙える。
4-6-2. フランチャイズ業態で集客
- 特徴:既に確立されたブランドや経営ノウハウを活用し、自店舗の課題を解決できる可能性がある。
- おすすめの店舗:集客がうまくいかず、店舗の箱を活かして別のアイデアを取り入れたい場合。
4-6-3. QRfood
- 特徴:世界40万店以上で導入されるモバイルオーダーアプリ。2.1億人以上のユーザー基盤があり、インバウンド対策にも有利。
- メリット:アプリ内から注文・決済が可能で、スタッフの負担を軽減しつつスムーズなサービスを提供できる。
4-6-4. 自社オリジナルのスマホアプリ
- 特徴:会員登録を促し、クーポン・割引券の配信や顧客データ管理など、きめ細かな販促を実施できる。
- 注意点:開発コストが大きいため、運用目標・予算を明確にしてから始めることが重要。
4-7. 目的に合ったツール選択で効果的な集客を目指そう
飲食店の集客には、「新規顧客の獲得」「リピーターの増加」「売上向上」といった目的があり、使うべきツールも多岐にわたります。グルメサイトやSNS、MEO(Googleビジネスプロフィール)、デリバリーサービスなど、それぞれに異なる強みがあるため、まずは 自店舗のターゲット と 求める効果 を明確にするのが最初のステップです。
- 新規顧客の認知度アップ:グルメサイト・ポータルサイト、Web広告、SNS
- リピーター対策:ポイントカード、LINE公式アカウント、サブスク導入
- 店舗収益の拡大:デリバリー&テイクアウト、ECサイト展開、自社ホームページ
- 地域・商圏内の集客:Googleビジネスプロフィール、チラシ、看板
これらの施策を組み合わせ、定期的に データ分析(来店数・予約数・口コミ評価など) を行いながら、PDCAサイクルを回すことが成功のカギです。
5. 飲食店がオフラインで使える集客ツール

オンライン施策が注目されがちですが、地域密着型の飲食店や年配層をターゲットとしたお店などでは、オフラインの販促方法も依然として効果があります。また、既存の集客ツールとの相乗効果を狙う場合にも、オフラインでの情報発信は欠かせません。看板やチラシ、ショップカードなど、昔ながらの手段をうまく活用することで、潜在顧客の来店を促すことができます。
5-1. チラシ・看板などの基本販促方法
近隣住民や歩行者へのアプローチ
店舗周辺の住民や通勤客を狙うなら、チラシ配布やポスティング、新聞折り込みなどが依然として有効な販促方法です。内容としては、お店の場所や人気メニュー、割引クーポンなどをわかりやすくアピールすると、手に取った人が「ちょっと行ってみようか」と思いやすくなります。
看板や店頭ポスターも重要な役割を果たします。特に視認性の高い場所にある看板は、道行く人々の興味を引く大きなチャンスです。シンプルながらインパクトのあるデザインに仕上げると、「これってどんなお店だろう?」と気になって入店する歩行者が増える可能性があります。もちろん、イメージ写真や価格帯を提示することで、顧客が安心して入れるかどうかを判断しやすくなる点も押さえたいポイントです。
内容やタイミングを最適化する
チラシを活用するときは、配布するタイミングに注意を払いましょう。たとえば「週末に家族連れを呼び込みたい」なら、金曜日や土曜日の朝刊に折り込むことで、「そういえば今度の休みに外食でもしようか?」と検討するタイミングにバッチリ合います。
さらに、期間限定のメニューやイベント情報を載せると、希少性による興味喚起が期待できます。「今だけ割引」「季節限定スイーツ」など、具体的な日程やサービスをわかりやすく記載することで、すぐに来店してもらえる動機づけをするのです。
5-2. ポイントカードやショップカードの活用
リピーター促進のための仕組み
ポイントカードやショップカードは、飲食店がリピーターを獲得するうえで代表的なアナログ施策です。1回の来店でスタンプを押したり、一定回数の来店で割引特典を提供したりすることで、「あと少しで割引がもらえるから行こう」と思ってもらいやすくなります。
また、コンパクトでデザイン性のあるショップカードをレジ横に置いておくだけでも、お店の雰囲気を伝える小さな広告として機能するでしょう。シンプルに店舗名と連絡先、営業時間を記載しておけば、持ち帰った顧客が「今度また行きたい」と思ったときにすぐアクセスできます。
デジタルとの連携も視野に
アプリやLINE公式アカウントといったデジタルツールと連動させることで、より効果的な販促を行うことも可能です。たとえば、「スマホでQRコードを読み取るとショップカードがデジタル化される」「一定回数のスタンプでアプリ内クーポンが届く」といった仕組みにすることで、顧客にとって管理がラクになるうえに、店舗側も来店データを蓄積できます。
ポイントカードを単なる紙の台帳にするだけではなく、オンラインとオフラインをうまく融合させることで、より幅広い顧客のニーズに応えられるでしょう。
5-3. 地域のコラボやイベント連携
商店街や地元コミュニティとの協力
飲食店がある地域では、商店街や観光協会、自治体のイベントが随時開催されているケースがあります。こうしたイベントに参加したり、地元の他業種店舗とコラボしたりすることで、新たな顧客層にお店を知ってもらうきっかけを作れます。例としては、商店街のスタンプラリーイベントに参加し、指定のスタンプを集めた来店客に特典を渡すなどがあります。
地域の取り組みに積極的に参加すると、地元メディアで取り上げられるチャンスも生まれ、結果として露出拡大と来店促進につながる可能性があります。
ポップアップや限定メニューの展開
オフラインでの販促は、遊び心を加えると話題性が高まります。期間限定のポップアップストアを出店したり、地域の祭りやフードフェスに出店したりすることで、お店の名前を知ってもらうだけでなく、新商品のテストや顧客の生の声を集める好機にもなります。
また、他店舗とのコラボメニューも面白い方法です。たとえば、近隣のパン屋とコラボして特別なサンドイッチを作り、それを期間限定で提供するといった企画を行えば、双方のファンが来店してくれる可能性が高まり、互いの販促に貢献できます。
6. SNSを活用した飲食店の集客方法
今やSNSは飲食店の集客ツールとして欠かせません。InstagramやFacebook、X(旧Twitter)などのSNSプラットフォームは、ユーザー層や投稿の特徴が異なるため、上手に使い分ける必要があります。ここでは、それぞれのSNSを活用する際のポイントや実践的なアイデアを紹介し、顧客獲得とリピーター確保につなげる方法を考えてみましょう。
6-1. InstagramとFacebookの違い
ビジュアル重視のInstagram
Instagramは写真や動画など、ビジュアルを中心としたコンテンツがメインのSNSです。飲食店が投稿する場合には、美味しそうな料理写真や店内の雰囲気を伝える画像が注目を集めます。若年層だけでなく、幅広い年代のユーザーが利用していることに加え、ハッシュタグを通じて「ジャンル別」「地域別」に検索されやすい点が特徴です。
効果を高めるためには、投稿写真のクオリティにこだわりつつ、ハッシュタグ戦略も重要。「#地域名+ランチ」「#カフェ巡り」「#肉料理」など、ターゲットが検索しそうなワードを入れると、多くの人の目に触れるチャンスが生まれます。また、ストーリーズ機能を活用して期間限定キャンペーンや裏メニューの告知などを行うと、「今だけ」の特別感を演出できて効果的です。
コミュニティづくりに強いFacebook
Facebookはユーザー同士のつながりを重視するプラットフォームで、主に30代以上のビジネスパーソンやファミリー層が多く利用しています。お店の公式Facebookページを作成し、定期的に投稿することで、既存顧客とコミュニケーションを深めながら、新規顧客にも存在感をアピールできます。
Facebook広告を利用すれば、年齢や興味関心、居住地域などを細かく指定したターゲットにアプローチが可能です。また、「イベント」機能を使って店舗での新メニュー発表やコラボ企画などを告知し、興味を持っているユーザーを簡単に集めることができます。コミュニティ機能も充実しているため、顧客の声をすぐに聞けるのがメリットです。
6-2. X(旧Twitter)での効果的な発信

拡散力とリアルタイム性
X(旧Twitter)は、短文投稿とリアルタイムの拡散力が特徴です。ユーザーのタイムラインに流れてくる情報は非常に速いサイクルで消費されますが、その分話題性のあるツイートは一気に拡散され、多数のユーザーの目に留まる可能性があります。
飲食店がXを活用する場合、今日のおすすめメニューや、本日の混雑状況、キャンセルが出て空席があるといったリアルタイムの情報を発信するのに最適です。「席が空いたからすぐに来店したい」という顧客がいれば、その情報をもとに急に集客できるかもしれません。また、ハッシュタグを活用しながら地域名やジャンルを入力しておけば、興味のあるユーザーが見つけやすくなるでしょう。
ユーザーとの双方向コミュニケーション
Xで効果的に集客するには、ユーザーとのやり取りも欠かせません。リプライ(返信)や引用リツイートを通じて感想をもらったり、質問に答えたりすることで、お店に対する親近感を高められます。飲食店の場合、料理やサービスに関するツイートを顧客が投稿してくれることがあるため、それを積極的にリツイートして「お客様の声」として共有するのも良い方法です。
キャンペーンを開催するなら、「フォロー&リツイートで抽選」といった施策も多くの店舗が実施しています。上手に設定すれば短期間でフォロワーを増やし、より多くのユーザーにお店の情報を届けることが可能です。
6-3. LINE公式アカウントの集客活用
顧客へ直接アプローチできるツール
LINE公式アカウントは、ユーザーが友達登録を行うことで、飲食店から直接メッセージを受け取れる仕組みを持っています。これが大きな強みで、プッシュ通知を活用することでクーポンやイベント情報、新メニュー告知などをタイムリーに届けられるのです。「今日これから食事に行こうか迷っている」という顧客層にとって、リアルタイムのクーポン情報は大きな来店動機になり得ます。
また、チャット機能を使えば顧客との個別やり取りも可能です。たとえば、予約や問い合わせに応じて返信すれば、スムーズに予約獲得につながります。
リピーターづくりに最適
LINE公式アカウントは、友達登録してくれたユーザーとの継続的な関係構築に役立ちます。たとえば、誕生日月に特別クーポンを配布したり、ランチタイム限定の割引情報を送ったりといったシチュエーション別の配信ができます。従来の紙ベースの販促ツールではできなかった「個別化したメッセージ」の提供がしやすいのです。
また、スタンプカード機能やポイント機能をアカウントに組み込むことも可能で、来店回数が一定に達した顧客へ特典を自動付与するといった施策を行えば、より効果的にリピーターを増やしやすくなります。
SNSと連動したブログ運用をすることでさらに集客をアップさせることができます。ブログ運用のコツは『飲食店のブログ集客の方法を大公開!来店や売上に繋げる上手な活用方法!』を併せて確認してみてください。
7. グルメサイトとGoogleビジネスプロフィール等のツールを効果的に活用
飲食店の集客を効率的に伸ばすうえで、グルメサイトやGoogleビジネスプロフィール(GBP)は欠かせないツールです。多くの顧客はお店を選ぶ段階で「検索する」「口コミを見る」行動を起こすため、この2つを最適に活用することは新規来店・予約の獲得に直結します。ここでは、より効果を高めるための具体的な方法を解説します。
7-1. 食べログ・ぐるなび・Rettyの活用法
掲載内容のブラッシュアップ
グルメサイトは、新規の集客ツールとして広く認知されている代表的な販促媒体です。食べログやぐるなび、Rettyといった有名グルメサイトはユーザー数が多く、ジャンルや地域を絞って検索する利用者が多いのが特徴といえます。こうしたプラットフォームを使う際は、掲載内容を常に最新かつ魅力的にアップデートすることが必要です。
- 写真の充実:料理のクオリティや店舗の雰囲気を伝えるためには写真が最重要。プロが撮影したような高画質の写真をそろえると、クリック率が上がる傾向があります。
- メニュー・価格情報の更新:価格が古いまま放置されていたり、すでに提供していないメニューが掲載されていると顧客の信頼を損ないかねません。定期的に見直しましょう。
- 店舗情報の詳細:席数、個室の有無、支払い方法など、細かな情報をしっかり書くことで、利用者が予約や来店を判断しやすくなります。
口コミとランキング対策
グルメサイトでは口コミ評価が高いほど上位表示され、検索されやすくなります。ただし、無理に高評価を要求するのは逆効果です。大切なのは自然な口コミを増やすこと。そのためには、来店後に「もし良ければ口コミをお願いします」という趣旨を軽く伝えたり、ショップカードやアプリ内でレビュー投稿を促したりして、顧客との接点を設計します。
また、食べログなどでは独自のランキングやスコアリングがあるため、写真やメニュー情報を更新し続ける、誠実な口コミ返信を行うなどの地道な運用が評価向上につながります。結果的にランキング順位が上がれば、さらなる新規顧客を呼び込む効果が期待できるでしょう。
7-2. Googleマップでの上位表示を狙うMEO対策
MEO(Map Engine Optimization)の基本
Googleビジネスプロフィール(GBP)を使った地域検索対策、いわゆるMEOは、飲食店の集客を左右する大きな要素です。「地域名+ランチ」「駅名+居酒屋」などで検索したときに上位に表示されるかどうかで、来店数に大きな差が生まれます。特に、スマートフォンで近場のお店を探すユーザーが急増しているので、GBPの最適化は必要不可欠といえます。
具体的な運用ポイント
- 店舗情報の正確性:住所や電話番号、営業時間、定休日はもちろん、料理ジャンルや提供サービスを詳細に記載します。変更があればすぐに更新することが大切です。
- 写真・動画の積極的な活用:店舗外観や料理、内観の写真を充実させると、ユーザーが来店をイメージしやすくなります。動画の投稿機能を活用すると、店内の雰囲気をよりリアルに伝えられます。
- 投稿機能の活用:GBPには「投稿」タブがあり、期間限定メニューやイベント情報などを配信できます。定期的に更新しておくと検索表示で目立ちやすくなるだけでなく、ユーザーの興味を引きやすくなります。
- 口コミへの適切な返信:良い口コミには感謝を、悪い口コミには改善意識を示す返信を行うことで、潜在顧客にも誠実な印象を与えられます。自然な形で口コミ件数が増えれば、MEO上位表示に好影響を与えます。
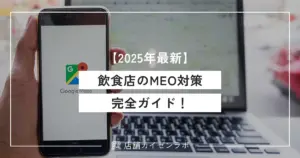
7-3. 口コミや写真投稿促進による評価向上
ユーザーの投稿を活用する
飲食店が口コミ評価を上げるには、実際の顧客に「また来たい」と思ってもらう満足度の向上が大前提です。そのうえで、グルメサイトやGoogleビジネスプロフィールに写真や感想を投稿してもらえるよう促すと、自然なクチコミの数が増え、掲載順位や評価スコアが上がりやすくなります。
たとえば、「お帰りの際に簡単なアンケートへのご協力をお願いします」と店頭やSNSで呼びかけたり、LINE公式アカウントでの再来店時に特典クーポンを配布したりすると、ポジティブなクチコミを得るチャンスが高まるでしょう。
SNSシェアとハッシュタグの相乗効果
TwitterやInstagramなどのSNSで顧客が投稿する場合、店舗が指定したハッシュタグをつけてもらうようにすると、さらに多くの潜在顧客の目に触れやすくなります。「#地域名+お店名」「#人気メニュー名」などのハッシュタグが増えていけば、自然と検索流入や口コミ拡散につながるので、グルメサイトやGBPの評価アップにも良い影響を及ぼすのです。
8. リピーター育成とツールとしてのアプリ活用

飲食店が長期的に安定した売上を実現するには、新規獲得だけでなくリピーターの継続的な来店が鍵となります。ここでは、アプリやスタンプカードの仕組みを活用し、リピーターを育成するための具体的な施策について紹介します。
8-1. スタンプカード・クーポン配信での顧客接点
再来店を促す仕掛け
リピート率を高める代表的な方法として、スタンプカードやクーポン配信があります。アナログな紙のスタンプカードはもちろん、スマホアプリやLINE公式アカウントでもデジタルスタンプを利用できることが増えています。たとえば、「5回の来店でドリンク1杯無料」「3回の利用でデザートサービス」などの明確な特典を用意しておくと、顧客が「あと少しで特典がもらえるから行こう」と思いやすくなるのです。
クーポン配信は、来店前にお店を思い出してもらう効果もあります。週末前や休日前を狙って、限定クーポンを配信することで「そういえば、あの飲食店に行ってみよう」という意欲を刺激できます。
タイミングを意識した通知
クーポン配信のタイミングも重要です。ランチに来てほしい場合は11時前後、ディナーなら夕方16〜18時頃を狙うと、利用率が上がりやすくなります。LINE公式アカウントやアプリのプッシュ通知は、こうした時間帯を柔軟に設定できるため、適切な販促を行いやすいのが利点です。必要以上に通知を送ると「うるさい」「しつこい」と感じられてしまうので、絶妙なバランスで配信する工夫も大切です。
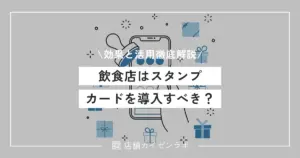
8-2. デリバリーやECサイトの展開と顧客獲得
デリバリーサービスの恩恵
近年、Uber Eatsや出前館、menuなどのデリバリーアプリの普及によって、飲食店の集客手段が店舗の外まで広がりました。これらを活用すれば、物理的に店舗へ来店できない顧客にも商品を届けられます。結果的に売上を伸ばせるだけでなく、自宅や職場で料理を味わった顧客が「次は店舗で食べてみたい」と思うきっかけにもなるのです。
デリバリー対応を行う際は、配達エリアやメニューを厳選して提供することが成功のコツです。人気メニューや調理後も品質が落ちにくい料理を中心にラインナップすることで、顧客満足度を維持しながら新規獲得を狙えます。
ECサイトやテイクアウトの併用
ECサイトで自慢のソースやドレッシング、焼き菓子などを販売する飲食店も増えています。特に地方ならではの特産品や、こだわりの食材を使用した商品はオンラインショップと相性が良く、地域外のお客様にもアピールしやすいのがメリットです。
また、テイクアウトにも対応しておけば、ランチやディナーを「家で楽しみたい」という顧客を取り込めるでしょう。店内で味わうのとは違った形でお店のファンになってもらい、後の再来店につなげる流れを作れるのが大きな利点です。
8-3. 店舗独自アプリやQR決済導入の利点
独自アプリがもたらすブランド力
飲食店が自社独自のアプリを開発・導入すると、ブランド力の向上とリピーター定着に大きく貢献します。具体的には、「オンライン予約」「スタンプカード機能」「限定クーポン配信」「メニュー紹介」「ポイント管理」といった機能が一元的にアプリ内で利用できるため、顧客はわざわざ複数のサービスを行き来しなくてもお店の情報にアクセスできるのです。
導入コストはかかるものの、使いこなせば「無料のSNSではできない個別のアプローチ」「顧客データの詳細な分析」など、競合店との差別化が図れます。特に常連客の囲い込みには強力なツールになるでしょう。
キャッシュレス化のメリット
QRコード決済やクレジットカード、スマホ決済サービスなど、キャッシュレスの導入が進んでいます。特に若年層だけでなく、中高年層の利用も増えており、「現金を持ち歩かない」ユーザーも少なくありません。キャッシュレス決済を導入しておけば、スムーズな支払いが可能で、顧客満足度を高める効果があります。
また、キャッシュレス決済時に顧客情報を紐づけられる仕組みを整えると、「どの時間帯にどんなメニューがよく売れるか」「新規来店かリピーターか」といったデータを蓄積でき、より戦略的な販促が実践できます。独自の電子マネーやハウスカードを発行する飲食店もあり、自社アプリと連携してポイントを付与するなど、オリジナルの取り組みで顧客ロイヤルティを高める事例も少なくありません。
9. 飲食店の店舗集客に役立つデータ分析と改善手法

複数のツールを導入し、集客方法を充実させても、運営状況を把握しながら継続的に改善していかなければ、効果が頭打ちになってしまいます。飲食店におけるデータ活用とPDCAサイクルの回し方は、今や重要な課題です。ここでは、POSシステムや顧客管理システムを中心に、具体的な分析手法と改善アプローチを解説します。
9-1. POSや顧客管理システムでのデータ活用
売上データの分析
飲食店で最も身近なデータといえば、売上情報です。POS(販売時点情報管理)システムを導入することで、時間帯別の売上や人気メニュー、リピーター比率などを簡単に集計できます。たとえば、「平日と週末の売上差がどれくらいあるか」「ランチタイムはどのメニューがよく出るのか」を可視化すれば、メニュー構成やスタッフ配置、仕入れ量などを最適化しやすくなります。
さらに、電子マネーやQR決済と連携したPOSシステムなら、顧客の購買履歴や個別属性を把握できるため、より精密な販促が可能となるのです。
顧客管理でリピート促進
顧客管理システム(CRM)を使えば、来店頻度や平均客単価、特定メニューの購入履歴といった個別のデータまで取得できます。これを分析すると、「一定の顧客層には新商品の割引を案内すると効果的」「SNS経由で来店した顧客には誕生日月に特別サービスを提供」など、きめ細かなターゲット施策が打てるようになります。
実際、飲食店アプリやLINE公式アカウントで友達登録している顧客の履歴を紐づけておけば、定期的にクーポンを送るタイミングを最適化でき、リピート率向上につながるでしょう。
9-2. 定性情報を収集する方法と分析のコツ
アンケートやSNSコメントを活かす
売上や来店数といった定量データだけでなく、顧客の声を直接拾うことも重要です。具体的には、会計時に短いアンケートを行ったり、SNSコメントをチェックしたりといった方法があります。たとえば、「料理の味付けが少し濃かった」「ソファ席が快適」というフィードバックは、実際の来店体験をリアルに示しているため、すぐに改善や強化につなげやすいでしょう。
SNSのDM機能やコメント欄で寄せられた意見をスタッフ同士で共有し、改善案を検討する仕組みを整えることで、お店のクオリティが日々ブラッシュアップされます。
見える化とチーム共有
定性情報は文章や意見ベースなので、人によって解釈が違う場合があります。そのため、「顧客からの声をリスト化して、スタッフ同士で共有」「共通のフォーマットにまとめる」などの工夫が必要です。改善活動を続けやすくするためには、スタッフミーティングやチャットツールなどを活用し、「これまでに寄せられたコメントは〇〇件で、こんな傾向がある」というように見える化しておくと良いでしょう。
9-3. PDCAを回して継続的な効果を狙う
Plan(計画)の明確化
どのような集客ツールを導入し、どういったKPI(重要業績評価指標)を達成したいのかを最初に明確にしておくことがPDCAの第一歩です。たとえば「SNS広告で月間100件の予約を獲得する」「Googleビジネスプロフィールの口コミを月10件増やす」といった具体的な目標を立てると、次のアクションを決めやすくなります。
Do(実行)とCheck(検証)
計画が固まったら、実際にSNSに投稿したり、グルメサイトの情報を更新したり、広告を出稿したりしていきます。その結果をPOSシステムやアクセス解析、予約数の変化などで確認するのがCheckのプロセスです。目標値に届いていない場合は原因を探り、広告文や投稿内容を工夫するなどの修正案を考えましょう。
Action(改善)によるサイクルの加速
最後に「Action」として、検証結果をもとに施策を調整します。たとえば、LINE公式アカウントでクーポンの配信タイミングを変えてみたり、グルメサイトの写真を差し替えたりといった改善を行い、再びPlanへと反映させるのです。こうしてPDCAサイクルを回し続けることで、集客ツールの効果が徐々に最適化され、飲食店の経営基盤が強化されていきます。
10. 集客ツール導入前後に押さえるべきステップと注意点
飲食店が集客ツールを導入する際には、ただ闇雲にサービスを増やすだけでは十分な効果を得られません。あらかじめ目的やターゲットを明確にし、導入に必要な予算や人員体制を整えておくことが大切です。さらに、導入後も継続的に運用や見直しを行いながら、店舗独自の強みを打ち出していく必要があります。ここでは、集客ツールを円滑に導入・活用するためのステップや注意点を順を追って解説します。
10-1. 導入前の目標設定と予算管理
目的を定義して必要な機能を洗い出す
最初のステップは、集客ツールを「どんな目的で導入するのか」を明確にすることです。たとえば「新規顧客を月に○人獲得したい」「予約をオンライン化してスタッフの負担を減らしたい」「SNS運用で店舗ファンを増やしたい」など、店舗ごとに求めるゴールは異なります。
これらの目標を定義すると、必要な機能や販促方法が自然と絞られてきます。たとえばオンライン予約を強化したい場合、予約システムが充実したグルメサイトの有料プランを検討したり、自社ホームページに予約機能を追加したりする選択肢が考えられます。一方、「デリバリーを始めて売上を伸ばしたい」という目的であれば、Uber Eatsや出前館などの導入が優先度を増すでしょう。
初期費用とランニングコストの把握
ツール導入には無料で利用できるサービスもあれば、有料プランへの切り替えによって効果が大きく変わるものもあります。導入前にしっかり調査し、「月額費用や掲載料がいくら必要か」「広告出稿にはいくらかけるのか」「SNSを運用する人件費はどれくらいか」などを算出し、予算を組むことが欠かせません。
特にグルメサイトの有料プランやリスティング広告は、短期的にはコストがかかる反面、うまく活用できれば多くの新規来店を得られる可能性があります。予算配分を決めるときには「長期的に見て回収できるか」「現在の売上規模に対して過度な投資にならないか」を意識し、身の丈に合った形で検討を進めることが重要です。
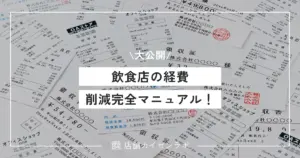
10-2. 運用体制・担当者の明確化
誰が何を担当するのかを決める
集客ツールを導入しただけでは成果は出ません。広告文の作成や写真撮影、口コミへの返信やSNS投稿のタイミング調整など、日々の運用作業が必要です。こうした作業を誰が行うのか、予算や時間の配分はどうするのかをあらかじめ定めておくと、スムーズに進めやすくなります。
たとえば「Instagram運用はAさんが週に3回投稿する」「LINE公式アカウントのクーポン配信はBさんが担当する」といった具体的な役割分担を社内で明確にすると、投稿漏れやダブルブッキングなどの混乱を防げます。店舗の規模が大きくない場合は、オーナーや店長が複数の業務を兼任することも少なくありませんが、無理なく運営できる体制づくりを心がけましょう。
社内研修や外部リソースの活用
飲食店のスタッフ全員がSNSやITツールの運用に精通しているとは限りません。必要であれば研修を行い、最低限の操作方法や集客目標を共有しておくと良いでしょう。とくに、Googleビジネスプロフィールの更新方法や、グルメサイトの管理画面の使い方などは、基本を理解しておくだけで操作の手間を大きく減らせます。
また、「SNSの運用やホームページのメンテナンスは専門家に任せたい」と考える飲食店もあるでしょう。その場合は、外部のWeb制作会社や広告代理店、SNS運用代行サービスなどを活用する方法もあります。費用対効果を見極めながら、店舗の状況に応じて最適な方法を選ぶのが賢明です。
10-3. 定期的な検証とツールの見直しで最適化
効果測定と改善の繰り返し
集客ツールを導入した後は、「本当に目標を達成できているのか」をチェックするため、定期的に効果測定を行いましょう。具体的には以下のような指標を追いかけると、現状把握に役立ちます。
- 予約数や来店数の推移:グルメサイト経由やSNS経由の予約が増えたのか、対前年比や対前月比で計測します。
- アクセス解析:自社ホームページやSNSのアクセス数、いいね数、クリック率などをモニタリングし、注目度の高いコンテンツを把握します。
- 口コミ数と評価:Googleビジネスプロフィールやグルメサイトに投稿されたクチコミ数や評価スコアの変化を見て、顧客満足度を測ります。
もし狙った成果が出ていない場合は、その原因を考えて施策を修正しましょう。たとえば、写真が少ないせいでクリック率が低い可能性があるなら、ビジュアルを強化してみます。クチコミの評価が低いなら、接客やメニューの改善点をスタッフ間で共有し、即座に行動を起こす必要があります。
最新動向をキャッチアップし続ける
SNSやデリバリーサービスなど、飲食店向けのツールは日々進化しています。たとえば、新しいプラットフォームが登場したり、既存のサービスでもアルゴリズムや料金体系が変わったりと、環境が絶えず変化しているのです。そのため、導入時に一度勉強して終わりではなく、定期的に情報収集を行うことが大切です。
さらに、ライバルとなる他店舗がどのような販促を行っているか、どんなグルメサイトやSNSを活用しているかといった競合分析も忘れてはなりません。自店舗の施策を改善し続けるためには、周囲の動きを観察することが有効な手段です。
集客ツールの導入前後には、このようなステップや注意点を意識するとスムーズに運用を進められます。特に飲食店の場合、接客や仕込みなど日常業務も忙しく、時間や労力に余裕がないこともしばしばです。しかし、だからこそツールを上手に活用し、業務効率を高めながら顧客を獲得していくアプローチが求められます。
オンラインとオフラインの販促を組み合わせることにより、より広範なターゲットにアプローチし、新規来店とリピーター育成の両方を狙うことができます。さらに、日々の運営で蓄積されるデータを分析し、PDCAサイクルを回しながら改善を進めることで、最適な集客効果を得られるでしょう。最終的には、店舗の個性や強みを最大限に引き出し、地域やジャンルにおいて独自のポジションを確立することが、飲食店の長期的な成功を支える大切な要素となります。
本記事で紹介した方法や効果的なツール選定の考え方を参考に、自店の実情に合わせた導入と活用を進めてみてください。魅力ある販促を続け、顧客満足度を高めながら店舗のファンを増やしていけば、自然と口コミも広がり、安定した集客につながるはずです。あなたの飲食店が、より多くの顧客の笑顔と「美味しかった」「また来たい」という声であふれることを願っています。