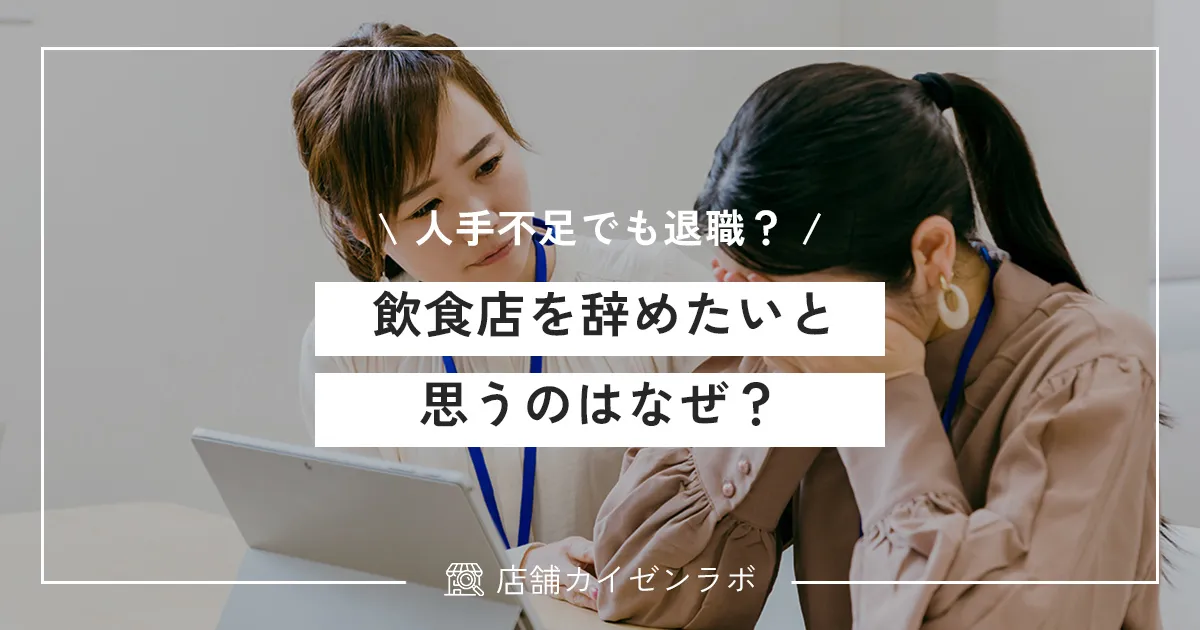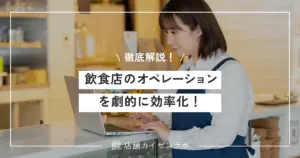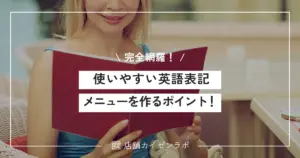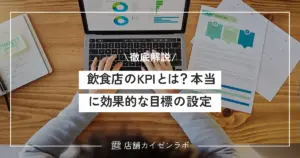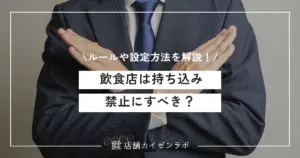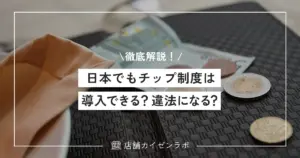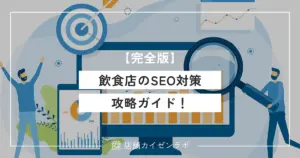1章. 飲食店を辞めたいと感じる主な理由

1-1. 長時間労働と休暇の少なさ
飲食店で働く人の多くが最初に挙げる理由は、「とにかく休みが少ない」「出勤時間が長い」といった労働時間の過度な長さです。飲食業では、開店から閉店までが長時間に及ぶうえ、営業時間外でも仕込みや清掃、事務的な業務が必要になる場合があります。特にスタッフの数が十分でないと、1日8時間以上のシフトが常態化し、体力的にも精神的にも大きな負担となりがちです。
また、土日祝や年末年始といった一般的に休日となる時期こそ、飲食店にとっては書き入れ時。そのため休暇を取りたいと思っても、「人手不足で回らない」「予約が多くて抜けられない」などの理由で希望日に休みをとれないことも多々あります。こうした忙しさに加え、従業員が少ないと交代要員を確保できず、長期休暇はもちろん有給休暇を申請しづらい雰囲気ができてしまうことも大きな問題です。
長時間労働が続くと睡眠不足や体調不良につながりやすく、仕事のパフォーマンス低下の要因にもなります。「きちんと休みたい」「もっと家族との時間を作りたい」といった当たり前の欲求すら満たされない環境に嫌気がさし、辞めたいと感じる人が増えてしまうわけです。こうした飲食業界の構造的なハードワークが、退職や転職を真剣に考える大きなきっかけにもなっています。
1-2. 給与が低く収入が不安定

長時間働いているにもかかわらず、思ったほど稼げない—これも飲食店を辞めたいと感じる理由の一つです。飲食業はそもそも利益率が低く、原材料費や設備投資、お店の運営費などに多くのコストがかかります。その結果、スタッフの人件費に余裕が回りにくく、「他の職種と比べて給料が低い」と感じるケースが少なくありません。
特にアルバイトやパート勤務の場合、シフトカットや突然の営業時間変更によって収入が大幅に減ってしまう恐れもあります。さらに業績の変動によっては、正社員であっても残業代やボーナスが思うように支給されないことがあり、先行き不安になりやすいのです。将来の生活を考えれば安定した収入源を求めるのは自然なことであり、「飲食店で働き続けるより別の仕事を探したい」と転職へ動くスタッフも多くいます。
1-3. 人間関係のトラブル・パワハラ・教育不足

人間関係の悩みはどんな職種でも起こり得ますが、とりわけ飲食店ではスタッフ同士のコミュニケーションが多いため、問題が起きやすいです。例えば新人を育成する立場の先輩が過度に厳しかったり、あるいは教育をそもそも放棄してしまったり。新人が「何をどうすればいいのか分からない」という状態で放置されれば、当然モチベーションは下がります。
パワハラまがいの指導が行われる現場も残念ながら存在します。忙しさのあまりイライラしてしまい、部下や後輩に暴言を吐くなど、人間としての尊厳を傷つけるような行為が常態化していると、当然「こんな環境では続けられない」と感じますよね。スタッフ間の温度差やシフト調整でのトラブルなど、人間関係で生じる小さな火種が退職につながるケースも後を絶ちません。
また、教育担当者が忙しすぎるあまり新人をフォローしきれない飲食業の現場は少なくありません。「教える余裕がないから自分で学んで」「辞めた人の穴を埋めるために今日からすぐ一人で対応して」など、現場が回らないことをスタッフ個人の努力に任せてしまうと、スキルが追いつかないままプレッシャーだけが増大します。こうした教育不足の連鎖は結果的に従業員の離職率を高め、さらなる人手不足を生む悪循環を招くのです。
1-4. クレーム・トラブル対応のストレス

飲食店は接客が主な業務となるため、顧客からのクレームやトラブル対応に追われるシーンが多く見受けられます。「料理が出てくるのが遅い」「注文と違う商品が運ばれてきた」「スタッフの態度が悪い」など、クレームの理由は千差万別ですが、その矢面に立たされるのは現場の従業員です。大声で叱られたり、理不尽な言いがかりをつけられたりする経験を重ねると、心身ともに疲れてしまいます。
加えて、人手不足が招くオペレーションの混乱がクレーム件数をさらに増やす要因となります。料理を提供するのに時間がかかったり、スタッフが不足しているせいで予約対応がスムーズに進まなかったりと、クレームやトラブルが起こるリスクは高まります。そして文句を言われるのは現場の人間であるため、直接的なストレスにさらされる時間が長くなるのです。
接客スキルの向上や心の持ちようである程度は対処できるものの、過度のストレスが続けば誰だって限界を感じます。「毎日こんな思いをするなら、いっそ退職して別の転職先を探したい」と考えるのも自然な流れと言えるでしょう。
1-5. 生活スタイルとの不一致
飲食店は夜間や深夜帯も営業するところが多く、また土日祝が繁忙となるため、一般的な平日休みのリズムとは異なる生活を強いられがちです。学生やダブルワークを前提にアルバイトをしている人であれば、むしろ好都合な働き方もあるかもしれません。しかし、家族との時間を大事にしたい人や規則正しい生活リズムを求める人にとっては「このままじゃ体がもたない」と感じることも多いです。
特に飲食業のホールスタッフやキッチンではピークタイムが夕方以降となるため、どうしても遅い時間の勤務が増えます。もし朝方の予定をこなしながら夜中まで働けば、睡眠不足が蓄積していくのは目に見えています。体力の低下はミスやクレーム増加にもつながり、精神的負担を増やしてしまうでしょう。
また一般企業に勤める友人と休みが合わず、なかなかプライベートな集まりに参加できないという悩みもあります。そうした孤立感から「もうこんな不規則な生活は続けられない」と思い、転職を検討する人は少なくありません。
1-6. 責任の重さとプレッシャー
最後に挙げられる主な理由は、他業界に比べて業務範囲が広く、責任が大きいわりに十分なサポート体制が整っていないことです。例えば小規模の個人経営店の場合、仕込みから接客、レジ締めなどの経理作業までを少人数でこなさねばなりません。スタッフが不足する中で複数の役割を同時に担当するため、日々の負担は非常に大きくなりがちです。
また店長や管理職クラスになると、アルバイトやパートを育成する立場であるにもかかわらず、自分自身が現場を回す時間も長く確保しなければなりません。「経営者から売上を上げろと言われるが、十分なスタッフは揃っていない」「対応しなければいけない業務が多岐にわたりすぎて手が回らない」など、プレッシャーばかりが重くのしかかり、心身の限界を超えてしまうのです。
こうした飲食店特有のオペレーション上の難しさや経営構造の不安定さが相まって、辞めたいという気持ちを加速させます。結果として退職者が増えればますます人手不足が進み、さらに残るスタッフへのプレッシャーが増大するという悪循環に陥るケースも多いのが実情です。
2章. 人手不足による業務負担と回らない飲食店の現場の実情

2-1. なぜ「人手不足で回らない」のか?
飲食店の人手不足が深刻化している背景にはさまざまな理由がありますが、中でも「ブラック職種」というイメージが根強いことは大きな要因の一つです。長時間労働、休みづらいシフト、低めの給与水準……そうした情報が広まり、求人を出しても応募が集まりにくい状況が生まれています。店長やオーナーが苦労してスタッフを採用しても、劣悪な労働環境では定着する前に退職してしまうことも珍しくありません。
もう一つ大きいのは離職率の高さ。アルバイトやパートを中心とした運営の飲食店では特に、シフトの融通がききづらかったり、想定以上の業務量に圧迫されたりすると「やっぱり合わない」と感じやすくなります。実際に働いてみると想像以上の体力・精神力が必要なため、早々に辞めてしまう人が相次ぎ、また新たに求人をかける…という繰り返しです。
こうした構造的な問題が続くと、現場に残っている従業員は少人数でお店を回さざるを得なくなります。その結果、日々の対応がいっぱいいっぱいになり、新しいスタッフをフォローする余裕も生まれず、さらに定着率が下がるという悪循環を生むのです。
2-2. 一人あたりの業務量の増加とストレス
人手不足の飲食店では、1人のスタッフが複数の業務を同時並行でこなすケースが多くなります。たとえばホール業務をしながらキッチンのフォローにも入る、ドリンク作りもしつつレジ対応をする、などです。本来なら専任の担当を配置したいところですが、従業員を増やすための採用コストや余力がないために実現できません。
このように業務の幅が広がると、それだけ責任が増しプレッシャーも強くなります。特にピークタイムに「注文ミスをしてしまった」「予約表を確認しきれなかった」などのトラブルが重なると、スタッフ側としては大きなストレスを感じるでしょう。余裕がない現場ではミスが起こりやすく、そのミスがクレームにつながり、結果的にさらなる負担増を招くという循環に陥ります。
さらに、複数業務を掛け持ちすると本来の仕事が疎かになるリスクもあります。接客がおろそかになれば顧客満足度が下がり、料理の質が落ちればリピーター離れが進むといった形で売上にも悪影響が出ます。スタッフそれぞれが「これ以上無理」と感じながら頑張っている状態が長く続けば、当然また退職の考えが浮かんでしまうのです。
2-3. 利益確保のための人件費削減
飲食業は原材料費やテナント料など固定費が多く、競合他店との価格競争も激しいため、収益を上げづらい構造にあります。そのため経営者側はどうしても人件費を抑えようとする傾向が強まります。「必要最低限の人数で回そう」「スタッフを増やせない」という方針が続くと、労働環境は厳しくなり、スタッフは過度な業務を強いられることになります。
ある程度の売上を見込める大手チェーン店であっても、全国展開に伴う固定費や広告費などの出費がかさむ場合、やはり従業員に十分な還元をする余裕が持てないケースがあります。そのため現場のスタッフが「この給料や待遇ではやっていられない」と感じて退職し、また新たに求人を出す…という負のスパイラルに陥ります。
3章. 飲食店が人手不足になる主な要因

3-1. 給与・待遇面の課題
「飲食店は給料が低い」イメージは、残念ながら業界全体を覆う固定観念の一つです。実際、飲食業には仕入れや光熱費、店舗維持費など多くのコストがあり、利益率が高いとは言い難いのが現状。採用したスタッフに十分な給与や福利厚生を用意するのが難しいため、「時給が割に合わない」と感じてしまう人は多いです。
さらに、昇給やボーナスといったプラスアルファの待遇が設けられていない現場も少なくありません。忙しさは増す一方で収入面が変わらなければ、当然離職率は高まります。アルバイトであっても、時給アップの明確な基準や評価制度がなければやる気が続かないでしょう。こうした給与面の不満が転職への動機となり、「飲食業は大変」という評判が外部へ広がることで、人手不足の加速を招いています。
また、大手チェーン店であっても同様の課題を抱えている場合があり、そこから逃げるように辞めてしまう人が後を絶ちません。求人広告では「高時給」「自由なシフト」と謳っていても、蓋を開けてみるとその実態は違う……というギャップも、人手不足に拍車をかける要因です。
3-2. 教育・研修体制の未整備
人手不足が続く飲食店では、新規スタッフをしっかり教育する余裕がないまま、すぐに現場へ投入してしまうことが多いです。特に繁忙期やディナータイムは、1日目から戦力扱いされる新人も珍しくありません。結果として接客や調理に関する基礎が身につかないまま業務をこなすことになり、本人は不安やストレスを抱え続けます。
また、中途採用やアルバイトで入った人が研修もないままホール対応を求められ、「お店のメニュー構成が分からない」「レジ操作の仕方が分からない」などの初歩的な疑問を抱えたまま仕事をするケースもあります。周囲に相談したくても忙しくて誰も捕まらない、マニュアルがあっても内容が更新されていない……こうした背景から、新人が短期で辞めてしまう現象が起こるのです。
飲食店で安定したスタッフ運営をするためには、基礎的な研修が必要不可欠です。しかし現場が回らないほどの人手不足の状態で、新人指導に割ける時間を確保するのは至難の業です。この悪循環こそが飲食業界全体の大きな課題と言えるでしょう。
業務のオペレーションを見直したい方は、『飲食店のオペレーションを劇的に効率化!マニュアルの作成方法まで徹底解説!』の記事を参考にしてみてください。
3-3. シフトの柔軟性欠如と休暇の取りづらさ
飲食店のシフトは営業形態や規模によって異なりますが、「土日祝こそ出勤する」「夜間帯も担当する」といった固定観念が強い場合が多いです。もちろん繁忙期にスタッフが必要なのは事実ですが、プライベートの予定や家族の行事などがあっても休みにくい雰囲気が続くと、長期的なモチベーション維持は難しくなります。
また、病気や急用などでやむを得ず休む必要があるときも、代わりに入る従業員が確保できず結果的に「休めなかった」という声も多いです。これでは心身ともに疲弊し、働き続けるのがつらいと感じても仕方ありません。
一方で、現場としては「誰かにフォローを頼めるほどの人数がいない」という状況があるため、簡単にシフトを組み替えられない事情もあります。アルバイトスタッフの中には「テスト期間中は週0にしてほしい」「掛け持ちの仕事と調整したい」という希望を持つ人もいますが、店舗側で対応しきれず「それなら辞めます」という話になってしまう例もしばしばです。
3-4. 職場の雰囲気・人間関係
職場の雰囲気が悪いと新人が入ってきてもすぐに辞めてしまうのは、あらゆる業種で共通する現象です。飲食業の場合、忙しいピーク時にはスタッフ同士の意思疎通が難しくなり、コミュニケーション不足や言葉のきつさが目立ちがちです。特に指示や連携がうまくできないままトラブルが起これば、誰かを責めたり責任を押し付け合ったりする雰囲気が生まれることもあるでしょう。
例えばホール担当とキッチン担当の連携がうまくいかず、提供する料理が間に合わない、オーダーが通っていないなどのミスが重なると、疑心暗鬼になりがちです。「自分は悪くないのに」と思う気持ちが高ぶると不満が募り、退職を考えるきっかけにもなります。また、アルバイト同士や正社員との間で上下関係が過度に厳しかったり、逆に責任感の差が大きすぎたりすると軋轢が生じやすいです。
3-5. コロナ前後で変わらないアルバイト離職パターン
コロナ禍を機に飲食店の営業時間短縮や休業が相次いだことから、人手不足に拍車がかかった面もあります。営業形態の変化によりアルバイトやパートのシフトが減らされ、収入源を別の業界へ求める人が増えました。しかしコロナ後に営業を再開しても、今度はバイトが集まらない状態に陥り「お店が回らない」といった声が続出しているのが現実です。
実際、1週以内や4週以内、8週以内など、短期離職するアルバイトが目立つとするデータもあります。これはコロナの影響があった時期だけの特殊な現象ではなく、もともと飲食業で一定数見られた傾向でもあります。体力的・精神的にきついイメージが根付いているうえ、研修体制の未整備が多いため、実際の仕事を体験した新人ほどギャップに耐えきれず早期に辞めるのです。
こうした離職率の高さを見れば、新たな人材の採用はもちろん、既存スタッフをどう定着させるかが飲食業界全体の大きなテーマであると分かります。結局、一度辞めた人に代わる新しいスタッフを探そうとしても、求人への応募が少なく、経営者や店長が自ら長時間勤務を強いられるケースも後を絶ちません。コロナ前から存在していた負のサイクルが、コロナ禍を経て一段と顕在化したといえるでしょう。
4章. 人手不足の飲食店を辞めたいと思っても退職しづらい現状

4-1. 後任が見つからないから辞められない
飲食店で「辞めたい」と感じても、実際に退職を切り出しにくい理由として多く挙げられるのが「後任が見つからないから」です。人手不足の飲食業では、新たなスタッフを採用してもすぐに辞めてしまうケースが珍しくありません。したがってオーナーや店長も、「今いる従業員を極力つなぎ止めたい」という心理が強くなります。「辞めるなら代わりを見つけてきて」と言われる場面もあり、現場の状況からしても、交代要員が決まらないと退職するのは気まずい雰囲気が漂いがちです。
こうした環境では、辞意を伝えるだけでも大きな負担を感じてしまいます。ましてや自分自身が限界を感じていても、「引き継ぎをどうすればいいのか」「スタッフ不足の状態で辞めたらお店が回らないのではないか」と考えてしまうと、なかなか一歩を踏み出せません。とりわけキッチンのメイン担当やホールのリーダー的存在が辞めるとなると、その穴を埋めるのは容易ではありません。結果的に、「もう少し我慢して働き続けるしかない」という思考に陥ってしまうのです。
しかし長期的に見れば、限界を超えたまま仕事を続けるのは本人の健康にも悪影響ですし、お店のサービス品質の低下も招きます。後任問題に対するプレッシャーを理由に退職を先延ばしにしているうちに、心身ともに疲弊してしまうケースも多いです。本来、退職の意思決定は個人の自由であり、飲食業界や人手不足が原因であっても、無理に引き留められるべきではありません。適切に退職手続きを進める方法を知ることが、結果的には自分だけでなく職場のスタッフ全員にとってもプラスになる場合があります。
4-2. 残っているスタッフへの罪悪感
人手不足の飲食店では、自分が辞めることで「残ったスタッフにしわ寄せがいくのではないか」という罪悪感も大きな障壁となります。とくに少人数で営業しているお店では、一人が退職するだけでシフトが組めなくなったり、仕事の分担が崩れてしまうこともあるでしょう。ホールスタッフが辞めればキッチン担当が接客を兼務せざるを得ない、あるいはアルバイトだけで回すには経験不足が露呈する……といった具合に、業務全体に影響が及びやすくなります。
このような状況で「私が辞めたら、あの人に多大な負担がかかる」という思いが強まると、辞意を切り出しづらくなるのは当然です。常連のお客様との関係性や、ほかの従業員とのチームワークに愛着を感じている人ほど、退職を後ろめたく思う傾向にあります。
しかし、現場に残る人々の気持ちを考慮することも大切ですが、自分の生活や健康を犠牲にしてまで我慢する必要はありません。飲食店の経営側が本来担うべき「スタッフの採用」「従業員が働きやすい職場環境づくり」を個人が背負い込むのは負担が大きすぎるからです。人手不足で回らない職場ほど「辞める人が悪者」という空気が生まれやすいものの、それは構造的な問題であり、個人の問題だけではないと認識しておきましょう。
4-3. オーナーや本部からの待遇交渉・説得
いざ退職を申し出ると、経営者やオーナー、チェーン店の場合は本部から「給料を上げるから続けてほしい」「もう少しだけ頑張ってほしい」などの交渉が入る場合があります。飲食店の人手不足が深刻であるほど、貴重な戦力を失いたくないという思いから、急に好条件を提示することも考えられるでしょう。特に店長クラスやベテランスタッフであればあるほど、引き留めは強くなる傾向があります。
もちろん待遇の改善や給与アップは魅力的かもしれませんが、これまで改善されなかった環境が突然大きく変わる保証はありません。「いまは一時的に優遇されても、長期的に見れば同じ問題が残るのでは?」という疑念が拭えないケースも多いです。たとえばシフト体制や休日取得の仕組みが根本的に変わらないまま、ほんの少し給与を上げるだけでは、人手不足そのものを解消できません。結果、働き方のストレスは継続してしまい、結局は同じ悩みにぶつかる可能性があります。
また、場合によっては退職を申し出たスタッフに管理職ポジションを提示したり、「店長を任せるからもう少し頑張ってほしい」と説得を試みる例もあります。昇進や役職は一見魅力的に見えますが、責任が増してプレッシャーが倍増するリスクを伴うのも事実です。そもそも「辞めたい」という思いに至った原因が、給料や地位だけではない場合も多いでしょう。待遇交渉で心が揺らいだとしても、冷静に「なぜ自分は退職を考えたのか」という理由を再確認することが大切です。
4-4. 転職活動の時間が確保できない
飲食業のシフトは朝から夜遅くまで長時間に及ぶことが多いため、転職活動の時間を十分に取れない人が少なくありません。土日祝は忙しく、平日もランチタイムやディナータイムに合わせて出勤するとなると、なかなか面接の予約を入れることができないでしょう。特にフルタイムで働く正社員や店長候補、社員候補として勤務しているスタッフにとっては、休みの日に体を休めるだけで精一杯という状況になりがちです。
このように「転職したいけれど、求職情報を調べる余裕がない」「次の仕事を見つけたいが、応募手続きをする時間すらない」という悩みを抱えていると、いつまでも退職を切り出せない悪循環に陥ります。また、一部の経営者の中には「辞めるなら後任を探せ」「就職先が決まらないまま辞めると損だよ」という言葉で心理的な圧力をかける人もいるため、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも多いです。
とはいえ、自分のキャリアを守るためには計画的な転職活動が不可欠です。少しでも時間を有効に使う工夫をしたり、転職エージェントに相談して日程調整や求人情報収集をサポートしてもらうなど、忙しい人こそ「外部の力を借りる」視点が重要になります。たとえ飲食店で働きながらでも、効率的に転職先を探す方法を知れば、退職をスムーズに進める道は開けるのです。
5章. 飲食店が人手不足のまま回らないと陥る悪循環
5-1. サービス低下によるクレーム増加
人手不足の飲食店が回らない状態になると、もっとも顕著に表面化するのが「サービスの質」の低下です。お店にとっては料理の提供スピードや接客対応のレベルが大きな評価ポイントですが、スタッフが足りずオペレーションが混乱していれば、当然品質は落ちがちになります。例えば、ホール担当が少ないと注文が集中してもすぐに対応できず、待ち時間が長くなる。キッチン担当が足りないと、調理が追いつかず料理の提供に遅れが出る。こうした細かなストレスは、お客様のクレームにつながりやすいのです。
しかも、すでに人手不足でギリギリの状態だと、クレームの対応そのものが追加の負担になります。1件1件に丁寧に向き合う余裕がなく、結果的に謝罪やフォローが雑になってしまい、「さらにクレームが増える」という悪循環に陥ります。顧客満足度が下がるだけでなく、スタッフのメンタル面にも悪影響が及び、離職意欲を加速させる一因にもなるでしょう。
そしてクレームが増加すれば、お店の評判が落ちてリピーターが減り、新規のお客様も来店しにくくなります。売上が下がれば経営状態が悪化し、ますます人件費を抑えようとする……という具合に、負のスパイラルに突入してしまうのです。経営者や店長としても、「これでは回らない」と分かっていても、迅速にスタッフを増やせない事情があり、状況は悪化の一途をたどりがちです。
5-2. スタッフのモチベーション低下
サービスの質が低下すると顧客からのクレームが増えるだけでなく、現場のスタッフが抱える精神的負担も大きくなります。「一生懸命やっているのに、クレームばかり浴びる」「ミスが続発して上司に叱られる」「休みたいときに休めない」などが重なれば、モチベーションを失ってしまうのは当然です。
特に、キッチンスタッフが限られた人数で大量の注文に対応しなければいけない場合、疲労が蓄積して常にギリギリの精神状態になることがあります。ホール担当も同様に、忙しさのあまり笑顔を保てず、お客様にそっけない対応をしてしまうかもしれません。「本当はもっと丁寧なサービスをしたいのに、人手不足が原因でできない」というジレンマが、スタッフのやる気を削ぐ要因にもなります。
また、長時間労働やシフトの過密化、給与の伸び悩みによる将来不安が加わると、「このままでいいのだろうか」と思うスタッフが増え、退職や転職を考え始める人が続出します。人が辞めると現場はさらに回らなくなり、残った従業員の負担は一層増大する——これが人手不足が続く飲食店にありがちな悪循環です。一度モチベーションが下がったスタッフを引き留めるのは難しく、経営者や本部としても対症療法的な対応に追われがちなのが現状となっています。
5-3. 経営面への打撃と離職率の加速
クレーム増加とサービス低下によって売上が落ちると、飲食店の経営はますます苦しくなります。売上が減少した分を補うために「さらにコストを削減しなければならない」という判断が下されると、真っ先に槍玉に挙がるのが人件費です。しかし、人件費削減はさらに人手不足を加速させ、従業員の勤務負荷を増大させる結果を招きます。そうなると、今度は離職率がさらに高まるという「負の連鎖」が発生するわけです。
一度離職が加速し始めると、募集をかけても応募が集まらず、ますます現場が回らない状態に陥ります。求人広告を出しても「飲食業は大変そう」という一般的なイメージに加え、口コミサイトやSNSでネガティブな評判が広まれば、採用が難しくなるのは当然です。こうして採用活動がうまくいかずに経営難に陥る飲食店は多く、最悪の場合は閉店に追い込まれる可能性すらあります。
人手不足が続く背景には、飲食業界特有の低利益率やシビアな価格競争があり、簡単には解決しにくい構造的な問題も潜んでいます。しかし、具体的な解決策を講じないまま放置すれば、現場の負担が増え、退職者や転職希望者が後を絶たない状況が続くでしょう。結果としてお店そのものが立ち行かなくなり、スタッフと経営側双方にとって不幸な結果につながることを、経営者や店長も真摯に認識する必要があります。
6章. 人手不足解消に向けた飲食店の具体的な解決方法

6-1. 給与・評価制度の改善と福利厚生の充実
飲食店で人手不足を解消し、スタッフが「辞めたい」と思わなくなる環境をつくるためには、まず給与面や評価制度の見直しが欠かせません。どれだけ忙しくとも、正当に報酬が支払われたり、明確な評価基準が存在すればスタッフのモチベーションは保ちやすくなります。例えば、時給アップの条件を具体的な数値(売上目標や接客スキルの達成度など)で設定し、一定の基準を満たせば確実に昇給する仕組みを用意することは効果的です。
正社員や店長候補の場合でも、昇格やボーナスに関する基準が曖昧では、先が見えず不安になります。客観的な評価項目を設けて、スタッフ一人ひとりが「自分の頑張りはどのように見られているか」を把握できるようにするだけでも違います。加えて福利厚生の充実も重要な要素です。例えば「まかない」や「食事補助」制度によって食費を抑えられたり、スタッフの健康管理に配慮した仕組みを導入したりすると、飲食業でも従業員の満足度を高めやすくなります。
また最近は「チケットレストラン」などのサービスを通じて、社員食堂がない職場でも食事補助をスマートに提供する企業が増えています。飲食店であっても、外部の補助サービスを活用すれば、従業員の経済的負担を軽減できるケースがあるのです。給与と福利厚生の両輪でスタッフの満足度を高めることが、人手不足解消の第一歩といえるでしょう。
従業員満足度を高めつつ、無理のないコスト削減を実現する方法を『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』に載せてますので併せて確認してみましょう
6-2. 働きやすい環境づくり(研修・休暇制度・DX化)
飲食業界は、どうしても「きつい仕事」というイメージが先行しがちです。そこで必要なのは、実際に働くスタッフが「ここなら続けられそうだ」と思えるような職場環境づくりです。まず取り組むべきは、研修の充実化。新人スタッフが何をどう学び、どこまでできるようになれば一人前なのかをわかりやすく明示し、ステップを踏んでスキルアップできるようにするのです。教育担当を決めてマニュアルを整備したり、動画教材やオンライン研修などDXの活用で時間と場所を問わず学べる仕組みを整えるのも効果的でしょう。

休暇制度やシフト調整の柔軟化も大切です。スタッフが繁忙期を把握しながらも、プライベートの予定や体調を考慮して休みを取りやすい仕組みを作れば、長期的に働く意欲を高められます。たとえば週休2日制を導入したり、有給休暇を取得しやすい雰囲気を作るなど、少しずつでも改善を積み重ねることが求められます。
また、飲食店でもDX(デジタルトランスフォーメーション)に力を入れる事例が増えています。予約管理システムを導入してオペレーションを簡略化したり、セルフオーダーや配膳ロボットを活用してスタッフの業務負担を軽減する動きが広がりつつあります。人的リソースの一部をロボットで補うことで、お客様とのコミュニケーションに注力できる時間を増やすことができれば、接客の質の向上やスタッフのストレス軽減につながります。
6-3. 多様な人材採用と助成金・補助金の活用
人手不足を抜本的に解決するには、求人の対象を広げ、多様な人材を採用する取り組みも必要です。例えば外国人材の積極採用をサポートする「特定技能」制度を活用すれば、海外からのスタッフを迎えやすくなります。また主婦(主夫)やシニア層など、従来はあまり意識しなかった層にもアプローチしてみることで、新たな視点や経験を職場に取り込めるかもしれません。
その際には、国や自治体が提供している助成金や補助金をうまく活用するのがポイントです。雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、従業員の教育や就業支援に対して補助を受けられる制度は少なくありません。助成金を受け取るためには一定の条件や手続きが必要ですが、スタッフのスキルアップや職場環境の改善を行う費用として有効に使えます。
さらに求人の方法を見直すことも大切です。従来の求人サイトだけでなく、SNSを使った採用活動やスタッフ紹介制度の導入など、新しい手段を試みることで従来の枠にとらわれない人材を獲得できる可能性があります。応募の幅を広げることで、飲食店の人手不足を緩和し、「辞めたい」と思わせない働きやすい環境づくりを加速させることができるでしょう。
6-4. アルバイト・スタッフへのフォロー体制強化
飲食店の運営は、アルバイトやパートスタッフが大きく支えています。彼らの定着率を高めることができれば、人手不足で回らないという深刻な事態を防ぎやすくなるでしょう。そのためには、フォロー体制の強化が不可欠です。具体的には、定期的に面談を設けて悩みや困りごとを把握したり、新人スタッフに対して「メンター」や「先輩係」を明確にする方法があります。
仕事の進め方や接客マナー、予約対応などの業務について、誰に聞けばいいのかが分かるだけでも、アルバイトスタッフは安心感を得られます。また、ポジティブなフィードバックや感謝の言葉を伝える習慣を作るだけで、モチベーションを大きく向上させる効果があります。人間関係が良好であるほど離職率は下がる傾向があるため、人手不足対策としても有効な手段です。
スタッフ同士のコミュニケーションを円滑にするために、チャットツールや業務管理アプリなどを導入してシフト情報や業務連絡を共有する例も増えています。ICTを活用して連絡漏れや情報の不透明さを減らせば、スムーズな連携が取りやすくなるでしょう。こうしたきめ細かいフォロー体制が整っている飲食店こそが、結果的に「辞めたい」という声が少なくなる環境を生み出し、人手不足の悪循環を断ち切る大きな鍵になるのです。
こうしたフォロー体制は、アイドルタイムで有効に活用することが良いです。『飲食店のアイドルタイムとは?その時間を活用して売上や集客に繋げる方法を大公開!』も併せて確認いただくことをおすすめします。
7章. それでも辞めたい!飲食店を辞める際の注意点と円満退職のコツ
7-1. 退職理由を整理しておく大切さ
飲食店で人手不足が深刻な状況だとしても、自分のキャリアや健康面を犠牲にしてまで働き続ける必要はありません。ただし、退職を考える際にはまず「なぜ自分は辞めたいのか」を明確にすることが大切です。たとえば長時間労働がつらいのか、給与が低く不安定な収入が厳しいのか、あるいは人間関係に我慢できなくなったのか…。理由がはっきりしていれば、上司やオーナーに伝えるときもスムーズですし、今後の転職先を探すうえでも方向性が見えやすくなります。
飲食業の現場では、人手不足ゆえに「そのうち改善されるだろう」「もう少し頑張れば楽になるかも」と淡い期待を抱きながら現状を耐え続ける人が少なくありません。しかし実際には、スタッフが足りないままお店を回し続ける経営方針が根付いていたり、採用計画が後手に回っていたりと、抜本的な改革が難しい場合も多いのが実情です。退職理由の整理は、そうした厳しい状況の中で自分にとって最良の選択をする第一歩といえます。
7-2. 退職の意向は早めに伝える
どの業種でも言えることですが、とくに飲食店はシフト制でありスタッフ同士の連携が重要です。後任の採用や引き継ぎ、予約・在庫管理の調整などを考慮すると、退職の意向は可能な限り早めに伝えるのがベターです。法律上は2週間前の告知があれば退職可能とされていますが、実際には1か月前、あるいは2~3か月前に伝えておく方が円満退職に近づけます。
特に飲食店の繁忙期(年末年始やゴールデンウィーク、夏休みシーズンなど)をまたぐタイミングで辞める場合、辞意を伝える時期が遅れると現場に大きな混乱を招く恐れがあります。スタッフの求人活動やシフト調整には時間がかかるため、早期に知らせることで残るスタッフへの負担を軽減しやすくなるのです。また、円満退職を望むのであれば、オーナーや上司との良好な関係を保ちながら計画的に行動することが欠かせません。
さらに、引き継ぎを円滑に進めるためにも早めのアナウンスは重要です。ホール業務の流れ、在庫の管理手順、キッチンのオペレーションなど、各職種それぞれに独自のノウハウがあります。これを急に辞める直前にまとめようとしても時間的に厳しく、後任が混乱する原因になります。「辞めるからといって無責任に放り出すのではなく、最後までお店に貢献したい」という姿勢を見せることで、今後の仕事や転職にも良い影響が期待できるでしょう。
7-3. 引き留め交渉・退職拒否への対処法
飲食店はただでさえ人手不足が続いているため、経営者側や店長が退職の意思を示すスタッフを引き留めようとするのは自然なことです。「辞めるなんて無責任だ」「代わりが見つかるまで働いてほしい」といった説得は、本人にとっては重荷に感じられるでしょう。場合によっては「バックれ」「飛び出すように辞める」という最終手段を取ってしまう人もいますが、そうした行為はトラブルを招きやすく、残るスタッフとの関係にも悪影響を及ぼします。
引き留め交渉を受けたら、まず冷静に自分の退職理由を再確認しましょう。給料や休暇制度など、改善されれば残れる余地がある理由であれば、妥協点を探ってみるのも一つの選択肢です。しかし、多くの場合は構造的・根本的な問題(慢性的なスタッフ不足、長時間労働が当たり前、経営者が意識を変えないなど)が背景にあるため、一時的な条件アップだけでは本質的に状況が変わらないケースが多いです。
どうしても話がこじれる場合は、労働相談窓口や専門家への相談も検討してください。退職拒否や過度な引き留めは違法な行為になることもあるため、自分だけで抱えこまずに外部の力を借りるのも賢明な手段です。飲食店であっても適切なルールに則って退職する権利は保証されています。円満退職を目指しつつ、実際に交渉が難航するなら、必要に応じて法律や周囲のサポートを活用しましょう。
8章. 飲食店を辞めた後の不安と転職先の候補について

8-1. 退職後に生じやすい不安の整理と解消策
飲食店を辞めたいと思っても、「退職後の生活が心配」「次の仕事が決まっていない状態で辞めて大丈夫かな」という不安がよぎる人は多いです。特に貯金があまりない場合や、家族を養わなければならない立場の人にとっては、収入が途絶えるリスクは大きな問題ですよね。転職先の採用面接で不利になるかもしれないと考えたり、社会保険の切り替えなど手続きの面倒さに気後れしてしまうこともあるでしょう。
このような不安に対処するためには、まずは自己分析と情報収集が大事です。自分の強み(接客スキル・マネジメント経験・調理技術など)を明確にし、それを活かせるお店や異業種の職種を調べるところから始めると、「意外と自分にはこんな可能性があるんだ」と前向きな気持ちになれるかもしれません。求人サイトの情報だけでなく、SNSや口コミサイトなどを活用して現場のリアルな声を集めるのも手段の一つです。
また、生活費が気になる人は、退職後一定期間だけはアルバイトやパートでしのぎながら転職活動をする方法もあります。飲食業での経験を活かし、短期のアルバイトやコールセンター、派遣など柔軟な働き方をしながら、じっくり次の仕事を探すという選択肢もあるのです。いずれにせよ、焦って決めた職場で再び「こんなはずじゃなかった」とならないよう、計画的に行動することで退職後の不安を解消しやすくなります。
8-2. 優良な飲食店・外食企業を探す方法
いくら「飲食店を辞めたい」と思っても、中には「やっぱり飲食業が好きだから、優良なお店や企業で続けたい」と考える人もいます。そもそも接客が楽しい、食べることが好き、人と話すのが得意……など、飲食業ならではのやりがいを感じる方は珍しくありません。その場合は、離職率が低く、待遇や働き方に配慮がある「ホワイト企業」や「優良企業」を見つけることがカギとなるでしょう。
また、大手転職エージェントや飲食業専門のエージェントを活用すると、非公開求人を紹介してもらえることもあります。表立って募集をかけていない優良企業を知るチャンスでもあるので、「飲食業を続けたいけど、もっと働きやすいお店を探したい」という人は相談してみるのがおすすめです。人材が確保しづらい外食産業だからこそ、充実した待遇やキャリアアップ制度を備えた企業も少なからず存在します。求人情報を丹念に探れば、自分にぴったりの職場が見つかるかもしれません。
8-3. 異業種・異職種への転職アイデア
一方で、「接客経験は好きだけど、飲食業の厳しい労働環境にはもう耐えられない」「食べ物を扱う仕事そのものには飽きた」という人もいるでしょう。その場合は、異業種や異職種への転職を視野に入れると、新たなキャリアパスが開ける可能性があります。具体的には、営業職や事務職、IT業界、食品メーカーなど、飲食店で培ったコミュニケーション能力や臨機応変な対応力を活かせる仕事は多種多様です。
営業職なら、接客経験で培った「人と話す力」や「サービス意識」が大きな武器になります。事務職でも、お店の在庫管理や簡単なパソコン操作の経験は活きてくるでしょう。また、IT業界と聞くと専門知識が必要と思われがちですが、近年は未経験OKの求人も増えています。オンラインでの予約システムを導入していた飲食店で働いていた経験があれば、多少のITリテラシーは身に付いているかもしれません。
食品メーカーや小売業界では、商品企画や販売促進の部門で、飲食店での実務経験が評価されることがあります。調理やメニュー開発などのスキルを活かす職種もあり、「食の現場を経験している人を求めている」という企業も存在します。これまでの経験を別の角度からアピールすれば、意外と幅広い仕事に挑戦できることに気づくでしょう。
8-4. 飲食店で働く魅力を再発見する視点
「人手不足で回らない」「辞めたい」といったネガティブな面ばかりが取り沙汰されがちな飲食業ですが、実は他にはない魅力があるのも事実です。たとえば、お客様から直接「おいしかった」「ありがとう」という声をもらえるのは接客業ならではのやりがいでしょう。仕事の成果が目に見えやすく、喜ばれる瞬間にやりがいを感じる人にとっては、飲食店ほど達成感を得られる職種は多くありません。
また、従業員同士の距離が近く、チームワークを大切にする文化が根付いているところも飲食店の特徴といえます。忙しいピークタイムを乗り切った後の達成感や、一緒に働く仲間との絆は、オフィスワークでは得にくい一体感を味わえるでしょう。そして何より、食べ物や飲み物の知識を深められるため、プライベートでも活かせるスキルが身に付くのもメリットの一つです。
もし飲食店が好きで、「本当は辞めたくないけど環境が合わない」だけが原因ならば、別のお店や好条件の外食企業を探すという方法も残されています。自身の体力やライフスタイルに合った規模や業態、勤務形態を選ぶことで、同じ飲食業でも働きやすさが大きく変わることは珍しくありません。転職活動をしながら改めて「自分が飲食業に求めるもの」を見直し、それを満たせる職場がないか探してみるのも一案です。
9章. 仕事で忙しくても転職を成功させるためのポイント

9-1. 転職エージェント活用のメリット
「次の職場を探したいけれど、シフトが不規則でそんな時間がない」「飲食店でクタクタになって帰宅すると、求人を見る余裕がない」という人には、転職エージェントを利用する方法が適しています。エージェントはプロのキャリアアドバイザーがヒアリングを行い、求職者の希望やスキルに合わせた求人をピックアップしてくれるサービスです。特に飲食業専門のエージェントであれば、業務内容やお店側の状況を理解しているため、ミスマッチが生じにくいというメリットがあります。
さらに、転職エージェントを通じて応募する場合は「非公開求人」に出会える可能性も高まります。大手外食企業や人気レストランなど、一般には公表せず、紹介経由でしか募集していない求人があるのです。忙しい人ほど、エージェントに日程調整や面接対策、応募書類の添削などを一括で依頼できる利点を享受しやすいでしょう。また、在職中でなかなか会社(お店)に相談しにくい人も、電話やオンライン、LINEなどでサポートを受けられるケースが多いため、時間を効率的に使えます。
9-2. 短時間で効率的な求人リサーチ法
忙しい合間を縫って転職活動を進める際、効率的な求人リサーチは欠かせません。まず、スマホのアプリを活用するのがおすすめです。大手求人サイトや転職支援サービスは専用アプリを提供しており、自分の希望条件(職種、勤務地、給与、アルバイト・正社員の別など)を保存しておけば、最新の求人情報がプッシュ通知される仕組みになっています。働きながらでも休憩時間や通勤時など、ちょっとしたスキマ時間に新着求人を確認できるのは大きな時短メリットです。
また、SNSやコミュニティサイトをチェックするのも有効です。飲食店のオーナーや人事担当者が独自に情報を発信しているケースもあり、一般の求人媒体には出回っていない「隠れた好条件案件」が見つかる可能性があります。たとえば、「スタッフ募集中です。研修しっかりします」「新業態立ち上げメンバー募集」など、直接声をかけてもらえることもあるかもしれません。
さらに、口コミサイトやレビューサイトでお店の評判を調べるのも大切なポイントです。「実際に働いているスタッフがどんな感想を持っているのか」「経営者の人柄はどうか」「職場の雰囲気は良いか」といった生の情報を集めれば、ブラック企業への就職を未然に防げる可能性が高まります。短時間でリサーチしても、要点を押さえた情報収集ができれば、忙しい中でも転職活動をスムーズに進めることが可能です。
9-3. 忙しい人こそ知っておきたい転職成功の鍵
飲食店で働きながら転職活動を行うのは、体力的にも時間的にも厳しいかもしれません。しかし、計画的に動くことでスムーズに次のステップへ進めるケースも多々あります。ポイントの一つは、スケジュール管理の徹底です。自分のシフトを見ながら面接可能な時間帯をいくつかピックアップしておき、候補をまとめておくと、いざ面接日程の打診があったときにやり取りがスピーディに進みます。
また、あらかじめ履歴書や職務経歴書を作成しておくのも大切です。飲食業での経験をどのようにアピールできるか、どんなスキルが他職種にも活かせるかを整理しておけば、エージェントや企業とのやり取りが一層スムーズになります。接客・予約対応・在庫管理・売上管理など、一見すると当たり前の「業務」も他の業界では評価される可能性があります。自分では気づきにくい強みを明確化するだけで、選考通過率がぐんと上がることもあるでしょう。
転職先が決まってからの退職手続きは、余裕を持って進めるのが理想です。新しい職場へ入社するタイミングと、今の職場でのシフトを丸ごと把握した上で計画を立てれば、引き継ぎや残務整理を円満に行いやすくなります。忙しい人ほど、「できるだけ早く辞めたい」と焦る気持ちもあるかもしれませんが、ここを慌ててしまうとトラブルの原因に。冷静かつ着実にステップを踏むことこそが、忙しくても転職を成功させる鍵と言えるでしょう。
10章. 飲食店の人手不足と退職に関するよくある疑問と対策
10-1. 「辞めたい」と思ったときは何日前に伝えればいい?
法律上は、正社員であっても2週間前に退職の意思を示せば辞めることは可能とされています。ただし実際の飲食店現場では、2週間では後任の採用やシフト調整が間に合わない場合がほとんどです。スタッフが少ないお店なら、営業が滞る可能性すらあります。そのため可能な範囲で1か月以上前には告知するのが円満退職につながる基本的なマナーです。
また、繁忙期を目前に控えている場合や、特に大きな責任を担っているポジションの場合は、2〜3か月前から上司やオーナーに相談しておくとスムーズに話が進みやすいです。退職交渉が難航しそうな場合でも、「〇月〇日をもって辞めたい」「後任が決まるまでどのくらい手伝えるか」など具体的なプランを用意しておくと、説得力が増してスケジュール調整もしやすくなります。
10-2. 転職先が決まっていない状態でも退職していい?
もちろん法的には問題ありませんが、飲食店はシフト制のため退職時のタイミングが現場に与える影響は大きいです。次の仕事先が未定だと、退職後の生活費や保険手続き、年金手続きなどを急いで整えなければならず、結果的に焦って再就職を決めるリスクもあります。できるだけ計画的に転職活動を進め、ある程度目星をつけてから退職するほうが望ましいでしょう。
ただし、心身の不調を抱えたまま無理を続けると取り返しがつかなくなるケースもあるので、「これ以上継続するのが難しい」という状況ならば勇気を持って退職に踏み切る選択も必要です。最近ではアルバイトやパート、派遣の求人なども多様化しており、とりあえず生活費を稼ぎながら転職活動をじっくり進める人も増えています。生活基盤を確保したい場合、失業保険の受給条件や自治体の支援策を確認しておくことも大切です。
10-3. アルバイト・パートの場合は正社員と違うの?
雇用形態がアルバイト・パートでも、基本的には2週間前に退職の意思を伝えれば辞めることができます。ただしお店によっては、雇用契約書や労働条件通知書で「退職する際は1か月前までに申し出ること」という文言を入れている場合があるため、確認が必要です。アルバイトやパートの場合は、より気軽に入退社が繰り返されがちな一方、急な離職が人手不足の飲食店に大きなダメージを与えることも多いです。
そのため、できる限り余裕を持って辞意を伝え、引き継ぎやシフト調整の協力をしてあげるのがお店側への配慮となります。また、アルバイト・パートのスタッフこそ「即戦力」としてカウントされている店舗が多く、辞められると困るからこそ引き留めが激しくなる場合もあります。自分の働き方を見直したい場合や学業との両立が難しくなった場合でも、最終的な判断は自分の将来プランを優先させることが大切です。
10-4. 退職時にトラブルにならないための準備は?
退職時にはスケジュール管理や引き継ぎ書の作成など、最低限の準備をしておくとトラブルを回避しやすくなります。具体的には、以下のようなステップを踏むと安心です。
- 退職希望日と理由の確定
まずはいつ辞めたいのかを決め、理由を簡潔にまとめておきましょう。あらかじめまとめることで、上司やオーナーと話す際にスムーズです。 - 業務の引き継ぎ資料作成
ホール業務の流れ、キッチンの発注方法、予約対応や会計業務など、後任スタッフが困らないようにメモやファイルを整理しておきます。 - 私物や書類の確認
ロッカーや持ち場に私物がないか、貸与されている制服や備品の返却漏れがないかをチェックします。最終日までにすべて返却できるように早めに整理しましょう。 - 必要なら労働相談窓口などに情報収集
もしオーナーや店長に退職を拒否されたり、違法な残業代未払いなどがあるなら、労働基準監督署や労働相談窓口への相談を考えます。書類や契約書、タイムカードのコピーを保管しておくと有利です。
このような段取りを踏めば、最終的に円満退職できる確率が高まります。辞めるタイミングや事情は人それぞれですが、トラブルを最小限に抑えるために計画的に準備することが大切です。
11章. 最終的に「飲食店を人手不足で辞めたい…」と決めた時の動き方
11-1. itk等の飲食店の求人・転職人気エリア
もし「やっぱり飲食業は好きだ」「もう少し条件の良いお店で経験を積みたい」という思いがあるなら、飲食業専門の人材紹介や転職サイトを活用してみるのがおすすめです。たとえば「itk」などのエージェントサービスを利用すれば、首都圏の居酒屋やレストランはもちろん、カフェやホテル内レストランなど多彩なジャンルの求人が見つかるかもしれません。人気エリアとしては、東京・大阪・名古屋など大都市圏が挙げられますが、地方でも観光客が多い地域や有名リゾート地などは一定の需要があるため狙い目です。
転職先を探す際には、できるだけ「なぜ前の店で辞めたいと思ったのか」を念頭に置きつつ、同じ失敗を繰り返さないよう注意が必要です。たとえば労働時間や休日数、給与アップの可能性など、妥協できない条件をあらかじめ決めておくと、自分にとってより働きやすいお店を探しやすくなります。
11-2. 業種から探す
飲食とひと口に言っても、和食、洋食、中華、ファストフード、カフェ、バーなど、その業態やコンセプトはさまざまです。ホール接客といっても高級レストランとファミリーレストランでは求められるスキルも雰囲気も違います。もし自分が「高単価のお店で丁寧なおもてなしを学びたい」「カジュアルなフードチェーンでマネジメントを担いたい」など明確な志向があるなら、業種を絞って求人情報をチェックすると良いでしょう。
また、飲食業のなかでもテイクアウト・デリバリー専門店やフードトラックなど、新たな業態も増えています。人手不足が深刻なところほど積極的に採用を行っている可能性が高く、ユニークな形態ゆえに個性的なスキルが身に付くかもしれません。お店のスタイルやコンセプトが自分に合うかどうかも重視し、納得のいく就職先を見つけるようにしましょう。
11-3. 職種から探す
同じ飲食業でも、ホールスタッフ・キッチンスタッフ・店長候補・SV(スーパーバイザー)・本部職など、職種によって求められるスキルや勤務形態は大きく異なります。調理の技術を高めたいならキッチン特化の職種を狙ったり、接客コミュニケーションに自信があるならホールリーダーや店長候補を目指すなど、自分の強みを活かせる道を選ぶと長続きしやすいです。
また、意外と見逃されがちなのが本部スタッフや事務職の募集です。大手チェーンでは店舗運営を統括するSVや採用・経理・企画などのバックオフィス部門にポジションが用意されている場合があります。現場の大変さを身をもって知っている人材は、本部側からすると貴重な戦力になり得ますので、自分の経験をアピールできれば採用されるチャンスは十分あるでしょう。
11-4. アルバイトの人材採用・求人広告掲載はトラコムに
もし飲食店側(経営者や店長)で「人手不足をどうにかしたい」「求人を出しても応募が来ない」という悩みを抱えているなら、アルバイト・パート採用の専門サービスを検討してみるのも手段の一つです。たとえば「トラコム」などの求人広告サービスでは、飲食業界に特化した採用ノウハウを提供しており、求人票の書き方やPRポイントの整理、効果的な媒体選定など幅広い支援を受けられる場合があります。
時給やシフトの融通だけでなく、研修内容や働きやすさ、キャリアアップの可能性など魅力的な要素をいかに打ち出すかが採用成功のカギとなります。また、応募を増やすだけでなく、採用後のフォローや定着率向上策までを考えられれば、一度採用したスタッフに長く勤めてもらうことにつながります。結果的に人手不足や離職率の問題を緩和し、現場の負担を大幅に削減できる可能性があるでしょう。