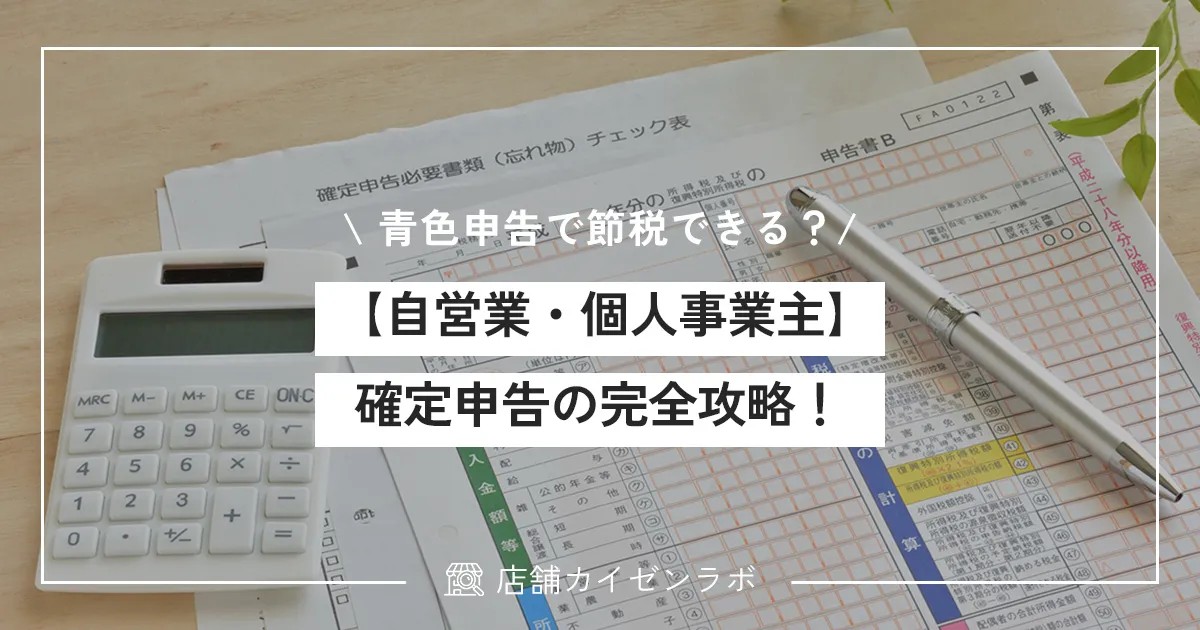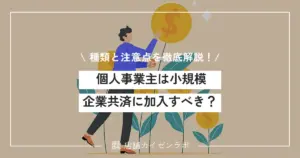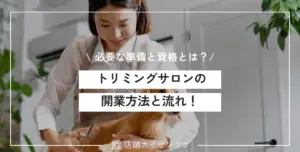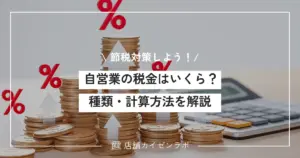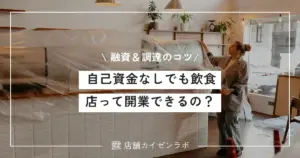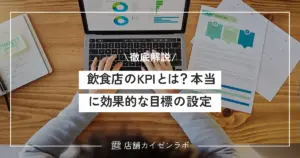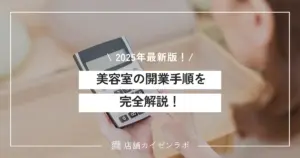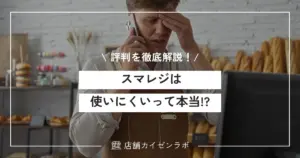「自営業になったけど、確定申告って何から手をつければいいの?」 「青色申告がお得って聞くけど、自分にできるか不安…」
会社員から独立した方や、初めて確定申告シーズンを迎える個人事業主の多くが、このような不安を抱えています。税金の手続きは専門用語が多く、複雑で面倒に感じられるかもしれません。
ご安心ください。この記事では、確定申告の基本から、節税効果の高い青色申告のやり方、具体的な準備や手順まで、7つのステップで徹底的に解説します。筆者自身が数々の失敗から学んだ経験や、専門家の知見も交えながら、あなたがこの記事を読み終える頃には「確定申告、自分でもできそう!」と自信を持って行動に移せることをお約束します。
第1章そもそも確定申告とは?自営業は申告が必要?

まずは確定申告の全体像を掴むところから始めましょう。「自分は申告が必要なのか?」という最も基本的な疑問に、明確にお答えします。
1-1. 確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)に得たすべての所得を自分で計算し、それに対する所得税額を国(税務署)に報告・納税するための一連の手続きのことです。
会社員の場合は、会社が毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、年末調整で過不足を精算してくれるため、個人で確定申告をする機会はあまりありません。
しかし、自営業・個人事業主は、給与所得者と違って誰も税金を計算してくれません。そのため、自分で事業の売上や経費を正確に把握し、「これだけの利益が出たので、税金はこれだけ納めます」と自己申告する必要があるのです。
事業のお金の流れを把握する「健康診断」
結局、確定申告は単なる納税作業ではなく、1年間の事業活動を数字で振り返る「健康診断」のようなものだと気づきました。どの仕事が利益率が高く、どこに無駄な経費がかかっているのか。確定申告を通じて、翌年の事業計画を立てるための貴重なデータが得られたのです。
1-2. 個人事業主・自営業者で確定申告が必要なケース
では、すべての自営業者が確定申告をしなければならないのでしょうか?答えは「No」です。申告義務が発生するのは、以下の計算式で求められる「課税所得」がプラスになる場合です。
(年間の総収入)−(必要経費)−(各種所得控除)=課税所得
各種所得控除の中で、すべての人が受けられるのが「基礎控除」で、その額は48万円です(合計所得金額2,400万円以下の場合)。
つまり、非常にシンプルに言えば、年間の事業所得(収入 − 経費)が48万円を超えたら、確定申告が必要になると考えてよいでしょう。
年間売上300万円のWebデザイナーの場合
- 年間の総収入: 3,000,000円
- 必要経費(PC購入費、ソフト利用料、通信費など):1,200,000円
- 事業所得(収入 – 経費):1,800,000円
この場合、事業所得180万円が基礎控除48万円を大幅に超えているため、確定申告は必須です。ここからさらに社会保険料控除や生命保険料控除などを差し引いて、最終的な税額を計算します。
1-3. 個人事業主・自営業者で確定申告が不要なケース
逆に、上記の計算で事業所得が48万円以下であれば、他に所得がない限り、所得税の確定申告は原則として不要です。
しかし、ここで注意点が2つあります。
- 住民税の申告は必要:
- 所得税の確定申告が不要でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要になる場合があります。確定申告をすれば、その情報が市区町村にも連携されるため住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は、忘れずに市区町村の窓口で手続きを行いましょう。
- 赤字でも申告した方がお得な場合がある:
- 事業が赤字(所得がマイナス)の場合、申告義務はありません。しかし、後述する「青色申告」で申告すれば、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺して税金を安くすることができます。
【この章のチェックポイント】
□ 自分の年間の事業所得(収入 – 経費)が48万円を超えるか確認した。
□ 赤字の場合でも、青色申告で損失を繰り越すメリットを理解した。
第2章 確定申告における青色申告と白色申告の違いは?

確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかで、納税額が数十万円単位で変わることも。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った方法を選びましょう。
2-1. 青色申告のメリット・デメリット
青色申告は、正規の簿記原則(複式簿記)に基づいて帳簿を作成し、申告することで、税制上の様々な優遇措置を受けられる制度です。
【メリット】
- 青色申告特別控除:
- 所得から最大65万円、55万円、または10万円を控除できます。
- 赤字の繰越し:
- その年に出た赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
- 家族への給与を経費にできる:
- 「青色事業専従者給与」として、生計を共にする家族に支払った給与を全額経費にできます(要届出)。
- 30万円未満の減価償却資産を一括経費に:
- 通常、10万円以上の備品(PCなど)は数年に分けて経費化(減価償却)しますが、30万円未満であれば購入した年に一括で経費にできます。
【デメリット】
- 事前の届出が必要:
- 申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
- 複式簿記での記帳が原則:
- 貸借対照表や損益計算書を作成する必要があり、簿記の知識がないと難しく感じられます。(※ただし、後述する会計ソフトを使えば知識がなくても作成可能です)
2-2. 白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、青色申告の承認申請をしていない人が行う申告方法です。
【メリット】
- 事前の届出が不要:
- 特別な申請なしで、誰でも利用できます。
- 簡易な帳簿付けでOK:
- 日々の収入と支出を記録する「単式簿記」で良いため、比較的簡単です。
【デメリット】
- 税制上の特典がない:
- 青色申告特別控除や赤字の繰越しといった、大きな節税メリットは一切ありません。
手軽さの裏にあった「機会損失」という大きなデメリット
2-3. 青色申告と白色申告の違い比較表
両者の違いを一覧表にまとめました。どちらを選ぶべきか、あなたの状況と照らし合わせてみてください。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越し | 3年間可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費にできる(要届出) | 経費にできない(事業専従者控除あり) |
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
| 帳簿の付け方 | 複式簿記(原則) | 単式簿記(簡易な方法) |
| おすすめな人 | 節税を最大限したい人/会計ソフトを使う人 | とにかく手間をかけたくない人/所得が少ない人 |
先輩事業主はどう選んだ?
【この章のチェックポイント】
□ 青色申告のメリット(特に65万円控除と赤字繰越)を理解した。
□ 会計ソフトを使えば、簿記知識がなくても青色申告は可能であることを理解した。
第3章 自営業が確定申告する場合の事前準備!開業から記帳まで!

確定申告は、申告期間(2月16日〜3月15日)に慌てて始めるものではありません。事業を開始したその日から、準備は始まっています。ここでは、申告をスムーズに進めるための3つの重要な事前準備について解説します。
3-1. 開業届の提出
個人で事業を開始したら、事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に、納税地を所管する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」を提出することが所得税法で定められています。
屋号(お店や事業の名前)で銀行口座を開設したり、小規模企業共済に加入したりする際にも提出を求められる、いわば「事業主としての公的な証明書」です。
提出は、税務署の窓口や郵送のほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えばオンラインで完結できます。
5分で完了!freee開業を使ったオンライン提出
私は「freee開業」という無料サービスを利用して開業届を作成・提出しました。
- Webサイトにアクセス: freee開業のサイトでアカウントを登録。
- 質問に答えるだけ: 「どんな事業?」「いつから始めた?」といった簡単な質問に答えていくだけで、開業届が自動で作成されます。
- スマホで電子申告: 作成された書類を元に、スマホアプリを使ってe-Taxで電子提出。マイナンバーカードの読み取りは必要ですが、税務署に行く手間も郵送代もかからず、5分ほどで完了しました。控えもPDFで保存できるので管理も楽です。
3-2. 青色申告承認申請書の提出(青色申告をする場合)
第2章で解説した青色申告のメリットを享受するためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が不可欠です。
この書類の提出期限は非常に厳格です。
- 原則: 青色申告をしようとする年の3月15日まで
- 新規開業の場合: 事業を開始した日(開業日)から2ヶ月以内
開業届と一緒に提出するのが最も確実で、忘れる心配がありません。この一枚の紙を出し忘れただけで、翌年の納税額が大きく変わってしまうため、最優先で対応しましょう。
3-3. 日々の記帳と帳簿・書類の保存
確定申告書の数字は、日々の取引の記録である「帳簿」に基づいて作成されます。そして、その帳簿の信憑性を担保するのが、領収書や請求書といった「証拠書類」です。
法律により、これらの帳簿と書類は、原則として7年間の保存が義務付けられています(白色申告の場合は5年)。
「1年分の領収書をまとめて入力する」というのは、非常に手間がかかる上、記憶も曖昧になりがちです。取引が発生するたびに、会計ソフトにこまめに入力・記録する習慣をつけることが、確定申告を乗り切る最大のコツです。
レシート撮影で経理作業が劇的に変化!
近年は電子帳簿保存法も改正され、電子取引のデータ保存が義務化されるなど、デジタルでの経理管理がスタンダードになりつつあります。早めに会計ソフトを導入し、ペーパーレスな経理体制を構築することをおすすめします。
【この章のチェックポイント】
□ 開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出する準備ができた。
□ 日々の取引を記録し、領収書を保管する重要性を理解した。
□ 会計ソフトを導入して、経理を効率化する検討を始めた。
第4章 個人事業主の具体的な確定申告の流れと手続きの手順
事前準備が整ったら、いよいよ確定申告の実作業に入ります。ここでは、申告書類の準備から納税までの一連の流れを、4つの具体的なステップに分けて解説します。この通りに進めれば、初めての方でも迷うことなく完了できます。
4-1. STEP1:確定申告の必要書類を準備する
確定申告は、必要書類を正確に集めることから始まります。申告期間の直前になって「あの書類がない!」と慌てないよう、以下のチェックリストを参考に、早めに準備を進めましょう。
【確定申告 必要書類チェックリスト】
| 必須度 | 書類の種類 | 概要と入手先 |
|---|---|---|
| ★★★ | 確定申告書 | 全員の所得を申告する書類。税務署または国税庁HPで入手。会計ソフトなら自動作成。 |
| ★★★ | 決算書 or 収支内訳書 | 青色申告の場合: 青色申告決算書白色申告の場合: 収支内訳書(会計ソフトなら自動作成) |
| ★★★ | 本人確認書類 | マイナンバーカード。ない場合は「通知カード+運転免許証」などが必要。 |
| ★★☆ | 各種控除証明書 | 社会保険料: 国民年金保険料や国民健康保険料の年間支払額がわかるもの生命保険料・地震保険料: 保険会社から秋頃に送付されるハガキiDeCo・小規模企業共済: 掛金の払込証明書 |
| ★☆☆ | 源泉徴収票 | 会社員との兼業や、報酬から源泉徴収されている場合に必要。支払元から入手。 |
4-2. STEP2:確定申告書を作成する
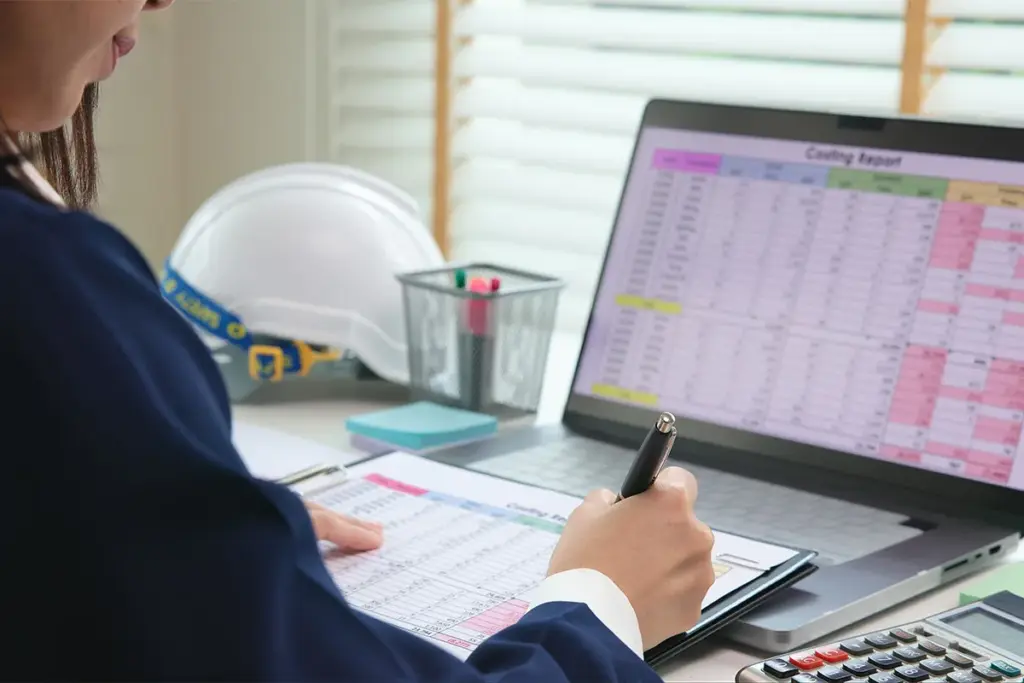
書類が揃ったら、いよいよ確定申告書を作成します。作成方法は主に4つあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| 作成方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| ① 確定申告ソフト | 簡単・正確・時短。簿記知識不要で青色申告が可能。銀行口座連携で自動入力。 | 月額/年額の費用がかかる。 | すべての人(特に初心者、青色申告をしたい人) |
| ② 確定申告書等作成コーナー | 無料。国税庁の公式サイトで安心感がある。 | 簿記の知識が前提。日々の帳簿は別途作成が必要。入力ミスが起こりやすい。 | 簿記知識があり、コストをかけたくない人。 |
| ③ 手書き | 費用がかからない。 | 非常に手間がかかる。計算ミスや転記ミスのリスクが最も高い。 | 簿記・税務知識が完璧で、PCが苦手な人。 |
| ④ 税理士に依頼 | 最も正確で安心。節税相談も可能。時間と手間を完全に削減できる。 | 費用が最も高い(数万円〜)。 | 売上が大きい人、事業が複雑な人、本業に集中したい人。 |
国税庁「確定申告書等作成コーナー」のつまずきポイント
結論として、これから始める自営業者の方には、多少のコストを払ってでも①の確定申告ソフト(クラウド会計ソフト)の利用を強くおすすめします。
4-3. STEP3:確定申告書と必要書類を提出する
完成した申告書は、期間内に税務署へ提出します。
申告期間
原則として、翌年の2月16日〜3月15日
提出方法
- e-Tax(電子申告):
- PCやスマホからオンラインで提出。青色申告65万円控除の必須要件であり、還付も早い(約2〜3週間)ため最もおすすめです。
- 郵送:
- 信書として、管轄の税務署へ郵送します。消印が提出日とみなされます。
- 税務署へ持参:
- 税務署の受付窓口や時間外収受箱に直接投函します。
4-4. STEP4:所得税の納付・還付
申告書を提出したら、納税または還付の手続きを行います。
- 納税の場合:
- 計算の結果、納めるべき税金がある場合は、原則3月15日までに納付します。方法は、口座振替(振替納税)、クレジットカード、コンビニ納付、e-Tax経由でのダイレクト納付などがあります。
- 還付の場合:
- 報酬から天引きされた源泉徴収税額が、年間の納税額より多い場合などは、税金が戻ってきます。これを「還付」といい、確定申告書に記載した銀行口座へ、申告から約2週間〜1ヶ月半後に入金されます。
クレジットカード納付でポイントゲット!
【この章のチェックポイント】
□ 確定申告の4ステップ(準備→作成→提出→納税/還付)を理解した。
□ 自分に合った申告書の作成方法と提出方法を選んだ。
□ 申告と納税の期限(原則3月15日)をカレンダーに登録した。
第5章 自営業の確定申告で経費にできるものとは?

確定申告における節税の基本は、「経費を漏れなく計上すること」に尽きます。経費を正しく計上すれば、課税対象となる所得を圧縮でき、結果として納税額を抑えることができます。この章では、経費の基本から具体的な判断基準までを解説します。
5-1. 経費とは、事業上必要とされる費用のこと
経費とは、簡単に言えば「事業の売上を上げるために直接的、または間接的に必要となった費用」のことです。
税務の世界では「売上原価」と「販売費及び一般管理費(販管費)」に分けられますが、個人事業主の場合はそこまで厳密に考える必要はありません。大切なのは、その支出が「事業と関連があるか」を客観的に説明できるかどうかです。
5-2. 経費にできるもの・できないもの一覧表
具体的にどのようなものが経費になるのか、代表的な勘定科目とともに見ていきましょう。
| 勘定科目 | 経費にできるものの例 | 経費にできないものの例 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 文房具、プリンターのインク、10万円未満の備品 | プライベートで使う日用品 |
| 旅費交通費 | 取材先への電車代、打ち合わせ先へのガソリン代 | 家族旅行の交通費 |
| 通信費 | 事業用のスマホ代、インターネット回線料、サーバー代 | プライベート用のスマホ代 |
| 広告宣伝費 | Webサイト制作費、チラシ印刷代、リスティング広告費 | – |
| 接待交際費 | 取引先との会食代、お中元・お歳暮代 | 友人との飲み会代 |
| 新聞図書費 | 専門書、業界紙、有料メルマガ購読料 | 趣味の雑誌、小説 |
| 地代家賃 | 事務所の家賃、月極駐車場の料金 | 自宅の家賃(按分が必要) |
こんなものまで?同業デザイナーの経費リスト
私の知人であるフリーランスデザイナーは、以下のようなものも事業との関連性を明確にした上で経費計上しています。
- 美術館のチケット代: デザインのインスピレーションを得るため(取材費)
- 競合調査のための他社サービス利用料: 市場分析のため(調査費)
- 有料フォントの購入費: 制作物のクオリティ向上のため(消耗品費)
ポイントは、領収書の裏に「〇〇のデザイン参考のため」「△△案件の競合調査」など、目的をメモしておくこと。これにより、税務調査などで質問された際に、事業との関連性を明確に説明できます。
5-3. 自宅兼事務所の家賃・光熱費は「家事按分」で経費に
自宅で仕事をしている自営業者にとって、最大の節税ポイントの一つが「家事按分(かじあんぶん)」です。これは、家賃や水道光熱費、通信費など、プライベートと事業の両方で使っている費用を、事業で使った分だけ経費として計上する考え方です。
按分の基準は、客観的で合理的ならOKです。
- 家賃:
- 事業で使っているスペースの床面積で按分する。(例:全体の床面積80㎡のうち、仕事部屋が20㎡なら、20 ÷ 80 = 25%を経費に)
- 電気代:
- 事業で使っている時間やコンセントの数で按分する。(例:1日24時間のうち8時間仕事をするなら、8 ÷ 24 = 約33%を経費に)
- 通信費:
- 事業での使用割合を自己申告する。(例:スマホの利用時間の半分が事業用なら50%)
ある在宅ワーカーの仕事部屋の家事按分(家賃10万円の場合)
- 家全体の床面積: 60㎡
- 仕事部屋の面積: 15㎡
- 事業使用割合: 15㎡ ÷ 60㎡ = 25%
- 経費にできる家賃額: 100,000円 × 25% = 25,000円/月
この場合、年間で 25,000円 × 12ヶ月 = 300,000円 を地代家賃として経費計上できます。このロジックを帳簿の摘要欄にメモしておけば、税務署にも自信を持って説明できます。
飲食店経営者で経費削減テクニックをもっと知りたい方は、『飲食店の経費削減完全マニュアル!すぐに効果が出るコスト最適化のアイデアをすべて大公開!』をご覧ください。
【この章のチェックポイント】
□ 「事業の売上を上げるために必要か?」という基準で経費を判断できるようになった。
□ 経費にできるもの・できないものの具体例を理解した。
□ 自宅で仕事をしている場合、家事按分の計算方法を理解した。
第6章 確定申告をしないとどうなる?ペナルティと注意点

確定申告は国民の義務ですが、中には「面倒だから」「バレないだろう」と申告をしない人もいます。しかし、その代償は非常に大きいものです。この章では、無申告のリスクと、知っておくべき注意点を解説します。
6-1. 無申告加算税、延滞税などの追徴課税がある
期限内に確定申告をしなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして以下の「追徴課税」が課せられます。
- 無申告加算税:
- 期限後に申告した場合に課される税金。税額に応じて15%〜20%が上乗せされます。(※税務調査前に自主的に申告すれば5%に軽減)
- 延滞税:
- 法定納期限(3月15日)の翌日から、納付する日までの日数に応じて課される利息。税率は年によって変動しますが、最大で年14.6%と非常に高率です。
- 重加算税:
- 意図的に所得を隠すなど、悪質と判断された場合に課される最も重いペナルティ。無申告加算税に代えて40%という重い税率が課されます。
知人が支払った追徴課税80万円の恐怖
6-2. なぜバレる?税務署に無申告が発覚するケース
「どうせ自分のような小規模事業者はバレない」というのは、大きな間違いです。税務署は、我々が思う以上に様々な情報網を持っています。
- 支払調書:
- あなたに報酬を支払った企業は、「誰に、いくら支払ったか」を記載した「支払調書」を税務署に提出しています。税務署はこれを見て、あなたが申告しているかを確認できます。
- 銀行口座の動き:
- 税務署は法律に基づき、金融機関に口座情報の照会を行う権限を持っています。不審な入出金があれば、調査の対象になる可能性があります。
- 第三者からの通報(密告):
- 「あの人は儲かっているのに申告していない」といった、取引先や知人からの通報が調査のきっかけになることも少なくありません。
- KSK(国税総合管理)システム:
- 国税庁が運用するこのシステムには、過去の申告状況や支払調書など、全国民の税に関するあらゆる情報が一元管理されています。これにより、無申告者は容易にリストアップされてしまうのです。
6-3. 会社員の副業でも確定申告が必要なケースがある
会社員として給与をもらいながら副業をしている場合も、確定申告が必要になることがあります。
一般的に「副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えた場合」に、確定申告が必要とされています。
ここで非常に重要なのが、この「20万円ルール」は所得税の話だという点です。住民税についてはこのルールは適用されず、所得が1円でもあれば、原則として市区町村への申告が必要です。確定申告をすれば住民税の申告も兼ねられますが、20万円以下で確定申告をしない場合は、別途、市区町村の役所で住民税の申告手続きを忘れないようにしましょう。
副業が会社にバレないための「普通徴収」
これを避けるには、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。こうすることで、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納めることができるため、会社に通知が行くことはありません。私は独立前に副業をしていた際、この方法で会社に知られることなく確定申告を済ませていました。
【この章のチェックポイント】
□ 無申告のペナルティ(加算税・延滞税)の重さを理解した。
□ 税務署に無申告が発覚する仕組みを理解した。
□ 副業の「20万円ルール」と、住民税の「普通徴収」について理解した。
第7章 確定申告で不安なときは専門家に相談しよう!
ここまで確定申告のやり方を解説してきましたが、それでも「自分のこのケースはどうなんだろう?」「本当にこのやり方で合っているか不安…」と感じることもあるでしょう。それは当然のことです。税金の手続きは複雑で、一人で完璧にこなすのは難しいものです。
大切なのは、一人で抱え込まないこと。幸い、自営業者には頼れる相談先がいくつもあります。ここでは代表的な3つの相談先と、それぞれの特徴、上手な活用法を紹介します。
7-1. 税務署(確定申告電話相談センター)
最も身近で公式な相談先が、国税庁(税務署)です。確定申告期間中は「確定申告電話相談センター」が設置され、電話で質問に答えてくれます。
- メリット:
- 無料で利用でき、公式な見解なので安心感がある。申告書の書き方など、手続きに関する基本的な質問に丁寧に答えてくれる。
- デメリット:
- 節税に関するアドバイス(「どうすれば税金が安くなりますか?」といった質問)はしてくれない。申告期間中は電話が非常に繋がりにくい。
7-2. 商工会議所・青色申告会
地域の事業者を支援する団体である「商工会議所」や、個人事業主の納税をサポートする「青色申告会」も心強い味方です。
- メリット:
- 比較的安価な会費で、記帳指導から確定申告の相談まで、年間を通じてサポートしてくれる。地域密着型で、アットホームな雰囲気で相談しやすい。
- デメリット:
- 会費が必要。税理士のような高度で専門的な節税コンサルティングは期待できない場合がある。
7-3. 税理士などの専門家に依頼する
「本業が忙しくて経理に時間をかけられない」「最大限の節税をしたい」という方には、税金のプロである税理士への依頼が最適な選択肢です。
- メリット:
- 記帳代行から申告書作成・提出まで全てを丸投げできる。法律の範囲内で最適な節税策を提案してくれる。税務調査の際には代理人として対応してくれるため、非常に心強い。
- デメリット:
- 費用がかかる(顧問契約で月額数万円〜、確定申告のみで5万円〜が目安)。
専門家・山田氏
【この章のチェックポイント】
□ 無料で手続きの基本を聞きたいなら「税務署」。
□ 安価で記帳から教わりたいなら「青色申告会」。
□ 時間と手間を削減し、節税を最大化したいなら「税理士」。
第8章 自営業なら適切な確定申告で節税につなげよう!
さて、全8章にわたる長い旅も、いよいよ最終章です。確定申告の基本から具体的な手順、そしてトラブル対処法まで、必要な知識はすべてお伝えしました。最後に、この記事で最も伝えたかったことをお話しします。
8-1. 正しく申告して賢く節税
この記事を読む前のあなたにとって、確定申告は「よくわからない面倒な義務」だったかもしれません。しかし、今はどうでしょうか。
確定申告は、決して単なる納税作業ではありません。それは、あなたが1年間、必死に事業と向き合ってきた汗と努力の結晶を「数字」という共通言語で可視化する、年に一度の重要なイベントです。
- どの事業が利益を生み、
- どこに無駄なコストがかかり、
- 法律で認められた権利(控除)を最大限活用できているか。
これら全てが、確定申告書という「事業の成績表」に表れます。この成績表と真摯に向き合うことで、翌年の事業戦略が見えてくるのです。
8-2. 確定申告を簡単に終わらせる方法
最後に、ここまで読んでくださったあなたが、最も簡単かつ確実に確定申告を乗り越えるための具体的な方法を提案します。
それは、「クラウド会計ソフト」を導入することです。
簿記の知識がなくても、銀行口座やクレジットカードを連携すれば日々の取引データが自動で取り込まれ、ガイドに従って操作するだけで、青色申告に必要な複雑な決算書まで作成できます。
| クラウド会計ソフト | 特徴 |
|---|---|
| freee会計 | 簿記の知識が全くない初心者向け。質問に答える形式で直感的に操作できる。 |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 連携できる金融機関が多く、自動化に強い。少し簿記をかじったことがある人にも使いやすい。 |
| やよいの青色申告 オンライン | 老舗ならではの安定感と充実したサポート体制。シンプルな操作性が魅力。 |
これらのソフトは、月々1,000円〜2,000円程度の費用がかかりますが、その費用は全額「経費」になります。そして何より、あなたが経理作業に費やすはずだった膨大な時間を節約し、本業に集中させてくれます。
ほとんどのソフトに無料のお試し期間が用意されています。まずは気軽に登録し、その便利さを体験してみてください。きっと、確定申告に対するハードルが、驚くほど低くなるはずです。
あなたの事業の成功と、初めての確定申告が無事に完了することを、心から応援しています。