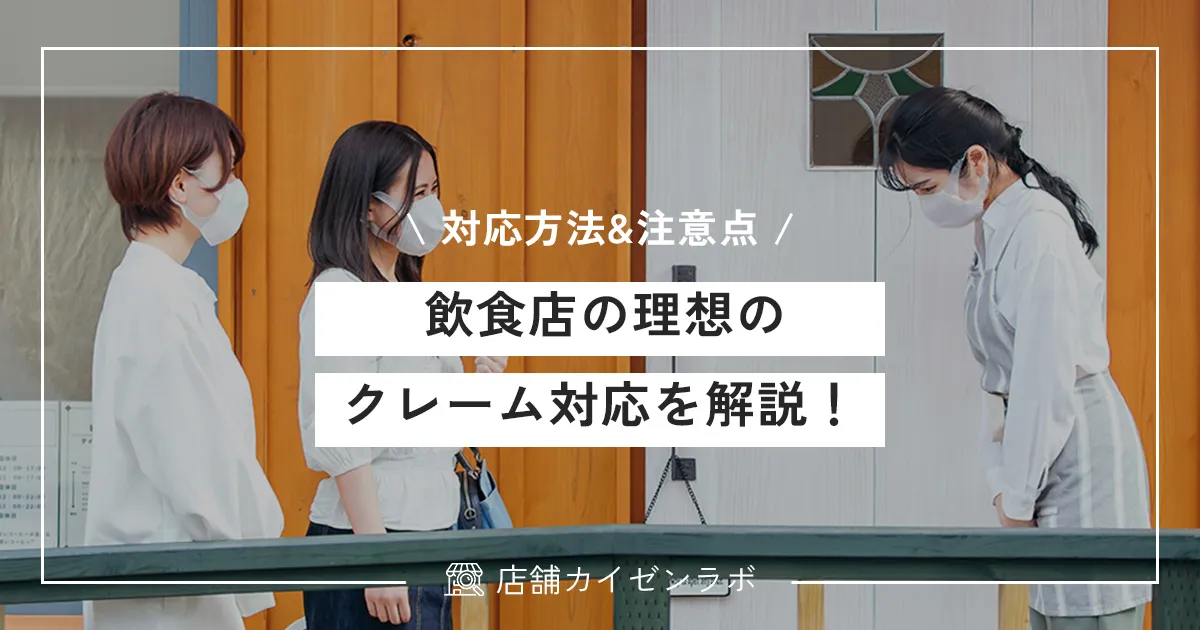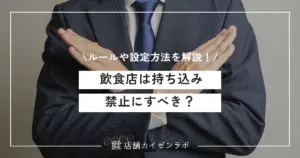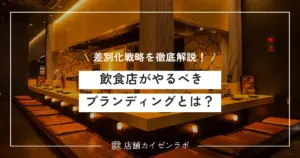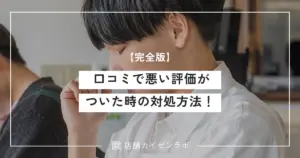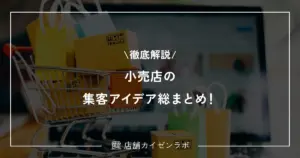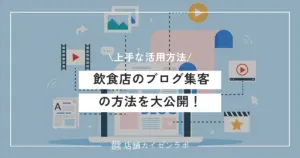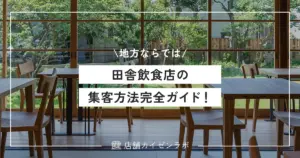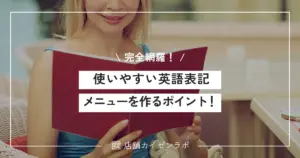第1章. 飲食店においてクレーム対応が重要な理由

飲食店では、料理の提供や接客といった“現場”そのものが顧客満足度に直結します。クレーム対応が起きた際の対応がまずいと、店舗の信頼が一気に崩れる可能性は高いです。特に近年はSNSでの拡散スピードが速く、クレーム内容が大きく広がると、集客への影響も見逃せません。
飲食店としてたとえ料理の味に自信があっても、異物混入や接客ミスが一度「問題」としてSNSに投稿されてしまうと、足を運ぶ前の段階で顧客が離れていくケースが増えています。こうした状況を防ぐため、クレーム対応を受けたときの初動や解決フローをあらかじめ整備しておくことが重要です。
SNSの運用方法について詳しく知りたい方は、『【2025年最新版】飲食店のSNS運用完全攻略!店舗集客に効果のある活用術を徹底解説!』を確認してみてください。
また、クレーム対応に力を入れると、お客様の満足度向上だけでなく、スタッフのモチベーション維持にもつながります。クレームは発生してから「どう解決できるか」で評価が決まるため、きちんとマニュアルを作り、現場で迷わないようにしておきましょう。
第2章. 飲食店でよくあるクレームとその原因

2-1. 提供スピード関連:遅れ・オーダーミスの火種
飲食店で忙しい時間帯に料理が遅れたり、オーダーの内容を間違えてしまったりすることは、飲食店ではよくあるクレーム対応のトラブルです。調理スタッフが不足していたり、注文管理システムの使い方が徹底されていないと発生しやすいでしょう。
この火種を放置していると「待たされた上に間違えられた」といった二重の不満となり、顧客の怒りが急速に大きくなります。特に短いランチタイムでの利用など、時間的制約を抱えるお客様が多い場合は、クレーム対応のリスクがさらに上昇します。
筆者の実践談:
2-2. 異物混入や衛生面:信頼を失う重大トラブル
クレームの中でも最も深刻になりがちなものが「異物混入」「衛生管理不備」です。これらはクレーム対応において食の安全や健康被害に直結する問題であり、悪化すると行政指導や営業停止といった大きなリスクにもつながります。
飲食店での異物混入の原因は、スタッフの髪の毛の落下や食材保管の不備などさまざまです。調理過程での異常を見逃したまま提供してしまうと「飲食店としてのモラルが欠けている」と顧客から強い批判を受ける可能性があります。弁護士によれば、食中毒に発展したケースでは損害賠償を求められることも少なくないそうです。
衛生面のトラブルを防ぐには、日々の清掃や定期的な厨房チェックを怠らないこと、そしてスタッフ一人ひとりが「何が問題になり得るか」を自覚することが不可欠といえます。
2-3. スタッフ対応や態度:接客トラブルから生まれる不信感

飲食店ではいかに料理のクオリティが高くても、スタッフの態度が悪いとクレーム発生率は一気に上がります。たとえば言葉遣いがタメ口だったり、明らかに不機嫌そうな表情で接客されたりすると、お客様は“軽視されている”と感じてしまうでしょう。
ほかにも、忙しくなるほどスタッフ同士の私語やイライラが表面化し、お客様の前で言い争いが起きたりすることもあります。こうした場面を目撃すれば、店全体の印象が下がるのは当然です。特に接客業である飲食店では、“人”によるトラブルがそのままクレーム対応の難しさを増幅させる原因になりがちです。
また、新人アルバイトの教育不足がトラブルを起こすこともしばしば。店舗のルールやマナーを教わらないまま現場に立つと、どうしても失礼な言動やミスが発生してしまいます。接客態度のクレームが重なると、店長やオーナーへの信頼も大きく損なわれるでしょう。

スタッフ対応による印象低下を防ぐために、『飲食店での好印象な接客の極意を徹底解剖!リピーターを獲得する理想の対応方法!』の接客ガイドもご覧ください。
2-4. 価格やコスパ感への不満:期待外れのギャップを埋める
「料金の割に量が少ない」「メニュー写真と実物の見た目が違う」といったコスパ面のクレームも少なくありません。お客様のイメージと実際に提供された料理にギャップがあると、「だまされた」という感情が生まれやすくなります。
対策としては、メニュー写真をできるだけ実物に近づけることや、サイズ・量を明記しておくといった努力が必要です。特にリーズナブルさをウリにしている飲食店は、かえって“安かろう悪かろう”と思われないよう、クオリティの維持にもこだわりが求められます。
2-5. 予約や席指定トラブル:来店前から始まるクレーム要素
飲食店のクレームは、来店後だけでなく「予約時点」で始まることもあります。たとえば予約システムの入力ミスでダブルブッキングしてしまったり、予約を取ったはずがデータに反映されておらず席が用意できないなど、重大な混乱を招くケースがあるのです。
また、座席指定の希望を受けていたにもかかわらず当日反映されていないと、「話が違う」と強い不満につながります。顧客の予定や記念日など大切な日程に影響するため、クレームも強めに発生しがちです。オンライン予約が普及している今こそ、システムや従業員の管理体制を見直す必要があります。
第3章. 飲食店のクレーム対応の基本と具体的な手順

3-1. お客様の話を聞ききる:遮らず、感情を受け止める
クレーム対応において、最初のステップである「ヒアリング」は何より大切です。飲食店でお客様が怒りを感じているときほど、話を最後まで聞かずに途中で口を挟むと反発を招き、怒りを増幅させる原因となります。
ここでは、相槌を打ちながらメモを取り、「どこで何があったのか」を正確に把握しましょう。スタッフは自分の言い分を伝えたくなる気持ちをぐっとこらえ、まずは“相手に気持ちよく話してもらう”姿勢を見せることが重要です。感情面を受け止めることで、次のクレーム対応ステップで説明や提案をしやすくなります。
3-2. 問題点の整理と迅速な解決策の提示
お客様の話を聞き終わったら、まずは「今回の問題は何か」を整理しましょう。遅延やオーダーミス、料理の品質、あるいはスタッフの態度なのか、複合的な原因なのかを特定します。
その上で、迅速に解決策を提示することがクレーム対応の要となります。再調理を行うか、返金するか、責任者が謝罪をするかなど、店舗が取りうる対処法を短時間で整理して案内することで、お客様が「誠実に取り組んでいる」と感じる可能性は高まるでしょう。
3-3. 必要に応じて責任者にエスカレーションするポイント
スタッフだけで解決が難しいと判断した場合、早めに店長やオーナー、もしくはクレーム対応専任者に連絡を入れます。飲食店によっては「一定金額以上の返金は責任者のみ可」といったルールがあることも多く、適切な権限を持つ人を呼ぶことが大切です。
この際、問題を共有する際に曖昧な情報だけではかえって混乱を生みます。具体的なクレーム内容、顧客の状況、スタッフ側の対応履歴などを正確に伝えられるよう、事前にメモをまとめておきましょう。
3-4. 結論と再度の謝罪:クレーム対応完結時の着地点
クレーム対応は、解決策を提示して終わりではありません。最終的な着地点として、お客様に納得してもらい、再度謝罪や感謝を示すことが望ましいです。
「こちらの不手際を教えていただいたおかげで、改善点が明確になりました。ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。」といった誠意ある言葉を伝えれば、クレームが収束しても「この店は真剣に取り組んでいる」とプラスの印象を残せる可能性があります。
3-5. アフターフォローと社内共有:ミスを次に活かす
クレーム対応後、すぐに忘れてしまうと同じミスを繰り返す恐れがあります。アフターフォローとして、お客様が再来店した際に「以前ご指摘いただいた件、改善いたしました」と声をかけることで、満足度が一気に向上するケースもあるでしょう。
社内的にも、クレーム内容と解決方法をすべての従業員と共有することが重要です。共有する際には「どんな問題が、なぜ起こったか」「どうすれば再発を防げるか」を具体的に示し、飲食店全体で改善策を実行に移します。このPDCAサイクルを回すことで、クレーム対応が単なる“火消し”ではなく、店舗レベルの向上につながります。
筆者の体験談:
第4章. 飲食店でクレーム対応する際の5つの注意点

4-1. 言い訳や責任転嫁で怒りを増幅させない
クレーム対応時、真っ先に避けたいのが「でも」「それは〇〇だから」という言い訳です。お客様が怒っている状況で自分やスタッフの非を否定すると、火に油を注ぐ結果につながります。たとえ店側に過失が少ないとしても、まずは相手の不満を受け止める姿勢を見せることが重要です。
特に、担当スタッフ不在を理由に「詳しい事情は知らない」と言い切ってしまうと、「誰も責任を持って対応しない店舗だ」と顧客が感じる可能性があります。実際、筆者の運営支援を行った飲食店で同様のクレーム対応をした結果、口コミサイトに「管理体制がずさん」「言い訳ばかり」と書かれて大きく評価を下げたケースがありました。責任転嫁は、クレーム対応そのものを長引かせるリスクが高いといえます。
4-2. スタッフ間でのたらい回しを防ぐコツ
「自分には権限がないので、他の者に代わります」など、何度も対応者が変わると、不信感は一気に高まります。飲食店のクレーム対応では、誰が最初に応対しても“一次対応”として最後まで責任をもつ意識を徹底するのが望ましいでしょう。
オペレーションマニュアルに「スタッフ全員が一定範囲で判断できる事項」や「責任者への連絡ライン」を明文化することで、混乱を防げます。筆者がコンサルしていたあるレストランチェーンでは、「1,000円以内の値引き対応ならホールスタッフでも可能」と決めたことで、余計なエスカレーションが減り、お客様の待ち時間が短くなりました。結果、飲食店でのクレームの再燃リスクも下がったのです。
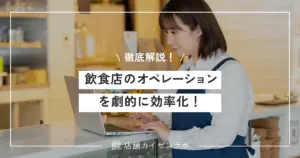
4-3. カスタマーハラスメントかどうかの見極め
正当なクレーム対応の範囲を超え、土下座を強要するなど度を越した要求があれば、カスタマーハラスメント(カスハラ)の可能性があります。弁護士によると、執拗な罵声や脅迫行為は場合によっては威力業務妨害や侮辱罪に該当することもあるため、毅然とした態度で臨むことが必要です。
ただし、相手が怒りの最中にこちらが強い口調で反論すると、問題がさらに複雑化する恐れがあります。まずは冷静に状況を把握し、店舗側のルールで対応しきれないときは警察や弁護士へ相談するフローを用意しておくと安心です。
店舗スタッフには「カスハラかどうか」を判断しやすいチェックリストを提供し、“不当要求をされた場合”と“苦情のレベルで収まる場合”をしっかり区別できるようにしておきましょう。
4-4. SNS時代ならではのリスク:拡散と炎上
SNSの普及に伴い、「店名を晒す」「写真や動画をアップして批判する」といった拡散リスクも増えています。飲食店での些細なトラブルでも短時間で多くの人に伝わり、いわゆる“炎上”状態に陥ると、飲食店の売上やイメージに大きなダメージを与えかねません。
焦った店舗側がネット上で誤った反論や説明をしてしまうと、逆に批判の矛先が一層強まる事例も見受けられます。ネット上の対応は迅速かつ誠実に、かつ問題点を認めるべきところは認めて謝罪する姿勢を示すことが大切です。あらかじめ口コミサイトやSNSレビューを定期的にモニタリングし、ネガティブな投稿に早めに対処できる体制を整えておくと良いでしょう。
SNSによる炎上やデメリットについては、『飲食店がSNS運用をするデメリットと注意点!リスクを把握して炎上やトラブルを回避!』の記事も参考になります。
4-5. 二次トラブルを防ぐ社内情報共有の必要性
クレーム対応がうまく収束しても、その情報を特定のスタッフしか知らない場合、別の担当者が同じミスを繰り返す可能性があります。こうした二次トラブルが重なると、「やはり何も改善されていない」というお客様の失望につながり、店舗全体の評判を落としかねません。
対策として、発生したクレームやその原因、解決策を全スタッフで共有する定例ミーティングを実施する飲食店が増えています。筆者がサポートした店舗では、週に一度「クレーム・改善報告会」を実施するようにしてから、同じトラブルが連続発生する件数が約3割減少しました。情報をオープンにすることで、スタッフ同士がクレーム対応の対策を考えやすくなるメリットもあります。
筆者の実践談:
第5章. 飲食店で適切なクレーム対応をするためのポイントと実用例
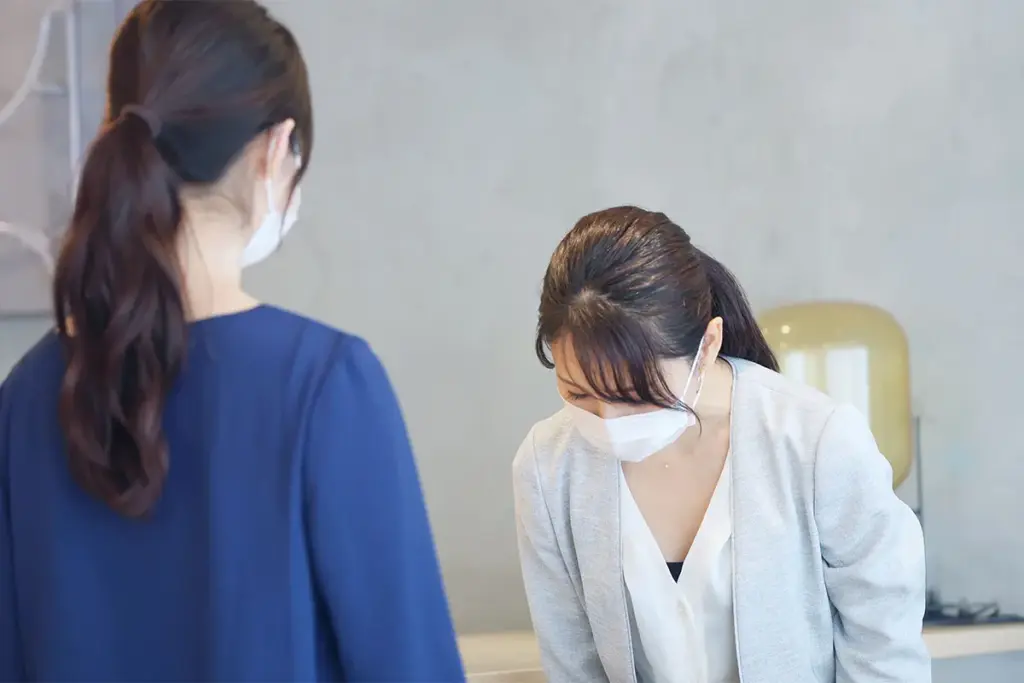
5-1. お詑びと感謝をセットで伝える
謝罪の基本は「申し訳ございませんでした」という言葉ですが、さらに「教えていただきありがとうございます」と感謝を付け加えると、お客様の心情を和らげる効果が高まります。クレーム対応を求める側には、それなりのストレスや時間的負担がかかっているからです。
たとえば、異物混入があった際に「このような事態が起こり、大変申し訳ございません。また、お知らせくださりありがとうございます。すぐに原因を確認いたします。」と伝えれば、単なる謝罪だけでなく“真摯に受け止めよう”という姿勢を見せられます。
5-2. 相手が何を望んでいるかを聞くフレーズ
クレーム対応で見落としがちなのが、「お客様は何を解決策として期待しているのか」をしっかりヒアリングすることです。
- 「何に一番ご不満を感じておられますか?」
- 「もしご要望がありましたら、できる限り対応したいと思っています。いかがでしょうか?」
こうした聞き方をすることで、相手自身も具体的な要望を言葉にしやすくなります。再調理をしてほしいのか、返金や割引を求めているのか、単に謝罪だけで十分なのか、ケースによってはまったく異なるからです。相手の意図を把握することで、無駄な提案を省き、適切な解決策へ導けます。
5-3. 感情表現に配慮した謝罪の言い回し
相手の感情が激しい場合は、ややゆっくり目に、落ち着いたトーンで話をすることが大切です。声を荒げたり、早口でまくし立てると「反抗的」「軽くあしらわれている」と受け取られがち。
飲食店での些細なトラブルでも短時間で多くの人に伝わり、トラブルはさらに深まると言われています。あえてテンポを抑え、「ご不快な思いをさせてしまい、重ね重ね申し訳ございません」と、相手の感情に寄り添う言葉を入れるだけでも、急激なエスカレートを防ぎやすくなります。
5-4. 謝罪だけで終わらず具体的改善策を伝える
「申し訳ございませんでした」で終わる謝罪は、形だけに感じられることも多いです。実際には、クレーム対応後に店舗内で再発防止策を検討し、どのように改善していくかをお客様に伝えることで信頼回復を図れます。
たとえば料理の味についてクレームがあった場合、「今後は調理手順の最終チェックを強化します。次回はぜひ改良した味を試していただければ幸いです」と具体案を示すと、単に謝る以上のポジティブな印象を残せます。こうした積極的アプローチが「また来店してもいいかも」という気持ちを誘発するのです。
5-5. ケース別フレーズ:味・衛生・接客・提供遅延に対応
飲食店のクレーム対応では、よくあるシーンごとに謝罪フレーズをある程度パターン化しておくと実務がスムーズです。
味に関するクレーム
- 「お口に合わず申し訳ございません。もしよろしければ、好みをうかがい再調理させていただきます。」
衛生面・異物混入
- 「異物混入などあってはならないことで、大変申し訳ございません。すぐ原因を調べ、再発防止に努めます。教えてくださりありがとうございます。」
接客態度
- 「スタッフの言動でご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。本人にも指導し、改善に取り組みます。」
提供遅延
- 「お待たせしてしまい大変申し訳ありません。時間がかかっている原因を確認し、早急にお料理をお出しできるよう手配いたします。」
あらかじめ簡潔なフレーズを用意し、スタッフ全員が同じ水準でクレーム対応を行えるようにすると、飲食店全体としてのクオリティが安定します。
第6章. こんなときどう動く? 現場でよくあるクレーム対応の6つの疑問
6-1. Q1:SNSに店名を晒すぞと脅されたら?
近年増えているのが「ネット上で悪評を拡散する」という脅し文句。店舗名や写真を晒すと宣言されるとスタッフは焦りがちですが、まずは冷静に対処を。弁護士によれば、虚偽の事実拡散は名誉毀損や業務妨害に該当するケースがあるものの、その場で強く反論すると逆に問題がこじれる可能性が高いです。
筆者が過去に運営支援した店舗でも、「晒す」と言われた際にスタッフが怒りを買ってしまい、実際にSNSで拡散され売上が落ち込んだ例があります。誠実な態度で解決策を提示しつつ、お客様の意見をじっくり聞くのがクレーム対応の初動リスクを最低限に抑えるポイントです。
ネットでの悪評を最小限に抑えるには、口コミ対策の『【完全版】口コミで悪い評価がついた時の対処方法!返信の仕方から削除依頼まで徹底解説!』の記事も参考にしてください。
6-2. Q2:責任者が不在のとき、どう対応すればいい?
責任者不在の時間帯にクレームが起こることは珍しくありません。一次対応の範囲や権限を明確にしていないと、現場スタッフがパニックに陥りやすいです。
たとえば「500円までのサービスや割引はスタッフ判断でOK」「再調理・返金可能ラインを明文化」といったルールを事前に設定しておけば、混乱を減らせます。筆者が関わったレストランでは、スタッフがスムーズに対応できる環境を整えたことで、責任者不在時のトラブル減に成功しました。
6-3. Q3:提供が遅れたときの追加サービスは何が適切?
「お詫びドリンク」「割引券」などの対応は一定の効果がありますが、過剰だと不公平感を招く場合も。筆者が運営指導した店舗では、注文の遅延時に「具体的な理由」をしっかり説明し、お詫びの気持ちを伝えたところ、追加サービスなしでも納得してもらえた事例が多数ありました。
忙しい時間帯に全員へサービスするとコストが重くのしかかるため、店舗方針とお客様の温度感を見極めながら適切なレベルを判断しましょう。
6-4. Q4:味が気に入らないとクレームされ、再調理を要求されたら?
飲食店では料理の味は個人差が大きい分、店側のミスか“好みの違い”かの区別が難しいところ。まずは「塩分が濃い」「焼き加減が合わない」など、具体的に何が合わなかったのかを聞き出すことが大切です。
再調理が難しい場合は代替メニューや味付け変更の提案も有効。筆者が現場で経験した例では、ソースを変更しただけでクレームが収まり「次回は違う味も試してみたい」とリピーター化したお客様もいます。
第7章. 飲食店のクレーム対応は店舗運営を左右する重要なポイント!

クレーム対応は、単に目の前の火種を消すだけでなく、今後の飲食店運営を左右する重要なプロセスです。今回紹介したように、一次対応の基本を押さえ、相手の希望を的確に聞き出し、誠意を示すことでトラブルは格段に解決しやすくなります。クレームの裏には「お店を良くしてほしい」「期待していたから残念だった」という前向きな動機が含まれることも多いもの。逆に考えれば、お客様の本音を聞ける貴重なチャンスでもあります。
具体的なマニュアルの整備や権限範囲の明確化、スタッフ同士の情報共有など、日常的に準備をしておけばクレームが大きくなる前に対処できます。クレームの発生を防げなくても、適切な初動と誠実なフォローを続けることで、店舗の評価を高め、リピーター獲得にもつなげられるでしょう。